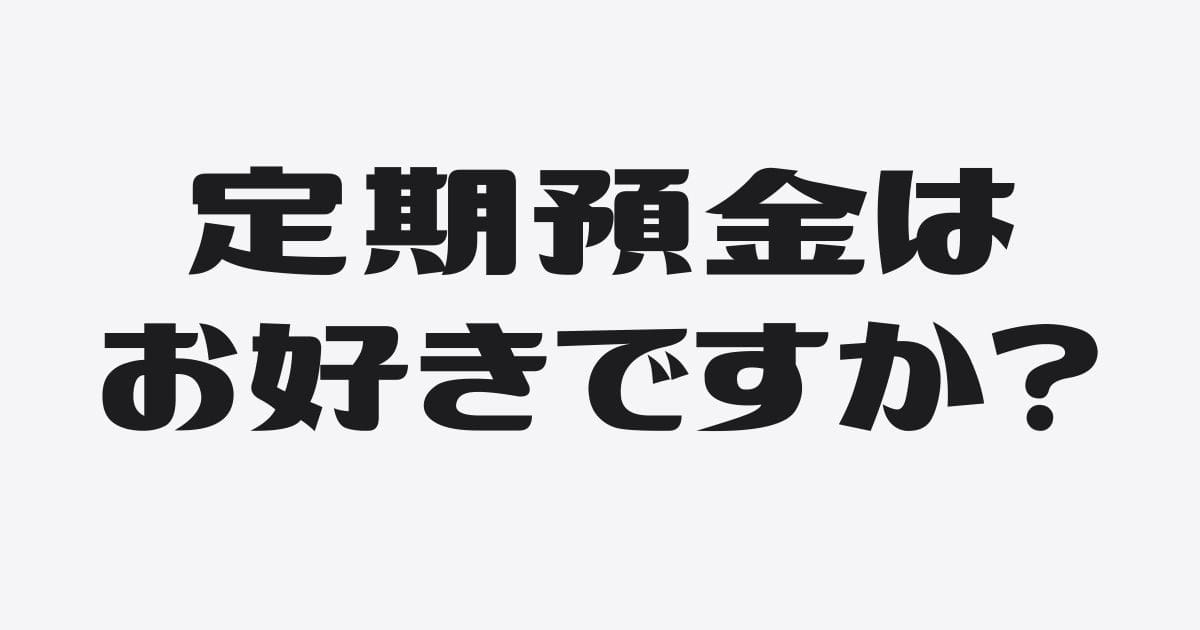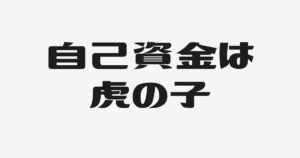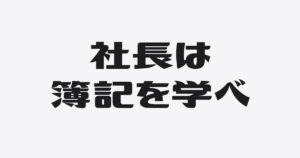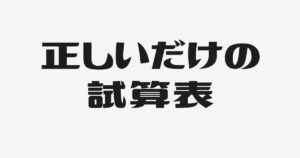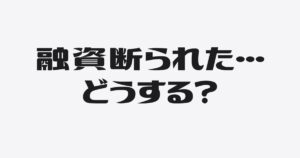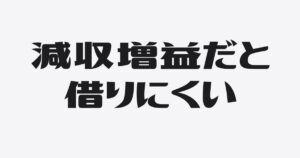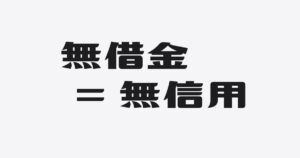日銀の利上げを受けて、世の中の金利が上昇しています。銀行から定期預金を勧められることもあるでしょう。では、会社は定期預金をするのがよいのか否か?これが今回のテーマです。
定期預金をするか否か
日銀の利上げを受けて、世の中の金利が上昇しています。銀行は、資金調達コストを下げるためにも預金集めに躍起です。よって、いままで以上に定期預金を勧められることもあるでしょう。では、会社は定期預金をするのがよいのか否か?これが今回のテーマです。
銀行から勧められると、「これもお付き合い」と定期預金に応じる会社もありますが。資金繰りの良し悪しや、融資の受けやすさに影響することを忘れてはいけません。そのうえで、「会社は定期預金をすべきでない」というのが結論です。
その理由や、定期預金をしない代わりにどうすればよいかなど、次のような項目についてお伝えします。
- 定期預金がダメな理由
- 普通預金がいいと知る
- 実質の預金を見える化
すでに定期預金をしている場合はもちろん、定期預金をしようと考えていたり、定期預金をしてもいいと考えているようなら、このあとの話をいちど確認されることをおすすめします。
定期預金がダメな理由
冒頭、会社は定期預金をすべきでないと言いました。これは、資金繰りや銀行融資の観点に依っています。言い換えると、おカネが潤沢にあって銀行融資が必要ないのであれば、定期預金をしたってかまわないということです。
しかし、おカネが「本当に」潤沢な中小企業はほとんどありません。平均月商(年間売上高÷12か月)の数か月分ていどの預金残高では、将来にわたって潤沢とは言えず、いつか融資を必要とするかもしれないからです。これをふまえて、目安として「最低でも平均月商6か月分以上の預金残高」となれば、おカネが潤沢な中小企業はかなりの少数派でしょう。
ではなぜ、おカネが潤沢でない会社が定期預金をしてはダメなのか?
解約して引き出したくても、それができない・しづらいことがあるからです。融資を受けている銀行に定期預金をあずけた場合、その銀行にとっては「担保」のようなものだといえます。会社が返済できなくなったときには、定期預金で相殺できるとの考えです。
だとすれば、銀行がカンタンには解約に応じないことはわかるでしょう。会社が解約しようとしても、あの手この手で引き止めようとするものです。すると、会社にとって定期預金は「死にガネ」となってしまいます。おカネはあるのに、実際には使えないおカネになってしまいます。
だから、会社は定期預金をすべきではないのです。
普通預金がいいと知る
とはいえ、定期預金は「普通預金よりも金利が高い」と考える社長もいます。だから、普通預金にしておくくらいなら定期預金にしたほうがいい、というわけです。たしかに、日銀の利上げによって預金金利も上がっていますし、これからもまだ上がるかもしれません。
ですが、預金金利よりも高いであろうものが「自社の利益率」です。利益率を考えれば、いまの定期預金の金利など知れている、というのが「あるべき状態」だといえます。つまり、定期預金の金利に期待をしているようでは、営利企業としてはおかしいということです。
それでも、「おカネを余らせておく(普通預金にしておく)のはもったいない」とおもわれるかもしれません。それも違います。余らせているのではなく、備えているのです。
事業は山あり谷あり。いつなんどきおカネが必要になるかはわかりません。震災や風水害、新型コロナといった不測の事態も起こりえます。もちろん、本当に困ったときには定期預金も解約することはできるでしょう。
ですが、おカネが必要になるのは、谷のときばかりではなりません。たとえば、会社があたらしい事業をはじめるにはおカネも必要です。人を採用したり、モノを買ったりでおカネがかかります。そのときにおカネがなければ、成長のチャンスを逃しかねません。
ですから、いかなるときでも自由におカネを使えるようにするためには、定期預金ではなく普通預金がよいのです。
実質の預金を見える化
ところが、普通預金におカネがあるとおもうと、おカネを使ってしまうという社長がいます。いわゆる「カネづかいが粗い」社長です。それはそれで困ります。
だったら、融資を受けない銀行・融資を受ける予定がない銀行に定期預金をする、というのは1つの方法です。前述したとおり、融資を受けている銀行に定期預金をすれば、自由に解約がしづらいので、それは避けようということになります。
しかし、この方法は「さいごの手段」と心得ましょう。なぜなら、せっかくの預金を銀行融資には活かせないからです。もし、定期預金ではなく普通預金のままであれば、預金をあずけている銀行からは融資を受けやすくなります。
定期預金ではなくても、銀行にとっては担保に近いものですから、融資を検討するにあたっては安心材料になるのです。ところが、融資を受けない銀行に定期預金をすれば、その分の預金を融資の受けやすさに活かすことはできません。もったいないハナシです。
そこでおすすめするのは、「実質の預金」を見える化することです。ここでいう実質の預金とは、「預金残高−借入金残高」を指します。普通預金の残高が多いように見えても、借入分の預金はないもの(返済に充てなければならない)とする考え方です。
毎月末の「実質の預金」の額を計算して、線グラフをつくっておくとよいでしょう。実際の預金残高よりも実質の預金残高のほうが少ないことから、社長がおカネを使うのにも慎重になるはずです。
まとめ
日銀の利上げを受けて、世の中の金利が上昇しています。銀行から定期預金を勧められることもあるでしょう。では、会社は定期預金をするのがよいのか否か?
結論、会社は定期預金をすべきではありません。その理由や、定期預金をしない代わりにどうすればよいかについてお伝えしました。定期預金が、資金繰りの良し悪しや、融資の受けやすさに影響することを理解しておきましょう。うかつに定期預金はできなくなるはずです。