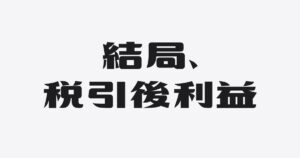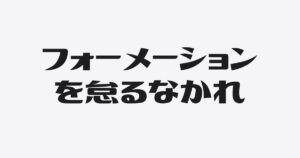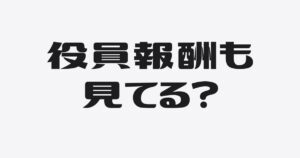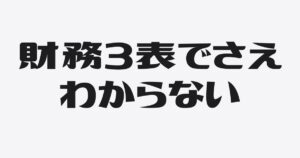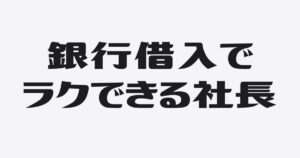事業計画づくりで大事なのに、多くの会社ができていないことがあります。すると、せっかくつくっても効果も半減です。というわけで、多くの会社ができていないことを押さえておきましょう。
「事業計画がある会社」は融資が受けやすい傾向にある
事業計画づくりで大事なのに、多くの会社ができていないことがあります。すると、せっかくつくった事業計画も効果は半減…どころか、場合によっては効果ゼロということにもなりかねません。
もったいぶらずに、まず結論を言うのであれば次のとおりです。
- 大風呂敷を広げない
- 行動計画も作成する
- 予実管理を継続する
これら3つが、多くの会社ができていないことに挙げられます。事業計画をつくってはいるのだけれど、これら3つのいずれかができていない、あるいはすべてができていない。そのようなケースをいくつも見聞きしてきました。
さて、あなたの会社ではいかがでしょうか?
ちなみに、僕はふだんから銀行融資の話をよくしています。関連して、「事業計画がある会社」は「事業計画がない会社」に比べると融資が受けやすい傾向にあることは、あらためてお伝えしておきたいところです。
ただし、それも上記3つができているかどうかによります。ただ事業計画をつくってさえいればよいわけではありません。上記3つのポイントを押さえていてはじめて、事業計画が銀行融資の受けやすさにつながるものと考えておきましょう。
そのあたりもふまえてこのあと、事業計画づくりで大事なのに多くの会社ができていないことを解説していきます。
事業計画づくりで大事なのにできていない会社が多いこと
中小企業において、事業計画がある会社は少数派だと言っていいでしょう。なかでも、このあと解説する3点をできている会社となると超少数派です。もちろん、良い意味での超少数派ですから、ぜひとも目指していきましょう。
結果として、銀行融資が受けやすくなることも前述したとおりです。
大風呂敷を広げない
事業計画づくりで大事なのにできていない会社が多いこと、1つめは「大風呂敷を広げない」です。
数値計画について、大風呂敷を広げてしまう会社は少なくありません。たとえば、実現が難しいほど大きな売上目標をつくってしまうのは典型例です。
社長の「売りたい」という希望や、「売れるはず」という自信も、けして悪いものではないのですが、そのまま計画にするのはやめておきましょう。繰り返しになりますが、大風呂敷を広げることになってしまうからです。
そこで、数値計画をつくるときには、まず「現状把握」からスタートします。具体的には、経営理念を言語化して、現状分析(SWOTや3Cなど)をして、それから経営戦略を定め、経営課題を抽出します。こういった「前提(現状把握)」があると、現実と計画の乖離は小さくなるものです。
このあたり、現状把握のための様式や詳しい考え方は、僕が執筆した書籍にまとめてあります。よろしければ、ご参考にどうぞ。
税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック
(リンク先はAmazonの商品ページです)
また、数値計画をつくったのであれば、過去の実績値と「繋がりで見る」ことが大切です。具体的にはまず、過去3〜5年くらいの実績値を横に並べます。たとえば、左から2023年3月決算期、2024年3月決算期、2025年3月決算期といった具合です。
次に、右へ向かって計画を並べます。3期の計画を立てるのであれば、2026年3月決算期、2027年3月決算期、2028年3月決算期といった具合です。そのうえで、数字を左から右に向かって、繋がりを見てみましょう。なだらかに繋がっているかどうかです。
大風呂敷を広げた場合、たとえば売上や利益は、過去(2023年〜2025年)の動きに対して、計画(2026年〜2028年)の急上昇が「異常値」として気付くことができるでしょう。折れ線グラフにしてみると、視覚的にも捉えやすくなるのでおすすめです。
過去と計画とが、なだらかに繋がっているかどうか。これは、実現可能性が高い計画をつくるうえでも大事なポイントになります。
行動計画も作成する
事業計画づくりで大事なのにできていない会社が多いこと、2つめは「行動計画も作成する」です。
さきほど、「現状把握」の話をしました。そのあと数値計画をつくりたいところですが、逸る気持ちを押さえてすべきことが、もうひとつあります。それが、行動計画の作成です。
僕が知る限り、数値計画はあるけど行動計画がない、という会社もけして少なくありません。ですが、「数値は行動の結果」だと考えると、おかしなことだと気づきます。行動計画がない、つまり、行動が決まっていないのに、どうして数値を決める(計画する)ことができるのか…?
よって、数値計画はあるけど行動計画がない場合、その数値計画は信用できない!ということになるわけです。とある銀行員の方からも、そのように聞いたことがあります。「計画の立てかたがわかっていないということなので、かえって心象が悪くなる」とも言っていました。
せっかくつくった事業計画がアダになるようでは、もったいないハナシです。そうならないためにも、事業計画のつくりかたを理解しておく必要があります。そうか…やっぱり勉強しようとおもわれたようでしたら、しつこいようですが前述した書籍もご参考にどうぞ。
税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック
(リンク先はAmazonの商品ページです)
上記の書籍では、行動計画の様式や、行動計画を検討するときの考え方や手順についても解説しています。いずれにせよ、数値計画と行動計画はセットです。行動計画なき数値計画は「絵に描いた餅」だと覚えておきましょう。
端的に言うのであれば、「誰が・何を・いつやるのか」を決めるのが行動計画です。「何を」やるのかは決めていても、「誰が」や「いつ」を決めていないケースも多いので気をつけましょう。「誰が」が欠ければ責任を追及できず、「いつ」が欠ければ実行タイミングを促すこともできません。
予実管理を継続する
事業計画づくりで大事なのにできていない会社が多いこと、3つめは「予実管理を継続する」です。
予実管理とは「予算(計画)」と「実績」とを管理することをいいます。ここでいう「管理」とはまず、計画と実績の対比です。行動計画・数値計画ともに、対比できるようにしておきましょう。毎月の試算表ができたタイミングで対比を行い、計画と実績のズレをなるべく早く把握します。
行動計画であれば、その月にやると決めていたことができたのかの確認です。できなかったのであれば、できなかった原因を特定し、どうするのかを検討します。
数値計画であれば、計画値に対して実績値はどうだったのか、つまりは「達成度」の確認です。達成度が低い項目については、原因の特定と対策を検討することになります。
と言えば、「あたりまえ」の話なのですが、そのあたりまえをやっていないケースもまた多いのです。つまり、計画をつくっておしまい、つくりっぱなしにしている会社は少なくありません。
この点、銀行にいちど提示した計画を、銀行は追い続けています。それこそ予実のズレがどうなっているか、銀行は確認をしているわけです。そのうえで、達成度が80%を割り込むようだと「計画が甘い、実行力がない」といった見方をされることになってしまいます。
すると、銀行に対しては逆効果となり、融資が受けいにくくなる可能性もあるでしょう。銀行対応について、事業計画を銀行に提示するのは有効ですが、中途半端をしていれば逆効果になることを忘れてはいけません。
これは、会社自身のためでもあります。計画をつくりっぱなしにしているようでは意味がなく、予実管理を継続できてこそ、経営改善が進み、会社の持続・成長が実現するというものです。
まとめ
事業計画づくりで大事なのに、多くの会社ができていないことがあります。すると、せっかくつくっても効果も半減です。というわけで、多くの会社ができていないことを押さえておきましょう。
- 大風呂敷を広げない
- 行動計画も作成する
- 予実管理を継続する
これら3つができていることで、銀行融資が受けやすくなるという効果が得られます。なぜなら、「実現可能性が高い計画をつくれる会社、その計画を管理・実行する能力がある会社」だと、銀行から見られるからです。
つまり、銀行融資を受ける・受けないにかかわらず、計画性がある「よい会社」だということであり、事業計画づくりをおすすめする理由でもあります。