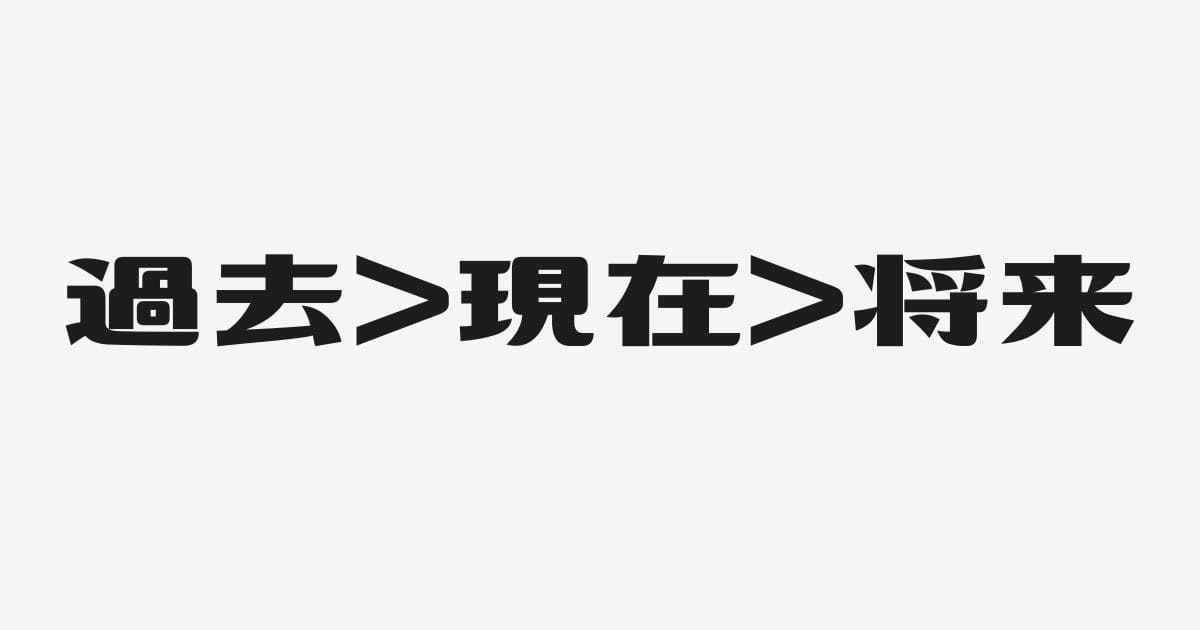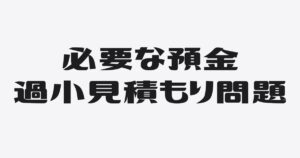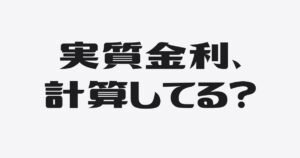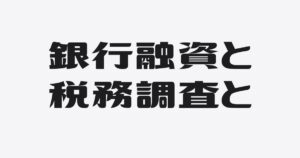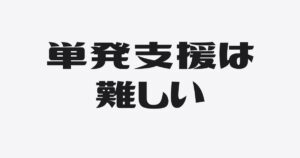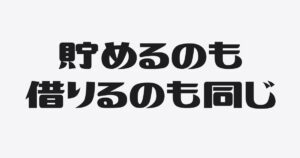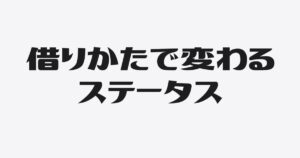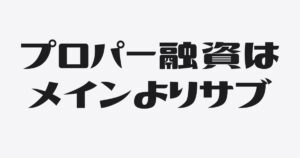会社の利益に対する銀行の見方として、覚えておきたいのが「過去の利益>現在の利益>将来の利益」です。これを社長が知らずにいると、「見当違いのアピール」をしかねません。
過去の利益を一番重視する
会社の利益に対する銀行の見方として、覚えておきたいのが「過去の利益>現在の利益>将来の利益」です。
つまり、銀行は「過去の利益」を一番重視して、次いで「現在の利益」、さいごに「将来の利益」という見方をしています。これを社長が知らずにいると、「見当違いのアピール」をしかねませんので注意が必要です。
いったい何のことを言っているのか?と、おもわれたかもしれませんが安心してください。このあと順を追って解説をしていきます。
そのまえに、そもそもの定義を確認しておきましょう。会社の利益を時系列で区分したものが、「過去の利益、現在の利益、将来の利益」です。これだと抽象的なので、もっと具体的にはこうなります。
- 過去の利益 → 決算書の利益
- 現在の利益 → 試算表の利益
- 将来の利益 → 計画書の利益
というわけで、前述の「過去の利益>現在の利益>将来の利益」にあてはめると、「決算書の利益>試算表の利益>計画書の利益」となります。つまり、銀行は「決算書の利益」を一番重視して、次いで「試算表の利益」、さいごに「計画書の利益」という見方をしているわけです。
よって、決算書の利益が大赤字にもかかわらず、社長が、試算表の利益や計画書の利益をアピールしたところで、銀行にはイマイチ響かない…ということが起こります。これが「見当違いのアピール」です。
このあと、この話をさらに深堀りしていきます。
過去の利益を重視する理由
ではまず、銀行が「過去の利益(決算書の利益)」を一番重視する理由から考えていきましょう。結論を先に言うのであれば、決算書の利益が一番信頼できる利益だからです。
言うまでもなく、決算書の利益というのは「決算」によって、「確定」しています。今後、変わることのない数字です。これに対して、「現在の利益」たる試算表の利益は「確定」していません。決算によって、変わる可能性を秘めています。事実、精度が低い試算表は少なくないのです。
いっぽうで、「将来の利益」たる計画書の利益はどうでしょう?経営計画書や事業計画書と呼ばれるものに示される利益です。これらは、会社がいかようにも描ける利益であり、やはり確定しておらず、実際の取引を直接反映していない点では「試算表の利益」よりも不確かだといえます。
以上をふまえた銀行の見方が、「過去の利益>現在の利益>将来の利益」です。よって、融資審査においては、「決算書の利益」を一番重視して、次いで「試算表の利益」、さいごに「計画書の利益」という見方になります。
ならば、「現在の利益」たる試算表の利益や、「将来の利益」たる計画書の利益はムダなのか?それらを銀行にアピールするのはムダなのか?といえば、そうではありません。むしろ逆です。
3つの利益には役割がある
時間軸で区分した3つの利益には、それぞれ役割があります。まず、「過去の利益」たる決算書の利益、その役割は「確定した業績」を示すことです。前述したとおり、今後、変わることのない数字として実績評価に役立ちます。
次に、「現在の利益」たる試算表の利益の役割は、「足元の業績」を示すことです。試算表は毎月くられるべきものであり、すると、決算がおわってからいままでの業績を評価するのに役立ちます。決算書は1年に1回しかつくられないことに比べれば、試算表はよりタイムリーに業績を把握できるのがメリットです。ただし、精度が低い試算表ほど、決算によって変わる可能性があることは前述しました。
さいごに、「将来の利益」たる計画書の利益の役割は、「将来の返済力」を示すことです。借りたおカネの返済原資は「利益」というのは、よくいわれるハナシです。ここで言う「利益」は、本来、「将来の利益」を指します。実際のところ、「過去の利益」で返済するのではなく、「将来の利益」で返済をするからです。言い換えると、過去の利益がいくらあろうと、将来の利益がなければ返済できなくなる、ということになります。
このように、3つの利益にはそれぞれ役割があるのです。よって、過去の利益だけが重要で、現在の利益や将来の利益がムダだということはありません。それぞれの利益の役割を理解して、それぞれの利益を、銀行にアピールすることが大切になります。
銀行にアピールをする方法
3つの利益をアピールするときに、覚えておくべき大事なことがあります。それが、「過去の利益>現在の利益>将来の利益」という銀行の見方です。これは、ここまで繰り返しお話をしてきました。では、具体的にどのようにアピールすればよいのか?
まずは、「過去の利益」をしっかりと出すことです。つまり、決算書の利益をしっかり黒字にすることです。決算で「確定」した利益が黒字であればこそ、不確かな試算表の利益であっても説得力が増しますし、いかようにも描ける計画書の利益もまた説得力が増すことになります。
逆に、決算の利益が大赤字となると、試算表の利益が黒字でも「決算では赤字になるのでは?」と見られがちであり、計画書の利益が黒字でも「絵に描いた餅なのでは?」と見られがちです。
試算表の利益に説得力がなくなれば、期中の借入は難しくなります。試算表で利益が出ていたとしても、銀行としては心配なので「決算書の利益を見てから」となるからです。
また、計画書の利益に説得力がなくなれば、計画書は融資審査の評価対象から外れてしまいます。すると、「将来の利益は不確定性が高い」として、評価上はマイナスです。
したがって、「現在の利益(試算表の利益)」や「将来の利益(計画書の利益)」を銀行にアピールするためには、「過去の利益(決算書の利益)」が欠かせないことを理解しておきましょう。本当はもっと利益が出せるのに、目先の納税を嫌って利益を減らすのは愚行だということです。
関連してもう1つ、気をつけることがあります。それは「粉飾決算」です。いくら決算書で利益が出ていても、それが粉飾されたものであれば、当然に銀行の信用を失います。結果、現在の利益も将来の利益も信用を失うこととなるので、銀行評価としては大打撃です。
現在の利益や将来の利益を、銀行評価に活かすためにも「過去の利益」たる決算書の利益が重要なのであり、その根底には「過去の利益>現在の利益>将来の利益」という銀行の見方があることを覚えておきましょう。
まとめ
会社の利益に対する銀行の見方として、覚えておきたいのが「過去の利益>現在の利益>将来の利益」です。言い換えると、「決算書の利益>試算表の利益>計画書の利益」です。これを社長が知らずにいると、「見当違いのアピール」をしかねません。
銀行に対して有効なアピールをするためには、まず「過去の利益」です。出せる利益をしっかりと出すこと。けして粉飾決算はしないこと。これにより、現在の利益と将来の利益もアピール材料として使えるようになります。
繰り返しですが、アピールには過去の利益が重要であること、そのうえで、現在の利益や将来の利益も忘れずにアピールしていきましょう(試算表を定期的に提示する、計画書を提示して進捗報告する)。融資がより受けやすくなるはずです。