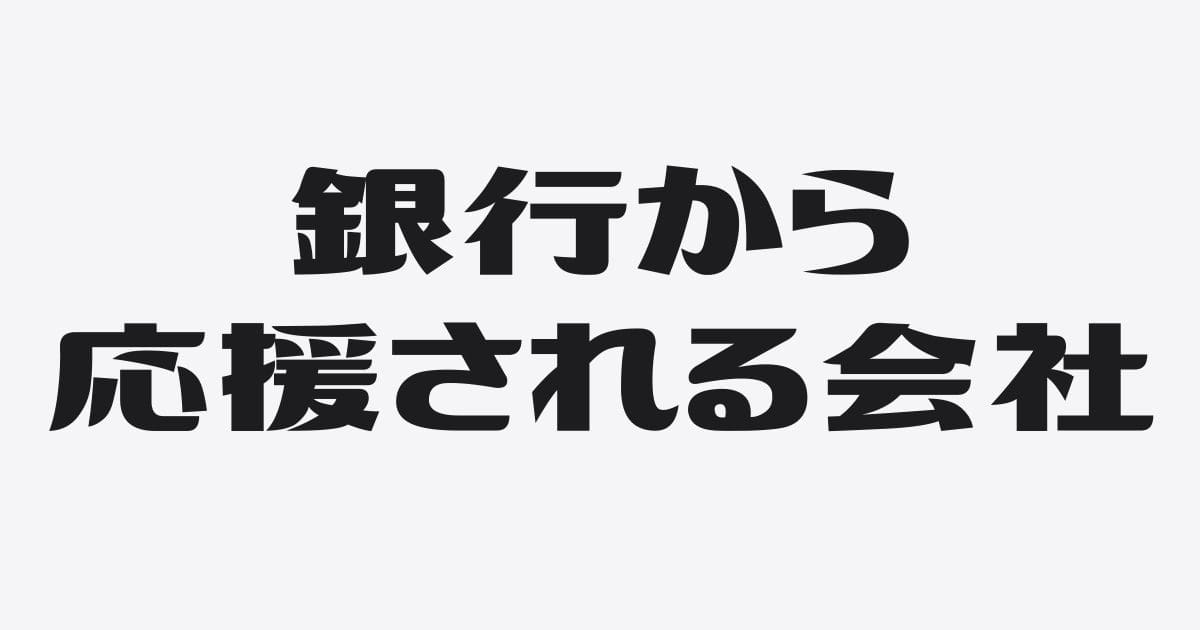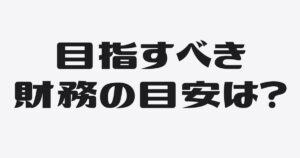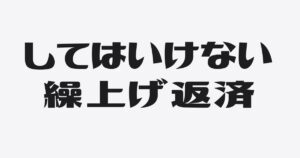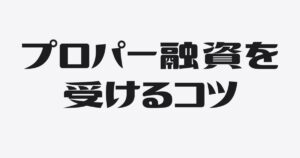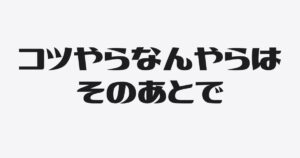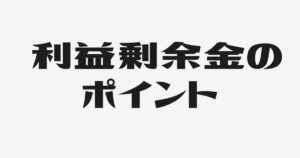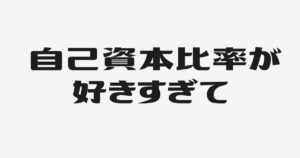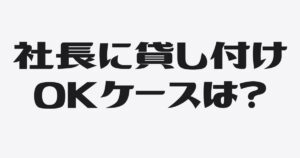銀行から応援される会社になれば、融資が受けやすくなり、資金繰りはより安定します。それを実現するために、会社が毎月すべき3つのことをお伝えします。
金利上昇が進むほど、融資は受けにくくなる傾向があります
銀行から応援される会社になれば、融資が受けやすくなり、資金繰りはより安定します。では、どうしたらそれを実現できるのか?結論、以下に挙げる「毎月すべき3つのこと」を実行することです。
- 試算表をつくる
- 資金繰り表をつくる
- 予実管理の結果を伝える
これらは「わりとあたりまえ」のようにおもえるかもしれません。ですが、「おもう」のと「できる」のとは別です。事実、上記3つのことをすべてできている会社を、僕はほとんど見たことがありません。さて、あなたの会社ではいかがでしょうか?
いまは「金利上昇」の過程にあります。世の中の金利とともに、融資金利も上がっているのです。すると、銀行による「選別」は強まります。ここで言う「選別」とは、銀行が応援する会社と応援しない会社との「線引き」です。
仮に融資金利が2倍になると、銀行は、これまでは2社に貸さなければいけなかったとしても、1社に貸せばすむことになります。だとすれば、2社のうち「よい会社」にだけ融資をすればよく、もう1社が「よくない会社」であれば、「もう融資をしない」という選択もあるわけです。
結果として、金利上昇が進むほど、銀行による選別が強まり、融資は受けにくくなる傾向があります。いままでは融資を受けられていた会社も、これからも融資を受けられるかはわかりません。
ゆえに、銀行から応援される「よい会社」になりましょう。そのために毎月すべきことは、前述しました。このあとは、それぞれを順番に解説していきます。
銀行から応援される会社になるために毎月すべき3つのこと
銀行から応援される「よい会社」になりましょう、と言いました。まずは、きちんと利益を出せる会社になることです。銀行にとって「利益=返済原資」ですから、利益が多いほど「よい会社」だと見られます。
そのうえで、毎月すべき3つのことができていると、「よい会社」だとの見方はより強まることでしょう。そうして銀行から応援される会社になれば、融資が受けやすくなり、資金繰りはより安定します。毎月すべきことを、きちんと実行していきましょう。
試算表をつくる
銀行から応援される会社になるために毎月すべき3つのこと、1つめは「試算表をつくる」です。
試算表をつくるなど、あたりまえすぎるほどあたりまえのハナシでしょう。ですが、試算表を「毎月つくる」ことができていない会社もあります。数か月にいちどだけとか。試算表は毎月つくってこそです。それにより社長は、自社の状態をタイムリーに把握できるようになります。
また、試算表を毎月つくっていたとしても、「速くつくる」ことができていない会社はあるものです。前月分の試算表が1か月も2か月もたってからつくられるのでは、意味がありません。言うまでもなく、社長が経営判断の材料とするには「情報が古すぎる」からです。
それから、もうひとつ。「精度が高い」試算表をつくれない会社もあります。端的に言えば、つくりかたが雑だということです。具体例を挙げると、棚卸をしていない、売上や仕入を発生主義で計上していない、減価償却費を計上していないなど。いずれも決算のときに、大きく利益が変動する要因となります。それでは社長が、経営判断を見誤るというものです。
したがって、試算表をつくるとは、「毎月つくる、速くつくる、精度が高い」の3点を満たしている必要があります。あらためて確認をしてみましょう。自社だけでは実現が難しいようであれば、顧問税理士に相談するのがおすすめです。
資金繰り表をつくる
銀行から応援される会社になるために毎月すべき3つのこと、2つめは「資金繰り表をつくる」です。
試算表をつくることはできていても、資金繰り表まではつくれていない会社は少なくありません。ここで言う資金繰り表とは、向こう1年先までの「毎月の収入・支出」と「毎月末の預金残高」がわかることを指します。
したがって、資金繰り表をつくれるということは、1年先までの資金繰りの目処が立っているということであり、これは銀行にとっての安心材料になります。また、資金繰り状況が「可視化」されることも、銀行にとっては有益な情報であり、資金繰り表が好まれる理由のひとつです。
逆に、資金繰り表をつくれない会社は、資金繰りが場当たり的になります。つまり、おカネが実際に不足してから慌てて融資を受けようとする…といったことが起こりがちです。これを銀行は嫌います。おカネがない人におカネを貸したくない(返済してもらえないから)のは、銀行も同じです。よって、資金繰り表がない場合、ある場合に比べて融資は受けにくくなります。
ちなみに、試算表をつくるには、仕訳の知識や会計ソフトが必要です。いっぽうで、資金繰り表をつくるのにそれらは要りません。必要なのは、入出金の情報であり、エクセルでつくることができます(手書きでもOK)。ですから、資金繰り表はぜひ、自社内でつくれるようになりましょう。
具体的なつくりかたについては、僕が執筆をしました本に掲載しています。よろしければ、ご参考にどうぞ(タイトルは「税理士必携」ですが、税理士でなくてもお役立ていただける内容です)。
税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック
(リンク先はAmazonの商品ページです)
予実管理の結果を伝える
銀行から応援される会社になるために毎月すべき3つのこと、3つめは「予実管理の結果を伝える」です。
これまでの試算表、資金繰り表に比べると、難易度は一気に上がります。ですが、社長が経営を考えるうえで、「予実管理」は欠かせないものだというのが僕の考えです。つまり、予実管理とはそもそも、銀行融資を受けるためのものではなく、社長自身・会社自身のためでもあります。
そのうえで、ここで言う予実管理とは、予算(計画)と実績との対比です。もう少し具体的にいうと、期首に立てた毎月々の予算にもとづき、実際の実績はどうだったのかを比較検証します。対象は、行動計画と数値計画です。
その月にやると決めていた行動はできたのか、行動の成果はどうだったのか。そして、その月の予算数値(売上や費用、利益など)に対して実績値(試算表の数字)との差はどうだったのか、なぜ差が生じたのか。といったことを、毎月検討することになります。
このとき、予算と実績の「違い(差)」や、それが生じた「原因」を把握するのはもちろんですが、加えて、「改善策・解決策」まで検討することが大切です。たとえば、売上が予算に未達だったのであれば、原因にもとづき「どう対応するのか」まで決めるということです。
そこまでできたら、予実管理の結果を銀行にも定期的(四半期にいちどていど)に伝えるようにしましょう。銀行からは「管理能力が高い会社」との見方になるため、心象がよくなります。また、予実管理によって「決算見込み」の精度も高まるため、銀行にとっては有益な情報です。
なお、行動計画や数値計画のつくりかたについても、前述した本に掲載しています。
まとめ
銀行から応援される会社になれば、融資が受けやすくなり、資金繰りはより安定します。それを実現するために、会社が毎月すべき3つのことをお伝えしました。
- 試算表をつくる
- 資金繰り表をつくる
- 予実管理の結果を伝える
これら3つのことをすべてできている会社は、現状、きわめて少数派です。少数派であるからこそ、他社との違いになり、自社が「よい会社」であることのアピールになります。銀行から応援される、よい会社を目指しましょう。