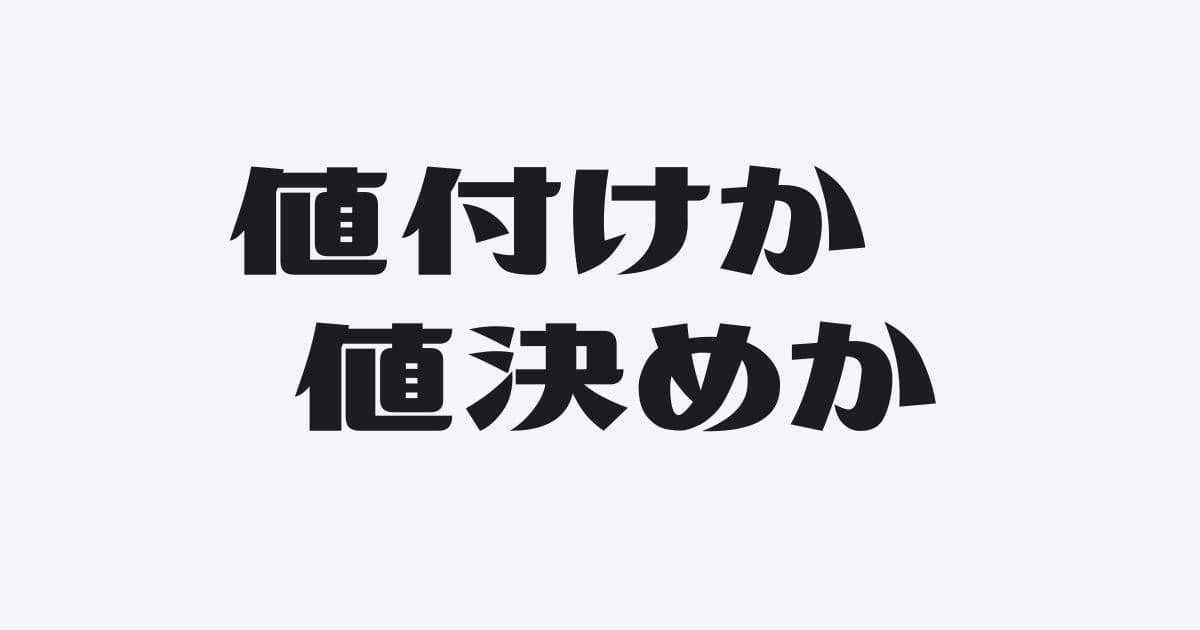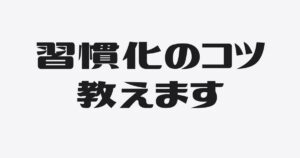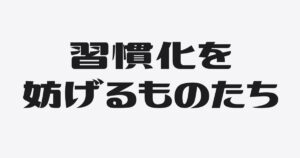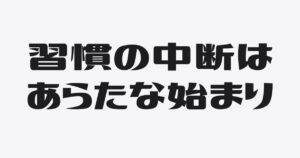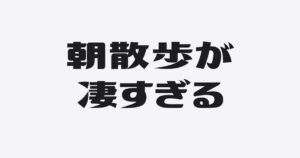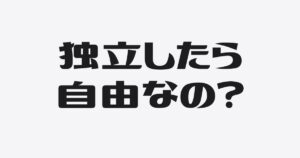似たような言葉に、「値付け」と「値決め」があります。ですが、どちらを使うかで、その行為が持つ意味合いは、実は大きく変わってくるのではないか…?というお話をします。
「値付け」と「値決め」の違い
「この商品(サービス)、いくらにしようか?」
事業に関わっていれば、この問いに何度も向き合うことになるでしょう。とくに、独立してじぶんで事業を営むようになると、価格をじぶんで決める機会がグッと増えます。
そして、いつも僕らを悩ませるのが「いくらにするか?」という、まさに値段の決定です。
この点、「値付け」と「値決め」と似たような言葉がありますが、どちらを使うかで、その行為が持つ意味合いは、実は大きく変わってくるのではないか…?僕はそう考えています。
パッと見は同じような言葉ですが、この2つには単なるニュアンスの違いを超えて、そもそもの「役割の違い」、もっと言えば行為に込められた「重さの違い」があるようにおもうのですね。
「値付け」とは作業としての「軽い」価格
たとえば、スーパーの惣菜コーナーで売られている「おにぎり」を想像してみましょう。
厨房でつくられ、パック詰めされて、そして「148円」と印字されたシールがペタッと貼られる。この一連の流れ、とくにさいごのシールを貼る行為が、僕がイメージする「値付け」です。
これは、どちらかというと作業的な意味合いが強く、どこか「軽い」印象があるのですがどうでしょうか? そこには深い思考や葛藤よりも、決められたルールにしたがってラベルを貼るような、いうなれば「オペレーショナル」な響きを感じます。
「値決め」とは意思決定としての「重い」価格
いっぽうで、そのおにぎりが「なぜ148円なのか?」を決定した人がいるはずです。
- 原材料費はいくらか?
- 人件費やその他のコストは?
- どれくらいの利益を見込んでいるのか?
- 競合となる他のおにぎりやパンの価格は?
- この価格でお客さまに価値を感じてもらえるか?
こういった様々な要素を考えて、経営的な判断として「148円」という価格を最終決定する。これが、僕がイメージする「値決め」です。ここには、単なる作業を超えた「意思決定」があって、経営者の判断や戦略が反映された「重み」がともないます。
つまり、「値付け」が現場レベルでの作業的な言葉だとすれば、「値決め」は経営層や意思決定層が使う、覚悟や哲学をともなう言葉だと言えるのではないでしょうか?
あなたの価格は「値付け」か「値決め」か
ここで、じぶんの商品やサービスの価格を思い浮かべてみましょう。その価格は、どのような理由で決められたものでしょうか?
- 同業他社の価格をリサーチして、大体これくらいが相場だから
- なんとなく、これくらいの金額なら払ってもらえそうだから
- あまり安すぎても怪しまれるし、高すぎても売れないだろうから
こうした理由だけで価格を決めているとしたら、それは深い思考をともなう「値決め」ではなく、どちらかというと周囲の状況に合わせた受け身的な「値付け」に近い行為なのかもしれません。
もちろん、市場の相場を参考にすることは大切です。でも、それだけで価格を決めてしまうと、そこに「じぶんの意思」や「事業としての哲学」が入り込む余地はなくなってしまいます。周りに合わせただけの、ある意味で「思考停止した価格設定」になってしまう危険性すらあります。
価格はメッセージであり宣言である
いまさらですが、価格というのは、じぶんが提供する商品やサービスの価値を表現するための、ものすごく重要な要素です。
というよりも、価格だけが「言葉(文章)を使わずに価値を伝えられる唯一の判断材料」だ、とさえ僕は思っています。
なぜなら、お客さまはその値段を見た瞬間に、無意識のうちに「この商品は、たぶんこれくらいのレベル(品質)のものだろう」と推測したり、判断したりしているからです。
たとえば、あるコンサルティングサービスが「1時間3万円」だとします。 これを見て「高い!」と感じるか「妥当だ」と感じるかは人それぞれですが、価格が高いほど「きっと、この人は相当なプロフェッショナルなんだろうな」とか、「それだけの価値を提供してくれるんだろうな」という期待や信頼感が自然と生まれたりもするでしょう。
逆に「1時間3,000円」と聞けば、「気軽に頼めそうだな」と感じるいっぽうで、「クオリティは大丈夫なのかな?」「専門性はどこまであるんだろう?」といった印象を持つ人はいるかもしれません。
つまり、価格はそれ自体が、提供者からの無言のメッセージなのです。 そう考えると、「価格を決める」という行為は、「じぶんはこの世界(市場)で、どういう立ち位置で勝負するのか」を宣言することだともいえます。ここに「値決め」の重さがあるのではないでしょうか?
経営とは値決めである by松下幸之助
ここで、経営の神さま・松下幸之助さんの有名な言葉が思い出されます。
「経営とは、値決めである。」
この言葉を聞いて、ハッとした方も少なくないはずです。 経営には、資金繰り、人材育成、マーケティング、営業、開発、組織づくりなど、実にいろいろな要素があります。でも、突き詰めていくと、「最終的に、いくらで売るのか?」という一点に、多くの要素が集約されていくと言っても過言ではありません。
そして「いくらで売るか?」は、「じぶんがどれくらいの価値を提供できる(したい)のか?」と「どれくらいの利益を確保したいのか?」という、2つのせめぎ合いのなかで決まるものでもあります。
そう考えると、価格を決めるという行為は、まさに「経営のすべてを反映する最終判断」であって、その決定にいつも「重い」責任がともなうわけです。
値決めは「覚悟」を決める作業
僕自身も、新しいサービスの価格を決めるときは悩みます。
最初に「これくらいかな?」とおもった価格に対して、「本当にそれでいいのか?」「安易に決めていないか?」と何度も自問自答します。
「もっと安くすれば、たくさんの人に買ってもらえるかもしれない。でも、それは本当に僕が届けたい価値に見合っているだろうか? 安売りすることで、かえって価値が低く見られてしまわないだろうか?」
「逆に、もっと高く設定することで、自分自身が『この金額に見合う価値を提供するぞ!』と、より高いレベルでの覚悟ができるんじゃないか?」
などと、迷いに迷ったり。 そして最終的には、「うん、この価格が、いまのじぶんの意思であり、お客さまへの責任であり、そして事業を続けていく覚悟だ」と、腹落ちする金額に着地させるようにしています。
ですから、僕にとって「値決め」とは「覚悟を決める作業」でもあるのです。単なる計算や相場調査だけではない、この「重さ」こそが「値決め」の本質だと感じています。
その覚悟がないままに、なんとなく値段を決めてしまう(=値付けしてしまう)と、あとになって「やっぱり、もっと高くしておけばよかった…」「思ったよりも安く見られてる気がする…」といったモヤモヤが、ずっと心に残り続けることにもなるでしょう。
逆に、じぶん自身が納得できる「値決め」ができていれば、お客さまから価格について質問されたときも堂々と説明できますし、「えぇ、この金額にはこれだけの価値がしっかりと含まれています」と自信を持って伝えることができるはずです。
「値付け」から「値決め」へ
いまの時代、インターネットで検索すれば、類似の商品やサービスはいくらでも見つかります。価格もカンタンに比較されてしまいます(ゆえに、安易な「値付け」に流されやすい側面もありますね)。
しかし、そんな時代だからこそ、他者の価格に合わせただけの「軽い値付け」で終わらせるのではなく、「じぶんはこの価値を提供する。だからこの価格なんだ」という、意思と覚悟のこもった「重い値決め」をすることが重要だと考えています。
その価格には、じぶんがこれまでの経験や積み重ねてきた実績、商品やサービスに込めた想い、そして、お客さまに対する真摯な気持ちが現れるはずです。 それは単なる数字ではなく、「じぶん自身の哲学や覚悟を映し出す鏡」だと言ってもいいかもしれません。
というわけで、いま、じぶんが提供している商品やサービスのなかから、何か1つでもよいので選んでみて、あらためてその価格をじっくりと見つめ直してみるのはどうでしょう?
- その価格設定は、いつの間にか単なる作業としての「値付け」になっていないか
- 他者に合わせただけ、あるいは、なんとなくで決めた「無難で軽い数字」になっていないか
- じぶんの信念やこだわり、お客さまに届けたい価値への想いという「重み」は、価格に表現されているのか
松下幸之助さんいわく、「値決め」は経営そのものです。 価格は、言葉(文章)を要しない強力なメッセージであり、じぶんの覚悟の表明です。
いちど決めた価格もあらためて見直して、考え続けること。それ自体が、じぶんの事業(商売)を再構成・再構築して、あらたなステージへ進むきっかけになるかもしれません。
単なる値札貼りとしての「値付け」から、じぶんの意思と覚悟を込めた「値決め」へ。そんな視点を持って、じぶんの商品やサービスの価格と向き合っていきましょう。
まとめ
似たような言葉に、「値付け」と「値決め」があります。ですが、どちらを使うかで、その行為が持つ意味合いは、実は大きく変わってくるのではないか…?というお話をしました。
過去の偉人も言うように、「使う言葉が行動を変える」ということはあるものです。「値付け」と「値決め」、意図的に使い分けてみるのもよいでしょう。
すると、単なる値札貼りとしての「値付け」から、じぶんの意思と覚悟を込めた「値決め」という行動に変えてゆくきっかけになるものと考えます。