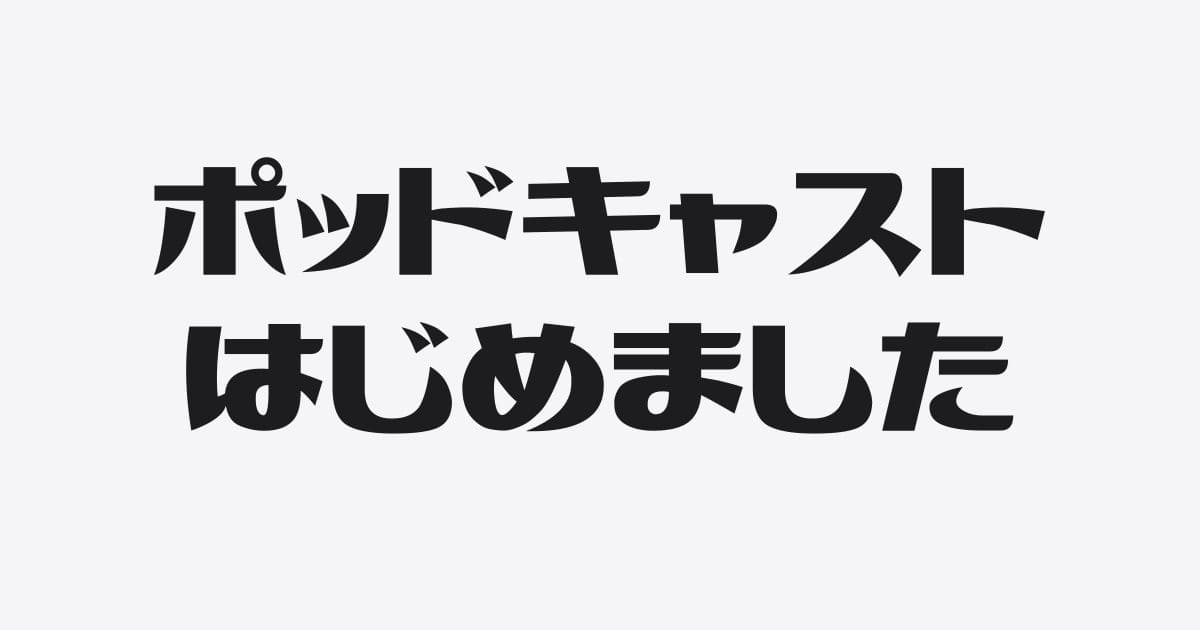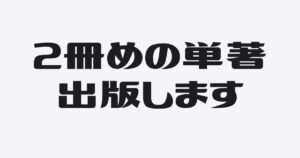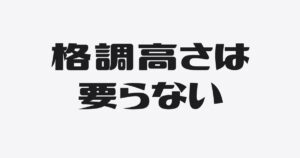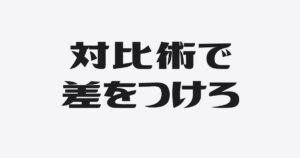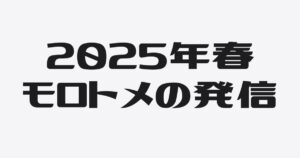発信に関する、あらたなた挑戦として「ビデオポッドキャスト」をはじめました。はじめるにいたった経緯や、舞台裏なんかも交えつつお話をしてみます。
ビデオポッドキャストをはじめました
いまや情報発信のやりかたは、本当にいろいろです。
少し前ならブログが主流だったのが、いまやSNSは当たり前、YouTubeのような動画もすっかり定着して、さらには音声配信も身近でお手軽にはじめられるものとなりました。 選択肢がたくさんありすぎて、どれがじぶんに合っているのか、どれから手をつけるべきか、迷ってしまうくらいです。
僕自身もこれまで、このブログだったり、YouTubeチャンネルだったり、あとは stand.fm(スタンドエフエム)での音声配信だったり、いろいろとかじってきました。それぞれによさがあって、特性も違います。
そのうえで今回、またひとつあらたににチャレンジしてみることにしました。それが「ポッドキャスト」です。もしかしたら「いまさら?」とおもわれるかもですが、僕にとってはあらたな挑戦、となります。
なぜいまポッドキャストなのか? その理由とか
なぜいま、ポッドキャストなのか?なんでこのタイミングでポッドキャストなのか?そうもおもわれるかもしれません。その理由はいくつかあって。ひとつは、YouTubeをはじめたときに、「もうちょっと早く手をつけておけばなぁ…」と感じた反省があります。
はじめたのは2020年4月。そのころにはもう、たくさんの人が参入していて、「あと1年、いや半年でも早ければ、また違った景色が見えていたのかも」などとおもうことがあるわけです。タイミングって大事だよなぁ、という反省です。
そんななか、最近耳にするようになったのが「ビデオポッドキャスト」という発信スタイルでした。音声だけでなく、映像もいっしょに配信するスタイルです。海外、とくにアメリカなどではもはや主流であり、人気番組もたくさんあると聞きます。その波が、日本にも来るのでは?などと言われたり。
しかし、まぁ、アラフィフおじさんのひとり語りや、その姿を映し出す映像に、どれだけのニーズがあるものか? という疑念は、僕のなかにも渦巻いているわけですが(笑)
それはともかく、この先、日本でビデオポッドキャストがホントに流行るのかはわかりません。一過性のブームでおわる可能性だって、じゅうぶんあります。でも、YouTubeでの「あー、乗り遅れた…」みたいな経験をもう繰り返したくはないのですね。
だから今回は、「あまりウダウダ考えすぎずに、まずは試してみよう!」と、そういうスタンスです。「走りながら考える」ではないですけど、なるべく早めにいちどやってみて、その感触をたしかめてみたかったということになります。
やってみて、もし「これは違うな」とか「もっとこうしたい」とかあれば、そこから軌道修正すればいいですし。そんな感じで、まずは一歩を踏み出してみた次第です。
はじめてみてどうか? 舞台裏をすこしだけ
とはいえ、じゃあ意気揚々とスムーズにスタートできたのか?というと、これがそうでもありません。
わたくしごとですが、すこし前にインフルエンザを患いまして、インフルエンザ自体は治ったものの、その後はやっかいな空咳だけがしつこく残りました。
ちょっと長く話していると(とくに、マイクに向かって意識して声を出すと)コンコンと咳が出やすい状況が続いたのです。これが、ポッドキャストの基本スタイルである「編集なし一発撮り」には、なかなかの難敵となりました。
YouTubeであれば、咳が出たところだけ編集でカットすれば済む話なのですけど。そういう意味では、「ある種のごまかし」が効かないビデオポッドキャストには、特有の難しさがあるとはいえます。 でも、「咳が完全に治まるまで待つ!」なんて言ってたら、いつになるかわからない。これ以上は待ちたくない!という気持ちもあって、なんとか気合で(?)収録をおえて、先日(2025年4月9日)の公開にいたりました。
実際にやってみると、「意外となんとかなるものだ」ということであり、「おもっていたより手軽にはじめられる」というのが、偽らざる正直な感想です。
音声配信は、かれこれ300日近く毎日配信しているので、ひとりで話すことに抵抗はありませんし、ビデオポッドキャストの場合、YouTubeほどの編集を要しないのが何よりラクチンでした。
道具もそれほど必要ない
ビデオポッドキャストの手軽さという点で、必要な道具についても触れておきます。結論として、それほど多くのものは要りませんし、初期投資としてもそれほど大きなものではありません。ご参考までに、僕が使っているものは次のとおりです。
マイク
もともとYouTube用として買った「Blue Yeti」というコンデンサーマイクを使いました。単一指向性の機能があるので、マイクの正面からの音をしっかり拾って、まわりの余計な音を拾いにくいのが特徴です。これを1,000円くらいのアダプターでiPhoneに繋ぎました。スマホのマイクに比べると、だいぶクリアに録れるので予算に余裕があればおすすめです。
カメラ
iPhoneのインカメラでじゅうぶんでした。僕が使っているiPhone16・無印には「シネマティックモード」っていう機能があって、これを使うと、人物にピントが合って背景がいい感じにボケてくれます。プロっぽい映像とはいかないまでも、それなりに見栄えがするので、今回は仕事部屋の本棚の前でこのモードを使って撮影してみました(YouTubeはグリーンバック合成なので、だいぶ雰囲気が違います)。
スタンド類
iPhoneをちょうどいい高さと角度に固定するための、かんたんな卓上スタンド(1,000円ちょっとでした)と、マイクを口元近くに持ってくるためのアームスタンドはあらたに買いました。アームスタンドは数千円くらいのリーズナブルなものでしたが、これがあると、なんとなく「ラジオDJっぽい」というか、「配信してる感」が出るみたいなので。そういう見た目も、ビデオポッドキャストには大事らしいです。
編集関連
これが一番、YouTubeとの違いを感じたところ。ポッドキャストは作り込まれた感じよりも、「生感」とか「ライブ感」を出すために「ほぼ編集なし」というのがスタンダードらしいです。僕もそれに倣って、収録したものをそのまま、頭とお尻にすこしだけBGMをのせるかどうかくらいにしています。
テロップを入れたり、細かくカットしたりする必要がないのは、正直かなりラクです。これなら無料の編集アプリとかでも、じゅうぶんに対応できます。最小限ならスマホ1台あれば、マイクもカメラも編集もなんとかなるでしょう。そういう意味でのハードルが低いのも魅力かもしれません。
大切なのは、機材を揃えることよりも「まず、やってみる」という、その一歩を踏み出すことだとおもいます。
どんな番組?古典・銀行融資ラジオ
さて、ここまで引っ張ってきましたが、僕がはじめるポッドキャストの番組名は、「古典・銀行融資ラジオ」です。
「古典・銀行融資ラジオ」
(リンク先はSpotifyのポッドキャストです)
タイトルだけ聞くと、「なんか難しそう…」「堅いハナシ?」とおもわれるかもしれません。たしかにそういう側面もあるのですが、コンセプトとしては以下のような感じです。
===
AIがどんどん進化して、いろんなことが自動化されていく時代。銀行融資のあり方や、銀行員の役割も、これからすこしずつ変わっていくのかもしれません。もしかすると、僕らが慣れ親しんできた銀行融資は、いつか「古典」と呼ばれるようになるのかも…。
でも、たとえ時代が変わっても、融資に関する基本的な知識とか、銀行が物事をどういう視点で見ているか(いわゆる銀行視点)っていうのは、中小企業の経営にとって、これからもきっと役に立つはずだと、僕は信じています。資金繰りは経営の根幹ですからね。
この番組では、そんな銀行融資の歴史的背景とか、銀行内部の考え方、審査の現場では実際どんなことが見られているのか、といったリアルな視点なんかを、できるだけわかりやすい言葉で、かみ砕いてお届けできればとおもっています。
「おカネのことではできるだけ悩みたくない」と考えている社長さんや、その社長を日々支えている税理士さん、あるいは金融機関との付き合い方を学びたいと思っている方に向けて、「財務の教養」として、気軽に聴いてもらえるような番組を目指します。
===
ちなみに、番組の「顔」にもなるカバーアート(ポッドキャストアプリなんかで表示される、サムネイル画像みたいなやつ)は、現在、大学でデザインを勉強中の娘に頼んで、つくってもらいました。何度かやり取りして、なかなかイイ感じにしあげてくれたと、親バカながら満足しています(笑)。
まとめに代えて
実際に収録・配信してみて感じたのは、「音声+映像」だからこそ伝わるなにか、言い換えるとパーソナリティみたいなものがある、ということです。
文章だけだと、どうしてもカチッとした印象になりがちですが、声のトーンとか、話すスピード、ちょっとした言い淀みなんかにまで、その人らしさがにじみ出ます。文章では伝えきれないニュアンスや、話しているときの「間(ま)」みたいなものを含めてです。 また、じぶん自身のことでいえば、話すことで考えが整理されたり、人にわかりやすく伝えるための構成力が自然と鍛えられたりするメリットもあります。リスナー側からすれば、耳から情報を得られるので、通勤中や家事をしながら、運転しながら、といった「ながら聴き」ができるのも、音声コンテンツの強みでしょう。
スマホひとつあれば、録音も配信も可能ですし、その手軽さも魅力です。もし、なにか情報発信をしてみたいけれど、文章を書くのは苦手だなとか、顔出しの動画はちょっと…と感じている方がいたら、選択肢のひとつとして「音声配信」を試してみるのは、けっこうアリかもしれません。僕も stand.fmでは、毎日配信してますし、これなら顔出ししなくても大丈夫です。
というわけで、今回は僕のあらたなチャレンジである「ポッドキャスト」について、はじめるにいたった経緯や、舞台裏なんかも交えつつお話をしてみました。
ビデオポッドキャストのフンイキを知る意味でも、「古典・銀行融資ラジオ」をご覧いただけたら嬉しいですし、フォローやコメントなどをいただけましたらなおうれしいです。
「古典・銀行融資ラジオ」
(リンク先はSpotifyのポッドキャストです)