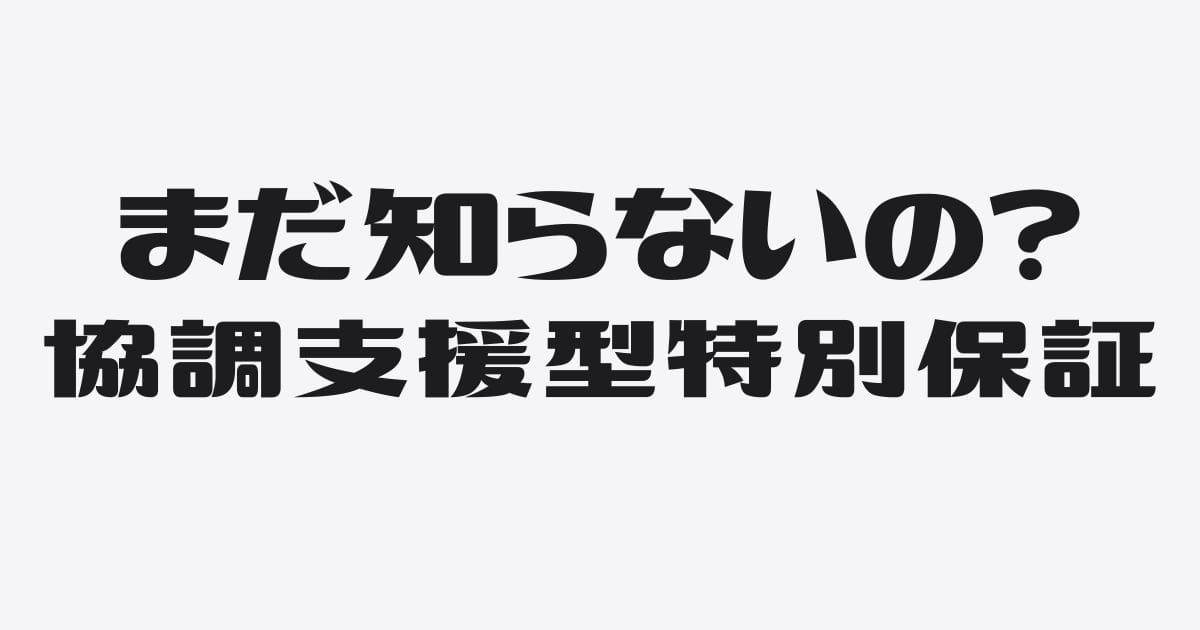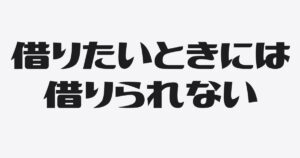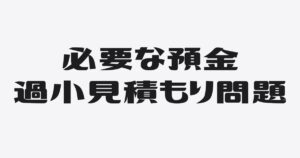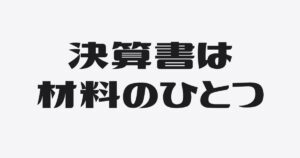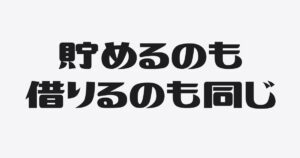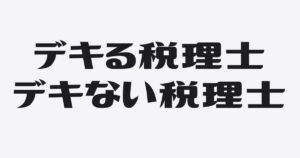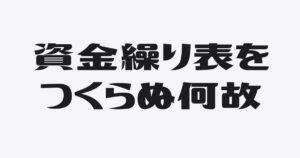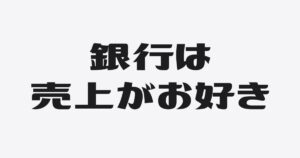2025年3月に始まった「協調支援型特別保証制度」について、制度の内容や、制度を利用する際のメリット・デメリットなどをまとめます。資金調達力を高めるチャンスとなる注目の制度です。
銀行に相談してみる価値がある
2025年3月に始まった、「協調支援型特別保証制度」はご存知でしょうか?中小企業の資金繰りをサポートするあらたな信用保証制度です。
民間金融機関のプロパー融資(信用保証協会の保証がない融資)と、信用保証協会(以下、保証協会)の保証付き融資を組み合わせるしくみ(=協調)で、会社の借入コストを軽減しつつ、銀行と保証協会が一体となって融資先の資金繰りを支援します。
資金調達力を高めるチャンスとなる制度であり、「まずは取引銀行に相談してみる価値がある」というのが結論であり、僕の意見です。
2028年3月まで期間限定の制度であり、早ければ早いほどメリットが大きい(保証料の補助が多い)ので、そういう意味でもまずは相談してみるのがよいでしょう。
利用できる会社と主な要件
この保証制度を利用できるのは、次のいずれかの条件を満たす会社です。
- 銀行が融資額の1割以上をプロパー融資として実行すること(保証付き融資の実行と原則同時、プロパー融資の融資期間は12か月以上)
- 例として、銀行が300万円プロパー融資してくれれば、あわせて保証付き融資3,000万円を借りられるイメージです
- 「1割以上のプロパー融資」がポイントで、銀行が最低10%のリスク(銀行にとってプロパー融資はリスク)を取ってくれれば、従来よりも大きな金額の融資を受けやすくなる効果があるわけです
- 経営行動計画の策定・実行・報告を行うこと(銀行の支援を受けつつ、自社で計画を作成し実行、進捗報告まで行う)
- 具体的には、自社の経営課題を整理したうえで、今後の経営改善や成長戦略の計画をつくります。その後は計画に沿って行動し、進捗を定期的に銀行へ報告します。銀行は計画策定やフォローに協力してくれることになっていて、計画に基づいた継続支援(いわゆる伴走支援)を受けられます
- この要件で利用する場合も、後述する「保証料の補助」は受けられますが、補助率は一律であり少し抑えめになっています(保証料補助は常に1/4相当)
以上のどちらかの要件を満たせば、「協調支援型特別保証制度」が利用可能です。要件1は、銀行側に1割のプロパー融資を求めるため、自社にとって「良好な関係の銀行があるか?」がカギとなります。要件2は、計画策定の手間がかかりますが、自社単独でも取り組める道です。
自社の状況に合わせて、銀行と相談していずれかを選ぶことになります。
制度内容(保証額・期間・保証料など)
本制度の内容を、以下にまとめます。
保証限度額
最大2億8,000万円(組合は4億8,000万円まで)。一般的な信用保証の普通保証枠(2.8億円)と同水準の大きな枠が設定されています。必要に応じて既存債務の借換えにも利用可能です(運転資金・設備資金ともに対象)。
保証期間
一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は最長10年以内です(据置期間は運転資金で最大1年、設備資金では最大3年まで可能)。よって、比較的長期の設備資金にも対応できます。
信用保証料率
表面上は年0.45%~1.90%ですが、本制度では国の補助により保証料の一部が減額されます。補助率は利用時期や前述の要件によって異なり、以下のとおりです。
- 要件1の場合(銀行がプロパー融資1割): 制度開始初年度がもっとも手厚く、保証料の1/2を国が補助します(~2026年3月末申込分)。翌年度(~2027年3月末申込分)は1/3補助、最終年度(〜2028年3月末申込分)は1/4補助
- 要件2の場合(経営行動計画の策定): 補助率は一律で1/4に固定されています。実質的な保証料率は 約0.34%~1.43%程度 と算定されます。要件1に比べると補助率は抑えめですが、それでも通常よりは負担が軽減されます
融資利率
金利は「銀行所定の利率」となります。制度上の特別金利はなく、各銀行との交渉になります。保証協会の審査で企業の信用度(保証区分)が決まると、銀行はそれをふまえて金利を設定します。複数の金融機関から借入れできる場合は、できるだけ有利な金利を提示してくれる銀行を選ぶとよいでしょう。
保証割合
責任共有制度の対象で、原則として保証協会が80%を保証し、銀行が20%のリスクを負担します。通常の信用保証付き融資と同じく、銀行と保証協会でリスクを分担する形です(セーフティネット4号など100%保証の例外とは異なります)。
その他
担保や第三者保証人については、必要に応じて 従来どおり求められる場合があります。基本的には信用保証協会の通常の方針にしたがって、法人代表者以外の保証人は原則不要ですが、ケースにより担保提供など条件が付く可能性はあります(詳細は銀行と保証協会の審査しだい)。
協調支援型特別保証制度のメリット
本制度を活用することで、中小企業には次のような メリットがあります。これは、会社が本制度に注目すべき理由でもありますので、しっかりと押さえておきましょう。
保証料負担の軽減
前述のとおり、保証料の1/2~1/4を国が補助してくれるので、これまでよりも借入コストを軽減できます。通常は数十万円~数百万円にもなり得る保証料が減る分、資金繰りに余裕が生まれるのはメリットでしょう。
より多くの資金調達が可能
銀行がいちぶプロパー融資をしてくれるのであれば、その10倍の金額まで保証付き融資を利用できます。銀行単独(プロパー融資)では難しかった大口の融資も、本制度を利用すれば保証協会のバックアップ込みで実現しやすくなるということです。
柔軟な資金用途と長期資金対応
運転資金から設備資金まで幅広く利用できて、返済期間も最長10年と長期設定が可能なので、資金使途に応じた柔軟な借入ができます。据置期間も最大3年取れるため、大型の設備投資を行う際には初期の返済負担を減らすことも可能です。
3年のあいだ利用できる
2028年3月までの期間限定措置であり、期間中の早期利用ほど保証料補助は手厚いです。この期間限定のメリットを活かして、コロナ後の経営立て直しや成長投資に向けた資金を、無理のない条件で確保できるチャンスと捉えることができます。
協調支援型特別保証制度のデメリット
いっぽうで、本制度を利用するにあたって押さえておきたいデメリットもあります。全体としては、本制度の難易度に関する内容です。
銀行の協力が不可欠
要件1の場合にはプロパー融資の実行、要件2の場合には経営計画への協力とフォローが銀行に求められます。そのため、「取引銀行が前向きかどうか」が制度利用のカギになります。
プロパー融資を出し渋る銀行だと要件1は使えません。また、経営計画支援に消極的な銀行だと要件2も難しいものがあります。ゆえに、自社に「メインバンク」と呼べる銀行がない場合には、本制度が使いにくい状況はあるかもしれません。
とはいえ、制度は3年のあいだ使えます。いまからでも銀行との関係構築に努めれば間に合うという考え方もあるでしょう。事業内容や計画を丁寧に説明していくことで、プロパー融資に応じてもらえる関係をつくることができます。本制度をきっかけに、銀行との付き合い方を見直すのもおすすめです。
計画策定・実行の手間
要件2を利用する場合、自社で詳細な経営計画をつくり、実行・報告する必要があります。計画策定には時間と労力がかかるうえに、銀行や専門家との打ち合わせも増えるでしょう。また、計画どおりの実行・報告を求められることから、事後フォローの負担も生じます。
計画未達の場合のペナルティは明示されていないものの、報告を怠れば銀行からの信用を損なうことは間違いありません。自社の管理体制を整えて、計画策定・管理のための時間を確保する必要があります。
融資審査は依然必要
保証協会の保証が付くとはいえ、融資を実行する銀行側でも所定の審査があります。業績が極端に悪化している、税金や借入の滞納があるなどの場合、保証付きでも融資不可となるケースはありえます。
とく本制度は「成長支援」の色合いが濃いため、著しく経営不振の会社は別制度(経営改善サポート保証など)を案内される可能性があります。「保証があるから大丈夫」とは油断せず、銀行に提出する決算書や事業計画の内容を改善する努力は欠かせません。
保証料・金利コストは残る
保証料補助があるとはいえ、いちぶ保証料の負担と銀行利息の支払いが発生します。ゼロゼロ融資(全額保証・実質無利子無担保)などと比べると、コストはかかる制度です。
借入額が大きければ総支払額も多くなるので、融資実行前に返済計画をシミュレーションして、「返済にムリがないか」を検討することが大切なのは、他の借入と変わりません。
2028年3月までの期限付き
本制度は時限措置であり、2028年3月末で終了予定です。それ以降はこの優遇措置がなくなる可能性があります。したがって、設備投資や事業拡大の計画がある場合は、期限内の早めの活用を検討するのが賢明です。期限ギリギリになると、駆け込み需要で手続きが混み合うこともありますから、余裕を持って準備・申込みを行うようにしましょう。
銀行の姿勢と現時点での動き
国は、本制度の活用について銀行に要請を行っています。事実、金融庁からも「令和7年3月に新たに開始した『協調支援型特別保証制度』を積極的に活用し、プロパー融資を含む金融仲介機能の発揮を通じて事業者の幅広い資金需要に応えていくこと」との要請が出されています。
よって、銀行としても本制度を前向きに取り扱うのが基本姿勢です。
また、銀行にとってもメリットがあります。本制度を使えば、国の保証料補助により企業の負担が減るため融資提案がしやすくなる点がひとつ。さらには、保証協会がリスクの大半(80%)を負担してくれるうえ、自行も一部プロパー融資を実行すれば取引深耕にもつながります。
コロナ禍で痛んだ取引先企業の立て直しや、あらたな資金ニーズに応える手段として、銀行にとっても有用な商品だといえるでしょう。
とはいえ、具体的な対応は銀行ごとに異なるものと考えられます。積極的にプロパー融資を出してでも融資を増やそうと考える銀行もあれば、1割のリスクも惜しんで要件2が中心の提案しかしない銀行もあるかもしれません。計画のフォローも面倒であれば、要件2さえ提案しないこともありえます。
自社のメインバンクが制度の利用に消極的な場合でも、他行が協力的であれば乗り換えや融資シェアの見直しも一考でしょう。長い目で見たときに、リスクや手間を惜しみすぎる銀行が、自社の「良き支援者」にはなりえないとの考え方です。
本制度を活用すべき会社の特徴
以上をふまえて、協調支援型特別保証制度の利用に向いているのは次のような会社です。
事業拡大・投資意欲がある
新規事業や設備投資、人材採用など、積極的な計画を持つ会社は、本制度は成長戦略を後押しする趣旨が強いため、「攻め」の資金需要としてマッチします。逆に、将来の展望が描けないまま運転資金のつなぎだけを繰り返すようなケースには向きません(別途リスケや再生計画の支援策が検討されます)。
銀行と信頼関係ができている
ふだんから取引のある銀行があり、一定の信頼関係ができている会社は、要件1を満たしやすくなります。具体的には、直近の業績が黒字かつ純資産がプラスで、銀行から「プロパーで貸してもよい」と見られる信用度があるような状態です。
また、ひとつの目安として、売上高が1億円以上あるような会社は、比較的活用しやすいと考えます。いっぽうで、売上1億円未満の会社でも、経営・財務内容が堅実であり、銀行とのコミュニケーションを重ねていけば利用は可能です。
財務改善・計画策定に前向き
自社の課題を分析し、経営計画を立てる意欲がある会社も適しています。計画実行とモニタリングを通じて業績向上を図れるので、経営管理体制を強化したい会社にとって、本制度は一石二鳥です。
税理士や中小企業診断士など、専門家のサポートを受けながら計画策定に取り組めば、銀行の見る目が変わることもあります。「計画なんてつくったことがない…」という場合でも、この機会にチャレンジすする価値があるということです。
現状で返済負担が懸念される
コロナ禍でゼロゼロ融資や保証付き融資を受け、これから本格的な返済期を迎える会社にとっても、本制度は選択肢になります。既存借入を本制度で借り換えて返済負担を平準化することも可能です。
とくに、長期運転資金に切り替えられれば月々の元本返済額を減らせます。ただし、根本的な業績改善策がないと単なる延命になりかねないので、借り換えとあわせて経営行動計画による抜本策を講じる前提で活用することを強くおすすめします。
プロパー融資の足がかりが欲しい
プロパー融資は保証料が不要で担保・保証人も柔軟であり、使い勝手のよい借入ですが、中小企業にとって一朝一夕に多額を引き出すのは困難です。この点、協調支援型特別保証制度は、そのプロパー融資をいちぶ取り入れるハイブリッド型です。
銀行からすると、保証協会の信用補完がある分だけプロパー融資もしやすく、会社からすると少額のプロパー融資を狙える可能性があります。
そこでまずは本制度を利用してみて、将来的に信用力がつけば、いずれはプロパー融資の拡大も見えてくるので、本制度をプロパー融資への橋渡しとして考えるのもよいでしょう。
実際、売上高が10億円を超えるような会社では、保証付き融資よりプロパー融資中心になる傾向もありますが、売上規模1億円から数億円規模の会社であれば本制度を活用して、プロパー融資割合を増やし、銀行からの評価を高めていくことが期待できます。
銀行に相談する際のポイント
本制度を利用するか検討する段階では、早めに取引銀行に相談してみるのがおすすめです。以下、銀行に相談する際のポイントを整理します。
制度の取扱状況を確認する
「協調支援型特別保証制度を利用したいと考えていますが、御行では取り扱っていますか?」と尋ねてみましょう。たいていの銀行内では既に周知されていますが、担当者レベルでは把握していない場合もあるため、具体的な制度名を挙げて確認します。
自社が満たせる要件の確認
要件1(プロパー融資1割)と要件2(経営行動計画の策定)のどちらになりそうか、銀行の見方を聞きます。「自社の場合、プロパー融資1割以上の条件は可能でしょうか?」あるいは「計画策定が必要な場合、どのようなサポートをいただけますか?」といった質問をしてみましょう。
これは、銀行の積極性を確認するのと同時に、銀行が稟議を通しやすい形を探る意図があります。
必要書類と手続きの確認
保証付き融資の申込みには通常の融資書類に加え、保証協会向けの申込書類や本制度独自の書類(申込人資格要件申告書兼誓約書、経営行動計画書など)があります。これらをいつまでに用意すべきか確認しましょう。
とくに、経営行動計画書は要件2の場合に必須となります。過去の決算書や試算表をはじめ、その他事業に関わる資料なども求められるので、チェックリストを早めに銀行から取り寄せて準備を始めることが大切です。
融資条件の打診と試算
金利や返済期間についても事前に銀行とすり合わせておきましょう。「金利はおおよそ何%になりそうか」「何年返済が適当か」などを質問してみます。加えて、「保証料率はどのくらいになりそうですか?(保証協会の審査結果によります)」と聞けば、銀行経由で保証協会に事前相談してもらえる場合もあります。
自社の格付けによって保証料率が変わるため、おおよその区分を教えてもらえればコスト計算がしやすくなります。保証料補助後の実質負担額や利息額を試算して、月々の返済と合わせて資金繰り計画に組み込みましょう。
スケジュールの確認
申込みから融資実行までの大まかな流れと所要期間も確認しましょう。保証協会の審査は通常だと数週間ほどかかるため、余裕を持ったスケジュールを立てます。たとえば、「〇月中に保証協会申請、〇月の第〇週に実行予定」といった目安を銀行と共有しておくと安心です。
これらのポイントをふまえ、銀行には遠慮せず質問しましょう。ここでイヤな顔をされたり、親身な対応がえられないのであれば、本制度の利用以前に、その銀行との関係性を見直す必要があります。
経営計画の共有
要件2の場合はもちろん、要件1であっても事業計画の概要を銀行に説明できるようにしておくと好印象です。資金使途と借入による効果(売上増やコスト削減、人手不足解消など)を数字で示しましょう。
銀行担当者が稟議を上げる際の材料にもなるため、事業計画書や資金計画書をつくって渡すのも効果的です。疑問があれば、「専門家に計画作成を手伝ってもらいたいのですが、紹介してもらえますか?」などと尋ねるのもよいでしょう。銀行経由で支援機関を紹介してもらえることもあります。
まとめ 〜まずは銀行に相談を
協調支援型特別保証制度は、中小企業の資金繰りと成長支援のために国が用意した後押し策です。
保証料補助というかたちで国も支援してくれるので、会社側の負担も軽減され、銀行も巻き込んだかたちでプロパー融資と同時に保証付き融資を受けられる点は注目に値します。
とくに、コロナ禍や物価高騰で苦労しつつも「これから巻き返したい」「攻めの投資をしたい」と考える会社にとっては、有効な資金調達手段となるはずです。
まずは、取引銀行に本制度の活用について相談してみましょう。 制度の詳細は、保証協会や中小企業庁の公開情報にも載っていますが、最終的には銀行を通じて申請する必要があるからです。銀行と二人三脚で準備を進め、本制度を上手に活用することがポイントになります。