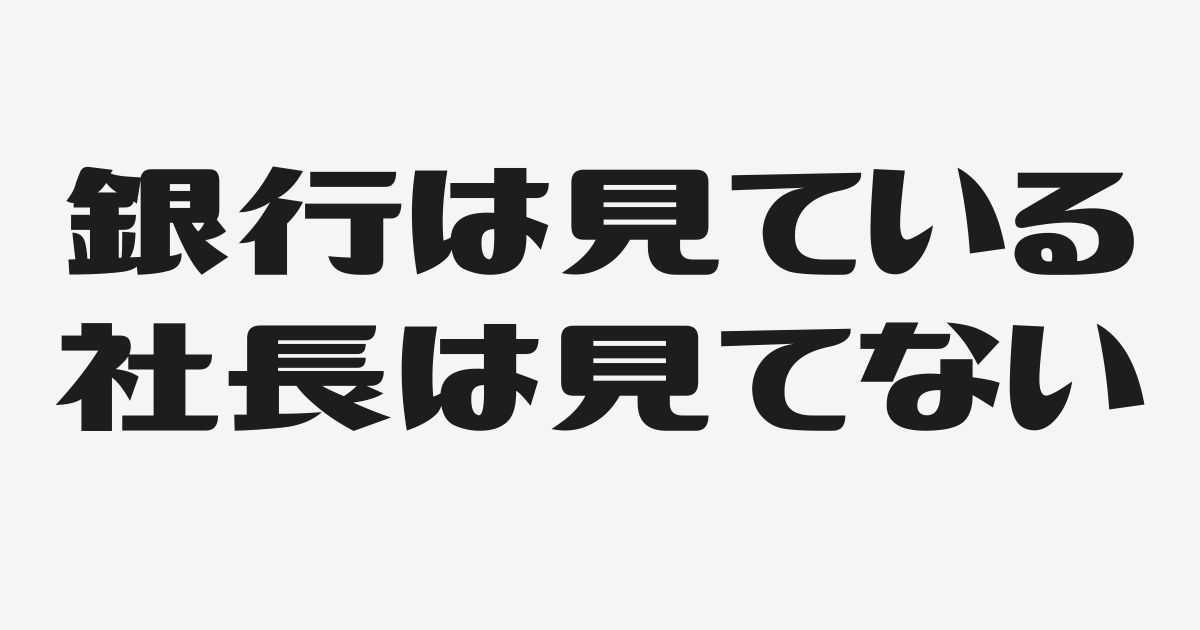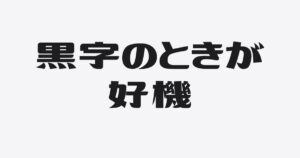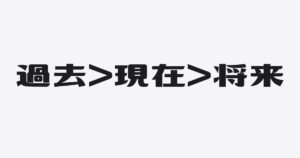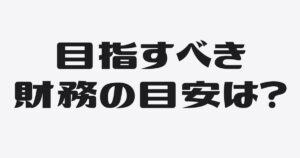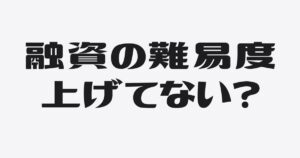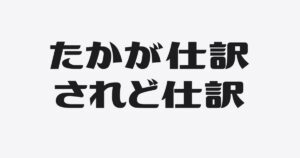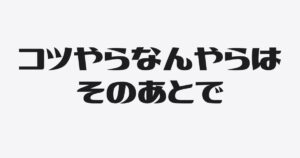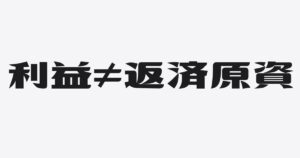銀行は見ているのに社長が見ていない書類があります。すると、社長が思いも寄らないところで、融資が受けにくくなるのが問題です。3つの書類を例として、解説していきます。
税理士に任せて社長自身は確認していない
会社が銀行から融資を受けるにあたり、銀行に提出する書類はいろいろあります。最たるものが決算書です。ひとくちに決算書といっても、なかにはいろいろな書類が含まれています。
そのうえで、銀行はよく見ているのに社長があまり見ていない書類はあるものです。すると、社長が思いも寄らないところで、融資が受けにくい原因が生じている(書類のなかに問題がある)といったことも起こりえます。というか、実際にしばしば見かける状況です。
銀行融資の相談をいただき、参考にそれらの書類を拝見すると問題がある。ところが、その点を社長に尋ねても「心当たりがない」と言われる。書類の作成は税理士に任せているので、社長自身は確認をしていない、といった状況はけして少なくありません。
というわけで、銀行は見ているのに社長が見ていない書類について、3つほど例を挙げてお話をします。具体的には次のとおりです。
- 貸借対照表
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
これらについて、「そう言えば、あまり見ていないかも」というのであれば、このあとの話も確認しておきましょう。書類のうち、銀行はどこを見ているのか、どこが問題になりうるのかをお伝えしていきます。
銀行は見ているのに社長が見ていない書類
銀行はよく見ているのに社長があまり見ていない書類はいろいろありますが、なかでもとりわけ重要で、とりわけ見られていないことが多い書類を取り上げます。いずれも決算書一式(法人税申告書一式)のなかに含まれる書類です。これを機会に確認してみましょう。
貸借対照表
銀行は見ているのに社長が見ていない書類、1つめは「貸借対照表」です。
決算書は大きく2つ、損益計算書と貸借対照表とに分かれます。このうち損益計算書は、多くの社長が目にしていることでしょう。売上や利益が記載されていて、興味や馴染みがあるものだからです。
いっぽうの貸借対照表は、損益計算書ほどには見られることがない書類です。損益計算書ほど見やすい内容ではなく、どことなくとっつきにくさがあります。実際、「自社の純資産はいくらくらいですか?」と聞かれて、即答できる社長はそれほど多くありません。ふだん見ていないのです。
ちなみに、社長が貸借対照表を見ていないのは、税理士があまり説明をしないからでもあるでしょう。貸借対照表よりも損益計算書のほうが説明しやすいからです。
ところが、銀行は損益計算書ばかりでなく貸借対照表をよく見ています。損益計算書よりも貸借対照表を重視していると言っても過言ではありません。ではなぜ、銀行は貸借対照表を重視するのか?
一番の理由を挙げるとすれば、「預金残高」です。貸したおカネを返済してもらうためには「おカネ」が要るのであって、そのおカネがいくらあるのかは貸借対照表を見ればわかります。
さらに、純資産の金額を見れば、その会社が「過去にわたって」どれだけの利益を積み上げてきたかがわかります。「その期かぎり」の利益しかわからない損益計算書とは対象的です。
ほかにも貸借対照表には、粉飾決算を見破る要素が多い、ムダ使いしているかどうかがわかるなど、銀行にとって(本質的には社長にとっても)見るべきものがいろいろあります。ゆえに、銀行は貸借対照表をよく見ているのであり、社長もまた注目するようにしましょう。
勘定科目内訳明細書
銀行は見ているのに社長が見ていない書類、2つめは「勘定科目内訳明細書」です。
決算書に付属する書類のひとつであり、決算書に記載されている勘定科目について、その明細をあきらかにする役割があります。たとえば、預金の内訳明細書を見れば、どの銀行のどの支店にいくらの預金があるかが一目瞭然です。銀行が関心を持つのは当然でしょう。
同じように、借入の内訳明細書を見れば、やはりどの銀行からいくら借りているかがわかります。銀行は自行にたくさん預けてほしいし、自行がたくさん貸したいのですから、内訳明細書は有用な情報になるのです。
また、売掛金の内訳明細書を見れば、得意先の情報(信用に足る会社か)を得られますし、前期以前の内訳明細書と比較をすることで、滞留債権(回収できそうもない売掛金)のあたりもつけられます。というように、銀行は内訳明細書を有効活用しているのです。
ところが、内訳明細書を見ていない社長はいます。まったく見たことがない社長もいるでしょう。つまりは、すべてが税理士任せです。すると、「対税務署」で問題はなくても、「対銀行」として問題が生じることはあります。
例をひとつ挙げるなら、さきほどの売掛金です。銀行は滞留債権と見れば、その分の金額を資産から除外して考えます。資産が減れば評価は下がりますし、資産よりも負債が大きくなれば「債務超過」として、融資が極端に受けにくくなるのです。
よって、貸借対照表の数字は「資産>負債」でも、銀行の評価上は「資産<負債」になることもあります。このとき、社長が貸借対照表の数字だけしか見ていなければ、銀行の評価に気づけません。なんでウチは融資が受けられないんだ?ということになってしまいます。
法人事業概況説明書
銀行は見ているのに社長が見ていない書類、3つめは「法人事業概況説明書」です。
決算書一式(法人税申告書一式)のうち、末尾のほうに位置していることが多い書類かとおもいます。内容としては、文字どおり「事業概況を説明する」ものです。
たとえば、自社の業種や事業内容、本支店の状況、社員数、帳簿の状況などが記載されます。また、数字に関する情報として、損益計算書や貸借対照表のダイジェストがあったり、月ごとの売上高や仕入高、人件費なども記載されます。
このうち、銀行によく見られているものといえば、月ごとの売上高でしょう。これがあれば、会社が毎月試算表を銀行に見せていなくても、銀行は月ごとの売上高を知ることができます。
銀行にとって、月ごとの売上高は重要な情報の1つです。12か月の売上高を見て、季節変動を把握することができますし、売上が増加傾向か減少傾向かのあたりもつけられます。
そのうえで、社長が気をつけたいのが「試算表の水増し」です。期中に銀行に試算表を提出する場合、「どうせ試算表だから」と売上高を水増しするケースがあります(決算書では水増し分を修正する)。
このとき、銀行が試算表の売上高と、法人事業概況説明書とを突き合わせることで、試算表に水増しがあったことはバレるわけです。結果として、銀行からは「この会社の試算表はアテにならない」と見られ、試算表を信じてもらえなくなると、期中の借入が難しくなることがあります。
いっぽうで、法人事業概況説明書の記載によっては、銀行に対していろいろとアピールできることもありますから、そういった視点で社長も法人事業概況説明書を確認できるのがよいでしょう。
前述した勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書について、詳しい見方などは書籍にまとめています。よろしければご参考にどうぞ(タイトルは「税理士必携」となっていますが、税理士でなくてもお役立ていただける内容です)。
税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック
(リンク先はAmazonの商品ページです)
まとめ
銀行は見ているのに社長が確認していない書類がいくつかあります。これらの書類を疎かにすると、融資が受けにくくなる可能性があります。
特に「貸借対照表」「勘定科目内訳明細書」「法人事業概況説明書」の3つは、銀行が重視しているにも関わらず、社長があまり確認していないことが多いです。
社長自身がこれらの書類をしっかり把握することで、融資の可否に大きな影響を与えることを理解し、定期的に確認しておくことが重要になります。