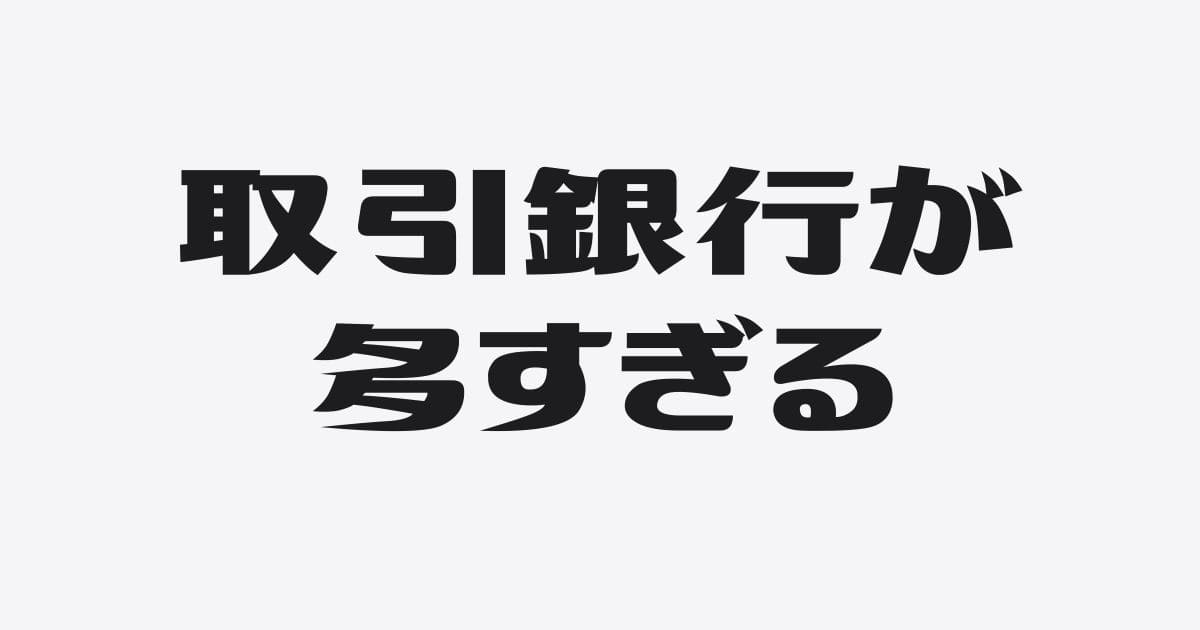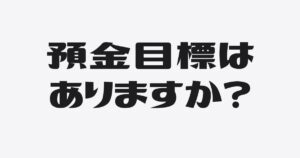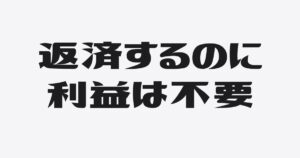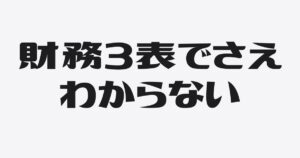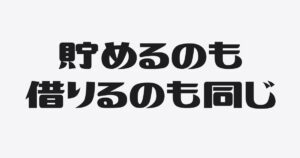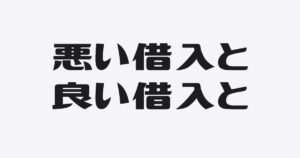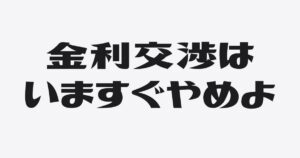「付き合う銀行は多いほうがよい」という思い込みには気をつけましょう。取引銀行が多すぎることには損がありますので、その理由をお伝えしていきます。
選択肢が多いと逆効果にもなりうる
社長とお話ししていると、こんなふうに考えている方がいらっしゃいます。
「たくさんの銀行と付き合っていれば、いざというとき、どこかが助けてくれるだろう」
たしかに、選択肢が多いのはよいことのようにおもえます。しかし、銀行融資に関して言えば、「数打てば当たる」という考え方は、むしろ損を招くことも多いのです。
取引銀行が多すぎることには、見過ごせないデメリットがあります。せっかく築いた銀行との関係が、逆効果になってしまうことすらあるわけです。
そこで今回は、取引銀行が多すぎると損をする3つの理由と、その対策について解説します。「付き合う銀行は多いほうがよい」という思い込み、この記事を読んで捨てていきましょう。それができずにると、いずれ後悔することになるかもしれません。
理由1/借入金額が少額で分散する
取引銀行が多いということは、1行あたりの借入金額はどうしても少額になります。たとえば、総額1億円の借入が必要な会社が、5つの銀行と付き合っていれば、単純計算で1行あたり2,000万円です。
さて、銀行にとって、この2,000万円という融資額はどう映るのでしょうか?
ハッキリ言ってしまえば、「儲からない客」です。銀行も商売ですから、融資をして利息収入を得ることで成り立っています。融資額が少なければ当然、利息収入も少ないわけで。手間ばかりかかって儲からない取引先、というのが銀行の本音でしょう。すると、どうなるか?
まず、金利が高止まりしやすくなります。銀行としては、少ない利息収入でも利益を確保するために、金利を下げにくいのです。また、銀行担当者の訪問頻度が減ったり、有益な情報提供が手薄になったりします。「儲からない客」に、わざわざ時間とコストをかけたくないからです。
まさに「他人事」のような扱いとなり、これでは良好な関係性を築くのは難しいでしょう。
僕が見てきたなかで、銀行が「この会社は大事にしたい、積極的に支援したい」と本腰を入れる融資額の目安があります。あくまで僕の感覚ですが、信用金庫なら3,000万円、地方銀行なら1億円、メガバンクなら5億円くらいの「プロパー融資(保証協会保証なしの融資)」があると、銀行の見る目は変わってきます。これくらいのボリュームがあれば、銀行にとっても重要な取引先となり、真剣に向き合ってくれる可能性が高まるのです。
取引銀行が多く、借入額が分散していると、どの銀行からも「そこそこの付き合い」としか見なされません。その結果、いざというとき、本当に困ったとき(業績が悪化したときなど)に、どの銀行からも真剣な支援を受けられないという、悲しい事態を招きかねないのです。そうならないように、深く付き合える銀行をつくることを考えましょう。
そのためには、取引銀行の数を増やしすぎないことです。
理由2/銀行に関わる時間が増える
取引銀行が多いということは、それだけ銀行対応に費やす時間と手間が増えるということです。
年にいちどの決算報告を例にとります。決算書ができたら、取引銀行すべてに報告に行くのが基本です。その際には、決算書一式だけでなく、最新の試算表、資金繰り表、借入金一覧表といった書類も準備して、会社の状況や今後の見通しを説明する必要があります。取引銀行が5行あれば、これを5回繰り返すわけです。訪問・説明の時間は、単純に5倍になります。
決算報告だけではありません。銀行ごとに、定期的な試算表提出や業況報告をするのも大切なことです。融資の相談をするときはもちろん、ふだんから「お付き合い」として情報提供が物を言います。だとすれば、銀行の数が多いほど、銀行に出向いて説明する時間が必要になるわけです。
言うまでもありませんが、社長の時間は有限です。そして、会社にとってもっとも重要な経営資源のひとつが、社長の時間でもあります。その貴重な時間を、取引銀行が多いがために、過剰な銀行対応に奪われていては、本末転倒だと言ってよいでしょう。
社長が本来やるべき仕事は、目先の銀行対応ではなく、会社の明日を考え、そのために今日、手を打つこと、つまりは「経営」です。銀行対応に忙殺されて、経営がおろそかになってしまっては、元も子もありません。非効率な銀行対応は、会社の成長機会をも奪いかねないのです。
理由3/リスケ時の調整がタイヘン
考えたくはないことですが、会社の業績が悪化し、資金繰りが厳しくなり、借入金の返済が困難になる状況も想定しておくべきです。その際のさいごの手段が「リスケジュール(返済猶予)」です。
このリスケジュール、原則として「すべての取引銀行の同意」が必要になります。「A銀行は返済を待ってもらうけど、B銀行にはいままでどおり返済する」といった不平等は許されません。「全銀行一律同条件」がリスケジュールの鉄則なのです。
想像してみてください。もしも取引銀行が5行あったらどうでしょうか?
すべての銀行に事情を説明し、経営改善計画を示し、返済猶予のお願いをして、同意を取り付けなければなりません。各銀行の担当者はもちろん、その上司である融資課長、さらに支店長など、多くの関係者を説得する必要があります。
ただでさえ厳しい状況のなかで、この調整作業は困難を極めるでしょう。銀行ごとに会社の状況に対する見方や、リスケジュールに対する方針・温度差も異なりますから、交渉が難航するリスクも高くなります。時間ばかりが過ぎていき、その間にも会社の資金はどんどん流出していく…
1行でも反対にあえば、リスケジュールは成立しません。調整に手間取っているうちに、資金が底をつき、再生のチャンスを失ってしまいます。そんな最悪の事態も、取引銀行が多すぎると現実味を帯びてくるのです。
いざというときに、迅速かつズムーズに再生への道筋をつけるためにも、ふだんから取引銀行の数は適切に絞っておくべきなのです。
まとめ
取引銀行が多いほうが安心だとする考え方には、注意が必要です。むしろ、多すぎる銀行付き合いにはデメリットがあります。
- 銀行から他人事扱いされ、いざというときに見放されるリスク
- 社長の貴重な時間を奪い、経営に集中できなくなるリスク
- リスケジュールが難航し、再生のチャンスを逃すリスク
といった、深刻なデメリットを招く可能性があるのです。
では、何行くらいが適切なのか?会社の規模にもよりますが、たとえば、年商3億円未満の会社であれば、民間金融機関は2〜3行、それに日本政策金融公庫を加えたていどで十分だというのが僕の考えです。やみくもに数を増やす必要はありません。
もし、「ウチは取引銀行が多すぎるかも」と感じたなら、関係を見直してみましょう。ただし、「すぐに縁を切る」必要は必ずしもありません。融資取引は特定の銀行に絞り込み、関係を見直す銀行には既存借入の返済を続けて、自然に関係性を整理するのがおすすめです。
「数はチカラ」にあらず。銀行融資においては、多すぎる取引銀行はリスクにさえなりえます。自社にとって本当に必要な銀行はどこなのかを見極め、それぞれの銀行と「質の高い」関係を築くこと。それこそが、安定した資金繰りと会社の成長につながる道です。