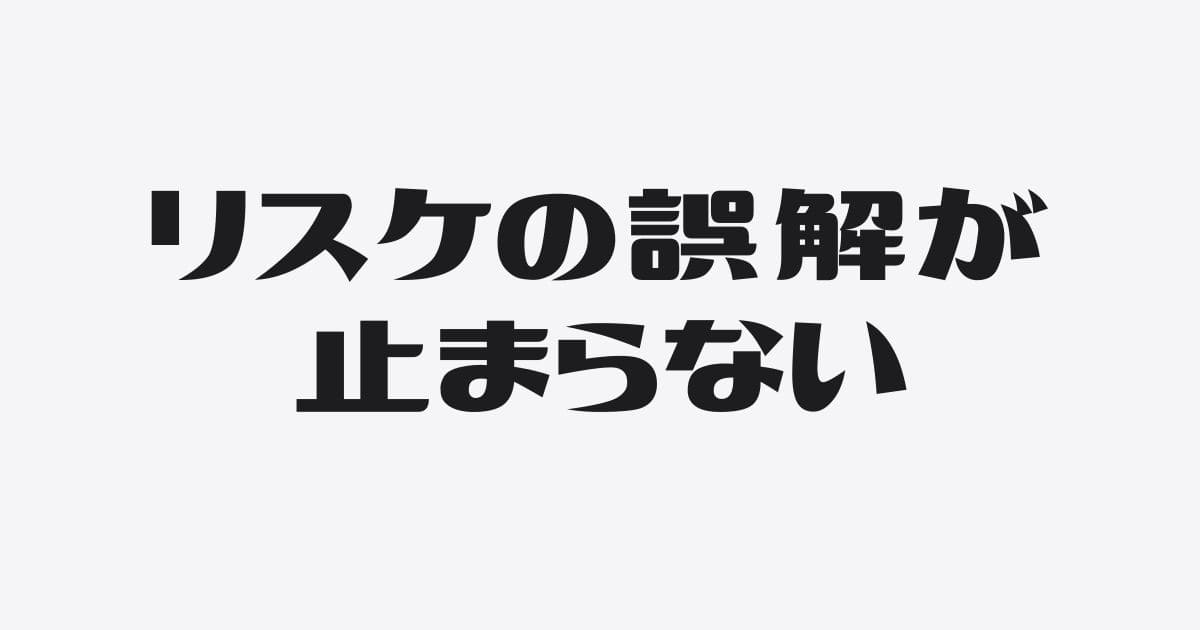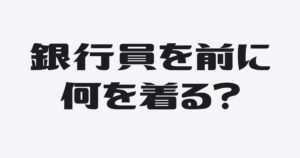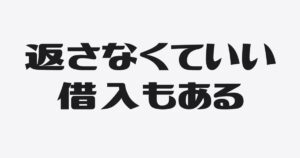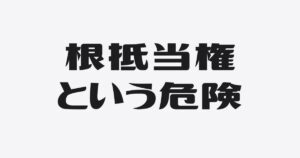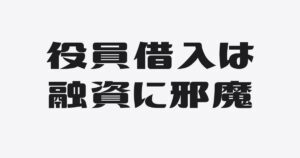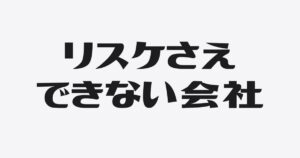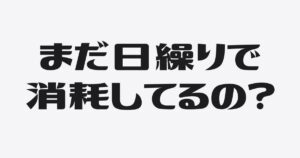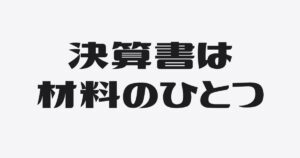リスケジュール(リスケ)について、けして少なくはない社長が陥る誤解が3つあります。それを放置して、再起のチャンスを逃してしまうことがないように、正しい知識を持ちましょう。
リスケの誤解が再起のチャンスを逃す
「リスケジュール(リスケ)」という言葉に、ネガティブな響きを感じてしまう社長は少なくないでしょう。いざリスケとなれば、「銀行からの信用を失ってしまうのでは…」「もうウチもダメかもしれない」と、そんな不安がよぎるかもしれません。
でも、そのリスケに対するイメージは本当に正しいのでしょうか?実は、リスケに対する「誤解」が会社の再生を妨げて、再起のチャンスを逃してしまっているケースがあります。
そこで今回は、社長が陥りがちなリスケの誤解について、詳しく解説していきます。具体的には次の3つです。
- リスケしたら借りれなくなる
- リスケはギリギリまで避ける
- できるだけ多く返済を続ける
上記の誤解があるようなら、放置してはいけません。リスケについて正しい知識を持つことが、厳しい状況にある会社を救う一助となるはずです。
誤解1・リスケしたら借りれなくなる
わりと多くの社長が抱いている誤解です。「リスケをすれば、銀行のブラックリストに載って、今後いっさい、融資が受けられなくなるのでは…」とか。
当初の約束を果たせず、その約束を変更するわけですから、ペナルティがあるように感じるのも無理はありません。ですが、そこには誤解があります。
そもそも、リスケを検討しなければならないほど厳しい状況であり、銀行があらたに融資をしてくれる可能性はきわめて低いのです。リスケしようとしまいと、あらたに融資を受けることが困難である状況は変わりません。
いっぽうで、リスケをすることで毎月の返済額を減らせれば、あらたに融資を受けたのと同じ効果が見込めます。たとえば、毎月50万円の返済を1年止められたら、600万円の融資を受けたのといっしょです。
リスケは、「将来の融資の道を閉ざす」ものではなく、「いま資金繰りの危機を乗り越えるための手段」と捉えるようにしましょう。返済負担を軽減し、会社が経営改善に取り組むための「時間」をつくり出すための、合理的な経営判断のひとつなのです。
なお、リスケ中は新規融資が原則として受けられません。しかし、それは永続的なものではありません。会社の収益力が回復して、元どおり返済ができるようになれば、またあらたに融資も受けられるようになります。
また例外的に、リスケ中であっても、資金使途と返済原資が明確な「短期のつなぎ資金」などであれば、融資が受けられる能性もゼロではありません。
「リスケしたら借りれなくなる」という漠然とした恐怖心から、必要なはずのリスケという選択肢を検討すらしないこと。それ自体が、会社にとって大きなリスクであることを理解しましょう。
誤解2・リスケはギリギリまで避ける
次は、「ガマンしすぎる」ことから生じる誤解です。「まだ大丈夫だ。もう少しがんばれば状況は好転するはずだから、自力で何とかしよう」とか。
社長にとって粘り強さは必要な資質ですが、ことリスケに関しては、その判断が手遅れを招くことがあります。ギリギリまで粘った結果、どうなるか?
リスケの交渉には時間がかかることもあります。経営改善計画書を作成し、取引しているすべての銀行と個別に交渉し、全行から同意を取り付けねばなりません。取引銀行の数にもよりますが、数ヶ月〜半年ていどかかることもあります。
そのあいだにも、会社のおカネ(預金残高)は日々減少していきます。また、預金が底をつきかけてから交渉をはじめるようでは、銀行も「この状況からでは、リスケしても再生は難しい」と考えて、交渉に応じてくれない可能性が高まります。こうなれば、もはや打つ手なしです。
では、いつ決断すべきか? リスケを検討すべきタイミングがあります。それは、次の2つの条件を満たすときです。
- 会社の稼ぐ力(≒ 税引後利益+減価償却費)が、年間の借入返済額を下回る状態が続く
- 新規の借入が困難、あるいは借入できても額が不十分
この2つの条件が当てはまるようなら、リスケを検討すべきです。資金繰りが厳しいときの支払いの優先順位(①手形 ②給料 ③仕入 ④経費 ⑤税金・社会保険料 ⑥借入返済)から考えても、借入金の返済は後回しにすべきであり、リスケという選択肢を検討することが賢明です。
誤解3・できるだけ多く返済を続ける
これは、真面目で誠実な社長ほど陥りやすい誤解と言えるでしょう。「銀行には本当に申し訳ない。少しでも誠意を示すために、無理してでもできる限りの返済は続けたい」とか。
その気持ちは理解できます。ですが、その遠慮が会社の再生の足かせになってしまうことがあるのです。リスケ本来の目的を考えてみましょう。言うまでもなく、会社の経営を立て直すことです。
そのためには、一時的にでも返済の負担を減らして、売上回復やコスト削減といった本質的な経営改善に社長が集中できる環境を確保することが、何よりも重要になります。
にもかかわらず中途半端に返済を続けて、手元のおカネがギリギリの状態が続けば、思い切った施策も打てません。いつまでも資金繰りの心配がつきまとい、結局、立て直しに失敗してしまっては元も子もないでしょう。
したがって、銀行にリスケを申し入れるときには、「当面の元金返済はゼロ、利息のみ支払う」ことを条件として相談するのがセオリーです。
もちろん、銀行側が難色を示すことはあるでしょう。「元金ゼロは困る、少しでも返してほしい」などと言われることはあります(最近はとくに、銀行の姿勢が厳しくなっています)。
しかし、そこで安易に応じてはいけません。なぜ元金返済ゼロが必要なのか、その期間にどのような経営改善を実行し、どうやって収益力を回復させるのか。それを「経営改善計画書」という形で具体的に示すことで、銀行にその必要性を論理的に、粘り強く説明することが大切です。
当初の約束を守れないという負い目や、銀行への遠慮から、過剰な返済負担を受け入れてしまっては、リスケの目的を果たせなくなってしまいます。そうなれば銀行だって困るのです。元金返済ゼロこそが、銀行にとっても望ましい道であることを説いていきましょう。
まとめ
リスケに対する3つの大きな誤解について、お話をしました。
- リスケしたら借りれなくなる
- リスケはギリギリまで避ける
- できるだけ多く返済を続ける
リスケは「会社のおわり」を意味するものではありません。むしろ、厳しい状況から会社を立て直し、再び成長軌道に乗せるための、前向きで合理的な戦略的選択です。
間違った思い込みや、一時的な感情、過度な遠慮によって判断を誤り、再生のチャンスを逃してしまうことは、絶対に避けなければなりません。
正しい知識を持ち、適切なタイミングを見極めて、正しい方法で銀行と交渉を進めることができれば、困難な状況からでも会社を再起させる道は見つかるものと考えます。