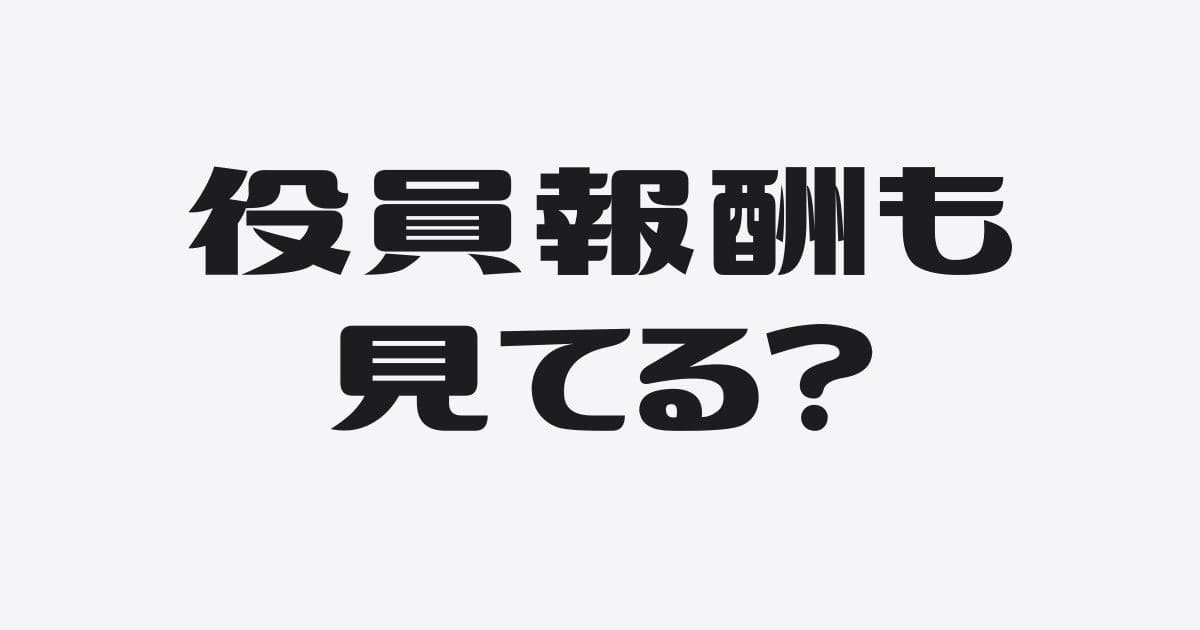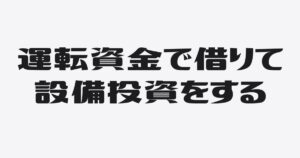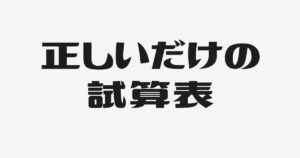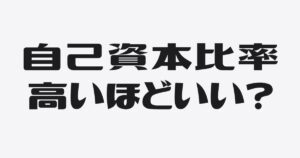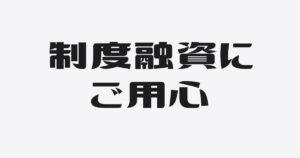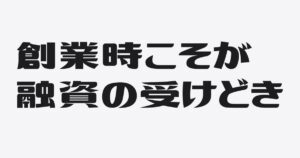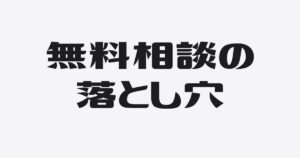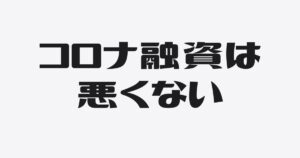損益計算書を見るときに、利益だけを見て一喜一憂していませんか?本当の収益力を知るには、役員報酬もあわせ見ることが大切です。その見方について、詳しくお話をします。
損益計算書の利益だけを見ない
会社の決算がおわると、損益計算書とにらめっこ。
「今期は黒字でよかった!」
「まずい、赤字になってしまった…」
などと、利益の数字に一喜一憂している社長もいます。もちろん、利益が出ているかどうかは会社にとって重要です。とはいえ、損益計算書に載っている「利益」だけを見て、会社の実力や、銀行からの評価だと考えるのであれば、早計と言えるかもしれません。
融資の審査において、銀行は表面的な利益だけを見ているわけではないからです。銀行が見ている「もうひとつの数字」、それこそが会社の真の実力を映し出すカギであり、融資の可否にも大きく関わっています。そのカギとは、ずばり「役員報酬(社長の給料)」です。
そこで今回は、損益計算書の見方として「役員報酬」に注目することの重要性を、詳しく解説していきます。お話の流れは以下のとおりです。
- 中小企業の役員報酬の実態とは
- 銀行はなぜ役員報酬を見るのか
- 赤字の会社も役員報酬の額次第
それでは、順番に確認をしていきましょう。
中小企業の役員報酬の実態とは
まずは、役員報酬の重要性を理解するにあたり、中小企業に特有の事情を理解するところからはじめます。多くの中小企業は(大企業とは違って)、社長が会社のオーナー(大株主)でもあることが一般的です。そのため、社長は自身の役員報酬の額を、自由に決めることができます。
これが何を意味するかというと、社長の考え方やさじ加減ひとつで、決算書に表示される「利益の額」が大きく変わってしまう可能性がある、ということです。
たとえば、「できるだけ税金は払いたくない」と考える社長がいるとします。その社長は、会社の利益を抑えるために、じぶんへの役員報酬を比較的多めに設定するかもしれません。結果として、決算書上の利益は小さくなります。
逆に、「銀行からの評価を良く見せたい」あるいは「じぶんの報酬(個人の収入)にはあまり関心がない」という社長は、役員報酬を低めに抑えているかもしれません。その場合、決算書上の利益は大きく見えますが、それが必ずしも会社の高い収益力を示しているとは限らいことはわかるでしょう。
このように、社長の個人的な判断や状況によって変動する「見かけの利益」だけを鵜呑みにしていると、会社の本当の実力を見誤ってしまう危険性があります。
銀行はなぜ役員報酬を見るのか
では、銀行は利益をどう見ているのでしょうか?
銀行は、融資審査において決算書を評価する際、損益計算書に載っている利益額と同時に、「社長(役員)に年間いくらの報酬が支払われているか」を必ずチェックしています。つまり、役員報酬の額を見ているということです。
そして、会社の収益力をより正確に把握するために、「利益 + 役員報酬」という視点を持っています(ここで言う「利益」は、税引前利益や経常利益、営業利益など、どの段階の利益を使うかは銀行や状況によって異なりますが、考え方は同じです)。
なぜ、「利益+役員報酬」で見るのか? それは、この合計額こそが、社長の報酬設定という調整要素を取り除いた、会社が本来稼ぎ出す力により近いものだと考えられるからです。役員報酬も、元をたどれば会社が生み出した利益から支払われているわけですから、利益と一体で見るのは合理的な考え方だと言えます。
具体例で見てみましょう。売上高が同じ2つの会社があるとします。
- A社:経常利益 1,200万円、社長の役員報酬 600万円
- → 損益計算書上の利益率は高く見える
- → 「利益+役員報酬」は 1,800万円
- B社:経常利益 300万円、社長の役員報酬 2,400万円
- → 損益計算書上の利益率は低く見える
- → 「利益+役員報酬」は 2,700万円
表面的な利益や利益率だけを見れば、A社のほうが良い会社におもえるかもしれません。ですが、銀行が見る「実質的な稼ぐ力」という点では、B社がA社を上回っていると評価する可能性があります。B社は、やろうと思えば役員報酬を調整して、A社以上の利益を出すポテンシャルがあるとも見れるからです。
このように、銀行は単純な利益額だけでなく、役員報酬とのバランスを見て、会社の真の実力を見極めようとしています。
赤字の会社も役員報酬の額次第
「うちは赤字だから、融資を受けるのはムリだろう…」
決算書が赤字だと、そのように悲観してしまう社長もいるかもしれません。しかし、ここでも役員報酬が重要になります。赤字という結果だけで、すぐにあきらめないようにしましょう。
もし、その役員報酬が相場(同業他社)よりもだいぶ高かったり、自身の生活費よりもだいぶ高かったりしたうえで赤字になっているのであれば、どうでしょうか?
その場合、役員報酬を「一般的な水準」まで減額すれば、計算上はすぐに黒字化できるケースも少なくありません。もちろん、実際に報酬を減額するかは別の問題ですが、少なくとも会社には「潜在的な黒字化余地がある」と見ることができます。
銀行も、そういった「赤字の質」を見極めようとしています。役員報酬をムリなく減額して黒字にできる会社であれば、返済能力は十分にあると判断する材料になるわけです。
逆に注意が必要なのは、社長が生活していくのにギリギリ(最低限)の役員報酬しかもらっていないにもかかわらず、それでも会社が赤字になっているケースです。この場合は、役員報酬を調整して利益を出すという余地はありません。事業(商売)の構造そのものに深刻な問題を抱えている可能性が高く、銀行からの評価も厳しくならざるをえないでしょう。
このように、赤字という同じ結果であっても、役員報酬の額によって会社の本当の実力は異なり、ひいては融資の可否も異なることになります。
まとめ
損益計算書を見るとき、利益の額だけを見て一喜一憂するのはやめましょう。
利益だけではなく「役員報酬」の額も確認して、「利益+役員報酬」によって、会社の本当の収益力を把握する。この習慣をつけることが、会社の現状を正しく理解するための第一歩です。それは、銀行が自社を見る視点でもあります
よって、社長は「利益+役員報酬」を把握することで、より的確な経営判断が可能になりますし、銀行に対しても自信を持って自社の状況を説明できるようになるはずです。