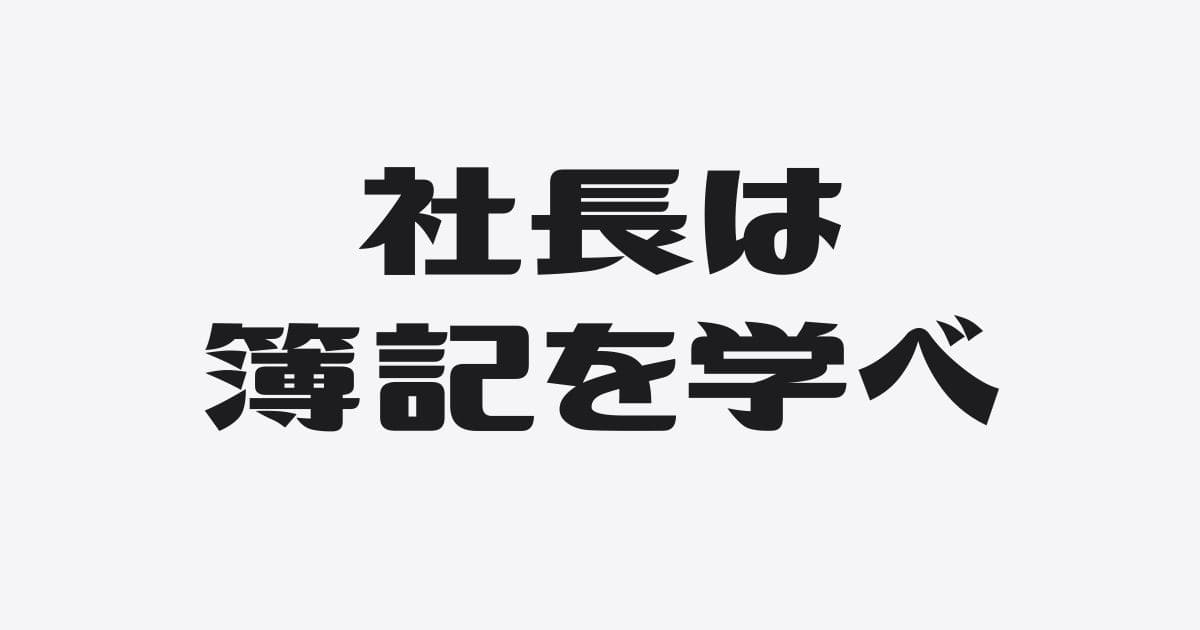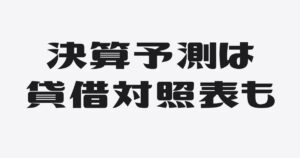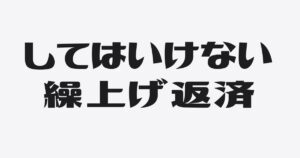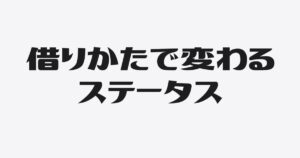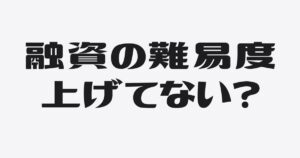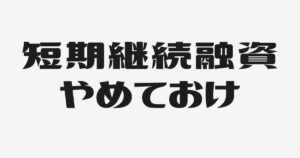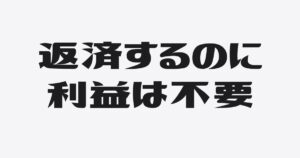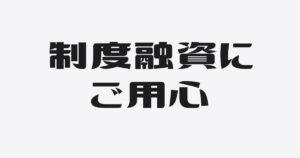かねてより、「社長は簿記を学ぶべきか否か」の議論があります。結論、「学ぶべき」と考える僕が、その理由についてお話をします。
簿記の勉強は社長に必要か?
「社長も、簿記くらいは勉強しておいたほうがいいですよ」
先輩経営者や、あるいは顧問税理士などから、そんなアドバイスを受けたことがあるかもしれません。
そのいっぽうで、「いやいや、社長は数字の細かいことよりも、事業そのものに集中すべきだ。簿記や経理は専門家(税理士や経理担当者)に任せておけばいいんだ」という意見も根強くあります。
会社経営において、「社長は簿記を学ぶべきか否か?」という問いは、昔からよく議論されているテーマです。どちらの言い分にも一理あり、社長自身も「実際のところ、どうなんだろう?」と迷われることがあるかもしれません。
専門家である税理士のあいだでも意見が分かれることがありますが、銀行融資の現場で日々、多くの社長や会社の数字と向き合っている僕としての結論は、ハッキリしています。
それは「社長は簿記を学ぶべき(ただし、最低限のレベルでOK)」です。
しかしなぜ、そう言い切れるのか?
今回は、社長が簿記(の基礎)を学ぶべき理由について、詳しく解説していきます。この記事を読みおえるころには、「簿記なんてじぶんには関係ない」とおもっていた社長も、少し見方が変わるかもしれません。具体的には次のとおりです。
- 取引から決算書をイメージしやすい
- 経理のブラックボックス化を防げる
- 簿記3級レベルの習得は難しくない
社長が簿記を学ぶべき3つの理由
「簿記なんて難しそうだし、そもそも勉強している時間なんてない」 そう感じる社長の気持ちもよくわかります。しかし、簿記の基礎を学ぶことには、その時間的・心理的な負担を上回る、たしかなメリットがあると僕は考えています。なぜ「学ぶべき」なのか、その理由を3つのポイントに絞ってお伝えしましょう。
取引から決算書をイメージしやすい
まず、簿記を学ぶ最大のメリットのひとつは、会社の「数字が動く仕組み」の基本的な構造を理解できるようになることです。 簿記の基礎(たとえば、借方・貸方の意味、おもな勘定科目の役割、仕訳から試算表、そして決算書へデータが集計されていく流れなど)を理解すると、日々の会社の取引(売上が発生した、商品を仕入れた、経費を支払った、銀行から融資を受けた、など)が、最終的に試算表や決算書(損益計算書や貸借対照表)のどの数字に、どのように反映されるのか、その流れと結果が頭のなかでイメージできるようになります。
「なるほど、この設備投資をすると、損益計算書の減価償却費が増えるだけでなく、貸借対照表の資産と負債(あるいは純資産)がこう動くのか」 「売掛金の回収が1か月遅れると、利益は変わらなくても、貸借対照表の資産の中身と、手元のおカネ(預金残高)にこれだけの影響が出るんだな」
といった具合に、取引と財務諸表との繋がりが見えてくるわけです。
この「数字の動き」のイメージができるようになると、自社の経営状態を、単なる損益計算書の利益だけでなく、貸借対照表の健全性やキャッシュフローの状況まで含めて、より深く、立体的に理解できるようになります。
これは、日々の経営において、より的確な判断を下していくうえで、大きなアドバンテージとなるはずです。税理士からの説明なども、「なるほど、そういうことか」と腹落ちしやすくなるでしょう。
経理のブラックボックス化を防げる
社長が簿記の知識をまったく持っていないと、自社の経理業務が「ブラックボックス」、つまり、社長にとって経理が中身が見えない箱のようになってしまう危険性があります。
経理担当者や顧問税理士にすべてを任せきりにしてしまい、「日々のおカネがどのように記録され、最終的に決算書の数字がどのように作られているのか」という過程が、社長にはまったく見えなくなってしまうのです。
社内へのメリット:ブラックボックス化を防ぐ
簿記の基本的な仕組みが分かっていれば、経理担当者から提出される試算表を見たときに、「なぜ、この勘定科目にこんなに大きな金額が計上されているんだろう?」「先月と比べて、ここの数字が大きく動いているのはなぜだろう?」といった疑問を持つきっかけになります。
これは、経理担当者任せにすることのリスク、たとえば、意図しない処理の間違いや、最悪の場合、不正行為の発生などを抑制するうえでも重要です。社長自身が最低限の「チェック機能」を持つことで、経理処理の妥当性を確認し、もし何か問題があれば早期に発見できる可能性が高まります。
また、「社長も数字の意味をきちんと理解している」という意識が社内に浸透すれば、経理業務の透明性が高まったり、社員全体のコスト意識が向上したりといった、内部管理体制の強化にもおのずと繋がっていきます。「どんぶり勘定」から脱却するための、たしかな第一歩となるでしょう。
社外へのメリット:対話レベルを上げる
このように、数字に対する社長自身の理解が深まることで、銀行担当者や顧問税理士といった外部の専門家との「会話の質」も向上します。
簿記や会計に関する基本的な専門用語(例えば、「減価償却費」「引当金」「繰延資産」「債務超過」「キャッシュフロー」など)の意味が分かるようになり、決算書や試算表に関する説明も、以前より深く、そして正確に理解できるようになるはずです。「その未払費用って何のことですか?」といった基本的な質問に、貴重な面談の時間を使う必要もなくなるでしょう。
さらに重要なのは、銀行に対して自社の状況や今後の計画を説明するにあたり、社長自身が数字の裏付けを持って、より具体的かつ説得力のある話ができるようになることです。「この売上目標を達成するために、固定費の中でもとくに人件費はこれくらいを見込んでおり、その結果、損益分岐点はこうなります」といった説明ができれば、銀行からの信頼度は大きく上がるでしょう。
「この社長は会社の数字をきちんと理解して、計画的に経営している」と銀行に感じてもらえることは、銀行からの評価を高め、有利な条件での融資を受けるうえで、間違いなく大きなプラスに働きます。専門家に近いレベルで対話ができるようになることで、より質の高いアドバイスや本質的な支援を引き出すことにも繋がるはずです。
簿記3級レベルの習得は難しくない
「簿記を学ぶべき」と言われても、「やっぱり難しそうだし、何年も勉強しないといけないのでは?」と、どうしても尻込みしてしまう社長もいるかもしれません。
しかし、ここで強調したいのは、社長が学ぶべき簿記は、経理のプロフェッショナルを目指すわけではないということです。税理士や経理部長のように、複雑な仕訳をじぶんで扱えるようになる必要はありません。社長が目指すべきは、あくまで会社の数字の基本的な仕組みや、おカネの流れを理解することです。
そのレベルであれば、「日商簿記3級」の知識で十分だと、僕は考えています。簿記3級は、まさに簿記の入門編です。日常的な取引の仕訳から、試算表の作成、そして最終的な決算書ができあがるまで、会社の経理の一連の基本的な流れを学ぶことができます。
では、その簿記3級に合格するには、どれくらいの勉強が必要なのでしょうか?
一般的に、合格に必要な勉強時間は50時間から100時間くらいと言われています。もちろん個人差はありますが、集中して取り組めば、早い人なら1〜2週間ていど、忙しい社長でも1か月か2か月もあれば、十分に合格レベルの知識を身につけることが可能です。最近では、初心者にも分かりやすいテキストや、パソコンやスマホで学べるオンライン講座なども充実しています。
もちろん、簿記2級や1級まで取得できれば、さらに深い知識が身につくわけですが、社長にとっては、まずは3級レベルの知識を押さえるのが費用対効果(投入時間に対するリターン)が高いと言えるでしょう。
「最低限の学習」で「経営判断力やコミュニケーション能力の向上」というリターンが期待できる。簿記3級の学習は、社長にとってコスパの高い自己投資だと、僕は考えています。
まとめ
社長が簿記を学ぶべきか、それとも専門家に任せるべきか。 銀行融資の現場を見てきた僕としての結論は、「学ぶべき(ただし、日商簿記3級レベルの知識で十分)」です。
簿記の基礎を学ぶことで、
- 数字が動く仕組みが理解できて、経営判断の質が上がる
- 経理のブラックボックス化を防ぎ、銀行や税理士との対話レベルが向上する
- 習得(3級レベル)はけして難しくなく、短期間でもできる
専門家に任せきりにするのではなく、社長自身が会社の数字をさらに深く読むための力を身につけること。それが、これからの変化の激しい時代において、会社をより力強く経営していくための、確かな土台となるはずです。
食わず嫌いせずに、まずは本屋さんで簿記3級のテキストを手に取ってみるところから始めてみてはいかがでしょうか?きっと、自身の会社経営にとって、あたらしい発見や視点が得られるはずです。