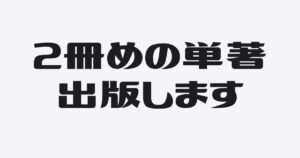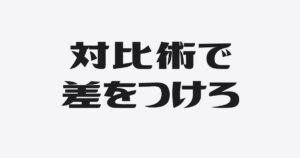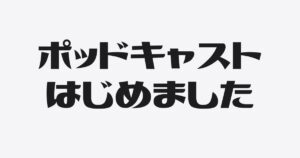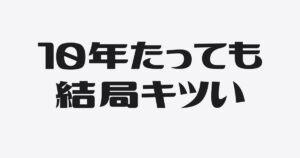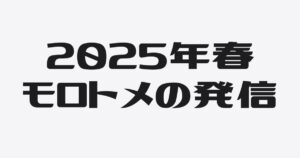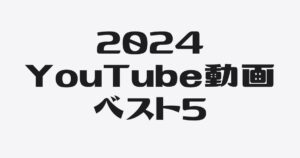話すのは苦手…そんなあなたへ。書くことと比較して、話すのが得意ではない僕が、YouTubeやセミナーなど話すことを続ける理由と、苦手に向き合うヒントをお伝えします。
書くのは得意だけど話すのは…
「書くのは得意ですが、話すのが得意ではありません」
僕がそんなことを打ち明けると、意外そうな顔をされることがあります。実際に「意外です」と言われることもあります。
たしかに僕は、ブログを毎日更新して、毎日メルマガも書き、書籍の執筆もしてきました。どう見ても「書く」ことを主戦場として情報発信をしてきたタイプです。その自覚も自信もあります。
そのいっぽうで、YouTubeでの動画配信、stand.fmやポッドキャストでの音声配信、加えてセミナーの講師として、人前で「話す」という活動もまた、細々とながら続けています。
「ならば、話すのが得意ではないのになぜ?」
そう、おもわれるかもしれません。実際、僕自身も「もっと上手く話せたらなぁ」と毎回のようにおもいますし、準備には書くこと以上に気を使います。
そこで今回は、書くことと比べて話すのが苦手な僕が、それでも話すというカタチで発信を続けようとしているのはなぜなのか?その理由と、僕なりに実践している「苦手との向き合い方」についてお話ししてみます。
もしあなたが、「話すのは苦手だけど、伝えたいことはある」「発信の幅を広げたいけど、なかなか一歩が踏み出せない」と感じているなら、この記事が少しでもあなたの背中を押すきっかけになれば嬉しいです。このあと、以下の内容をお伝えしていきます。
- 話すのが苦手でも話し続ける理由
- 話すための心持ちと必要な準備と
- 苦手でも一歩踏み出すことの価値
話すのが苦手でも話し続ける理由
「話すより書くほうが得意」と公言している僕が、それでもYouTubeや音声配信、セミナーといった話す活動を続けるのには、その苦手意識を上回るだけの理由があります。
理由1:書くだけでは伝わらないものがある
- 映像と声のチカラ
僕は、文章で論理的に情報を伝えたり、じぶんの考えを整理したりすることには、あるていどの自信がありますし、それが好きです。でも、文章だけではどうしても伝えきれないものがある、とも感じています。
それは、話す人の「人となり」やそのときの「熱量」、話の「間(ま)」や「抑揚」から伝わるフンイキやニュアンスといったものです。同じ内容を伝えるにしても、文字だけで読むのと、その人の声で、ときには表情を見ながら聞くのとでは、受け手の印象や理解度、共感の度合いが変わることはあるでしょう。
とくに、僕がよくテーマにする「銀行融資」のような少し硬い内容であっても、僕自身の言葉で、僕自身の声で直接語りかけることで、少しでも親近感を持ってもらえたり、内容が頭に入りやすくなる効果があるのではないかと期待しています。
YouTubeや音声配信、セミナーといったメディアは、そうした「非言語な情報」を乗せることで、より深くメッセージを届けるチカラを持っていると考えているのです。
- 新しい層へのアプローチ
また、現代は情報収集の手段が多様化しており、テキストを読むよりも動画や音声を好むという方も確実に増えています。僕のブログや書籍を普段あまり読まないような方々にも、YouTubeやポッドキャストを通じて、僕の考えや銀行融資に関する専門知識に触れてもらう機会が生まれるかもしれません。それは、これまでリーチできなかった新しい層へのアプローチという意味で、非常に価値のあることだと考えています。
理由2:「書く×話す」には相乗効果がある
- 話すことで思考が深まる
これは意外に思われるかもしれませんが、「話す」という行為は、僕にとって「書く」ための準備の役割になったり、あるいは、じぶんの思考をさらに深めるための役割にもなっています。
たとえば、セミナーで話す内容を検討するなかで、関連情報をあらためて整理し直せば、じぶんのなかで曖昧だった点が明確になったり、話の構成を考えるうちにもっと良い伝え方や新しい気づきを得たりすることがあります。
YouTubeや音声配信なども同じです。話していることで、思考が整理されたり、より確信を得られることで、ブログやメルマガなど書くことにも活かされています。
つまり、話す(アウトプットする)ことを前提に情報をインプットしたり思考を巡らせたりすることで、より内容の理解が深まるし、考えが整理されるという効果があるのです。
- 反応が次の発信につながる
セミナーでの質疑応答や、YouTubeのコメント欄などからいただくご質問やご感想は、僕にとっては貴重な「反応(フィードバック)」です。
「こういう点がわかりにくいのか」「こんなことに関心があるのか」「こういう悩みを持っているのか」といったリアルな気づきは、次回以降の発信内容を考えるうえで大きなヒントになります。これは、どちらかというと一方通行になりがちな「書く」という行為だけでは得られにくい、双方向のコミュニケーションから生まれる大きなメリットだと感じています。
理由3:じぶん自身の成長機会と捉えている
- 苦手なことへの挑戦
正直に告白すると、セミナーなどで大勢の人の前で話したり、カメラに向かって1人でよどみなく話し続けたりするのは、いまでも得意ではありません。毎回それなりに準備もしますし、多かれ少なかれ緊張もします。
でも、だからこそ、それを「じぶん自身の成長機会」と捉えています。苦手なことから逃げずに、あえて挑戦し続けることでしか、得られない経験やスキルがあると信じているからです。
話し方、間の取り方、声のトーン、話の構成の組み立て方、聞き手の反応の読み取り方など、反省点は毎回山ほど出てきますが、少しずつでも改善していければ、それはじぶんにとって大きな財産になるはずだと考えています。
- 伝えるチカラを多角的に磨く
たとえば、銀行融資について伝える僕の役割は、社長や税理士の方などに、融資の仕組みや銀行の考え方をわかりやすく伝えて、納得してもらい、そして具体的な行動を促すということです。そのために必要な「伝えるチカラ」は、文章力だけでなく、話すチカラも含めた総合的な伝達力です。
「話す」という訓練を意識的に行うことで、相手の反応を見ながら臨機応変に説明の仕方を変えたり、より共感を呼べる言葉を選んだりする能力が磨かれるはずだと考えています。
話すための心持ちと必要な準備と
では、話すのが苦手な僕が、実際に話す活動を続けるために、どんな準備や工夫、あるいは心持ちでいるのか?いくつかご紹介してみます。
準備1:話す内容の骨子は書く
僕はやはり「書く」ほうが得意なので、話す場合でも、まず伝えたいことの骨子や全体の流れ、重要なキーワードなどは、事前に必ず文章で書き出します。 セミナーであればスライドを、YouTubeであれば台本をつくりますし、音声配信であれば、少なくとも話すポイントを箇条書きにしたメモは用意することがほとんどです。
行き当たりばったりで、アドリブで上手に話せるほど器用ではないので、この「書く」という準備が、僕にとっては精神的な安心材料でもあり、話のクオリティを最低限担保するための生命線とも言えます。
準備2:事前練習を欠かさない
とくにセミナーなど、持ち時間や話すべき構成が決まっているものの場合は、実際に声に出して練習したり、頭のなかで全体の流れをシミュレーションしたりします。どの部分をとくに強調して話すか、どんな事例を具体的に話すか、質疑応答ではどんな質問が出そうか、などを事前に考えておくだけで、当日の心の落ち着きが違ってくるでしょう。
心持ち1:完璧を求めず他人と比べない
世の中には、上手に話す人がたくさんいます。いっぽうで僕は、アナウンサーのように流暢に淀みなく話せるわけでもなければ、人気タレントのようにおもしろく、人を惹きつけるトークができるわけでもありません。
でもそれでいい、と僕はおもっています。僕が目指すのは「完璧なプレゼンター」や「カリスマ講演家」ではありません。「誠実に、わかりやすく、じぶんの言葉で伝える」こと。それができれば十分だと考えています。他人と比較して落ち込むのではなく、背伸びせず、いまの自分にできる精一杯で臨む。そう考えるようにしています。
心持ち2:小さな手応えこそ大切にする
YouTubeの再生回数や「いいね」の数、セミナーの集客人数なども、気にならないと言えばウソになります。でも、それ以上に僕が大切にしているのは、セミナー後のご感想で「わかりやすかったです」「きょうから実践してみます」という言葉をいただいたり、YouTubeのコメントで「悩みが解決しました」といった声をいただいたりしたときの、「ちゃんと伝わったんだな」という小さな手応えです。
この「誰か1人にでも、ちゃんと伝わった」という喜びが、苦手意識を乗り越えて、「また次も話そう」「もっとわかりやすく伝えられるようになりたい」というモチベーションになっています。
苦手でも一歩踏み出すことの価値
もしあなたが、「話すのは苦手だから、情報発信はブログやメルマガとかの文章だけにしておこう」と考えているとしたら、少しもったいないかもしれません。
たしかに、じぶんの得意な土俵で勝負するのは、商売の基本です。ですが、あえて苦手だと感じていることに挑戦することでしか見えない景色や、そこからしか得られない自己成長があるのも、また事実でしょう。
僕自身、話すことへの苦手意識が完全に払拭されたわけではありません。いまでも、セミナー前は緊張しますし、動画収録では撮り直しをすることがあります。それでも、そうして「話す」という活動を続けることで、少しずつではありますが、以前よりは落ち着いて話せるようになったり、伝え方や表現の幅が広がってきたりするように感じています。
そして何よりも、文章だけでは出会えなかったであろう多くの方々との、新しい繋がりが生まれています。 だから、最初からうまく話そうとしなくても大丈夫です。流暢である必要もありません。まずは、短い動画や音声配信から始めてみる、あるいは、ごく少人数のセミナーで、じぶんの考えを伝えてみるなど、じぶんにとってハードルの低いところから「話す」という経験を積んでみるのはいかがでしょうか。
「話すのが苦手」という方が、それでも勇気を出して、じぶんの言葉で、じぶんの想いを語り始めたとき、そこには、単に流暢な話し方以上に、人の心を動かす何かが宿ることもあるはずです。熱意や誠実さには、チカラがあります。
まとめ
「話すのが苦手」と言いながらも、僕がYouTubeや音声配信、セミナーといった話す活動を続ける理由と、そのための僕なりの工夫や心持ちについてお話ししてきました。
- 書くだけでは伝わらない「人となり」や「熱量」を届けたい。そして、新しい層にもリーチしたい
- 「書く」ことと「話す」ことの相乗効果で、じぶん自身の思考を深めて、発信全体の質を高めたい
- 苦手なことへの挑戦を通じて、じぶん自身を成長させて、「伝えるチカラ」そのものを多角的に磨きたい
そのために、
- 話す内容の骨子はまず書き、準備する
- 完璧を目指さず、他人と比較せず、伝わることを大切にする
- 小さな伝わったという手応えを、次へのモチベーションにする
「話すのが苦手だから、やらない」のではなく。苦手だけど、それでも伝えたいことがあるから、じぶんなりに工夫してやってみる。そんなスタンスで、これからも僕は「話す」ことにも挑戦し続けていきたいと考えています。
もし、この記事を読んで、「じぶんも少しだけ、話すことに挑戦してみようかな」とおもっていただけたなら、これ以上嬉しいことはありません。あなたの「話したいこと」は何ですか? きっと、それを聞きたいと思っている人が、どこかにいるはずです。