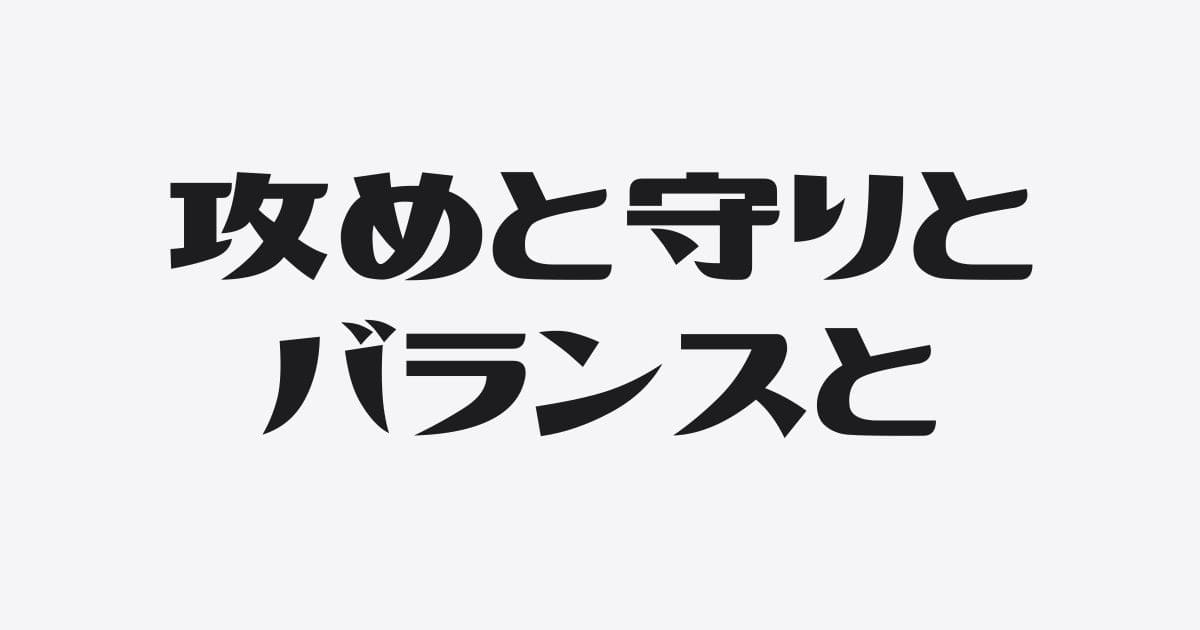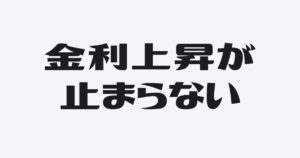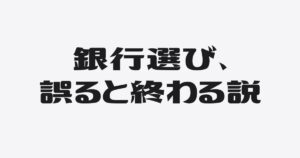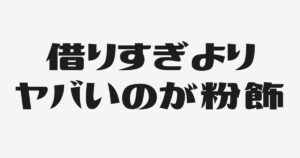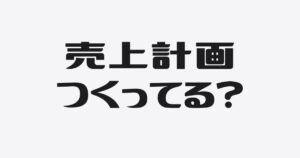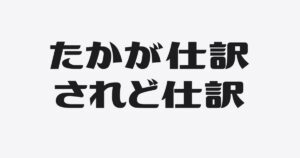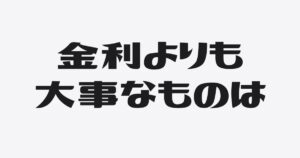銀行に融資を申し込むとき、「いくら借りるか」を感覚で決めていませんか?融資額の決定は、会社の未来を左右する重要な経営判断です。そこで、融資額を合理的に決めるための3つの視点を解説します。
「いくら必要ですか?」に社長はどう答えるか
銀行に融資の相談に行くと、担当者から必ずこう聞かれます。
「社長、今回はいくらご入用ですか?」
このとき、あなたならどう答えるでしょうか。「借りられるだけ借りたい」「とりあえず1,000万円くらい」といったように、明確な根拠なく、感覚で金額を伝えてしまってはいないでしょうか。
融資をいくら借りるか、という問題は、会社の財務戦略の根幹に関わる重要な経営判断です。どんぶり勘定やその場の雰囲気で決めてよいものでは、けしてありません。
金額の根拠を明確に語れない社長を、銀行が信用することはなく、金額が過小であればチャンスを逃し、過大であれば返済に苦しむことにもなりかねない…
本記事では、この「いくら借りたらいいか問題」に決着をつけるべく、社長が融資額を検討する際に持つべき「3つの視点」について解説していきます。この視点があれば、自信を持って銀行に希望額を伝えられるようになるはずです。
この記事のポイントは以下のとおりとなります。
- 視点1:攻め
- 視点2:守り
- 視点3:バランス
いくら借りたらいいかの3つの視点
「攻め」「守り」「バランス」という3つの視点は、どれか1つだけを見ればよい、というものではありません。これらを総合的に検討することで、自社にとって最適で、かつ、銀行にも納得してもらえる融資額が見えてきます。それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
視点1:攻め
「攻め」の借入とは?
これは、会社の未来の成長のために行う、前向きな投資のためのおカネです。たとえば、以下のようなものが挙げられます。
- あたらしい機械や車両を購入するための設備投資
- 新店舗の出店や、工場の増設
- 新商品・新サービスの開発費用
- 事業拡大に伴う、採用費や広告宣伝費
銀行にとっても、このような「攻め」の資金使途は、会社の成長意欲の表れとしてポジティブに評価されやすいものです(ただし、業績悪化時はネガティブに見られがち)。
どうやって金額を決めるか?
「攻め」の融資額は、感覚ではなく、具体的な根拠(見積書など)に基づいて算出します。
機械を買うならメーカーからの見積書、店舗を出すなら内装工事や保証金の見積書が必要です。それらを積み上げて、「今回の事業投資には、合計で〇〇円が必要です」と、明確に算出することが大切です。
以上の金額が、まず考えるべき融資額の1つめの基準となります。
視点2:守り
「守り」の借入とは?
これは、不測の事態から会社を守るための、手元資金(現金預金)を十分に確保するためのおカネです。会社は赤字だからつぶれるのではなく、おカネが尽きたときにつぶれます。そうならないための「保険」としての借入です。
では、「十分な手元資金」とは、いくらぐらいを指すのでしょうか。そのひとつの目安が「平均月商の3か月分」です。
どうやって金額を決めるか?
まず、自社の平均月商(年間売上高÷12か月)を計算します。そして、その3か月分が、会社が当面の目標として確保すべき預金残高の目安となります。その目標額に達するまでの不足分を借入で補う、という考え方です。
たとえば、平均月商が1,000万円の会社であれば、目標預金残高は3,000万円。現在の預金が2,000万円しかないとすれば、差額の1,000万円が「守り」の視点から見た必要な借入額、となります。
銀行に対して、「財務基盤を安定させるため、手元資金を月商の3か月分まで厚くしたい」という説明は、社長のリスク管理能力を示すものとして、十分に説得力を持ちます。
視点3:バランス
「バランス」の借入とは?
「攻め」と「守り」の視点から必要な金額が見えてきましたが、さいごに必ず確認しなければならないのが、「そもそも、その借金を会社は返していけるのか?」という返済能力とのバランスです。
この返済能力を測るための重要な指標が、「簡易キャッシュ・フロー」です。算式であらわすと、
- 簡易キャッシュ・フロー = 税引後利益 + 減価償却費
この金額が、会社が1年間に自由に使えるおカネ(借入返済の原資)の目安となります。
どうやって金額を決めるか?
まず、自社の簡易キャッシュ・フローを計算します。そして、今回あらたに借りようとしている金額と、既存の借入金の残高を合計した総借入額について、年間の返済額がいくらになるかをシミュレーションします。
その年間の返済額が、簡易キャッシュ・フローの範囲内に収まっているかどうか。これが、身の丈に合った借入額かどうかの判断基準です。
もし、年間の返済額が簡易キャッシュ・フローを大幅に超えてしまうようなら、その借入計画にはムリがあると考えます。その場合は、借入額を減らすか、あるいは、より多くの利益を出して簡易キャッシュ・フローを増やすための、具体的な収益改善計画が不可欠です。
ただし、借入したおカネを手元に置いておくだけということであれば、返済原資は置いてあるおカネであり、必ずしも利益を必要とはしないことも理解しておきましょう。
まとめ
銀行融資で「いくら借りるか」を決める際には、以下の3つの視点から、総合的に判断することが重要です。
- 攻めの視点
- 守りの視点
- バランスの視点
どんぶり勘定で金額を決めるのではなく、これら3つの視点から導き出した、根拠のある希望額を銀行に伝えること。
それができれば、銀行からの信頼を得やすくなるだけでなく、社長自身も、自社の未来の財務状況にもより安心を持てるようになるはずです。
ぜひ、次の融資相談の前に、この3つの視点から自社の状況を整理してみましょう。