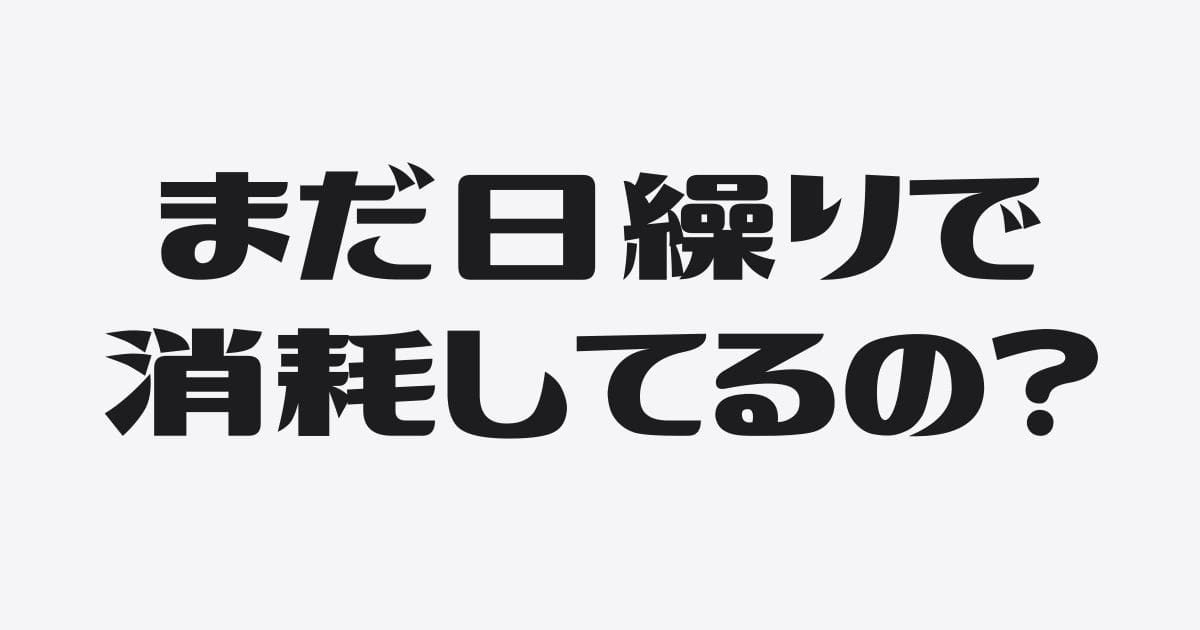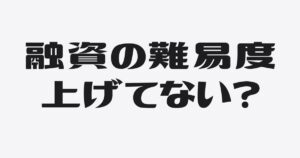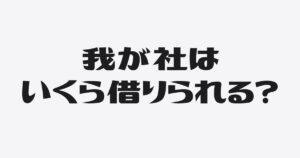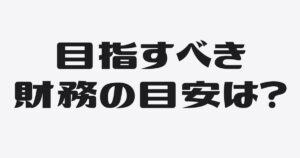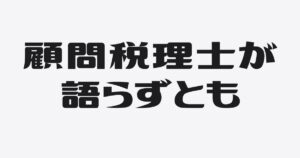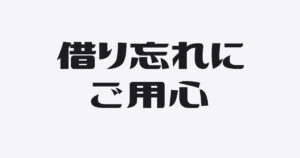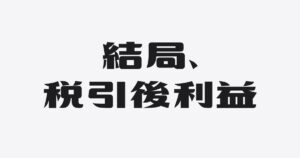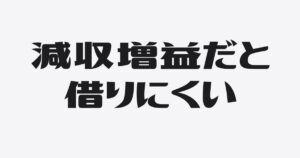毎日、会社の預金残高とにらめっこし、日次の資金繰り表を作成する…一見、几帳面で優れた経営者のように思えますが、実はその行為自体が、会社が危機的状況にあるサインです。
その日次管理は必要なのか?
「今日の支払いは〇〇円、明日の入金は△△円、だから残高は…」
このように、毎日会社の預金残高とにらめっこし、日次の資金繰り表を作成して、なんとか支払いを乗り切っている。そのように努力されている社長もいらっしゃるかもしれません。その勤勉さには、頭が下がる思いです。
しかし、僕から見ると、その状況はきわめて危険だと言えます。なぜなら、会社が「日次」の資金繰り表をつくらなければいけない状況に陥った時点で、その会社は資金繰りという戦いに「負けている」、あるいは負ける寸前だからです。
これは、日々の管理を否定しているわけではありません。日次の資金繰り表の作成が「目的」になってしまっている状態、それ自体が、より深刻な問題の「症状」に過ぎない、ということをお伝えしたいのです。
そこで本記事では、なぜ「日次の資金繰り表をつくったら負け」なのか、その理由と、社長が本来やるべきことは何なのかについて解説していきます。この記事のポイントは以下のとおりです。
- 日次の資金繰り表が必要になる「末期症状」
- 「月次」の資金繰り表で先手を打つことが王道
- 銀行は「日次」より「月次」の計画性を評価する
なぜ「日次の資金繰り表」が負けなのか?
それでは、なぜ一見すると勤勉な行為である「日次管理」が、実は「負け」のサインなのか。その理由を3つの視点から見ていきましょう。会社の資金繰り管理に対する考え方が変わるはずです。
日次の資金繰り表が必要になる「末期症状」
なぜ日次管理が必要になるのか?
そもそも、なぜ日次の資金繰り表が必要になるのでしょうか? それは、会社の預金残高にまったく余裕がなく、その日その日の入出金を確認しないと、支払いが乗り切れるかどうかが分からないからです。
「今日のA社からの入金がなければ、B社への支払いができない」「明日のC社への支払いのために、今日の売上をかき集めなければ…」
これは、いわゆる「自転車操業」の典型的な姿です。
それが「負け」である理由
この状態に陥ると、社長の頭の中は「今日と明日の支払いをどうするか」で100%埋め尽くされてしまいます。
本来、社長が考えるべきである、数か月後、1年後の会社の未来や、事業の成長戦略、あらたな打ち手といった、重要で長期的な意思決定にまったく時間とエネルギーを割けなくなります。
目の前の火消しに追われるだけで、火事の根本原因に手をつけることができない。これは、経営としては完全に後手に回っており、「負け」の状態と言わざるをえません。
「月次」の資金繰り表で先手を打つことが王道
本来あるべき資金繰り管理
では、会社をつぶさない、強い会社の資金繰り管理とはどのようなものでしょうか? それは、「月次」の資金繰り表を活用することです。
日々の残高を追いかけるのではなく、数か月先(最低でも3か月、できれば6か月〜1年先)までの、月ごとの「おカネの出入り」と「月末の預金残高」を予測・管理します。
「月次」管理が「勝ち」につながる理由
月次の資金繰り表があれば、「このままいくと、3か月後に資金がショートする危険性がある」といった未来のリスクを、かなり早い段階で察知できます。
3か月も前に危険を察知できれば、打てる手はたくさんあります。経費の削減、売掛金の早期回収交渉、そして、銀行への計画的な融資相談など、余裕を持って準備をすることができます。
つまり、月次の資金繰り表は、社長が後手に回るのではなく、「先手を打つ」ための強力な武器なのです。日次管理が「延命治療」だとすれば、月次管理は「予防医療・健康管理」と言えるでしょう。
銀行は「日次」より「月次」の計画性を評価する
銀行の視点
融資の相談に行った際、社長が銀行員にどのような資料を見せるか。これも重要なポイントです。
もし社長が、必死の形相で「日次の資金繰り表」を見せて、「今日の支払いができないんです、助けてください!」と訴えたら、銀行員はどう思うでしょうか?
「この会社は、今日明日にもつぶれかねない、きわめて危険な状態だ」「経営が計画的ではなく、完全に行き詰まっている」と感じ、融資に対して極めて慎重になるでしょう。
このようなケースで日次の資料は、会社の「切迫度」を伝えるだけで、銀行を安心させる材料にはなりません。
銀行に評価される資料とは
いっぽうで、社長が「月次の資金繰り表」を見せて、「3か月後にこれだけの資金が不足する見込みなので、〇〇という目的のために、〇〇万円の融資をお願いしたい」と、計画的に相談したらどうでしょうか。
銀行員は、「この社長は、きちんと未来を予測し、課題を把握して、早めに対策を打とうとしている。管理能力が高い」と評価します。
つまり、銀行が評価するのは、日々の場当たり的な対応ではなく、「月次」で未来を管理する計画性なのです。融資を受けやすくするためにも、日次の資料ではなく、月次の資金繰り表が不可欠となります。
まとめ
「日次の資金繰り表」を作成している、あるいは、作成せざるを得ない状況は、すでに会社の資金繰りが危機的状況にある「負け」のサインです。
- 社長が目先の支払いに追われ、未来への手を打てなくなるから
- 本来やるべきは、未来のリスクを予測して、先手を打つための「月次」の管理だから
- 銀行も「日次」の切迫度より、「月次」の計画性を評価するから
もしいま、自社が日次の資金繰りに追われているのであれば、それはもはや猶予のない状態です。一刻も早く、銀行や専門家に相談し、まずは当面の資金繰りを安定させる必要があります。そして、資金繰りが少しでも落ち着いたら、すぐに「月次の資金繰り表」の作成・活用に移行しましょう。
日々の残高を追いかける経営から脱却し、未来を管理する経営へとシフトすること。それこそが、「負け」の状態から抜け出し、「勝ち」のサイクルに入るための、社長がやるべき唯一の道なのです。