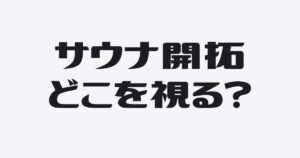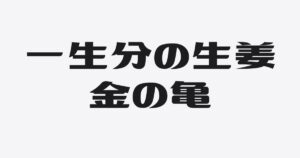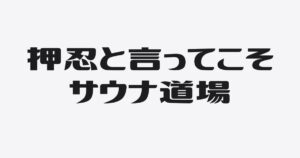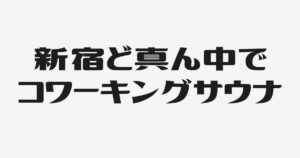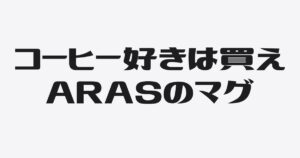Apple信者の僕が、なぜApple Watchではなく「Oura Ring」を6年以上も愛用し続けるのか?その理由を解説。さらに、ガジェット選びの本質について深掘りします。
Apple信者だけどアンチApple Watch
僕は自他ともに認めるApple信者だとおもっています。スマホはiPhone、タブレットはiPad、パソコンはMac、イヤホンはAirPods…と、僕の仕事や生活はApple製品なしでは成り立たないと言っても過言ではありません。
そんな僕が、あえて使っていないApple製品があります。それが、スマートウォッチの「Apple Watch」です。
と聞けば、「Apple信者なのにApple Watchを使わないの?」と意外に思われるかもしれません。
たしかに、Apple Watchは単体で決済もできるし、さまざまなアプリと連携できる、とても高機能で便利なデバイスです。それでも僕が使わないのには、明確な理由があります。そして、その代わりに6年以上も愛用し続けているデバイスがあるのです。
今回は、Apple信者の僕がApple Watchではなく、あるデバイスを使い続ける理由と、その話を通じて本当に伝えたい「たった1つの本質的なこと」について、深掘りしてお話しします。
これは単なるガジェット選びの話ではなく、僕自身の「習慣」や「生き方」にも繋がる話です。
僕がApple Watchの代わりに選んだ「Oura Ring」
僕がApple Watchの代わりに使っているのは、「Oura Ring(オーラリング)」という指輪型のフィットネストラッカーです。
見た目はシンプルな指輪ですが、内側に搭載されたセンサーで、睡眠の質(睡眠時間、深い睡眠、レム睡眠など)や日中の活動量、心拍数、体表温といった体のコンディションを24時間、自動で測定(トラッキング)してくれます。
価格は6万円弱と、ちょうどApple Watchが買えるくらいの値段です。僕は2019年から使い始め、モデルチェンジのたびに買い替えて、今のもので3代目になります。
ではなぜ、一見すると万能に思えるApple Watchではなく、このシンプルな指輪を選び続けているのか。おもな理由は3つです。
理由1/すべてを支配する「圧倒的な身軽さ」
腕時計と指輪では、身につけたときの「身軽さ」がまるで違います。そしてこの身軽さこそが、測定データの質と継続性を左右する、もっとも重要な要素だと僕は考えています。
とくにその差が顕著になるのが「睡眠時」です。
Oura Ringの大きな目的のひとつは、睡眠の質を正確に測定することです。そのためには、当然、寝ているあいだも装着し続ける必要があります。
ここで、腕時計型のデバイスを想像してみましょう。慣れれば平気という方もいるでしょうが、僕にとっては、腕に常に何かが巻かれているという圧迫感や、寝返りを打ったときにシーツに引っかかる感覚が気になってしまいます。最悪の場合、無意識のうちに外してしまい、肝心なデータが取れない、なんてことにもなりかねません。
その点、指輪であるOura Ringは、つけていることを忘れるほど自然です。睡眠を妨げることなく、もっとも無防備な状態の体のデータを、静かに、そして正確に記録し続けてくれます。
もちろん、この身軽さは日中の活動においても大きなメリットです。
夏場、汗をかく時期に腕時計をしていると、バンド部分が蒸れて不快に感じることがあります。パソコンでタイピングをするときも、腕時計が机にあたってカチカチと音がしたり、手首の動きを微妙に制限したりするのが気になります。
Oura Ringであれば、そうしたストレスは一切ありません。どんな季節でも、どんな作業をしていても、僕の体の一部として、ただそこにあるだけ。この「存在感のなさ」こそが、僕がOura Ringを使い続ける最大の理由のひとつです。
理由2/「通知が来ない」という積極的な選択
Apple Watchをはじめとするスマートウォッチの魅力のひとつが、スマホと連携した「通知機能」でしょう。メッセージの受信やスケジュールのリマインドを手元で確認できるのは、たしかに便利です。
しかし僕にとっては、その便利さが逆に「思考を妨げるノイズ」だと感じています。
僕たちは今、常に情報に接続されている「通知過多」の時代に生きています。手元のデバイスがひっきりなしに振動し、光るたびに、僕たちの集中力や注意力は容赦なく削られていきます。
その点、Oura Ringにはディスプレイがなく、通知機能もありません。測定されたデータは、僕が「見たい」と思ったときにだけ、能動的にスマホのアプリを開いて確認します。
これは、情報を「プッシュ型(押し付けられる)」で受け取るのではなく、「プル型(自ら取りに行く)」で接したいという、僕の仕事や生き方に対するスタンスそのものでもあります。
常に外部からの刺激に反応させられるのではなく、じぶんの内側から湧き出る思考や、目の前のタスクに集中するための「静けさ」を、僕は大切にしたいのです。
「でも、時間がわからないじゃないか」とおもわれるかもしれません。たしかにそのとおりですが、僕はもともと腕時計で時間を確認する習慣がありません。必要なときはスマホやパソコンの画面を見れば十分です。
むしろ、「時間を見ない」ことにもメリットを感じています。常に時間に追われる感覚から解放され、より「いま、この瞬間」の活動に没頭できる。Oura Ringの「通知が来ない」という潔い仕様は、そんなマインドフルな状態を後押ししてくれるのです。
理由3/他人と「かぶらない」という意思表示
これは僕の天の邪鬼な性格もあるのですが、「人と一緒がイヤだ」という気持ちが根底にあります。
街中で周りを見渡すと、Apple Watchをつけている人は本当によく見かけます。それは素晴らしい製品であることの証左でしょう。しかし、Oura Ringをつけている人に出会うことは、ほとんどありません。
この「かぶらなさ」は、単なる目立ちたがり屋の気質とは少し違います。僕にとっては、「流行や他人の評価に流されず、じぶんの軸でモノを選ぶ」という意思表示でもあるのです。
「みんなが持っているから」「これがスタンダードだから」という理由で選ぶのではなく、「じぶんにとって本当に必要な機能は何か?」「じぶんのライフスタイルに最適な形は何か?」を考え抜いた結果が、僕にとってはOura Ringでした。
この選択のプロセスは、僕がブログや書籍で何かを発信するときのスタンスにも通じています。世の中の常識や「それっぽい正論」を鵜呑みにするのではなく、じぶん自身の経験と考察にもとづいて、独自の視点を提示したい。
Oura Ringを選ぶという行為は、そんな僕のささやかなポジショニング戦略のひとつなのかもしれません。
話の本質は「じぶんの体を客観的にモニタリングする」習慣にある
ここまでOura Ringの良さをお話ししてきましたが、今日、僕が本当に伝えたいのは、特定のデバイスの優劣ではありません。
Apple Watchであれ、Oura Ringであれ、他のどんなデバイスであれ、それらを活用することの本質的な価値は「じぶんの体を客観的にモニタリングし、行動を変える習慣を身につけること」にあります。
感覚とデータの「ギャップ」に気づく
僕たちは、じぶんの体のことを意外とわかっていません。「きょうはよく寝れたな」という主観的な感覚と、実際の睡眠データが示す客観的な事実が、まったく違うことは日常茶飯事です。
僕自身、「昨夜はぐっすり8時間寝たぞ」と満足していたのに、Oura Ringのデータを見ると、深い睡眠の時間が極端に短く、スコアが低かった、という経験が何度もあります。そして、そういう日は決まって、日中の集中力が続かなかったり、夕方にどっと疲れが出たりするのです。
このじぶんの「感覚」と客観的な「データ」とのギャップに気づくこと。それが、じぶんの体をより深く理解し、本当のコンディションに合わせたセルフケアを行うための、重要な第一歩になります。
体調変化の「先行指標」を手に入れる
さらに、データを継続的に記録することで、体調変化の「兆候」を早期につかめる可能性もあります。
Oura Ringは、平常時の心拍数や心拍変動、体表温などを基準として、そこからの逸脱を検知します。たとえば、僕自身の経験では、「体表温がいつもより少し高い」というアラートがアプリに表示されることがあります。
その時点では自覚症状がなくても、そのアラートを見て「今日は無理せず、早めに休もう」と備えることができるのです。
これは、体からの小さなサインをデータとして可視化し、本格的な不調に陥る前に対策を打つための「先行指標」を手に入れることに他なりません。
データを行動に変える「習慣」こそがすべて
そして、もっとも重要なのが、これらのデータを具体的な「行動変容」に繋げることです。データをただ眺めているだけでは、何も変わりません。
- 「睡眠スコアが低いから、今夜は寝る前のスマホをやめて、読書の時間にしよう」
- 「日中の活動量が目標に達していないから、帰りに一駅手前で降りて歩こう」
- 「心拍数が高い状態が続いているから、今日の午後は少し休憩時間を多めにとろう」
このように、データにもとづいて日々の行動を微調整していく。この**「データ→分析→行動変容」のサイクルを回し続ける**ことこそが、「習慣化」の真髄です。Oura Ringは、そのサイクルを回すための、僕にとっての最適なコーチなのです。
まとめ
Apple信者の僕がApple Watchを使わない理由は、「身軽さ」「通知がない静けさ」「他人とかぶらない」という3点から、Oura Ringを愛用しているからです。
しかし、今日の本質的なテーマは、その先にある「じぶんの体を客観的に知る習慣」の重要性です。
じぶんの感覚だけに頼るのではなく、何かしらのツールを使って日々の体の状態を数値化・可視化してみる。そして、そのデータをもとに行動を変えていく。
ガジェット選びは、単なる機能やデザインの好みだけでなく、その人の価値観やライフスタイル、そして「どんな習慣を築きたいか」という意思のあらわれでもあります。
あなたにとって、本当に価値のあるものは何でしょうか?そして、その価値を守り、育てるために、あなたはどんなツールを選び、どんな習慣を築いていきますか?
まずは、じぶんの体を客観的に見つめ直すことから、始めてみてはいかがでしょうか。