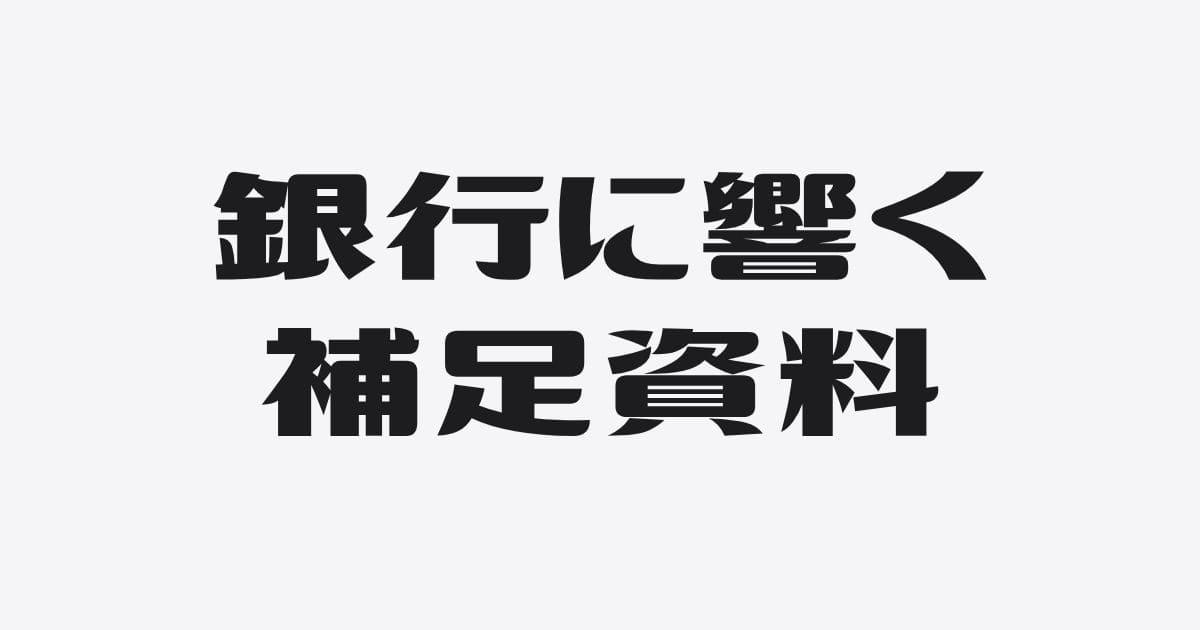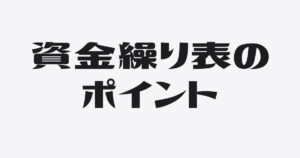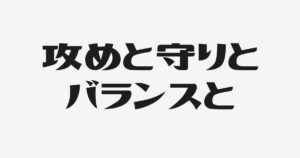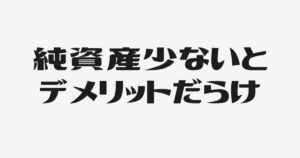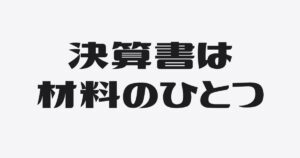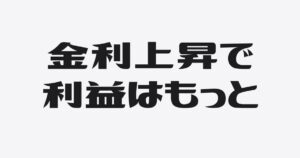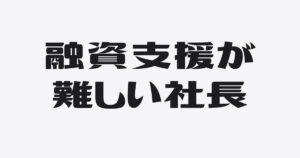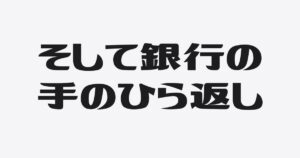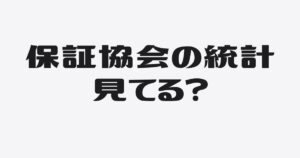銀行の評価を高めるはずの補足資料が、実は逆効果になっているかも?銀行に「この会社は将来が楽しみだ」と思わせる、効果的な補足資料作成の3つのポイントを解説します。
なぜ「+α」の資料が銀行評価を変えるのか?
決算書、試算表、資金繰り表…銀行に提出すべき必須書類はきちんとそろえている。それでも、銀行の評価がいまひとつ上がらない、融資交渉がスムーズに進まないと感じていませんか?
それは、社長が伝えるべき「会社の魅力」が、銀行に届いていないからかもしれません。
銀行は、「過去の数字」である決算書と同じくらい、あるいはそれ以上に、会社の「未来」や「社長の考え」を知りたがっています。貸したおカネが将来きちんと返済されるか、その将来性を判断したいからです。
しかし、良かれとおもって提出した補足資料が、要点が不明瞭だったり、根拠が薄かったりすると、かえって評価を下げる「逆効果」にもなりかねません。銀行員は忙しく、分かりにくい資料、信憑性のない資料は評価を下げかねないのです。
銀行に響く補足資料とは、銀行が知りたい「未来への信頼性」を具体的に示すもの。それは「具体性」「透明性」「分かりやすさ」の3つのポイントで決まります。
銀行に「響く」補足資料作成の3つのポイント
銀行を納得させ、融資審査をスムーズに進めるための補足資料には、3つの共通点があります。銀行が決算書の数字の裏で何を求めているのか、その本音を理解し、担当者の心に「響く」資料を作成しましょう。
ポイント1:「具体性」と「根拠」で未来の行動を示す
銀行が融資判断で最も知りたいのは、「貸したおカネが将来きちんと返済されるか」です。そのため、社長の「がんばります」といった精神論や、「景気が良くなれば回復します」といった根拠のない楽観論は評価されません。銀行が求めているのは、未来の返済能力を裏付ける、具体的で客観的な根拠です。
経営計画書で「行動」を語る
たとえば、経営計画書を作成する際は、単なる数値目標だけでなく、「何を」「いつまでに」「誰が」「どのように」実行するのかという具体的な「行動計画」をセットで示すことが重要です。なぜその数値目標が達成できると考えるのか、その根拠(自社の強み、市場の機会、競合との差別化など)を明確に語ることで、計画は「絵に描いた餅」から「実現可能な未来図」へと変わります。
見積書とシミュレーションで「投資」を語る
設備投資を検討するなら、メーカーからの「見積書」はもちろん、「なぜ今その投資が必要なのか」「その投資によってどれだけの効果(生産性向上、コスト削減、利益増加)が見込めるのか」を具体的に説明します。可能であれば、投資回収の簡易なシミュレーションを添えると、社長が計画的に投資判断をしていることのアピールになります。
受注リストで「売上」を語る
売上増加を見込む場合、その裏付けは不可欠です。特に「増加運転資金」を申し込む際には、具体的な「受注見込みリスト」や「契約書」を提示することが、銀行の納得感を高めるために最も有効な手段の一つです。こうした具体的な根拠こそが、銀行の信頼を得る第一歩となります。
ポイント2:「透明性」を高め、銀行の不安を払拭する
銀行は融資審査において、常に「この決算書は実態を正しく映しているか?」「粉飾決算や隠れたリスクはないか?」と警戒しています。なぜなら、中小企業の決算書は税務会計が優先されがちで、必ずしも会社の実態と一致しない(あるいは意図的にズラされている)可能性があることを知っているからです。社長がその不安を先回りして払拭することが、信頼獲得のカギとなります。
在庫・売掛金の「実在性」を証明する
たとえば、在庫(棚卸資産)が多い場合、銀行は「不良在庫や架空在庫ではないか」と疑います。これは粉飾決算の典型的な手口だからです。この不安を払拭するために、「在庫一覧表」を提出したり、銀行担当者を招いて「実際に現物を見てもらう」ことは効果的です。
同じように、売掛金も「不良債権や架空債権ではないか」と見られています。勘定科目内訳明細書を詳細に記載することはもちろん、「売掛金の売掛先別増減一覧」を別途作成し、回収サイトの実態を明確にすることで、資産の健全性を証明できます。
雑勘定を整理し「公私混同」の疑いを晴らす
「仮払金」や「社長への貸付金」といった雑勘定は、使途不明金や社長の公私混同、粉飾の温床として銀行から厳しく見られます。これらの勘定科目を日ごろから整理・精算し、決算書をスマートにしておくこと自体が、経営の透明性のアピールになるのです。
「実態貸借対照表」で誠実さを示す
銀行が内部で行うであろう決算書の修正(資産の評価減、簿外債務の認識など)を、社長自らが「実態貸借対照表」として開示することも有効です。自社の弱点を隠さず、誠実に向き合う姿勢は、銀行に「この社長は信用できる」という強い印象を与えます。自ら情報をオープンにし、ガラス張りの経営をアピールすることが、銀行の信頼を勝ち取ります。
ポイント3:「分かりやすさ」を追求し、担当者を味方につける
銀行員はあなたの会社の専門家ではありません。また、何十社もの担当先を抱えて多忙です。分厚すぎる資料や、業界の専門用語だらけで要点が不明瞭な長文資料は、読んでもらえない(=評価されない)可能性が高いと心得ましょう。
「A4一枚」に要点を凝縮する
忙しい銀行員が短時間で概要をつかめるように、決算報告書や計画書の要約を「A4用紙1枚」ていどにまとめるのは有効な手段です。これは、担当者が稟議書を作成する際の手助けにもなり、審査のスピードアップにも繋がります。
図やグラフで「視覚」に訴える
文字ばかりの説明ではなく、「商流図(ビジネスモデルを説明するため)」や「業績推移グラフ」など、視覚的に分かりやすく伝える工夫も求められます。銀行は「この会社は何屋さんで、どうやって儲けているのか」を理解したいのですが、決算書だけではそれが分かりにくいものです。
基本資料で「何屋さん」かを明確に
自社のビジネスモデルを簡潔に伝える「会社概要」や「商品パンフレット」も、銀行が事業内容を理解するうえで重要な基本資料となります。
相手の目線に立ち、「どうすれば伝わるか」を最優先に考えた資料こそが、担当者に「この社長の説明は分かりやすい」と感じさせ、「この会社を支援したい」というポジティブな感情を引き出し、審査をスムーズに進めるカギとなるのです。
まとめ
決算書以外の補足資料は、銀行評価を高め、融資を有利に進めるための強力な武器になります。
ただし、その効果を最大限に発揮させるには、「具体性・根拠」「透明性」「分かりやすさ」の3つのポイントを押さえることが重要です。
銀行が何を知りたいかを考え、先回りして質の高い情報を提供することで、単なる融資先から「信頼されるパートナー」へと関係性を深めることができます。
まずは自社のアピールポイントや課題を整理し、それを「伝わる」資料に落とし込むことから始めてみませんか?