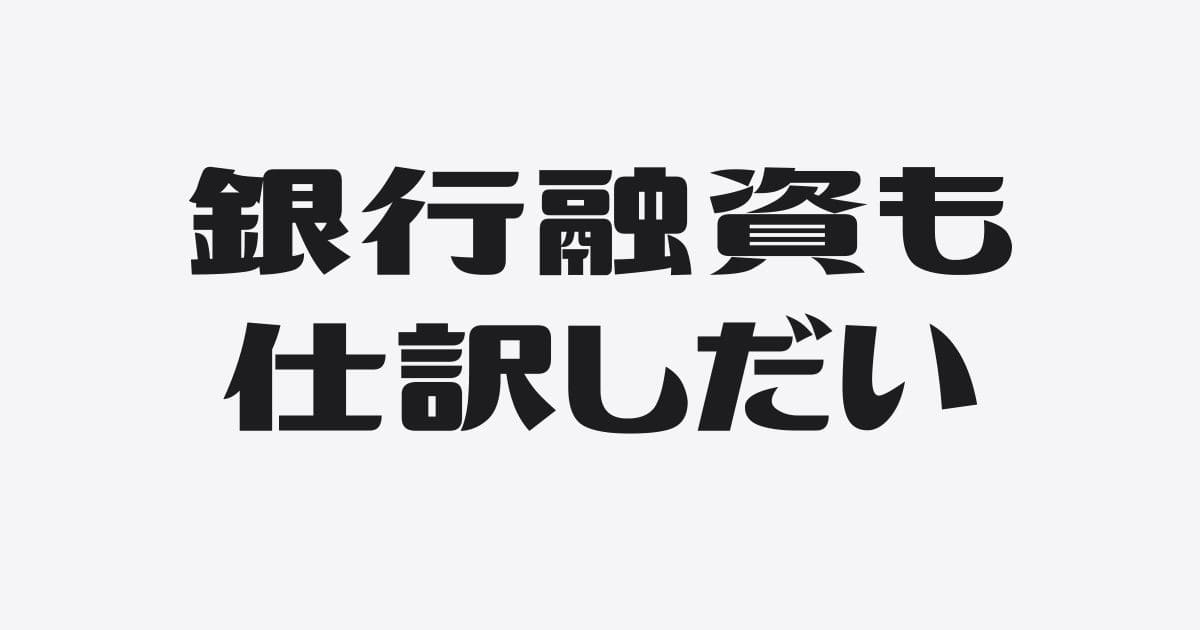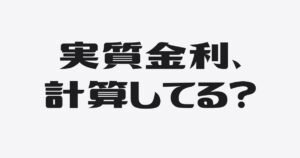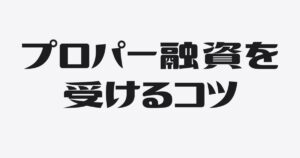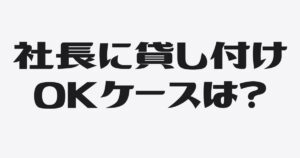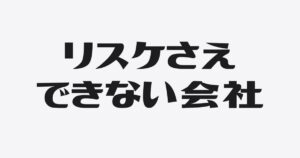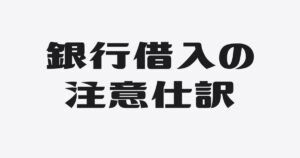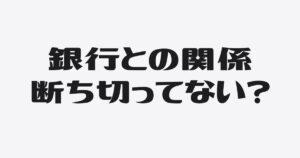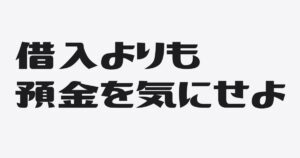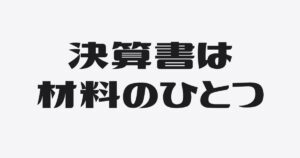仕訳しだいで銀行融資は受けやすくなります。仕訳だけで融資が受けやすくなるわけではないものの、仕訳によって融資が受けやすくなる可能性はある。この話を深堀りしてみます。
妄想ではなく事実として
会社の銀行融資について、仕訳しだいで融資は受けやすくなります。仕訳「だけ」で融資が受けやすくなるわけではないものの、仕訳によって融資が受けやすくなったり、受けにくくなったりする「可能性はある」ということです。
これは僕が勝手に考えている妄想のたぐいではなく、きょうまで銀行融資支援にかかわるなかで、銀行員の方々からお聞きした話をふまえたものであり、事実にもとづいています。
というわけで、「仕訳しだいで融資は受けやすくなる」との話を、順を追って深堀りしてみましょう。このあと次のような流れで考えていきます。
- 仕訳だけでは変わらない
- 仕訳で変わる部分もある
- それが会社のためになる
これらを理解することで、仕訳「だけ」で融資が受けやすくはならないことや、それでも仕訳しだいで融資は受けやすくなる「可能性がある」との気づきになるはずです。
仕訳だけでは変わらない
仕訳しだいで銀行融資は受けやすくなります。が、仕訳「だけ」で融資が受けやすくなるわけではない、ともいいました。これを具体例で考えてみましょう。
たとえば、経常利益をよく見せるために、本来は特別利益として区分すべき「固定資産売却益」を、営業外収益として区分しているケースがあります。たしかに一見すると経常利益はよく見えるので、仕訳しだいで銀行融資が受けやすくなるようにおもえるかもしれません。
しかし、事実とは異なるという点で、銀行から見れば粉飾決算にあたる行為です。本来は特別利益なのですから、営業外収益とするのは事実と異なります。
ちまたには、このような行為もいっしょくたにして「仕訳しだいで融資は受けやすくなる」とのアドバイスもあるので気をつけましょう。銀行は仕訳(=決算書)だけを見ているのではなく、事実も確認をしているため、仕訳だけで融資が受けやすくなることはありません。
繰り返しになりますが、事実と異なる仕訳をすれば、銀行融資においてはむしろ逆効果です。銀行からは「信用ならない仕訳をする会社(=信用ならない決算書をつくる会社)」とみなされれば、以降の融資は受けにくくなってしまいます。
とはいえ、それでも仕訳しだいで融資が受けやすくなる可能性があるのも事実です。仕訳しだいで、銀行の心象や銀行の評価が変わる可能性はあるのです。
仕訳で変わる部分もある
たとえば、会社が社長からおカネを借りているときに、これを「短期借入金」として仕訳しているケースがあります。しかし、その借入が長期に及ぶものであり、社長がすぐに返済を求める状況でなければ、勘定科目は「役員借入金」として固定負債に区分するのがよいでしょう。
銀行に資本とみなしてもらえる可能性があるからです。すると、決算書の見た目よりも、銀行の評価上は「負債が減り、資本が増える」ので、融資が受けやすくなる可能性があります。
もっとも、勘定科目を「短期借入金」としていても、銀行が勘定科目内訳明細書などの情報から、実態は「役員借入金」であると気づくケースもあるでしょう。しかし、それは期待にすぎず、必ずしも銀行が気づくかどうかはわかりません。気づかなければ、ムダに評価を下げてしまいます。
いっぽう、「役員借入金」で仕訳をしておけば、銀行が気づかないことはまずありません。ですから、銀行に期待をするのではなく、会社自身でできることはやりましょう。できることとはつまり、「より実態をあらわす仕訳をする」ということです。
ほかには、減価償却をしていない会社の例が挙げられます。減価償却費は法定限度額まで計上すべきというのが、銀行の考え方です。それが実態をあらわすということであり、その減価償却費を計上していなければ、実態をあらわしていない(=粉飾決算)と見られてしまいます。このとき、「赤字だから減価償却はしません」との言い訳は通用しません。
このように、仕訳は実態をあらわしているかが重要なのであり、仕訳しだいで融資が受けやすくなったり、受けにくくなったりすることを理解しておきましょう。
それが会社のためになる
仕訳「だけ」で融資が受けやすくはならないことや、それでも仕訳しだいで融資は受けやすくなる「可能性がある」ことについてお伝えしてきました。これを受けて、おもわれたかもしれません。
銀行のために仕訳をするのか?融資を受けるために仕訳を変えるのか?
それは違います。銀行のため、融資を受けるために仕訳を変えたかのように見えても、それが会社自身のためでもあるからです。
ここまで、いくつかの仕訳例を挙げました。まず、本来は特別利益として区分すべき「固定資産売却益」を、営業外収益として区分しているケース。このままでは、社長が自社の業績(経常利益)を見誤る可能性がありますが、仕訳を正すことでそれを防げます。
次に、会社が社長からおカネを借りているときに、これを「短期借入金」として仕訳しているケース。短期借入金とは本来、1年以内に返済する借入金であることから、そこに返済しなくてもよい役員借入金が混じっていれば、社長は資金繰りを見誤る可能性があります。やはり、仕訳を正すことでそれを防げるでしょう。
さいごに、減価償却をしていない会社の例を挙げました。減価償却をしなければ、その分だけ決算書の利益は過大となるため、社長は自社の収益力を見誤る可能性があります。仕訳を正せば、社長は正しい収益力を把握できるようになるのです。
結果、社長が正しい経営判断できるようになれば、より経営は改善して利益は増える。ひいては資金繰りはさらによくなる、という好循環が期待できます。これに対して、銀行による仕訳の見方を知らずにいると、実態をあらわさない決算書となり、社長が経営判断を誤るおそれがあります。
よって、銀行のため、融資を受けるための仕訳をすることが、本質的に会社のためにもなるのです。本記事で取り上げた例以外にも、確認したほうがよい仕訳はいろいろあります。詳しくは書籍に書きましたので、よろしければこちらも参考にどうぞ。
『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90(日本法令)』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
まとめ
仕訳しだいで銀行融資は受けやすくなります。妄想ではなく事実として、この話を深堀りしてみました。
- 仕訳だけでは変わらない
- 仕訳で変わる部分もある
- それが会社のためになる
これらを理解することで、仕訳「だけ」で融資が受けやすくはならないことや、それでも仕訳しだいで融資は受けやすくなる「可能性がある」との気づきになるはずです。