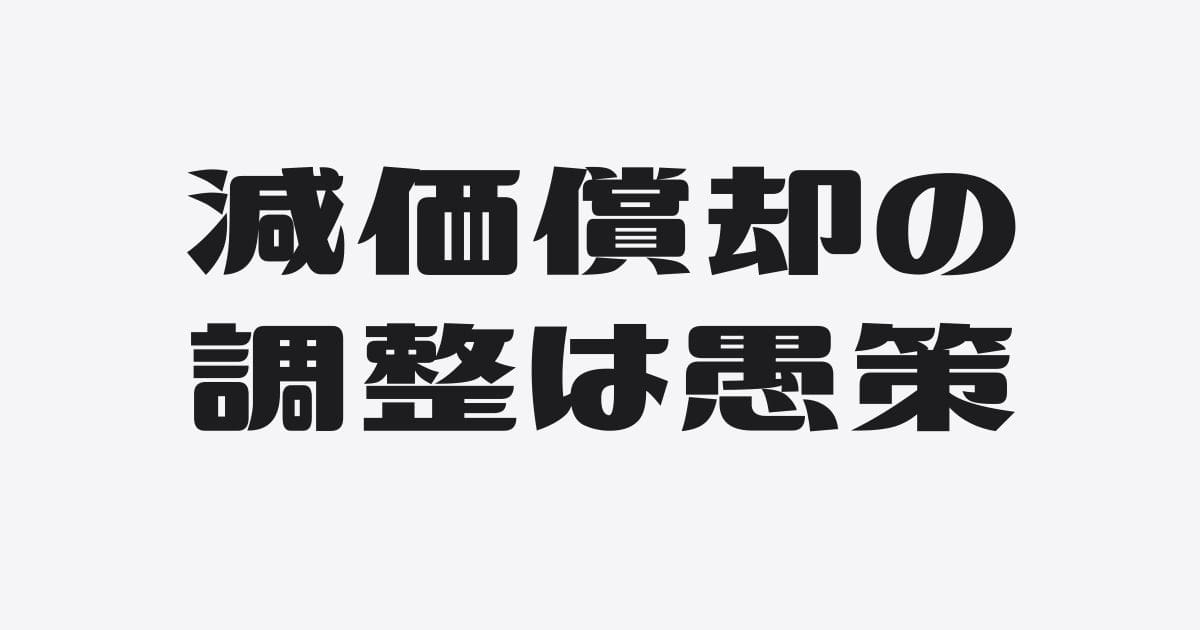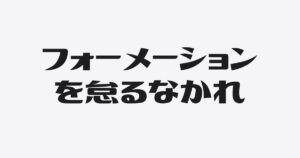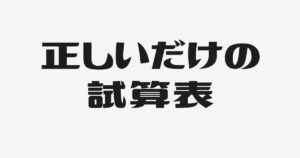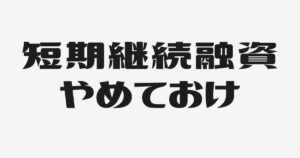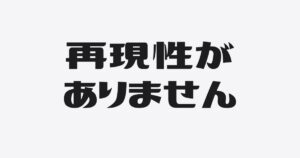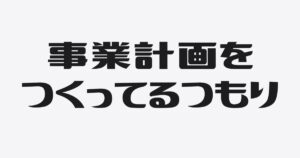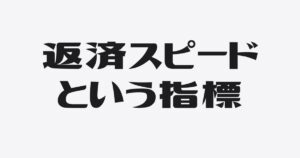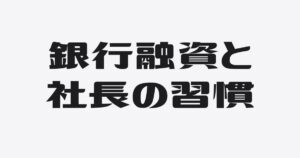ちまたには、いろいろな銀行対策のハナシがありますが。減価償却費を減らして利益を増やす、その銀行対策は無意味です。その理由を理解して、誤解を正しましょう。
減価償却費を減らして利益を増やせば
銀行から融資を受けるための銀行対策、というハナシがあります。このうち、有効な対策として誤解されているものの1つが「減価償却費を減らす」ことです。
減価償却費とは費用であり、それを減らすことで利益を増やせば銀行からの評価は上がる。すると、融資が受けやすくなるはずだ。と、そんな考え方にもとづいています。が、誤解です。
減価償却費を減らして利益を増やす、その銀行対策は無意味だといえます。理由は3つ、以下のとおりです。
- 粉飾と見られる
- 銀行は修正する
- CFは影響なし
誤解を正すためにも、これらの理由を押さえておきましょう。誤解したままでいると、つまり、本当に減価償却費を減らしているようだと、むしろ融資が受けにくくなってしまいます。
減価償却費を減らすのが無意味な理由
融資を受けるための銀行対策として、減価償却費を減らすのが無意味な理由は3つあります。それぞれの理由について、何が問題になるのかを理解するようにしましょう。
粉飾と見られる
減価償却費を減らすのが無意味な理由、1つめは「粉飾と見られる」です。
そもそも粉飾とは「利益や資産の水増し」であり、事実とは異なる決算書をつくる行為をいいます。当然、良いことではありません。減価償却費を減らせば、銀行から「良くないこと(粉飾)をしている会社」と見られてしまうのが問題です。
では、減価償却費を減らすとはどういうことなのか。まず、減価償却費に対する銀行の考え方は、「法定限度額を計上すること」です。法定限度額とは、税法で定める限度額であり、減価償却の対象となる資産ごとに異なります(詳しくは税理士に確認を)。
なんにせよ、減価償却の対象となる資産があるのなら、法定限度額まで計上することが銀行にとっての「正義」です。それよりも少ない額しか計上しないとなると、利益・資産の水増しとして粉飾と見られることになります。
なお、減価償却費を法定限度額よりも少なく計上するのは、税法的にはOKです(費用が減って税金が増えると考えれば、税務署としてはむしろ喜ばしい)。なので、減価償却費を減らすのは会社の自由といえば自由なのですが、「利益を調整している」ことが問題だと銀行は考えます。
そして、「減価償却費で調整しているのであれば、ほかにもなにか調整をしているかもしれない。そういう調整を毎年しているかもしれない」として、「信用ならない決算書をつくる会社」とみなされることになります。その結果として、融資が受けにくくなるのです。
だとしたら、減価償却費を減らすことは、融資を受けるための銀行対策としては無意味だといえるでしょう。
銀行は修正する
減価償却費を減らすのが無意味な理由、2つめは「銀行は修正する」です。
前述したように、銀行から粉飾と見られたからといって、必ずしも融資が受けられないわけではありません。ただし、銀行は法定限度額で減価償却費を計上したものとして決算書を修正しています。そのうえで、会社の業績を評価しているのです。
たとえば、減価償却費の法定限度額が800万円だとします。減価償却費を計上する前の利益が300万円である場合、800万円の減価償却費を計上すると赤字です。そこで、減価償却費を200万円として100万円の黒字に見せかけようとする会社があります。
ところが、銀行は決算書を見れば「法定限度額は800万円」とわかるので、本当の利益は「減価償却費を計上する前の利益300万円−減価償却費の法定限度額800万円=500万円の赤字」として修正して評価をしているわけです。
なので、銀行からは減価償却費を減らしていることについて何もいわれていないとしても、銀行は「勝手に」修正をして評価をしているのであり、銀行が気づいていないのではありません。
だとしたら、減価償却費を減らすことは、融資を受けるための銀行対策としては無意味だといえるでしょう。
ちなみに、ほかの「調整(粉飾)」についても同じことです。たとえば、貸倒損失を計上しない、不良在庫の損失を計上していない、買掛金や未払金の計上を見送っているなど。そういった調整を銀行は見抜いているものですし、なかったものとして修正されていることになります。
CFは影響なし
減価償却費を減らすのが無意味な理由、3つめは「CFは影響なし」です。
ここでいうCFとは、「キャッシュフロー」のことであり、もう少し具体的にいうと「税引後利益+減価償却費」をいいます。銀行は、そのCFを「返済力(返済原資)」と見ているのです。そのうえで、「CF>年間返済額」が望ましいと考えています。
逆に、「CF<年間返済額」となれば、理屈としては融資ができません。貸しても返してもらうことができるなくなるからです。では、減価償却費を減らす(粉飾する)とどうなるのか?CFをよく見せかけることができるのか?具体例で考えてみましょう。
税引後利益が300万円の赤字、減価償却費が500万円とした場合、CFは「▲300万円+500万円=200万円」です。
ここで、減価償却費をゼロに調整すると、税引後利益は200万円の黒字になります。するとCFは、「200万円+0万円=200万円」です。減価償却費を調整する前と変わりません。つまり、減価償却費を調整しようとしまいと、CFは影響を受けないのです。
言い換えると、減価償却費を調整してもしなくても、銀行の「返済力(返済原資)」の評価には影響しないということです。だとしたらやはり、減価償却費を減らすことは、融資を受けるための銀行対策としては無意味だといえるでしょう。
そのうえ、減価償却費を調整すれば、銀行からは「調整(粉飾)をする会社」という悪い印象が付いてしまうのでは損しかありません。
なお、前述のCF「▲300万円+500万円=200万円」のケースは、利益こそ赤字ですが、返済原資としては200万円のプラスであることから、年間返済額200万円までの融資は可能という見方ができます。
まとめ
ちまたには、いろいろな銀行対策のハナシがありますが。減価償却費を減らして利益を増やす、その銀行対策は誤解であって無意味です。その理由を3つ、お話ししました。
- 粉飾と見られる
- 銀行は修正する
- CFは影響なし
誤解を正すためにも、これらの理由を押さえておきましょう。誤解したままでいると、つまり、本当に減価償却費を減らしているようだと、むしろ融資が受けにくくなってしまいます。