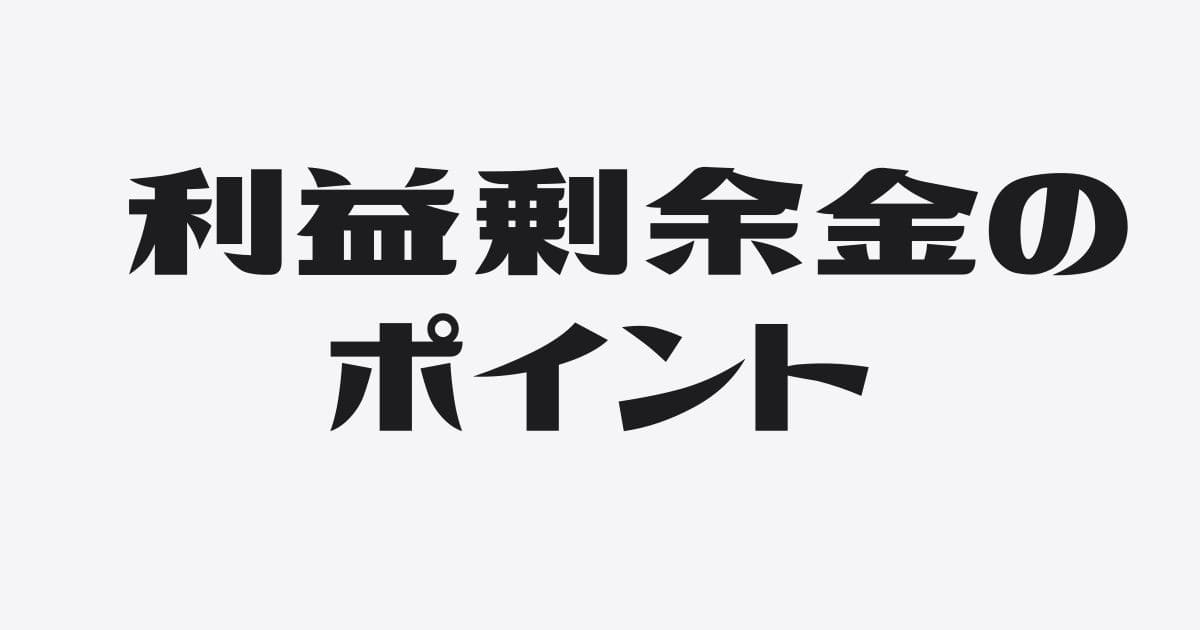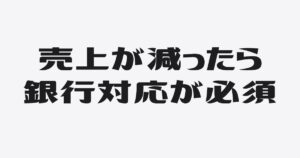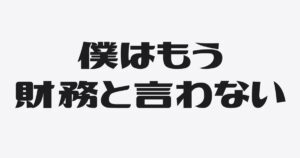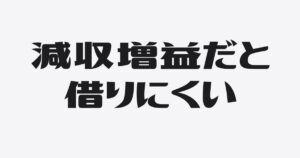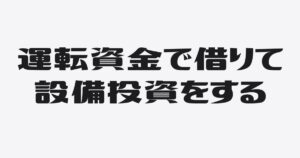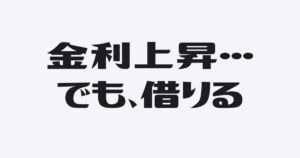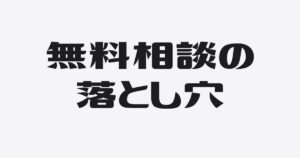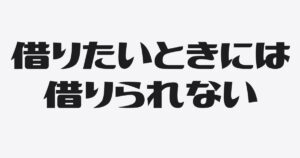銀行が決算書を見るときには、利益剰余金に注目をしています。ですから、社長もまた注目すべく、銀行融資における利益剰余金の確認ポイントを押さえておきましょう。
「利益剰余金?なにそれ?」と社長は言った
会社の銀行融資について、銀行が決算書を注目しているのはご存知のとおりです。このとき、銀行がどこに注目をしているのか?そのひとつに挙げられるのが「利益剰余金」です。
ところが、決算書を提出する社長はといえば、「利益剰余金?なにそれ?」といった状況もありえます。つまり、社長は利益剰余金にはなじみがなく、注目もしていないということです。このギャップが、銀行融資を受けにくくしている原因になっていることがあるので気をつけましょう。
ちなみに利益剰余金とは、決算書のうち「貸借対照表」の「純資産」を構成する勘定科目です。直接的な取引や、直接的な仕訳によって利益剰余金が登場する機会はめったにありませんが、いっぽうで利益剰余金は常に変動しています。ゆえに、定期的な確認も必要なのです。
そのうえで、銀行融資における利益剰余金の確認ポイントは3つあります。
- 1年平均はいくらか
- 赤字の何年分あるか
- 債務超過は3年まで
これらは銀行の見方でもありますので、銀行融資を受けやすくするためにも、社長は覚えておきましょう。このあと、3つのポイントを順番に解説していきます。
銀行融資における利益剰余金の確認ポイント
繰り返しになりますが、利益剰余金とは、決算書のうち「貸借対照表」の「純資産」を構成する勘定科目です。この点、損益計算書ばかり見ている社長もいますし、貸借対照表を見るクセをつけましょう。そのうえで、利益剰余金も確認を怠らないことです。
1年平均はいくらか
銀行融資における利益剰余金の確認ポイント、1つめは「1年平均はいくらか」です。利益剰余金を見ることで、1年平均でどれくらいの利益を出しているのかがわかります。
冒頭、利益剰余金は常に変動しているといいました。利益剰余金とは、過去の税引後利益の累計額であり、税引後利益に連動して利益剰余金は変動しているのです。よって、税引後利益が黒字であれば利益剰余金は増えるし、税引後利益が赤字なら利益剰余金は減ります。
だとすれば、「利益剰余金÷期数(創業からの年数)」によって、1年平均どれくらいの利益かを計算できることがわかるでしょう。
上記の計算をした結果、たとえば500万円だとします。いっぽうで、今期の税引後利益がマイナス100万円だとしたら、「赤字ではあるけれど、過去の利益から見たらそれほど心配はなさそうだ」との見方もできるわけです。銀行もまた、そのような見方をしています。
これに対して、今期の税引後利益が1,000万円という場合、「過去の利益から見たら調子がよさそうだけれど、たまたま(まぐれ)かもしれない」との見方をするのが銀行です。
以上をふまえて、会社はできるだけ利益剰余金を積み上げること、つまり、毎期の税引後利益をできるだけ増やすことが有効だといえます。そうすれば、1年平均の利益は大きくなり、赤字のときにも銀行の心配をやわらげられますし、大きな黒字も実力として見られやすくなるからです。
税金を減らすために利益を減らそうとする社長がいますが、利益剰余金の観点からすると得策とはいえません。節税も悪くはありませんが、利益剰余金にも目を向けましょう。
赤字の何年分あるか
銀行融資における利益剰余金の確認ポイント、2つめは「赤字の何年分あるか」です。利益剰余金がプラスの金額であれば、何年の赤字に耐えられそうかを銀行は見ています。
そもそも、銀行は純資産がプラスかどうかを重視しています。純資産のマイナスは「資産<負債」(債務超過)を意味するのであり、だとしたら融資をするわけにはいきません。ゆえに、銀行は純資産がプラスであることを求めます。
その純資産とは「資本金+利益剰余金」でもあり、だとすれば、利益剰余金のマイナスが資本金を超えると純資産がマイナスになることがわかるでしょう。この点、具体例で考えてみます。
資本金300万円、利益剰余金が700万円という会社があったとして、赤字の場合には年300万円ていどが想定される場合はどうでしょう?
3年赤字が続けば、利益剰余金は「700万円−300万円×3」なので、マイナス200万円になります。それでも資本金が300万円あるので、純資産は「300万円−200万円」でプラスを維持することが可能です。つまり、債務超過にはなりません。
よって、この会社の利益剰余金であれば、3年の赤字に耐えられることになります。というように、資本金と利益剰余金とをあわせて、想定される赤字の何年分あるかを確認しておきましょう。
目安として、2年分以上は必須だといえます。2年連続赤字というのは起こりうる状況なので、そのときにも債務超過にならないくらいの利益剰余金は確保しておきたいということです。
3年分以上であれば、より安心だといえます。3年連続赤字は、2年連続赤字に比べれば起きる可能性が小さくなるからです。
債務超過は3年まで
銀行融資における利益剰余金の確認ポイント、3つめは「債務超過は3年まで」です。債務超過とは、純資産がマイナスの状態であり、3年で解消すべしというのが銀行の見方になります。
仮に、純資産(資本金+利益剰余金)がマイナス900万円とした場合、3年で債務超過を解消するには、1年あたり300万円の黒字が必要です。銀行は「それが実現できるのか?」と考えます。
よって、債務超過の状態であれば、会社は「3年で債務超過を解消できる」ものとして、利益計画を提示することが重要です。前述の例であれば、1年あたり300万円の黒字という計画です。
これに対して、計画をつくれない・つくらない場合や、そもそもそれだけの利益を出すのは不可能だとなれば、銀行から追加で融資を受けることは難しくなります。そのときには、リスケジュール(返済の猶予)を相談することになるでしょう。なお、その場合にも、5年で債務超過を解消する計画を求められることになります。いずれにせよ、債務超過は問題なのです。
ゆえに、社長は常に「債務超過」に目を光らせましょう。まずは、債務超過にならないようにすることです。債務超過になった時点で、融資を受ける難易度は格段に上がります。今期赤字を免れないのだとしても、債務超過にならない範囲(資本金+利益剰余金>0)に赤字をおさめられないかにこだわるということです。
これに関連して、「特別損失で赤字になっても、営業利益や経常利益がプラスなら大丈夫」といったハナシには気をつけましょう。たしかに、特別損失は本業の収益力には関係がないため、本業の評価には影響を与えません。ですが、特別損失を計上したことで税引後利益が大きく赤字になり、その結果として純資産がマイナスになったとしたらどうでしょう?
当然、銀行は債務超過を問題視します。そこは、本業の評価とは別ですから注意しなければいけません。
まとめ
銀行が決算書を見るときには、利益剰余金に注目をしています。社長にとってはなじみがなく、注目もしていなかったりするので注意が必要です。そこで本記事では、銀行融資における利益剰余金の確認ポイントを3つ、お伝えしました。
- 1年平均はいくらか
- 赤字の何年分あるか
- 債務超過は3年まで
これらは銀行の見方でもありますので、銀行融資を受けやすくするためにも、社長は覚えておきましょう。逆に、これらがわかっていないと、融資を受けにくくすることにもなりかねません。