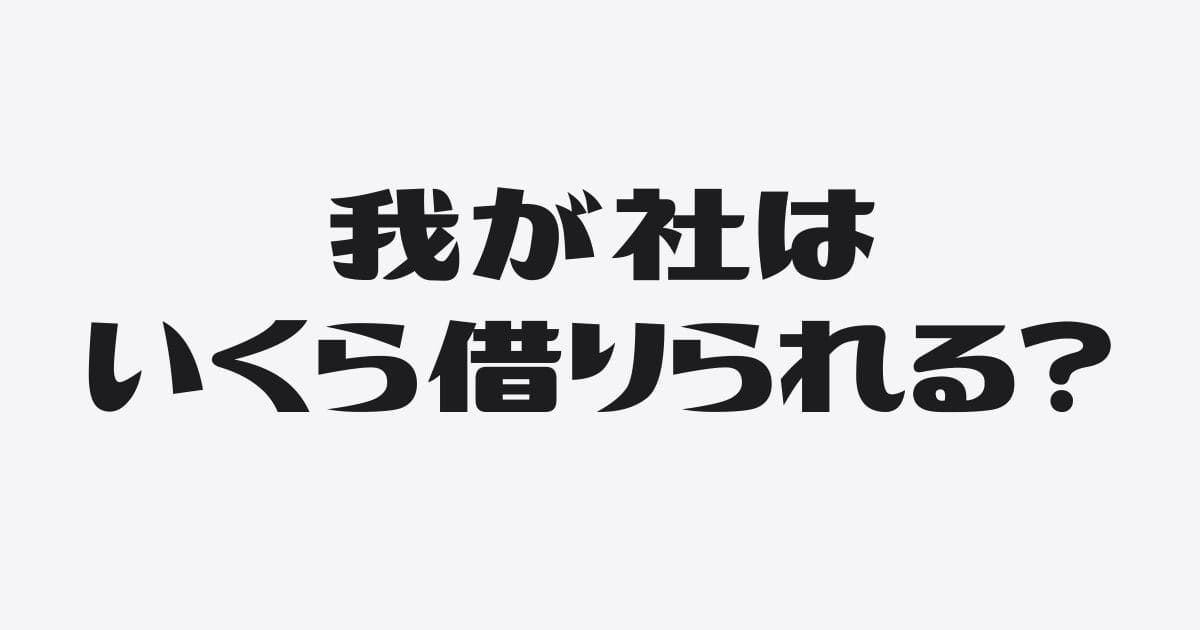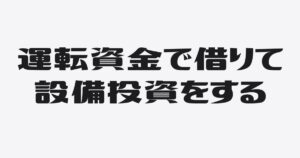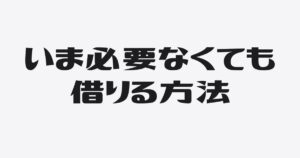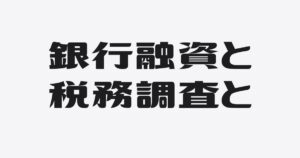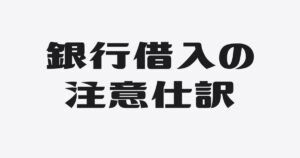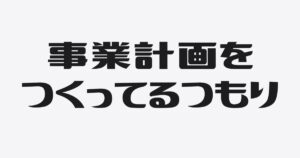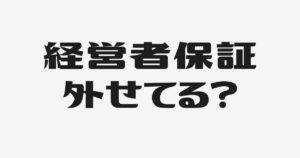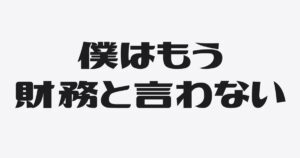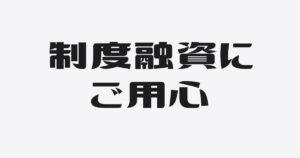社長にとって、銀行からいくら借入できるかは関心事のひとつでしょう。とはいえ、銀行に聞けばよいかというとそうでもありません。そこで本記事では、いくら借入できるかの目安をお伝えします。
銀行は、貸せるだけ貸すのではない
社長にとって、銀行からいくら借入できるかは関心事のひとつでしょう。いくら貸すかを決めるのは銀行なので、銀行に聞けばよいかというとそうではありません。社長が「いくら借入できますか」などと聞こうもうのなら呆れられてしまいます。なぜなら、銀行は必要な金額を貸すのであって、貸せるだけ貸すのではないからです。
とはいえ、銀行に借入の相談をするにも、あらかじめ「いくら借入できるか」を知りたいのが社長の本音でしょう。そこで、会社が銀行からいくら借入できるかの目安をお伝えします。次の3つです。
- 経常運転資金
- 債務償還年数
- 借入月商倍率
これらが、「いくらくらい借入できそうか」の目安になります。あくまで参考であり、絶対の目安ではありませんが、何の目安もないよりは借入の検討がしやすくなるはずです。このあと、3つの目安について解説をしていきます。
銀行からいくら借入できるかの目安
会社が銀行からいくら借入できるのかの目安として、参考になるものが3つあります。銀行もいろいろありますが、どの銀行であってもおおむね共通する目安です。それぞれの目安について、自社の決算書や試算表を見ながら確認をしてみましょう。
経常運転資金
銀行からいくら借入できるかの目安、1つめは「経常運転資金」です。
そもそも、借入をするときには「資金使途(おカネの使いみち)」を問われます。大きく分けると、設備資金と運転資金です。設備資金とは設備投資をするためのおカネであり、運転資金とは設備資金以外のおカネをいいます(仕入代金や各種経費の支払いとか)。
このうち運転資金の借入の目安になるのが、経常運転資金です。その経常運転資金を算式であらわすと、「売掛金+棚卸資産−買掛金」となります。これは、会社が事業を続けるにあたって立て替える必要がある金額であり、銀行借入で用意するのが資金繰りのセオリーです。
よって、銀行も経常運転資金の額までは積極的に融資をしようと考えます。そこで、自社の決算書や試算表から経常運転資金を計算してみましょう。その金額が、仮に1,000万円だとします。そのうえで、いま現在の運転資金の借入残高が700万円だとしたら、あと300万円くらいは借入できそうだと考えられるわけです。
ちなみに、経常運転資金の金額は変動します。売上が増えれば、いっぱんに経常運転資金も増えますから、その分だけ借入の余地が生じるものです。したがって、売上増加時には運転資金の借入を検討しましょう。このとき、借入が不十分だと資金繰りが悪化するので要注意です。
債務償還年数
銀行からいくら借入できるかの目安、2つめは「債務償還年数」です。
債務償還年数を算式であらわすと、「(借入金−預金−経常運転資金)÷(税引後利益+減価償却費)」です。このうち「税引後利益+減価償却費」は年間の返済力であり、いまある借入金を何年で完済できるかを求める算式となっています。
なお、借入金から預金をマイナスしているのは、預金があればその分の借入金はないのといっしょだという考え方です。経常運転資金をマイナスしているのは、経常運転資金は返済力(≒利益)を必要としないからです。経常運転資金の返済財源、「売掛金や棚卸資産(の現金化)」であり、だとすれば、経常運転資金分の借入もないものとする考えに依っています。
そのうえで、債務償還年数は「10年以内が健全」というのが銀行の見方です。ここから債務償還年数の算式を変形すると、「(税引後利益+減価償却費)×10−(借入金−預金−経常運転資金)」となります。このうち「借入金」には、いまの借入金残高をあてはめることで、あとどれくらいの借入ができそうかの目安になるとわかるでしょう。
ちなみに、上記の算式で求められる金額は、厳密にいうと「設備資金分の借入」が対象です。運転資金分の借入については、「経常運転資金」として前述しました。ただし、運転資金分の借入もひっくるめて全体的に債務償還年数を見られることもあります。その場合の債務償還年数の算式は「(借入金−預金)÷(税引後利益+減価償却費)」となるのであわせて確認しておきましょう。
借入月商倍率
銀行からいくら借入できるかの目安、3つめは「借入月商倍率」です。
借入月商倍率を算式であらわすと、「借入金÷(売上高÷12か月)」となります。「売上高÷12か月」は、いわゆる平均月商です。よって、借入月商倍率とは「いまの借入金残高が月商の何か月分か」を示していることになります。
そのうえで、「3か月以内が安全圏、3か月から6か月は注意、6か月超は危険」というのが銀行の見方です。結果として、借入金残高が年間売上高の半分に近づくと、融資が受けづらくなる傾向があります。
これを聞いて、不思議におもわれるかもしれません。なぜなら、「借入金の返済財源は利益であって、売上ではない」とのハナシがあるからです。売上がいくらであろうと、大事なのは利益ではないのか?とおもわれるのであれば、そのとおりです。
前述したとおり、借入金の返済財源は「運転資金分の借入」を除いては利益(税引後利益+減価償却費)です。なので、借入月商倍率は誤りであるかのようにも見えます。ですが実際には、借入月商倍率で「借入が多いか・少ないか」を判断されることはあるのです。
この点、ある銀行員の方は「印象評価」と表現していました。つまり、正しくは経常運転資金や債務償還年数で考えるのだけれど、簡便的に全体の印象として借入月商倍率も参考にしているということです。以上をふまえて、借入月商倍率についても確認をしておくとよいでしょう。
まとめ
社長にとって、銀行からいくら借入できるかは関心事のひとつでしょう。とはいえ、銀行に聞けばよいかというとそうでもありません。そこで本記事では、いくら借入できるかの目安をお伝えしました。
- 経常運転資金
- 債務償還年数
- 借入月商倍率
あくまで参考であり、絶対の目安ではありませんが、何の目安もないよりは借入の検討がしやすくなるはずです。銀行に借入の相談する前に、3つの目安を確認してみましょう。