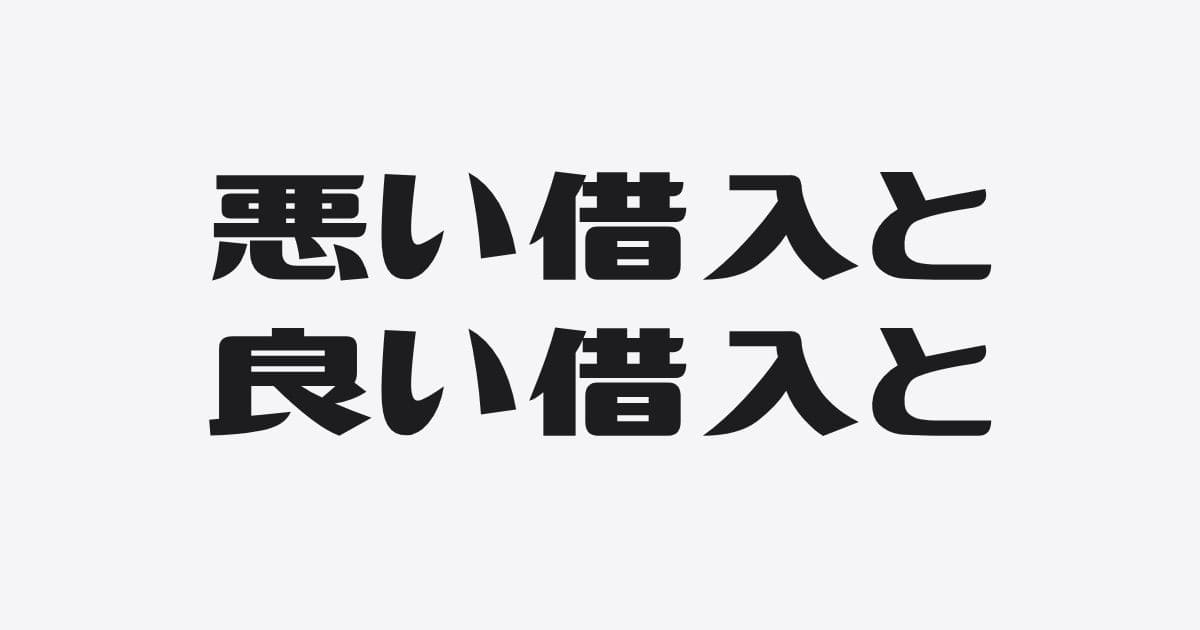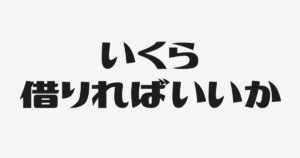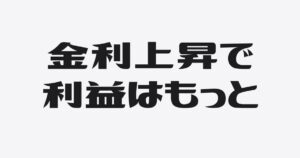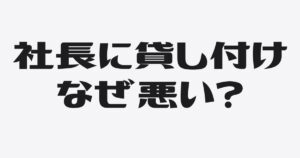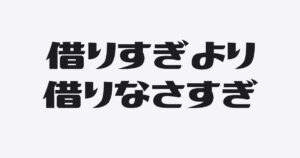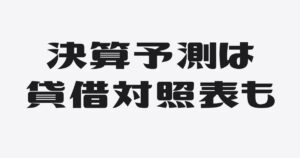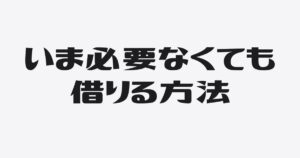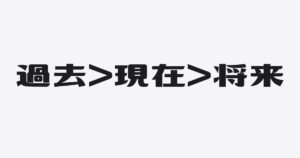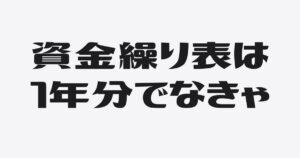「借金は悪」という思い込みが、会社の成長を止めているかもしれません。会社の利益を食いつぶし、大切な預金を減らしてしまう「悪い借入」の3つの特徴を解説します。
悪い借入と良い借入がある
「借金は怖いものだ」「無借金経営こそ、目指すべき理想の姿だ」
社長であれば、いちどはこのように考えたことがあるのではないでしょうか。たしかに、借入はないに越したことはない、と感じるのが人情かもしれません。
しかし、世の中の真実として、「銀行からおカネを借りたことが原因で潰れた会社」というのは、ただの1社もありません。いっぽうで、「必要なおカネを、銀行から借りられなかったことが原因で潰れた会社」は、数え切れないほどあります。
これは、多くの社長が「会社が潰れる本当の理由」を、根本的に誤解していることから生じる悲劇だと言えるでしょう 。
つまり、すべての借入が悪なのではなく、会社をダメにする「悪い借入」と、会社の成長を加速させる「良い借入」があるのです。
にもかかわらず、その違いを知らないばかりに、知らず知らずのうちに「悪い借入」をしてしまい、会社の体力を削っているケースは少なくありません。そこで今回は、社長が絶対に避けるべき「悪い借入」の3つの特徴について、その理由とともに解説していきます。
- 利益が減る(支払利息>営業利益)
- 預金が減る(ムダな買い物をする)
- トクがない(融資条件が悪いまま)
自社の借入が、会社を蝕む「悪い借入」になっていないか。この記事をとおして、ぜひ確認してみましょう。
1.利益が減る借入(支払利息>営業利益)
どんな借入か?
本業の儲けである「営業利益」よりも、銀行に支払う「利息」のほうが多くなってしまうような借入です。これは、財務指標で言うと「インタレスト・カバレッジ・レシオ(支払利息÷営業利益)」が1倍を下回っている状態で、銀行も危険視します 。
なぜ悪いのか?
会社は事業で利益を出すために存在しますが、この状態は、その利益がすべて利息の支払いに消えてしまうことを意味します。まさに「銀行のために働いている」ようなものであり、これでは会社の成長は見込めません。
とくに、審査が甘いからといって、金利が高いノンバンクからの借入に安易に手を出してしまうと、この状況に陥りやすくなります 。ノンバンクの金利やファクタリングの手数料は、銀行融資に比べてとても高コストです 。高金利の負担は、じわじわと会社の体力を奪っていくのです。
どう考えるべきか?
借入は、あくまで会社の利益を増やすための「手段」です。その手段が目的(利益)を食いつぶしてしまっては本末転倒です。自社の営業利益と支払利息のバランスを常に確認し、利息負担が過大になっていないかをチェックする習慣を持ちましょう。
2.預金が減る借入(ムダな買い物をする)
どんな借入か?
銀行から借りたおカネで、事業の利益に直接つながらないものを買ってしまう。これも「悪い借入」の典型です。たとえば、会社の状況に見合わない高級車や、利益を生まない遊休不動産、投機目的の有価証券などです 。
なぜ悪いのか?
銀行は、会社の事業を成長させるためにおカネを貸しています。それを社長が私的に使ったり、利益を生まないモノに換えたりするのは「資金使途違反」と呼ぶべきものであり、銀行との信頼関係を根底から破壊する行為です 。
なにより、会社の生命線である「おカネ(預金)」を減らしてしまいます。いざというときに会社を守るべきおカネが、モノに形を変えて固定化されてしまう 。これは、会社の「守りの力」を自ら弱めていることに他なりません 。
どう考えるべきか?
借入によって増えたおカネは、けして「あぶく銭」ではありません。将来の利益で返済すべき、未来からの預かり金です。そのおカネの使い道が、本当に会社の未来のためになるのかを厳しく自問自答する必要があります。「貸借対照表をスマートにする」という意識を持ち、利益を生まない資産は買わない、と決めることが重要です 。
3.トクがない借入(融資条件が悪いまま)
どんな借入か?
会社の業績が良くなっているにもかかわらず、いつまでも金利が高いまま、あるいは担保や経営者保証が外れないままになっている。そんな、会社の成長がまったく反映されていない「トクがない借入」もまた、悪い借入と言えます。
なぜ悪いのか?
これは、社長が「どこで借りても同じ」と思い込んでいたり 、銀行との交渉を怠っていたりすることで、本来得られるはずのメリットを逃している状態です。
会社の信用力が高まれば、より低い金利で借りられたり、担保や経営者保証を外して身軽になったり 、あるいは保証付き融資から銀行が直接リスクを負う「プロパー融資」に切り替えられたりする可能性があります 。これらは、目先の金利以上に会社の価値を高めるものです 。
どう考えるべきか?
銀行との関係は、一度契約したらおしまいではありません。会社の状況が良くなれば、それに見合った、より良い条件を求めるのは当然の権利です。定期的に自社の借入条件を見直し、必要であれば銀行と交渉する。
あるいは、より良い条件を提示してくれる銀行との関係を深める(メインバンクを見直す)といった、積極的な姿勢が求められます。
まとめ
「借入=悪」という思考停止に陥るのではなく、「悪い借入」とは何かを正しく理解し、それを避けることが重要です。
- 利益が減る(支払利息>営業利益)
- 預金が減る(ムダな買い物をする)
- トクがない(融資条件が悪いまま)
これらを避け、会社の利益と預金を増やし、より良い条件を追求していく。それが、会社の成長を加速させる「良い借入」です。
あなたの会社の借入は、「良い借入」になっていますか?銀行借入は、会社の体力を強化し、不測の事待から会社を守るための重要な手段です 。賢く使いこなしていきましょう。