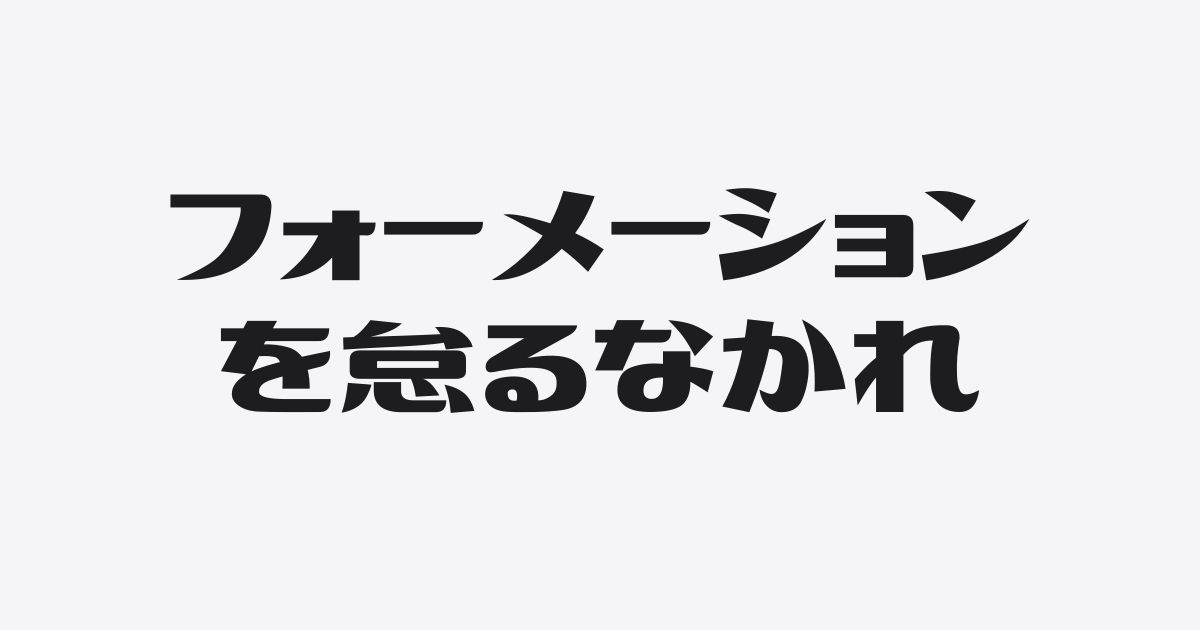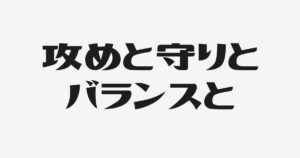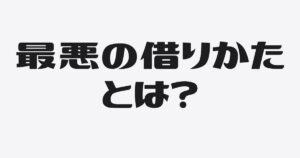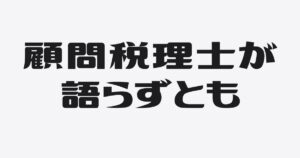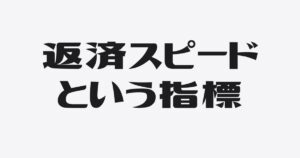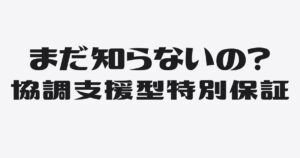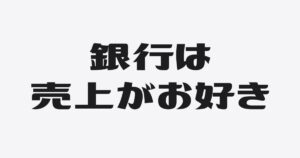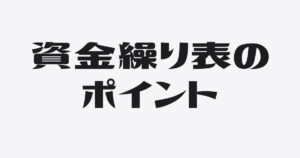会社が銀行融資をスムーズに受けるために、「バンクフォーメーション」は大事な考え方です。そのバンクフォーメーションの重要性を理解しつつ、実践する際のポイントを確認していきます。
バンクフォーメーションとは何なのか?
会社の銀行融資に関連する言葉に、「バンクフォーメーション」があります。端的に言えば「1つの銀行だけに頼るんじゃなくて、複数の銀行といい関係をつくっておこう」という考え方であり、会社がスムーズに銀行融資を受けるためには欠かせません。
にもかかわらず、バンクフォーメーションがなおざりになっている会社はあるものです。そこで、今回はバンクフォーメーションを実践する際のポイントをお伝えしていきます。ぜんぶで3つ、次のとおりです。
- 銀行選びの基準
- 複数銀行と取引
- 担保と保証付き
社長がこれらのポイントがわからずにいると、銀行融資は受けづらくなります。つまり、バンクフォーメーションが実践できずにいると、資金繰りが悪くなってしまうということです。たとえば、「メインバンクがなかなか融資に応じてくれない」…とか。
資金繰りは会社の生命線なのですから、放置するわけにはいかないとわかります。このあと、3つのポイントを順番に確認していきましょう。
バンクフォーメーションの実践ポイント
バンクフォーメーションとは、「1つの銀行だけに頼るんじゃなくて、複数の銀行といい関係をつくっておこう」という考え方だと言いました。その考えを実現するために、バンクフォーメーションを実践する際のポイントを押さえていきます。
銀行選びの基準
バンクフォーメーションの実践ポイント、1つめは「銀行選びの基準」です。「複数の銀行といい関係をつくる」といっても、やみくもに取引銀行を増やせばいいわけでもありません。自社の規模やステージに合った金融機関を選ぶことが、効果的なフォーメーションづくりの第一歩です。
- 創業期~売上3億円未満
まずは地域密着型の信用金庫・信用組合、そして日本政策金融公庫との取引を検討しましょう。これらの金融機関は小規模会社への支援に積極的で、親身になって相談に乗ってくれることが多いです。とくに日本政策金融公庫は、民間の金融機関を補完する役割を担っているため、創業融資などでも頼りになります。
- 売上3億円~2、30億円
信用金庫・信用組合に加えて、地方銀行との取引を開始するタイミングです。地方銀行は、中小企業向けの融資メニューも豊富で、より多様な資金ニーズに対応できる体力があります。信金・信組とは異なる視点でのアドバイスも期待できるでしょう。
- 売上2、30億円以上
メガバンク(都市銀行)との取引も視野に入ってきます。全国規模のネットワークや海外取引など、ビジネスの拡大にともなう高度なニーズに対応可能です。ただし、一般的に中小企業への対応は地方銀行や信金・信組ほど手厚くない場合も多く、既存の取引銀行との関係も維持しながら、バランスを取ることが重要です。
ポイントは、「銀行の知名度」で選ぶのではなく、「自社の現状と将来の展望に対して、どの銀行がもっとも合いそうか?」という視点で判断することです。
複数銀行と取引
バンクフォーメーションの実践ポイント、2つめは「複数銀行と取引」です。
これは、バンクフォーメーションの核ともいえます。単に預金口座を持つだけでなく、実質的な取引実績を積み重ねて、信頼関係を築くことが重要になります。しかし、そもそもなぜ複数銀行との取引が不可欠なのか?次のとおりです。
- メインバンクの「変化」に備える
長年付き合いのあるメインバンクでも、担当者の異動や支店の統廃合、銀行全体の方針転換などで、突然融資姿勢が変わることがあります。「前の担当者は積極的だったのに…」と嘆いても後の祭りです。でも、サブバンクとの関係があれば、慌てずに代替策を検討できるでしょう。
- 急な資金ニーズに対応する
「大型案件が決まった」とか「想定外のトラブル発生」とか、急にまとまった資金が必要になる場面は少なくありません。メインバンクの審査が間に合わない、あるいは融資枠がいっぱいという状況でも、他の取引銀行があれば、資金調達の選択肢が広がります。
- 有利な条件を引き出す交渉力
新規融資や借換えの際、複数の銀行から提案(相見積もり)を取ることで、金利や返済期間などの条件を比較検討できます。「A銀行さんはこの条件ですが、御行ではどうですか?」といった具体的な交渉が可能になるため、より有利な条件を引き出しやすくなります。銀行側にも「他行に取られたくない」という意識が働くので、より良い提案に繋がる可能性が高まるものです。
ではここで、複数銀行と取引の成功例と失敗例を挙げてみます。
- 成功事例 B社(製造業・売上5億円)
メインバンクの地方銀行に加え、地元の信用金庫とも長年取引を継続。あるとき、新工場建設のために大型の設備投資が必要になった。地方銀行だけでは希望額に届かなかったが、信用金庫にも相談したところ、両行の担当者が連携し、協調融資という形でスムーズに資金調達が実現。日頃から両行と良好な関係を築き、会社の状況をオープンに伝えていたことが功を奏した。
- 失敗事例 C社(建設業・売上8億円)
地元の有力地方銀行をメインバンクとして、ほかの銀行とは一切取引がなかった。「メインバンクが一番よく分かってくれている」と信じて、依存しきっていたところ、公共事業の減少で一時的に業績が悪化すると、メインバンクは追加融資に難色。慌ててほかの銀行に融資を申し込むも、「なぜ、いままでお付き合いがなかったのですか?」「まずは預金取引からお願いします」と門前払い同然の扱いを受けて、資金繰りに窮してしまった。
以上をふまえて、重要なのは、単なる「口座開設」でおわらせずに、地道に「取引実績」と「コミュニケーション」を積み重ねて、信頼関係を育むことです。いざというときに頼れる関係は、一朝一夕には築けません。
なお、ここでいう取引とは借入・返済だけではなく、売上入金口座のいちぶとして利用する、公共料金や家賃などの支払い口座に指定するなどが含まれます。
担保と保証付き
バンクフォーメーションの実践ポイント、3つめは「担保と保証付き」です。
多くの中小企業にとって、不動産などの担保や信用保証協会の保証付き融資は、資金調達において重要な役割を果たします。しかし、これらの扱いかたにもバンクフォーメーションの視点が必要です。
注意したいのは、「担保や保証を特定の銀行に集中させすぎない」ということです。
たとえば、会社の最も価値ある不動産をすべて、メインバンクの担保に入れてしまっていると、ほかの銀行(サブバンク以下)は「うちは担保も保証もないのに、リスクを取って融資するのは難しい」と考えるので、追加融資に消極的になってしまうことがあります。
これでは、せっかく複数行と取引があっても、実質的な資金調達の選択肢が狭まってしまうでしょう。よって、担保を提供する、保証協会付き融資を利用する際には、「どの銀行にどのていどの担保・保証を提供するのか、計画的に考え、バランスよく分散させる」ことが重要です。
これにより、各取引銀行がそれぞれのリスクを分担する形となり、いざというときの協調融資なども受けやすくなります。また、将来的にプロパー融資(担保や保証に頼らない融資)を目指すうえでも、複数の銀行と保証協会付き融資などで取引実績を積み、信頼を得ておくことが有効なステップです。
まとめ
銀行融資を有利に進め、安定した資金繰りを実現するための「バンクフォーメーション」について、その重要性と3つの実践ポイントを解説しました。
- 銀行選びの基準: 会社のステージに合わせて銀行を選ぶ
- 複数銀行と取引: 実績と信頼関係を築き、リスク分散と交渉力向上を図る
- 担保と保証付き: 特定の銀行に集中させず、バランスよく分散させる
これらのポイントを理解し、実践できているかどうかで、会社の資金調達力、ひいては経営の安定性は大きく変わってきます。「うちは大丈夫」とおもっていても、いちど、現在の取引銀行との関係性を見直してみてはいかがでしょうか?
バンクフォーメーションの構築は、一朝一夕に完成するものではありません。ですが、日頃から意識し、地道に関係性を築いていくことが、予期せぬ事態が起こった時に会社を守る「備え」になります。
まずは、サブバンク候補となりそうな金融機関に相談してみる、あるいは既存の取引銀行の担当者に、改めて会社の現状や将来の計画を話してみることから始めてみましょう。 その一歩が、自社の資金繰り改善につながるはずです。