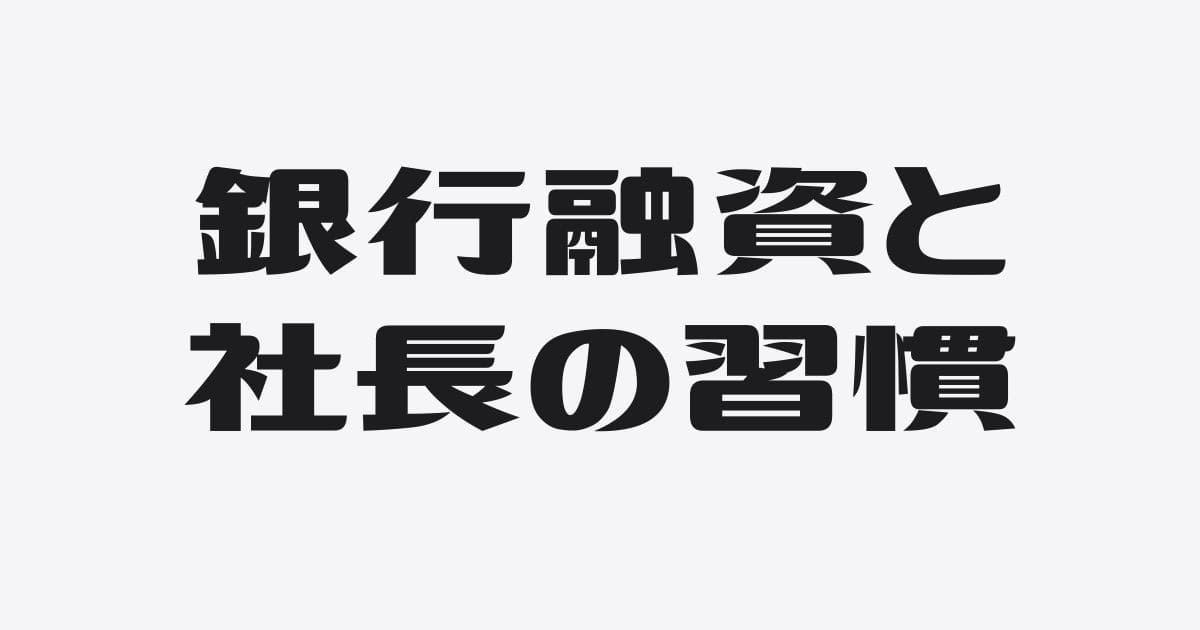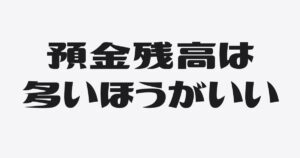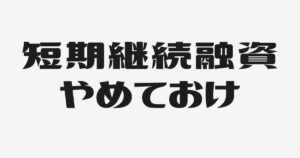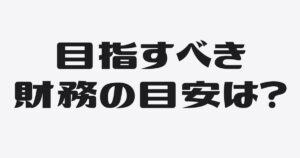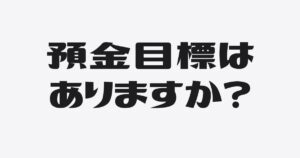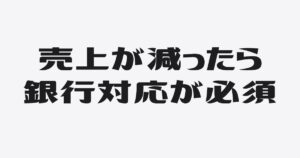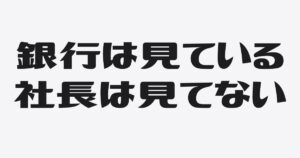銀行が融資審査のときに見ているのは、決算書だけではありません。実は、社長個人の習慣にも注目をしています。その理由や、とくに大事な習慣を取り上げて解説しました。
銀行員が決算書の裏で見ているものは
「決算書さえ良ければ、銀行融資は大丈夫だろう」
多くの社長が、このように考えているかもしれません。もちろん、良い決算書は銀行評価の基本であり、とても重要です。良い数字でなければ、融資審査のスタートラインにすら立てないこともあります。
しかし、とくに中小企業の場合、現実はそれほど単純ではありません。銀行は、損益計算書や貸借対照表といった「数字(定量評価)」と同じくらい、あるいはそれ以上に、社長個人のこと、つまり「定性評価」も注意深く見ているのです。
この「定性評価」こそが、融資の可否や融資条件を左右する、隠れたキーポイントである可能性があります。「なぜウチは決算書が悪くないのに、融資がスムーズにいかないんだろう…」と感じている社長がいるとしたら、もしかすると、この定性的な部分、社長の日々の「習慣」や経営に対する「姿勢」に、銀行が何らかの懸念を抱いているのかもしれません。
今回は、銀行員が決算書の数字の裏で、社長のどのような「習慣」や「姿勢」を見ているのか、そしてその定性評価がいかに重要であるかについて、解説していきます。
このあとの話の流れは以下のとおりです。
- 社長の習慣(定性評価)が大事な理由
- 銀行が注目する「社長の習慣」の具体例
- 社長の習慣を改善して評価を高めるヒント
社長の習慣(定性評価)が大事な理由
銀行も営利企業ですから、当然、貸したおカネがきちんと回収できるかどうかを考えます。そのため、会社の状況を示す決算書を徹底的に分析するのは当たり前です。ではなぜ、それ以外の「社長の習慣」のような、数字には表れない部分まで、銀行は見ようとするのでしょうか? それには、ちゃんとした理由があります。
理由1:数字は過去、社長は未来
決算書に書かれている数字は、あくまで会社の「過去の経営成績」や「ある時点での財産状況」を示すものです。もちろん、それは会社の現状を理解するうえで重要な情報ではあります。しかし、銀行が本当に知りたいのは、「この会社は、これからどうなっていくのか?」という未来の姿です。融資の返済は、未来の利益から行われるのですから当然でしょう。
そして、会社の未来を創り上げていくのは、社長にほかなりません。社長の経営に対する考え方、日々の判断や行動、つまり社長の「習慣」こそが、会社の将来性や返済能力を示す、重要な先行指標のひとつとなるわけです。
いくら過去の数字が良くても、社長の習慣に問題があれば、未来は危ういかもしれない。逆に、いまは数字が厳しくても、社長の習慣が素晴らしければ、未来は良くなるかもしれない。銀行にはそのような見方があります。
理由2:中小企業は「社長=会社」
とくに中小企業においては、社長の存在が会社そのものと言っても過言ではありません。社長の経営手腕、リーダーシップ、経験や人脈、さらには健康状態や人間性といった要素が、会社の業績や存続に大きな影響を与えています。
大企業であれば、社長が交代しても組織として継続していく仕組みがありますが、中小企業ではそうはいきません。だからこそ銀行は、「社長という人」を信頼できるかどうかを、さまざまな角度から慎重に見極めようとします。
いくら現時点での決算書の数字が良くても、社長個人に「この人はどうだろう…?」と不安要素を感じれば、銀行は安心しておカネを貸すことはできないのです。
理由3:もしもの対応力を見たい
会社経営には、予期せぬトラブルや困難な状況はツキモノです。市場環境の急変、取引先の倒産、自然災害、あるいは社長自身の急病など、いろいろな「もしも」が起こりえます。
そうした危機的な状況に陥ったときに、社長がどのような考え方をし、どのように行動するのか。危機対応能力や問題解決能力は、社長の日々の「習慣」の中にこそ表れるものです。ふだんから情報を集め、リスクを想定して、誠実に対応している社長は、いざというときにも的確な判断ができる可能性が高いでしょう。
銀行は、そうした「もしも」のときに、社長が会社を立て直し、きちんと返済していく力を持っているかどうかを、過去の具体的な行動や現在の経営姿勢から見極めようとしているわけです。
銀行が注目する「社長の習慣」の具体例
では、具体的に銀行員は社長のどのような「習慣」や「姿勢」に注目しているのでしょうか。僕がこれまで多くの社長や銀行員と接してきたなかで、とくに、銀行評価に影響すると感じる3つのポイントをお伝えします。
習慣1:情報開示に対する習慣
銀行との信頼関係を築くうえで、もっとも基本となる習慣です。具体的には、会社にとって都合の良い情報(たとえば、業績が良いときの試算表や、新規受注の明るいニュースなど)だけでなく、悪い情報(業績が悪化した試算表、発生してしまったトラブル、資金繰りの懸念など)も、隠さずに、迅速かつ正直に銀行に開示する姿勢です。
また、銀行の担当者から会社の状況について質問を受けた際に、言葉を濁したり、あいまいな返答をしたりせず、真摯に、そして具体的に答える習慣も重要です。わからないことはわからないと正直に伝えて、きちんと調べて回答する。そうした誠実な対応が求められます。
人間誰しも、悪い情報は隠したいものですし、都合よく見せたいとおもうものです。しかし、銀行はそうした社長の「人間的な弱さ」も見抜きます。一時的には取り繕うことができたとしても、いずれ本性は明らかになります。
だから、ふだんからありのままの情報を誠実に開示し続けること、それが、銀行に「この社長は信頼できる。何かあっても正直に話してくれるだろうから、いざというときも一緒に解決策を考えられる」という安心感を与え、信頼関係の土台となるのです。
習慣2:学び続け変化する習慣
経営環境が目まぐるしく変化するいま、社長が現状に満足することなく、常に新しい情報を求めて、謙虚に学び続ける姿勢を持っているかどうかは、会社の将来性を占うえで重要なポイントになります。 自社の業界動向はもちろんのこと、新しい技術の進展や競合他社の動き、経済全体のトレンド、さらには経営戦略や財務に関する新しい知識など、さまざまなことにアンテナを張り、それを自社の経営に活かそうとする前向きな習慣はあるか。そして、過去の成功体験に固執することなく、外部環境の変化に合わせて柔軟に経営の舵を切り、事業モデルや戦略を見直せる習慣はあるか。
こうした「学びと変化への対応」を習慣化している社長に対して、銀行は「この社長なら、厳しい環境変化にもきっと対応して、会社を成長させていけるだろう」という強い期待感と安心感を抱きます。逆に、古いやりかたに固執して、学ぶことをやめてしまった社長の会社は、どんなに過去の実績が良くても、将来性は低いと判断されかねません。
習慣3:周囲を大切にする習慣
銀行は、その会社が「儲かっているか」だけでなく、社員や取引先といった周囲(ステークホルダー)と、どのような関係を築き、社会のなかでどのように事業を営んでいるか、ということにも関心を持っています。
社員を単なるコストとしてではなく、大切な財産として扱い、働きがいのある職場環境づくりに努めているか。仕入先や売上先といった取引先と、目先の利益だけを追うのではなく、良好な関係を築き、長期的な信頼関係を重視しているか。地域社会への貢献なども含め、いわゆる「三方よし」の精神で事業を行っているか。
こうした習慣は、すぐには利益に結びつかないかもしれません。ですが、長い目で見れば、社員の定着率向上やモチベーションアップ、取引先からの協力や信用の獲得、地域社会からの応援につながり、結果として会社の評判を高めて、事業の継続性をたしかなものにします。
銀行も、そのような会社を「社会に必要な応援したい会社」と感じるので、長期的な視点で支援しようと考えるものです。
社長の習慣を改善して評価を高めるヒント
前述した習慣は、一朝一夕に簡単に身につくものではありません。長年染み付いた考え方や行動パターンを変えるのは、誰にとっても容易なことではないでしょう。
しかし、社長が日々意識して行動を少しずつ変えていくことで、必ず銀行からの見えかたは変わってきます。それは、会社の成長や安定にもつながっていくはずです。では、どうすれば良い習慣を身につけて、銀行からの定性評価を高めることができるのでしょうか?
まずは自己認識から始める
最初の一歩は、まず現在の自社の状況(決算書などの数字で示される定量的な評価)と、社長自身のこれまでの行動や考え方(習慣から生まれる定性的な評価)について、客観的に振り返ってみることです。「銀行という第三者から見て、いまのじぶんや会社は、どのように映っているだろうか?」という視点を持つことが大切になります。
ときには、信頼できる右腕や、あるいは外部の専門家(顧問税理士など)の意見を聞いてみるのもよいかもしれません。
行動目標を立てて実践する
改善したい習慣や、新たに身につけたい習慣が見つかったら、それを具体的な行動目標に落とし込み、日々の業務のなかで実践してみましょう。たとえば、「四半期にいちどは、銀行に試算表を持って報告に行く」「業界のセミナーに積極的に参加する」「社員との面談の時間を増やす」。
大切なのは、実際に行動して、それを続けることです。小さな行動の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出し、社長自身の「良い習慣」として定着していくはずです。
そうした銀行評価における『社長の習慣』の重要性に着目し、銀行員が具体的にどのような点に注目しているのか、そして社長はどうすればそれを実践できるのかを、より詳しく、体系的にまとめたKindle本を書きました。
『銀行に好かれる社長の習慣 ~定性評価で差がつく35の行動原則』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
この本では、今回お話しした3つの習慣はもちろんのこと、銀行が評価する社長の行動原則をぜんぶで35個選び出し、それぞれについて、なぜそれが銀行評価にとって重要なのか、具体的に社長は日々何を意識し、どう行動すれば良いのかを、僕自身のこれまでの経験や多くの事例を交えながら解説しました。
日々の「習慣」を見直すことで、銀行との関係が変わり、融資がスムーズになり、ひいては会社の未来もより良い方向へ変わっていく。この本が、そんなきっかけのひとつになれば、これほどうれしいことはありません。
まとめ
銀行からの評価は、けして決算書の数字(定量評価)だけで決まるものではありません。とくに中小企業においては、社長自身の「習慣」や経営に対する「姿勢」(定性評価)が、銀行からの信頼を大きく左右するということを、あらためて理解しておきましょう。
良い決算書を作るための日々の努力はもちろん重要です。しかし、それと同時に、銀行員から「この社長なら信頼できる、この会社なら応援したい」とおもわれるような、日々の「良い習慣」を一つひとつ積み重ねていくことも重要です。
それが結果として、銀行に好かれ、必要なときに必要な融資を受けやすい、盤石な経営基盤を持つ強い会社をつくることにつながります。どこから手をつければいいかわからない…ということであれば、僕の新刊『銀行に好かれる社長の習慣』をご利用いただければとおもいます。