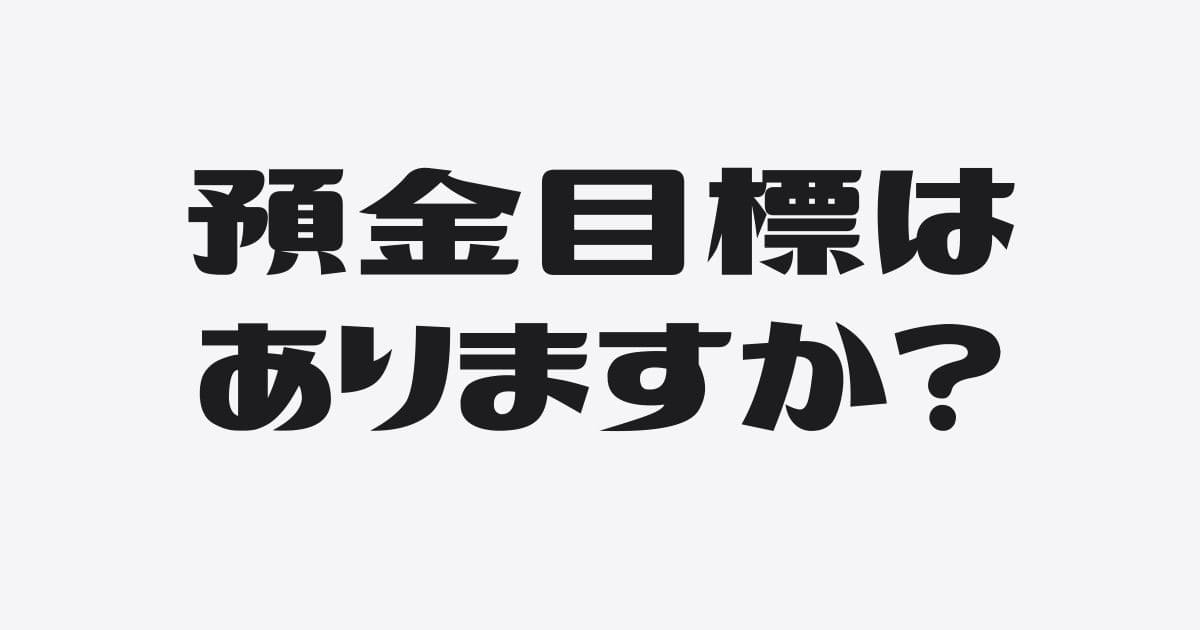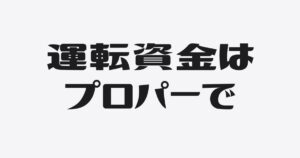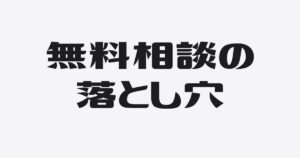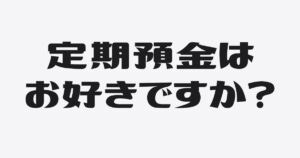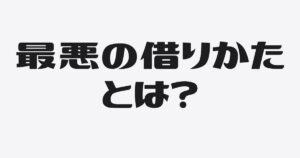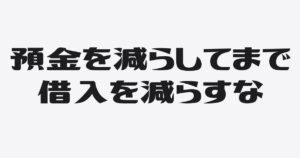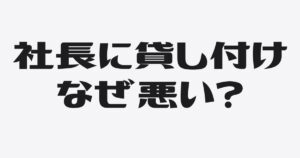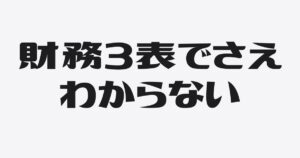預金に関する目標を決めましょう。これにより、資金繰りによい変化をもたらすはずです。というわけで、預金の「いくら」に関する3つの目標についてお話をします。
もし決めているならば超少数派
会社は、預金に関する目標を決めましょう。これが今回の結論です。
会社の目標というと、売上や利益をイメージしたり、実際に決めていたりもするでしょう。ところが、預金に関する目標を決めているという会社は、僕が知る限りほとんどありません。もし決めているならば超少数派です。
そのような現状もふまえて、僕は、預金に関する目標をつくることをおすすめしています。具体的には、以下3つの目標です。
- どの銀行にいくら預けるか
- 預金残はいくらを目指すか
- 預金をいくら投資に回すか
会社がこれらの目標を決めることによって、資金繰りにはよい影響があるものと考えます。預金の「いくら」に関する目標を決めることで、自社の資金繰りはよくなるということです。「そんなバカな」とおもわれるようであればとくに、このあとの解説をご一読いただければとおもいます。
きっと、資金繰りによい変化をもたらすはずです。
預金の「いくら」に関する目標
端的にいえば、資金繰りの良し悪しは「預金の残高」で決まります。預金の残高が多ければ資金繰りはラクになるし、少なければ資金繰りは苦しくなる。そこで、預金の残高をより着実に、より確実に増やすためにも、預金に関する目標が必要になるのです。
どの銀行にいくら預けるか
預金の「いくら」に関する目標、1つめは「どの銀行にいくら預けるか」です。
この点、なんとなく都市銀行にあずけている会社は少なくありません。ここでいう「なんとなく」とは、「都市銀行からは融資を受けないのに」と同義です。
そもそも、銀行にとって預金は担保のようなものだといえます。融資をしている会社から預金をあずかっていれば、いざというときには融資残高と預金を相殺できるからです。よって、預金があるほど銀行にとっては安心なのであり、預金をあずかっている会社ほど融資がしやすくなります。
だとしたら、会社は戦略的に預金をあずけることで、より多くの融資が受けられるとわかるでしょう。言い換えると、預金をあずけても融資をしてくれないような銀行には、預金をあずけないということです。では、都市銀行はどうなのか?
都市銀行は、中小企業に融資はしてくれません。もともとが大企業向けの銀行であり、大企業よりもリスクが大きい中小企業に、少額の融資をしても割に合わないからです。
でも、都市銀行から融資が受けられているというのであれば、それが「プロパー融資」かどうかを確認してみましょう。プロパー融資ではなく、信用保証協会の保証付き融資(会社が返済できないときは信用保証協会が銀行に返済する融資)であれば、本当の意味で都市銀行から融資を受けていることにはなりません。
なお、保証付き融資には制度上の限度額があるため、都市銀行ではなく、信用金庫や地方銀行で利用するのがセオリーです。信用金庫や地方銀行はリスクを軽減できるので、保証付き融資に加えてプロパー融資をしやすくなります。
いっぽうで都市銀行の場合、中小企業相手にリスクをとってプロパー融資をすることはまれであり、だとしたら預金は都市銀行にあずけるのではなく、信用金庫や地方銀行にあずけることで、プロパー融資を受けやすくすることを狙うのが得策です。
結果として、より多くの融資を受けられれば資金繰りはよりよくなります。
預金残はいくらを目指すか
預金の「いくら」に関する目標、2つめは「預金残はいくらを目指すか」です。
1年後(決算時)の売上目標や利益目標を決める会社はあっても、1年後の預金目標を決める会社は少ないものです。ところが、会社にとって一番大事なものは「おカネ」だといっても過言ではありません。
なぜなら、売上や利益がどれだけ多くても、おカネが無くなれば会社はつぶれてしまうからです。にもかかわらず、おカネ(預金)の目標を決めないのは不思議だと言わざるをえないでしょう。
預金残の目安として、まずは「平均月商(年間売上高÷12か月)の2か月分」です。これは、実際の資金繰りにおけるひとまずの安全圏であり、銀行もそのような見方をしています。逆に、預金残が平均月商の2か月分未満になると、プロパー融資が受けにくくなるなどするものです。結果として、資金繰りはいっそう悪くなります(預金が少ないうえに融資も受けにくい)。
そのうえで、ひとつ上の目標が「平均月商の3か月分」です。それだけの預金があると、だいぶ安全圏だといえるでしょう。銀行からも、安全な会社だと見られます。さらに上の目標を挙げるなら「平均月商の6か月分」です。ここまでくると、資金繰りはかなり盤石になります。売上が6か月ゼロでも耐えられるということです。
この話をすると、「おカネを持ちすぎでは?」と反論する人もいます。つまり、おカネを余らせておくのはもったいないとの考えです。しかし、それは「大企業発想」というものです。中小企業は大企業のように、いつでも増資や銀行借入で資金調達できるものではありません。大企業ほどの信用がないからです。
よって、いざというときに備えて、預金を「多め」に持つことが重要になります。預金残を増やすのは、おカネを余らせるためではなく、備えるためであることを理解しましょう。
預金をいくら投資に回すか
預金の「いくら」に関する目標、3つめは「預金をいくら投資に回すか」です。
さきほど、いざというときに備えて、預金を「多め」に持つと言いました。そのために、預金残の目標を決めておきましょう、ということになります。ただし、預金を多めに持つのは「投資」をするためでもあります。
ここでいう「投資」とは、株式投資や不動産投資のたぐいではなく、事業に対する投資です。具体的には、新商品や新サービスの開発、新規出店、新規採用・教育、新規事業など。これら事業に対する投資には「おカネ(預金)」が要ります。
預金を多めに持つのは、「必要なときに、タイミングを逃さず投資ができるように」というためでもあるのです。逆に、預金が少なければ、投資のタイミングを逃したり、投資そのものができないことになってしまいます。
すると、会社の持続・成長は難しくなるでしょう。新型コロナの折、あたらしい生活様式への変化にともない、事業転換できた会社が持続・成長をはたしたいっぽうで、既存事業に終始したことで変化に対応できず、廃業に追い込まれた会社もあります。この点、投資するだけのおカネを持っていなかったことも、変化に対応できなかった要因の1つです。
よって、会社は投資のためのおカネを持つ必要があります。新型コロナにかかわらず、いまは変化が速い時代であり、会社はこれまで以上に変化を求められているのです。だとすれば、変化に対応するために投資ができない会社は、遅かれ早かれつぶれてしまいます。
預金残はいくらを目指すかの目標とあわせて、預金をいくら投資に回すかの目標も決めましょう。現状維持は衰退とはよくいわれるところです。変化するための投資は必須と考えましょう。
まとめ
預金に関する目標を決めましょう。これにより、資金繰りによい変化をもたらすはずです。というわけで、預金の「いくら」に関する3つの目標についてお話をしました。
- どの銀行にいくら預けるか
- 預金残はいくらを目指すか
- 預金をいくら投資に回すか
端的にいえば、資金繰りの良し悪しは「預金の残高」で決まります。であれば、預金の残高をいかに管理するかです。いま現在の残高を見ているだけでは管理とは言えず、将来の残高(=目標)にまで目を向けてこそ管理です。預金の「いくら」に関する目標を決めましょう。