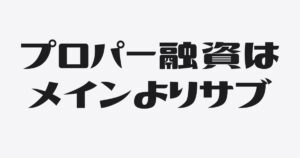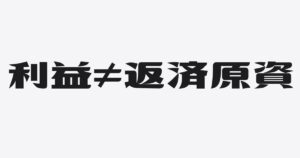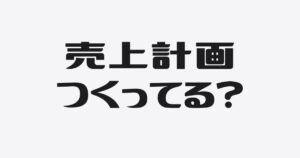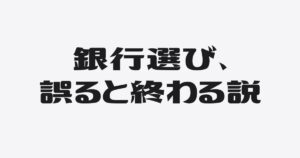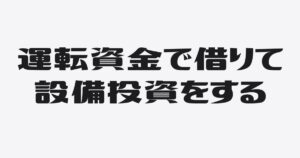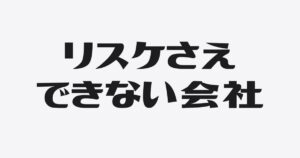計画書をつくりましょう、という話があります。いっぽうで、「どうせ計画どおりにはならないからつくらない」と考える社長はいるものです。そこで、会社は計画をつくったほうがいい理由をお伝えします。
計画どおりにならないからつくらない
会社を経営するにあたって、「計画をつくりましょう」という話があります。ここでいう計画とは、事業計画書とか経営計画書と呼ばれるたぐいのものです。
もっとも、会社に限らず個人であっても計画性は必要とされることから、計画の重要性は誰しも「アタマ」のなかでは理解をしていることでしょう。ですが、計画をつくっていない会社はけして少なくありません。そのような会社の社長が、次のように考えていることがあります。
「どうせ計画どおりになんてならないから、計画はつくらない」
はたしてこれでよいものか?結論、よろしくありません。会社は計画をつくったほうがいい、というのが結論になります。ではなぜ、会社は計画をつくったほうがいいのか?
納得ができるように、理由を確認してみることにしましょう。次のとおりです。
- 計画と占いは違うもの
- 記憶の改ざんを避ける
- 銀行融資の受けやすさ
これらについて、このあと順番に解説をしていきます。一読いただければ、計画どおりにならないからつくらないとは、もう言えなくなるはずです。
会社は計画をつくったほうがいい理由
計画が大事だなどといわれても、心底から納得できないと行動には起こせないものでしょう。というわけで、会社は計画をつくったほうがいい理由を、3つお伝えします。3つめの理由などは会社の存続にも関わるものであり、社長であればけして無視できるものではありません。
計画と占いは違うもの
会社は計画をつくったほうがいい理由、1つめは「計画と占いは違うもの」です。
冒頭、「どうせ計画どおりになんてならないから、計画はつくらない」という社長の考えを挙げました。たしかに、計画どおりになんてならないことが割合としては多いのすが、それが計画をつくらない理由にはなりません。
なぜなら、計画は占いではないからです。当たる計画(計画どおりになる)がよくて、当たらない計画(計画どおりにならない)が悪いなんてことはありません。言い換えると、計画の価値は「当たること」ではないということです。では、どこに価値があるのか?
どうなるかわからない未来に「備える」ところに、計画の価値があります。具体的には、まず計画をつくる。その計画に沿って実行する。結果と計画とを比較してみる。差があれば原因を把握して、必要があれば改善策を検討し、今後の計画を見直す。また計画に沿って実行する、以下繰り返し。
計画は目指すべき「道」であり、計画があれば道から逸れていることにも早く気づけるのがメリットです。早く気づけるほど、元の道に戻るにも速いしラクでしょう。逆に計画がなければ、社長は場当たり的に道を選ぶことになります。進むべき道から逸れてしまっても、比較対象(計画)がないのですぐに気がつくことはできません。そして、気づいたときには遅すぎます。
だとすれば、「どうせ計画どおりになんてならないから、計画はつくらない」との話が、いかに的はずれなハナシであるかはあきらかでしょう。事業の持続・成長を考えれば、社長は「計画はつくる」の一択です。
記憶の改ざんを避ける
会社は計画をつくったほうがいい理由、2つめは「記憶の改ざんを避ける」です。
気をつけないと、社長はじぶんの記憶を改ざんします。「気をつけないと」とは言いましたが、実は気をつけようがありません。なぜなら、ヒトには「じぶんを正当化する」という傾向があるからです(いわゆる、正当化バイアス)。
たとえば、事業がうまくいきましたというときに、「はじめからこうなると確信をして、〇〇に取り組んでいたのだ」みたいに考えることがあるでしょう。ですが、実際には当初そのようなことは考えておらず、要はあとづけであって、これこそが記憶の改ざんにあたります。
すると、事実は「たまたまうまくいっただけ」なのに、みずからの実力を過大評価しするのでは問題です。同じようなことは、事業がうまくいかなかったときにも起こります。
たとえば、「はじめからこうなるとおもっていた」などと社長が考えるケースです。でも、実際にはそんなことは考えていなかったということはあるでしょう。それを確認するためにも、計画として明文化しておくことが大切です。
計画をつくるときには、現状分析にはじまり、課題や問題のあぶり出しをします。それらも計画のうちに含まれるのですから、「こうなるとおもっていた」かどうかは、計画を見れば一目瞭然です。実際にうまくいこうがいくまいが、計画があれば記憶の改ざんを避けられます。
恐ろしいのは、記憶を改ざんして場当たりな経営まで正当化することです。計画をつくらなくてもいいのだと正当化することです。場当たりな経営では、道を逸れたことにも気づけなくなってしまいます。これは、前述したとおりです。
銀行融資の受けやすさ
会社は計画をつくったほうがいい理由、3つめは「銀行融資の受けやすさ」です。
計画がある会社とない会社と、どちらが銀行融資を受けやすいかといえば、計画がある会社です。その理由は、もはや語るまでもないでしょう。計画性がある会社と場当たりな会社と、どちらを銀行が好むかとういハナシです(もちろん、計画性がある会社のほう)。
中小企業にとって、銀行融資は資金繰りの生命線だといえます。銀行融資を受けられずにつぶれる会社はありますが、受けられてつぶれる会社はないのです。いざというときのためにも、銀行融資が受けやすい会社であるに越したことはありません(社長が大金持ちの場合は別として)。
にもかかわらず、計画をつくらないというのであれば、社長はみずから「会社をつぶす確率を上げている」と言ってよいでしょう。繰り返しですが、銀行は計画性がある会社を好み、場当たり的な会社を好まないからです。
というように銀行融資の話をすると、「銀行のために計画をつくるのか?」と反論する社長もいます。ですが、計画は本来、会社自身のためのものであることは、ここまでお伝えをした「計画と占いは違うもの」や「記憶の改ざんを避ける」という話からご理解いただけることでしょう。
したがって、銀行融資が受けやすくなるのは「結果」であり、「目的」ではありません。会社は会社自身のために、社長は社長自身のために計画をつくるのです。勘違いのないようにしましょう。
まとめ
計画書をつくりましょう、という話があります。いっぽうで、「どうせ計画どおりにはならないからつくらない」と考える社長はいるものです。そこで本記事では、会社は計画をつくったほうがいい理由をお伝えしました。
- 計画と占いは違うもの
- 記憶の改ざんを避ける
- 銀行融資の受けやすさ
計画をつくったほうがいい理由はわかったけれど、具体的な様式やつくりかたがわからない…ということであれば、僕が執筆をした本のなかで詳しく解説をしています。本のタイトルは「税理士必携」となっていますが、税理士でなくてもお役立ていただける内容です。よろしければ参考にどうぞ。
『税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック』
(リンク先はAmazonの商品ページです)