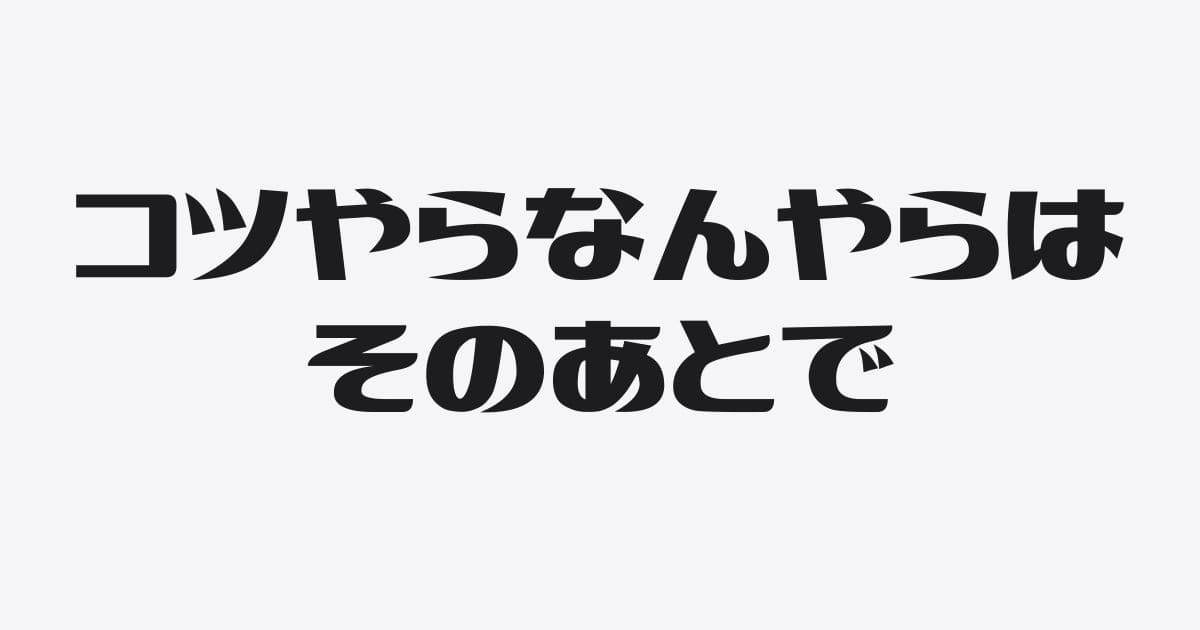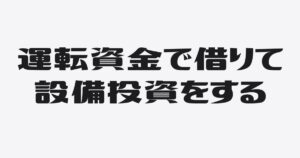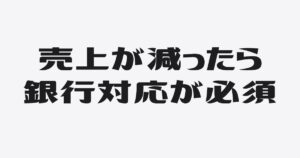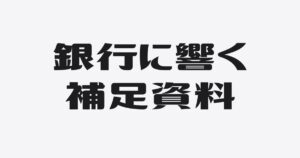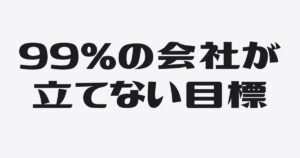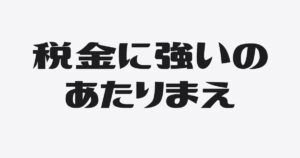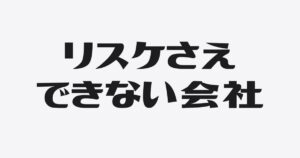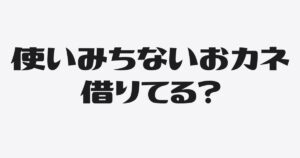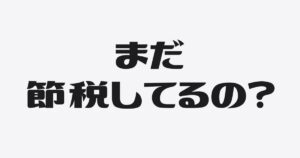「融資を受けられるようになる銀行対応のコツは何だ?」と躍起になる社長もいます。が、まずは「できることをやるところから」です。では、できることは何なのかをお伝えしていきます。
穴のあいたバケツに水を
銀行からスムーズに融資が受けられる会社になりたい。と、考える社長は少なくないでしょう。そこで、「融資を受けられるようになる銀行対応のコツは何だ?」と躍起になる社長もいます。コツを学ぶのも悪くはありませんが、その前に「できることをやるところから」です。
できることがあるのにそれもやらずしてコツを押さえようとするのは、穴のあいたバケツに水をいれるような行為だといえます。では、できることとは何なのか?次の3点です。
- 利益きちんと
- 商売を伝える
- 仕訳を見直す
銀行対応は、これらできることをやるところからがスタートになります。自社ではできているのかどうか、あらためて確認をしてみましょう。コツやらなんやらを考えるのはそのあとです。
上記3点について、このあと詳しく解説していきます。
銀行対応でできることは
銀行対応のスタートとして、できることをやるところからだといいました。そこで、できることとは何なのかを理解して、確実に実行できるようになりましょう。バケツに穴があいているのであれば、それを塞ぐところからです。
利益きちんと
銀行対応でできること、1つめは「利益きちんと」です。文字どおり、利益をきちんと出す。
そんなのあたりまえだとおもわれるかもしれませんが、実際にはそうでもありません。決算で納税が多いとわかると、利益を減らそうと考える社長もいるのです。
銀行は、「利益=返済力」と見ています。利益を減らせば、返済力も減るのであり、結果として融資は受けにくくなることを忘れてはいけません。納税は減っても、借りれる額が少なくなる。それでもよいのか、利益を減らす前に検討する必要があります。
もっとも、利益を減らすのは得策ではありません。繰り返しですが返済力が減るからです。すると、どのような銀行融資のコツも効果を発揮しづらくなってしまいます。コツを活かしたいのであれば、利益をきちんと出しているという前提が大切です。
また、いまは金利が上昇局面にあり、銀行は回収不能を警戒しています。つまり、利息の支払負担が増加することで、返済できなくなる融資先が増えるのではないかと考えています。こうなると、融資審査はこれまで以上に慎重になりますし、これまで以上に利益が重視もされるでしょう。
だとすれば、出せる利益を出し惜しんでいる場合ではありません。また、利益改善が遅れている会社も要注意です。これまでは借りれていても、これからも借りれるとは限りません。銀行対応のいの一番として、「利益きちんと」です。
商売を伝える
銀行対応でできること、2つめは「商売を伝える」です。ここでいう商売とは、ビジネスモデルを指します。さらに言い換えると、「誰に・何を・どのように売るか」です。
銀行が会社の商売を理解していないと、融資がしづらくなります。極端をいえば、怪しい商売には融資をできません。怪しい商売ではなくても、「誰に・何を・どのように売るか」がわからなければおカネの流れもわからず、おカネを貸しづらくなってしまいます。
そこで、社長は自社の商売を銀行に伝えることが大切です。これができていないケースは、けして少なくありません。銀行(の担当者)に聞けばわかります。「ウチの商売は何ですか?」と聞かれて、「誰に・何を・どのように売るか」を答えられないケースはあるのです。
ただし、銀行ばかりを責められず、伝えようとしていない社長にも責任はあります。おすすめは図解をして、説明することです。経済産業省がWEBで提供している「ロカベンシート(Excelデータ)」に含まれている、「商流・業務フロー」を利用してみるとよいでしょう。「誰に・何を・どのように売るか」が、整理できるようになっています。
前述した「利益きちんと」ができていても、商売を伝えることができずに融資を受けられずにいる会社もありました。なかには「自社の商売など銀行もわかっているだろう」と考えている社長もいるようですが、伝えなければわからないこともあります。少なくとも、決算書を見ても「誰に・何を・どのように売るか」はわかりません。
銀行対応でできることとして、「商売を伝える」のを怠らないようにしましょう。
仕訳を見直す
銀行対応でできること、3つめは「仕訳を見直す」です。実態をあらわしていない仕訳をしている会社があります。典型例を挙げると粉飾決算をしている会社です。
実態と決算書がズレているようでは、銀行も融資ができません。これを聞いて、「わが社は粉飾決算などしていない」とおもわれるかもですが、故意ではない粉飾・自覚がない粉飾というのはあるものです。
そうなると、「利益もきちんと出ている、商売も伝えているのに、どういうわけか融資が受けにくい」ということにもなりかねません。ゆえに、決算書をつくる過程となる仕訳を見直す必要があります。
そのときのポイントは、「仕訳が実態をあらわしているかどうか」です。これには、既存の仕訳が不適当であることもあれば、あるべき仕訳がされていないといったこともあります。このあたり、詳しくは書籍としてまとめましたので、よろしければ参考にどうぞ。
『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
実態をあらわしていない仕訳となると、実態と決算書がズレることとなり、「そんな決算書を見て社長は正しい経営判断ができるのか?(できるはずがない)」と銀行は考えます。実際、経営判断を誤るようでは社長も困ってしまいます。
銀行対応でできることとして、「仕訳を見直す」という視点も忘れずに。
まとめ
「融資を受けられるようになる銀行対応のコツは何だ?」と躍起になる社長もいます。が、まずは「できることをやるところから」です。では、できることは何なのかをお伝えしました。
- 利益きちんと
- 商売を伝える
- 仕訳を見直す
これらを確実に実行できるようになりましょう。バケツに穴があいているのであれば、それを塞ぐところからであり、コツやらなんやらを考えるのはそのあとです。