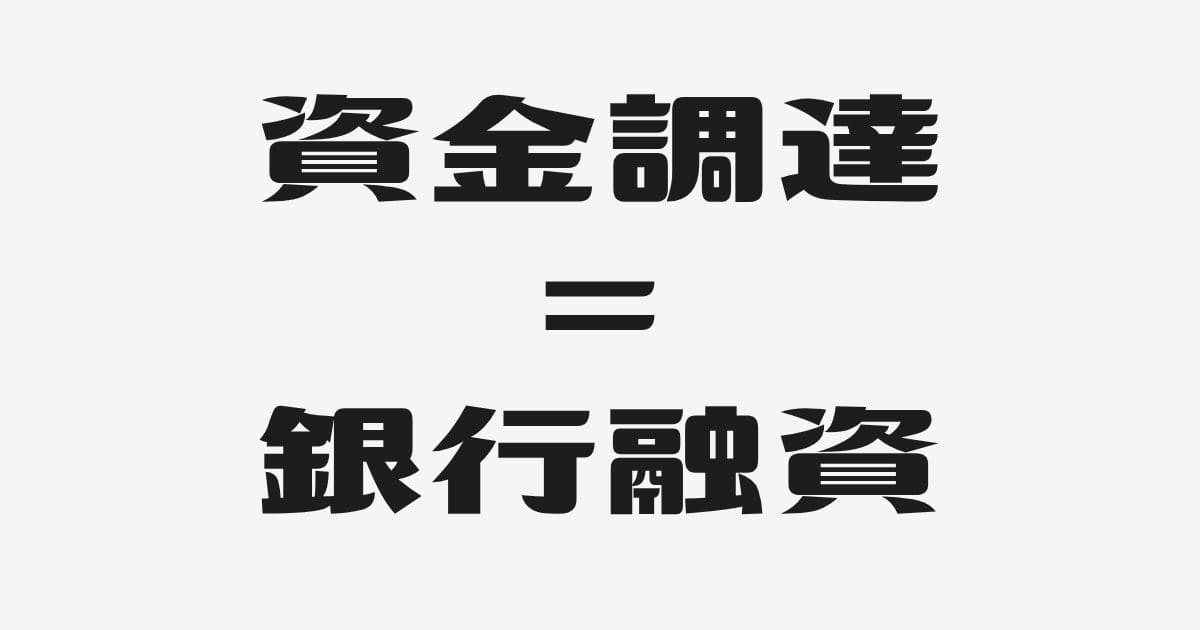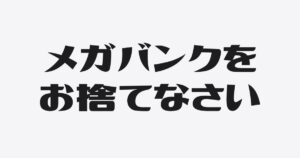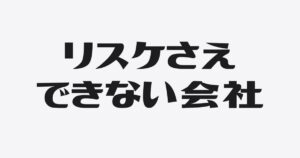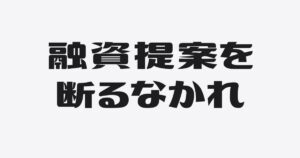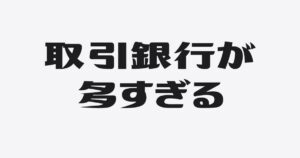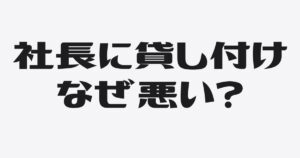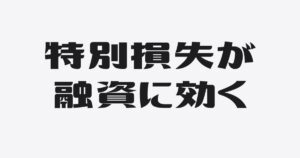ベンチャーキャピタルやクラウドファンディング… そんな華やかな「資金調達」は、ほとんどの中小企業には縁遠い話かもしれません。だとすれば、社長が本当に向き合うべきは、もっと身近で、もっと強力な「銀行融資」という現実です。
あなたの会社の資金調達とは
「資金調達」と聞くと、どのようなイメージが浮かぶでしょうか。
ベンチャーキャピタルからの出資、クラウドファンディング、エンジェル投資家… 華やかであり、革新的な響きが感じられるかもしれません。
もちろん、それらも資金調達の手段のひとつです。しかし、日本に数多く存在する中小企業にとって、それらの手段はどれほど現実的だといえるのか。少なくとも銀行融資ほど現実的ではない、と僕は考えています。
つまり、僕が日々、社長方々と向き合うなかで感じているのは、多くの中小企業にとって資金調達とは、「ほぼ銀行融資」を意味するということです。にもかかわらず、「資金調達」という言葉を使い、どこか格好つけてしまうことは、社長が本来向き合うべき資金繰りの生々しさや、その重要性から目をそらしてしまっているケースがあるように感じます。
そこで、あえてその「資金調達」という言葉の幻想に切り込み、中小企業の社長が本当に向き合うべき「銀行融資」について、その現実と重要性を解説してみることにしました。この記事のポイントは以下のとおりです。
- 資金調達という言葉がもたらす幻想
- 中小企業の現実的な選択肢は銀行融資
- 社長は「資金調達」から「銀行融資」へ
資金調達という言葉がもたらす幻想
まずはじめに、なぜ僕が「資金調達」という言葉に違和感を覚えるのか、その理由からお話しします。それは、この言葉が中小企業の社長に、ある種の「幻想」を抱かせてしまう危険性があるからです。
ポイント1:中小企業にはほぼ縁がない世界
メディアなどで華々しく語られる「資金調達」の成功事例は、そのほとんどが、急成長を目指す一部のスタートアップやITベンチャーのものです。それらのケースでは、革新的なビジネスモデルやテクノロジーを武器に、事業の将来性を投資家にプレゼンし、エクイティ(自社の株式)と引き換えに、ベンチャーキャピタルなどから大きな資金を得ます。
ところが、日本経済を支える大多数の中小企業、たとえば、地域に根ざした製造業、建設業、飲食業、サービス業などは、ビジネスモデルが異なります。このような堅実な事業を営む会社が、ベンチャーキャピタルの門を叩いても、残念ながら話を聞いてもらうことすら難しいのが「現実」でしょう。投資家が求める「短期間での爆発的な成長」とは、性質が違うからです。
「資金調達」という言葉が持つ「幅広さ」のイメージに惑わされ、自社にとっては非現実的な世界を追い求めてしまうと、本来もっと力を注ぐべきことに使うはずだった、貴重な時間と労力を無駄にすることにもなりかねません。
ポイント2:借りることへの生々しさの欠如
「資金調達」という言葉は、どこかスマートで客観的な響きがあり、「おカネを借りる」という行為の生々しさや、返済義務の重みが薄まって聞こえるところがあります。
ですが、銀行融資は、会社の信用を担保に、「返済する」という約束のもとで「おカネを借りる」という、きわめて現実的でシビアな行為です。そこには、事業計画の妥当性や返済能力の客観的な証明、そして何よりも社長個人の覚悟が問われます。
「資金調達」という、どこかよそゆきの言葉を使うことで、この銀行融資が持つ本来の重みから目をそらし、経営判断が甘くなってしまうことを、僕は懸念しているのです。借りたおカネには、必ず返す責任がともないます。その生々しい現実と向き合うことが、正しい財務感覚の第一歩です
中小企業の現実的な選択肢は銀行融資
では、幻想を追い求めるのではなく、中小企業の社長が現実に目を向けるべき選択肢とは何でしょうか。もはや言うまでもなく、それが「銀行融資」です。
ポイント1:最も身近で、最も強力な手段
銀行や信用金庫は、日本全国の津々浦々に存在し、地域の中小企業との取引を前提とした融資商品を用意しています。ゆえに、中小企業にとっては身近で、もっとも利用しやすい資金調達の手段だと言えるでしょう。
運転資金のほか、あらたな機械を買うための設備投資、社員の賞与資金、法人税などの納税資金など… 事業のさまざな場面で必要となるおカネを、会社の規模や状況に応じて柔軟に調達できる可能性があります。
他のどの手段と比較しても、銀行融資は圧倒的に現実的で、かつ会社の成長と安定を支える上で強力な選択肢である、という事実をまずはっきりと認識することが重要です。
ポイント2:会社の信用力を育てるプロセス
銀行融資は、単におカネを借りておしまい、ではありません。
融資を受けたあとも、会社の業績を決算書や試算表という形で定期的に報告し、事業の状況をきちんと説明する。そして、計画どおりに返済を重ねていく。この一連の流れを通じて、銀行との信頼関係が築かれ、会社の「信用力」が育っていきます。
この「信用力」こそが、貸借対照表には載らない、目には見えずとも会社の重要な財産です。自社の信用力が高まれば、いざというときに会社を守るための追加融資を受けやすくなったり、あらたな挑戦をするときには銀行の積極的な支援を得やすくなったりします。
他の資金調達手段にはない、金融機関との継続的な関係性のなかで、会社の信用力を着実に高めていける点は、銀行融資が持つ大きなメリットなのです。
社長は「資金調達」から「銀行融資」へ
中小企業にとっての現実が銀行融資であるならば、社長の意識もそれに合わせて変えていく必要があります。「資金調達」という少しぼんやりとした言葉の響きから離れて、より具体的な「銀行融資」という手段に、はっきりと焦点を当てるのです。
ポイント1:イベントから日常業務へ
「資金調達」というと、何か特別な準備をして臨む、一世一代の「イベント」のように聞こえるフシがあります。しかし、「銀行融資」はそうではありません。日々の売上管理や支出管理と同じように、会社の継続的な「日常業務」のいちぶとして捉えるべきです。
決算書や試算表を、税務申告のためだけでなく、銀行に説明できるような品質で作成して管理する。資金繰り表を使って、日々のおカネの動きを正確に把握する。このような地道な活動の積み重ねこそが、銀行融資を受けやすくするための土台になります。
銀行融資は、けして特別なイベントではなく、日常業務の積み重ねなのです。
ポイント2:プレゼンから対話へ
いわゆるベンチャーキャピタル向けのピッチのように、夢を語る派手な「プレゼンテーション能力」もありますが、銀行融資でより求められるのは、銀行の担当者との地道で誠実な「対話力」です。
自社の強みや将来性だけでなく、いま抱えている経営課題についても正直に伝え、それに対して今後どう取り組んでいくのかを、社長みずからの言葉で語れるか。銀行との継続的な対話を通じ、良いとき悪いときも隠さずに報告できて、相談ができるような信頼関係を築いていくことが、何よりも重要になります。
そのためには、社長自身が自社の数字をきちんと理解して、事業の状況を客観的に整理、把握しておくことが大切です。
まとめ
中小企業の社長が真剣に向き合うべきは、「資金調達」という漠然とした言葉ではなく、きわめて具体的で現実的な「銀行融資」だと言えます。
いわゆるスタートアップが追い求めるような幻想を追うのではなく、日々の経営のなかで、銀行との信頼関係を地道に築き上げ、会社の信用力を着実に高めていくこと。それこそが、会社を強くするための王道です。
「資金調達」という、どこか格好つけた言葉に逃げることなく、「銀行融資」という現実と真摯に向き合う。そういった社長の意識改革こそが、自社の未来を切り開く、大きな一歩になると僕は考えています。