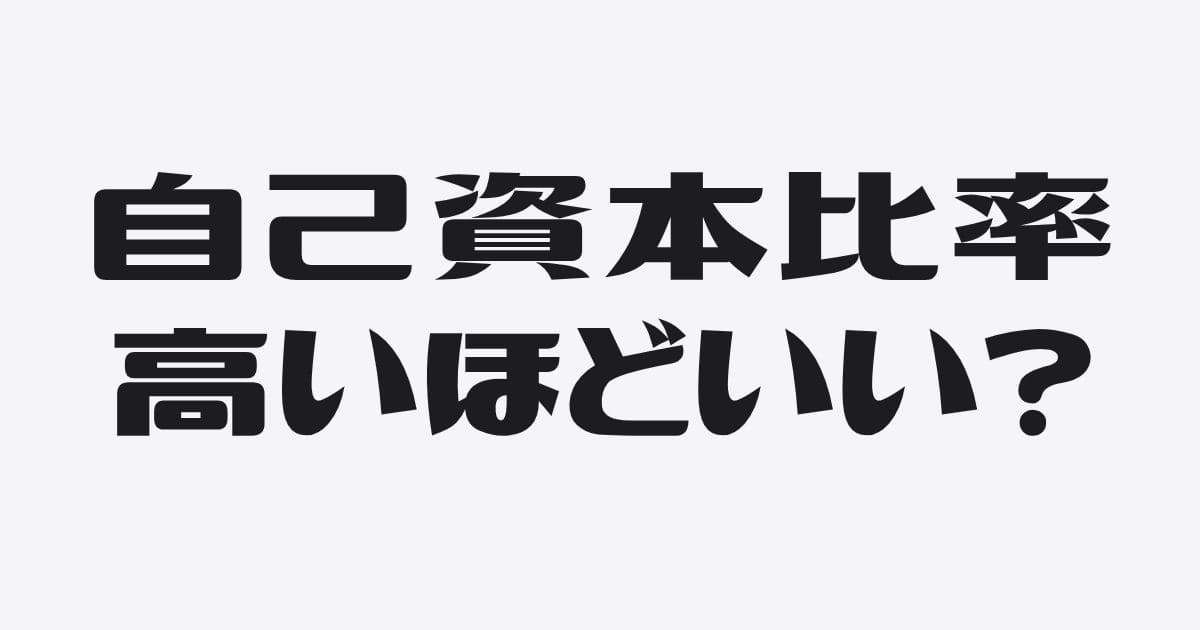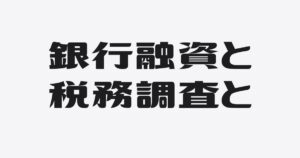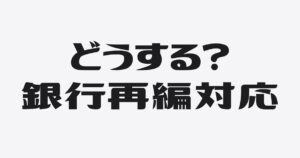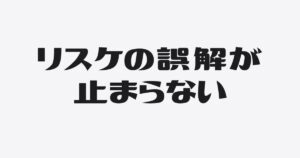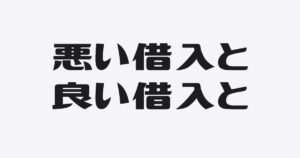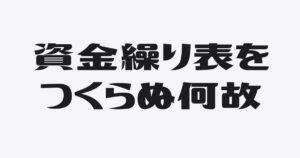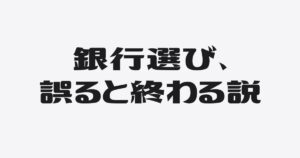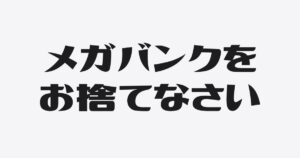自己資本比率は高いほど良い?必ずしもそうではありません。銀行も認める「20%でOK」という考え方と、借入を活用する攻めの財務戦略について解説します。
自己資本比率は高いほうがいい、というけれど
会社の財務について話していると、「自己資本比率は高いほうが良い」「最低でも30%は目指しましょう」なんてアドバイスを、よく耳にすることとおもいます。たしかに、自己資本比率は会社の安全を示す大事な指標のひとつです。僕もそれは否定しません。
でも、その「高いほうが良い」という常識を、鵜呑みにしていませんか?
もし、自己資本比率という数字を上げること自体が目的になってしまうと、かえって会社の成長を止めてしまう危険性があるのです。これは意外と多くの社長が見落としがちな「ワナ」だと僕は考えています。
銀行にも「これくらいあれば、まあ一定の安全性はあるよね」と認めてくれる目安があるのです。そして、その目安からすれば、自己資本比率はなにも30%もなくても十分だったりします。むしろ、あえて「20%台をキープする」くらいの考え方のほうが、攻めの経営には必要です。
そこで今回は、自己資本比率という数字の呪縛から解き放たれて、会社の未来のために社長が本当に注目すべきことについて、僕なりの考えをお話ししてみます。
自己資本比率という「数字」がもたらすワナ
まず、自己資本比率とはについて、カンタンにおさらいしておきましょう。これは、会社の総資産(会社が持っている財産のぜんぶ)のうち、返済しなくていいじぶんのおカネ(純資産=株主からのおカネ+これまでの利益の蓄積)が、どれくらいの割合を占めているかを示す数字です。
自己資本比率(%) = 純資産 ÷ 総資産 × 100
この比率が高いほど、借入への依存度が低くて、財務的に安定している、と一般的には言われます。では、この比率を上げるにはどうしたらいいか?おもな方法は2つです。
- 利益を増やして純資産を積み上げる
- 借入を減らして負債を減らす
社長が陥りがちなのが、2つめの「借入を減らす」選択肢に偏ってしまうことです。
「自己資本比率を上げたいから、もう借入はしないぞ!」とか、「手元におカネ(預金)があるなら、さっさと繰り上げ返済して借入を減らしてスッキリしたい!」とか。どんなふうに考えてしまう気持ちはわかります。でも、そこに大きな落とし穴があるのです。
貸借対照表のしくみ(資産 = 負債 + 純資産)を思い出してみましょう。負債である借入を減らすために、資産である預金を使えば、資産も同じだけ減ってしまいますよね?すると、純資産の「額」自体は、1円も増えないのです。
たしかに比率は計算上、ほんのわずか改善するかもしれません。でも、そのために会社の成長に必要な資産(潤沢な現金預金、売上を増やすための売掛金や棚卸資産、未来の利益を生む設備など)まで増やせなくなってしまっては、元も子もないでしょう。
自己資本比率という「数字のための数字」にとらわれすぎて、会社の成長機会をみすみす逃してしまう。これが、僕が考える「自己資本比率のワナ」です。
なぜ20%でOKなのか?銀行も認める基準がある
ならば、自己資本比率はどれくらいあれば、銀行も「まあ、ひとまず大丈夫かな」と見てくれるのか?
そのひとつの目安として、注目したいのが「私募債特定社債保証制度」の適債基準です。これは、信用保証協会が会社の社債(私募債)の保証をするときの基準のひとつであり、そこに「自己資本比率20%以上」という項目があります。
つまり、自己資本比率が20%を超えていれば、信用保証協会、ひいては銀行も「財務的に一定のレベルはクリアしている」と認めてくれる、ひとつのラインだと考えられるわけです。
もちろん、30%、40%と高ければ高いほど、見た目の安全性は増します。でも、さきほども言ったとおり、比率を上げることばかりに固執すると、必要な投資ができなくなって、成長が止まってしまうリスクがあるのです。
とくに、これから会社を大きくしていきたい成長段階にある社長や、積極的にあたらしいことにチャレンジしたい社長にとっては、あえて自己資本比率を20%台をキープするという目標設定も、有効な考え方だといえるでしょう。
自己資本比率20%台キープという攻めの財務戦略
自己資本比率20%台をキープと聞くと、「え、財務規律を緩めるの?」とおもわれるかもしれません。でも、僕が言いたいのはむしろ逆です。これは、会社の成長と安定のバランスを取るための、より積極的で高度な財務戦略だと考えています。
自己資本比率を上げること自体が目的になってしまうと、「とにかく借入を減らそう」という短絡的な思考に陥りがちです。たしかに比率は上がるかもしれませんが、そのために手元のおカネ(預金)を減らしたり、必要な投資まで見送ったりしていては、会社の成長を止めてしまうことになりかねません。本末転倒です。
だからこそ、あえて「20%台をキープする」と考える。これは、「守りに入りすぎてはいないか?攻めの姿勢を保てているか?」と、みずからに問いかけるためのルールとなります。
自己資本比率20%台という銀行も認める安全圏 を意識しつつ、必要な場面では借入を恐れずに活用していくぞ、という意思表示でもあるわけです。
比率は結果、見るべきは額
そもそも自己資本比率は、日々の事業活動の「結果」としてついてくるものだと僕は考えています。比率を上げること自体を目的にするのではなく、まず優先すべきは、事業を成長させてしっかりと利益を出して、純資産の「額」そのものを増やしていくことです。
そのために意識したいのが、「おカネ(預金)の確保 → 成長のための投資 → 利益の拡大」というサイクルを回していくこと。手元のおカネをしっかり確保しながら、成長が見込める分野(あたらしい設備、優秀な人材、商品開発など)には、借入も賢く活用して積極的に投資する。
そして、その投資から得られた利益で、さらに会社を強くしていく。この循環こそが、会社の持続的な成長の鍵になるものと考えます。
社長が本当に注目すべき2つのポイント
自己資本比率という「率」だけに目を奪われるのではなく、社長は何を重視して会社の数字を見ていけばいいのか?僕が大事だと考えるのは、次の3つの視点です。
ポイント1:「率」よりも「額」を見る
貸借対照表を見るとき、自己資本比率もチェックしつつ、それ以上に「現金預金」そして「純資産」、これらの「絶対額」がどう動いているかをしっかり追いかけましょう。会社の本当の体力や成長の実態は、「率」よりも「額」にこそ表れるものです。純資産の「額」が増えていれば、比率は後からついてきます。
ポイント2:投資判断は「回収見込み」で
あたらしい機械を買うなど、大きな投資を検討するときに、「自己資本比率が下がるから…」とためらうのではなく、その投資が将来どれくらいの利益(キャッシュフロー)を生み出して、借入をした場合にきちんと返済できる見通しが立つかどうか、これを冷静に判断することが大切です。
しっかりとした回収見込みがあるのであれば、借入を恐れる必要はありません。むしろ、成長のチャンスを逃さないために、積極的に活用すべきです。
まとめ
自己資本比率は、会社の安全性を測るうえでたしかに重要な指標のひとつです。でも、その数字自体を追い求めるあまり、会社の成長に必要な投資までためらってしまうのは、もったいない。
銀行も認める「自己資本比率20%」というラインを目安にしつつ、社長が本当に重視すべきは、会社の成長に必要な資産を増やして、利益(純資産の額)を着実に積み上げていくこと、そして何よりも十分なおカネ(現金預金)を確保することです。
自己資本比率は、その結果として自然とついてくるもの。「数字のための数字」に振り回されることなく、会社の未来を創るためのバランス感覚を大切にしていきましょう。