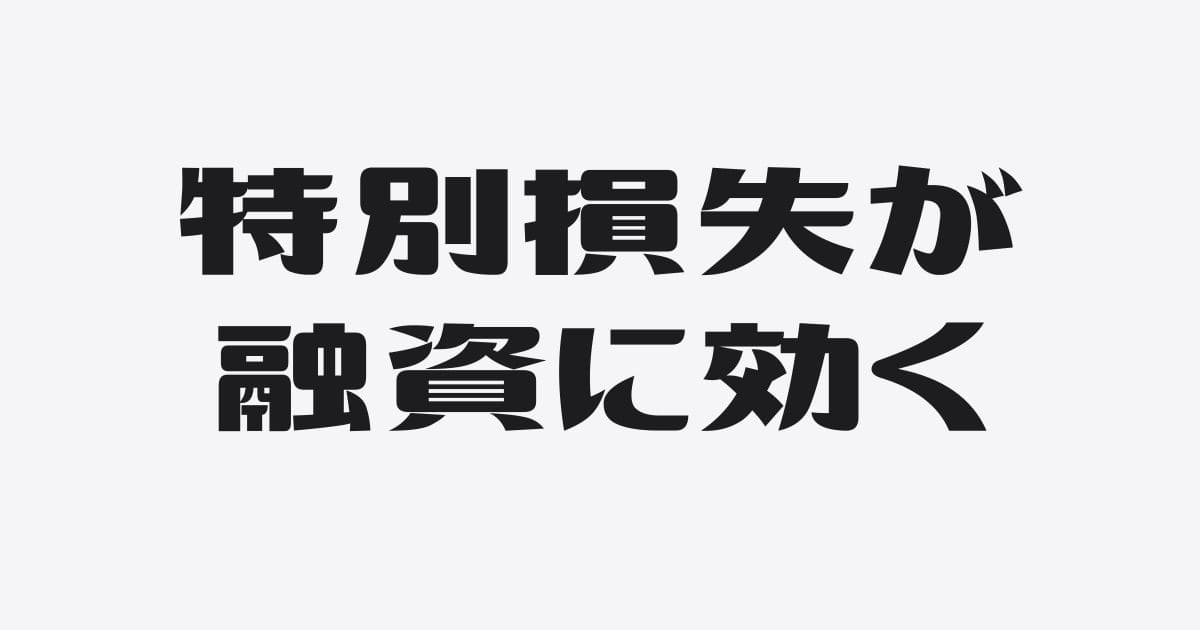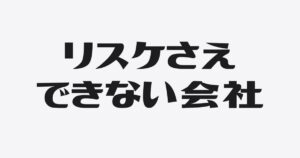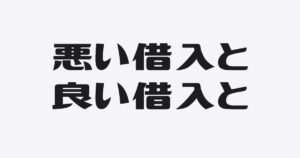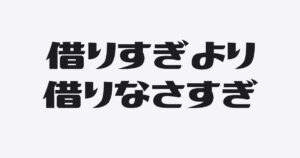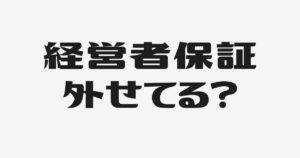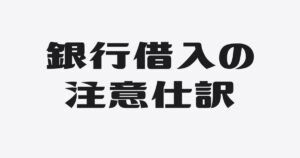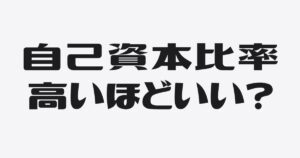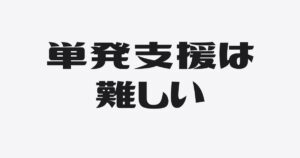会社の決算書について、「特別損失で銀行の評価を上げよう」という話があります。ですが、なんでもかんでも特別損失にすればいい、というハナシではありません。では、どうすればよいのか?
特別損失で銀行の評価が上がるのはなぜ
会社の決算書について、「特別損失で銀行の評価を上げよう」という話があります。
同じ費用であっても、決算書(損益計算書)の「販売費及び一般管理費」に区分するよりも、「特別損失」に区分するほうが、銀行からの評価が上がるという考え方です。
たしかに、特別損失に区分すれば、最終利益は変わらずとも、営業利益や経常利益は増える点では、銀行の評価を上げることになるでしょう。これが、特別損失で銀行の評価が上がると言われる理由です。
とはいえ、なんでもかんでも特別損失にすればいい、というハナシではありません。実質的には「販売費及び一般管理費」なのに、銀行の評価を上げようと「特別損失」にするのは本末転倒です。それに気づいた銀行からは「誤った経理処理」と見られ、むしろ評価が下がることでしょう。
では、会社が「特別損失」で銀行の評価を上げるにはどうしたらよいのか?3つのポイントについてお伝えします。次のとおりです。
- 金額の大小
- 頻度の多少
- 債務超過か
これらのポイントが理解できていないと、特別損失によって、むしろ銀行の評価を下げることになりかねません。このあと順番に解説をするので、確認しておきましょう。
特別損失で銀行の評価を上げるポイント
繰り返しですが、「なんでもかんでも特別損失にすればいい」というハナシではありません。特別損失で銀行の評価を上げるにはポイントがあります。そのポイントを、セルフチェックできるようにしましょう。ぜんぶで3つ、次のとおりです。
金額の大小
特別損失で銀行の評価を上げるポイント、1つめは「金額の大小」です。
特別損失は、文字どおり「特別」な損失であり、金額としては「インパクトの大きなもの」と考えられます。この点、あまり小さな金額を特別損失に区分していると、「小手先感」が出てしまうでしょう。
本来、特別損失に区分する目的は、「より正しく事業の実態を示すため」です。銀行の評価が上がるのは、その結果でしかありません。ところが、「少しでも銀行の評価を上げるために、小さな金額でも特別損失に…」というのでは、目的を見誤っていることになるでしょう。小手先です。
とはいえ、特別損失かどうかを判断するにあたって、「いくら以上なら特別損失」といった基準はありません。金額による絶対的な基準はない、ということです。したがって、「金額の大小」の判断はケースバイケースとなります。
たとえば、最終利益が500万円の会社であれば、50万円の特別損失にはそれなりのインパクトがあるとしても、最終利益が5,000万円の会社であれば、同じ50万円の特別損失はそれほどのインパクトがないことはわかるでしょう。
言い換えると、金額的にインパクトが大きな費用が「販売費及び一般管理費」に混じっていないかの確認を忘れないように(混じっていれば特別損失に区分)、ということです。
頻度の多少
特別損失で銀行の評価を上げるポイント、2つめは「頻度の多少」です。
特別という意味には、前述した「金額」のほかに「頻度」があります。特別な頻度とはつまり、「たまたま」生じたものなのかという基準です。いつも生じている費用であれば特別とはいえませんが、たまたま生じた損失は特別だといえるでしょう。
なお、頻度についてはも「〇年に1回生じるなら特別損失」といった基準はありません。やはりケースバイケースです。金額と同じく、「より正しく事業の実態を示すため」という目的に沿って考えるようにしましょう。
たとえば、役員に対する退職金であれば、「役員の退職は頻繁に起きるものではない」との理由から、特別損失に区分することになります。また、決算の状況にともない支給する賞与であれば、「状況によっては支給しないこともある」との理由から、特別損失に区分するのもよいでしょう。
なんにせよ、目的は「より正しく事業の実態を示すため」であり、銀行に対しても「特別損失」に区分した理由を説明できる必要があります。ところが、それを説明できなかったり、説明に納得感がなければ、銀行からは「小手先」と見られて評価を下げることになりかねません。
以上をふまえて、特別損失に区分するときには、ひと目で内容がわかる勘定科目名が望ましく(勘定科目を「特別損失」などとしない)、そのうえで、銀行に決算書を渡すときには特別損失の内容について口頭でも説明を加えるのが賢明です。
債務超過か
特別損失で銀行の評価を上げるポイント、3つめは「債務超過」です。
さいごは、これまでの2つのポイントとは少し異なる視点になります。特別損失を計上することによって、債務超過になるかどうかです。債務超過とは、貸借対照表において「資産<負債」の状態をいいます。見た目のとおり危険な状態であり、債務超過は銀行が忌み嫌うものの1つです。
特別損失は、営業利益や経常利益に影響を与えない、最終利益に影響はするけれど特別な損失である点(翌期以降は損失が生じない)は銀行からも考慮されるのでと、安易に特別損失を計上する会社があります。
たとえば、含み損がある遊休不動産があるので、それを売却して特別損失を計上しようとか。しかし、特別損失によって最終利益がマイナスになると、その分だけ貸借対照表の純資産が減少します(利益剰余金が減るので)。結果として純資産がマイナスになると、債務超過です。
債務超過とは「資産<負債」であるのと同時に、「純資産<0」の状態でもあります。すると銀行から嫌われることは前述しました。したがって、特別損失を計上するのであれば、「債務超過にならないか」を必ず事前に確認しましょう。
言い換えると、「特別損失を計上するなら、債務超過にならない範囲で」ということです。いざ債務超過になってしまえば後の祭りですから、十分に注意しなければいけません。
まとめ
会社の決算書について、「特別損失で銀行の評価を上げよう」という話があります。ですが、なんでもかんでも特別損失にすればいい、というハナシではありません。
では、どうすればよいのか?
その疑問への答えとして、特別損失で銀行の評価を上げるポイントを3つお伝えしました。
- 金額の大小
- 頻度の多少
- 債務超過か
これらのポイントが理解できていないと、特別損失によって、むしろ銀行の評価を下げることになりかねません。セルフチェックできるようにしておきましょう。