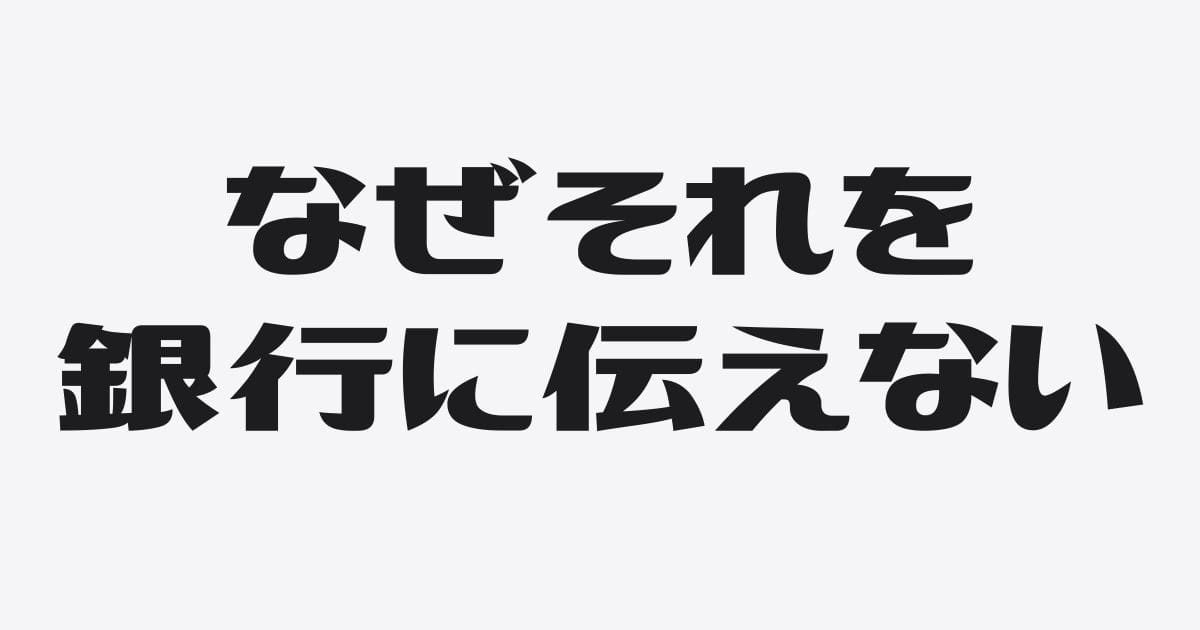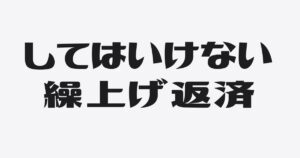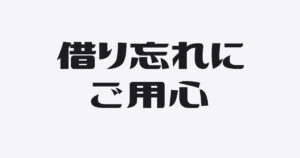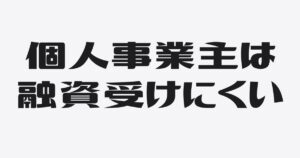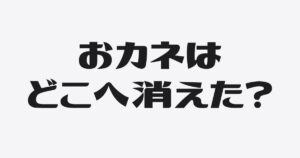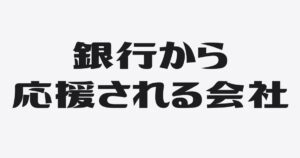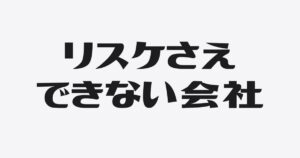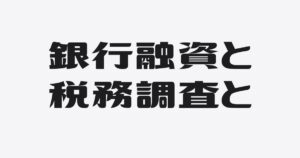銀行に決算書を渡すだけで、おわらせてはいませんか?いっぽうで、社長が銀行に伝えるべきなのに、意外と伝えていない重要な情報があります。
決算書だけでは伝わらない
「決算書はきちんと銀行に提出しているし、数字のことも担当者には説明している。だから、銀行はウチの会社のことをちゃんとわかってくれているはずだ」
多くの社長が、そう考えているかもしれません。たしかに、決算書は会社の業績や財産状況を示す重要な書類です。しかし、それだけで、自社のすべてが銀行に伝わっているでしょうか?
実は、銀行は決算書の数字だけでは見えてこない、会社の「本当の強み」や「社長の熱意」、そしてその先にある「将来性」などをもっと知りたい、と考えています。
社長にとっては「当たり前すぎて、わざわざ説明するまでもない」と思っていることが、銀行にとっては融資判断や今後の支援を考えるうえで、重要な情報になることがあるのです。
今回は、社長が銀行に対して「もっと伝えたほうがいいのに、意外と伝えていない」と僕が感じる、会社の重要情報を3つ取り上げます。以下のとおりです。
- 商売(ビジネスモデル)
- 決済情報と与信管理
- 将来計画と進捗管理
これらがなぜ、銀行にとって大切なのか。そして、どう伝えればより効果的なのかについて解説します。
銀行に伝えるべき重要情報
決算書の数字ももちろん大切ですが、それと同じくらい、いや、時にはそれ以上に銀行が知りたいと考えている情報があります。銀行とのコミュニケーションをより深め、信頼関係を築くために、社長が積極的に伝えるべき3つのポイントを具体的に見ていきましょう。
商売(ビジネスモデル)
なぜ伝わらないのか?
社長にとっては、自社の商売のやり方や特徴は「当たり前」のこと。毎日そのなかで仕事をしているのですから、わざわざ銀行に詳しく説明する必要性を感じないのかもしれません。
しかし、銀行員は必ずしも自社の業界の専門家ではなく、業界特有の慣習や、自社が持つ独自の強み、他社との違いなどを、最初から深く理解しているとは限らないのです。
なぜ銀行は知りたいのか?
銀行は、融資先が「誰に、何を、どのように売る」のか、それにより、「どうやって利益を生み出しているのか」というビジネスモデルを理解したいと考えています。これがわからなければ、融資したおカネがどのように使われ、将来どのようにして返済の原資(利益やキャッシュフロー)に繋がっていくのか、具体的なイメージができません。
また、自社のビジネスモデルが持つ「独自性」や「優位性(他社にはない強み)」がわかれば、銀行はより高く評価しやすくなります。たとえば、特定の技術力、強力なブランドイメージ、独自の販売チャネル、顧客との強い信頼関係などです。
こうしたビジネスモデルの理解を通じて、市場環境の変化や競合他社に対して、自社がどのように対応して、勝ち残っていこうとしているのか、その戦略や社長の考えも見えてきます。
どう伝えればいいのか?
決算説明や銀行との定期的な面談の際に、あらためて「自社のビジネスモデル」について、説明する機会をつくりましょう。その際、経済産業省が提供している「ローカルベンチマーク(通称:ロカベン)」を活用するのも非常に有効な方法です。
ロカベンは、企業の「商流・業務フロー」や「4つの視点(事業面、組織面、財務面、外部環境との関わり)」を整理し、自社のビジネスモデルを可視化するための共通のツールとして、多くの金融機関でも活用されています。
ロカベンを使って自社のビジネスモデルを図示したり、あるいは社長自身の言葉で、「ターゲットとしている顧客は誰か(あるいはどのような層か)」「その顧客にどのような価値(商品・サービスの特徴やメリット)を提供しているのか」「どのようにして顧客にそれを届けて、対価を得ているのか(販売戦略や収益構造)」「他社と比べてどこが優れていて、何が違うのか(競争優位性)」といった点を、具体的に伝えることが大切です。
「自社の事業は、こういう社会的な背景や顧客のニーズがあるから伸びしろがある」「この強みがあるから、簡単には他社に真似されないし、価格競争にも巻き込まれにくい」といった具体的な根拠を示すことで、銀行に安心感と将来への期待感を持たせることができます。
決済情報と与信情報
なぜ伝わらないのか?
主要な売上先や仕入先の会社名は、決算書に添付する「勘定科目内訳明細書」などで銀行にもあるていどは伝わります。しかし、それぞれの取引先との具体的な取引条件(決済サイトの長さ、取引シェアの大きさなど)や、ふだんからどのような与信管理を行っているかといった、より踏み込んだ情報までは、なかなか伝わりにくいものです。
なぜ銀行は知りたいのか?
おもな取引先の決済条件(たとえば、入金が何か月後になるか、支払いは何か月後かなど)は、会社の日常的な資金繰りに直接的な影響を与える重要な情報です。これがわからないと、銀行は自社の資金繰りの状況や今後の見通しを、把握することができません。
また、特定の取引先への依存度が高い場合(たとえば、売上の大部分を1社に頼っている、あるいは仕入の大部分を1社から行っているなど)、その取引先の経営状態が悪化すれば、あなたの会社も大きな影響を受けます。銀行は、そうした「取引先の集中リスク」や、その相手先の信用力について常に気にしています。
そして、社長が自社の取引先に対して、ふだんからどのような与信管理(新規取引開始時の信用調査の実施、取引限度額の設定、売掛金の回収遅延のチェックなど)を行っているかという点は、銀行にとって「この社長はリスク管理意識が高いな」と安心できるポイントになります。きちんと与信管理をしていることが伝われば、それは銀行からの信頼向上につながります。
どう伝えればいいのか?
おもな売上先と仕入先について、それぞれの取引シェア(全売上・全仕入に占めるおおよその割合)や、具体的な決済条件(例:「月末締め、翌月末払い」「月末締め、翌々月末入金」など)を一覧表にするなどして、銀行にわかりやすく説明できると、資金繰りの実態を把握してもらいやすくなります。
新規に取引を始める際の与信調査の方法(何をどこまで調べているか)や、既存の取引先に対する定期的な信用状況のチェック(たとえば、決算書を入手しているか、信用調査会社の情報を活用しているかなど)といった、自社で行っている与信管理の具体的な取り組みについて、積極的に伝えましょう。
「この取引先とは、もう何十年にもなる信頼関係で結ばれていて、安定した取引が継続している」「特定の取引先に過度に依存しないように、常に新規の取引先開拓も意識して行っている」といった情報も、銀行にとっては安心材料になります。
将来計画と進捗管理
なぜ伝わらないのか?
「将来はこんな会社にしたい」「売上をこれくらいまで伸ばしたい」という夢や目標は、多くの社長が持っているものです。しかし、それを具体的な数値目標や行動計画に落とし込んだ「経営計画書」のように目に見える形にして、それを銀行に提示して説明している会社は、それほど多くないのが実情です。
多くの場合、社長の頭のなかにはビジョンがあっても、銀行には口頭での断片的な説明に終始してしまいがちだと言えます。
なぜ銀行は知りたいのか?
銀行融資の返済原資は、結局のところ「将来、会社が生み出す利益やキャッシュフロー」です。だからこそ銀行は、社長が会社の未来をどのように描き、それをどのような戦略と具体的な行動で実現しようとしているのか、その「計画」を知りたいのです。
そして、単に立派な計画が紙の上に描かれているだけでなく、その計画を実際に実行して、目標を達成していけるだけの「社長の実行力や管理能力」があるかどうかを、銀行は確認したいと考えています。
したがって、計画と実績の比較(予実管理)が行われていること、計画とズレが生じている場合には、その原因を分析して、対策が打たれていること、そうした「計画→実行→検証→改善」のサイクル(PDCAサイクル)を回しているかどうかに、銀行は注目しているのです。
どう伝えればいいのか?
可能であれば、3〜5年の中期的な「経営計画書」を作成して、銀行に提出・説明することを強くおすすめします。このとき、売上高や利益といった目標数値だけでなく、それを達成するための具体的な戦略(たとえば、新商品開発、新たな販路の拡大、コスト削減策など)や行動計画、必要な投資計画などを織り込むと、計画の具体性と社長の本気度が伝わり、より説得力が増します。
また、銀行には定期的に業況を報告して、計画の進捗状況(予算と実績の比較、計画との差異が生じた原因の分析、今後の具体的な対策など)を説明しましょう。
「この社長は、単に夢を語るだけでなく、会社の未来をきちんと見据えて具体的な計画を立てられる。それを着実に実行していく力もあるな」と銀行に感じてもらうことが、長期的な信頼関係となり、いざというときの力強い支援を得るための鍵となります。
まとめ
銀行は、決算書に書かれた過去の数字だけではわからない、会社の「本当の強み」や「社長の熱意、経営能力」をもっと知りたいと考えています。
今回挙げた3つの重要な情報、
- 商売(ビジネスモデル)
- 決済情報と与信管理
- 将来計画と進捗管理
これらは、社長にとっては当たり前のことでも、銀行にとっては融資判断や今後の支援を考えるうえで、とても価値のある情報なのです。
これらの情報を、日ごろから銀行に伝える努力をすることで、銀行との信頼関係は格段に深まります。結果として、よりスムーズな融資や、より積極的な支援にもつながるはずです。
「言わなくても、これくらいわかってくれているだろう」と考えるのではなく、「どうすれば、もっと自社のことを伝えられるだろうか」と考えて、銀行とのコミュニケーションに取り組みましょう。社長の大事な仕事のひとつです。