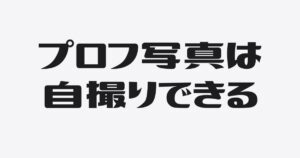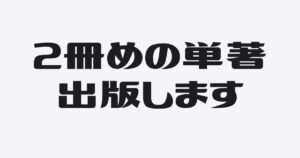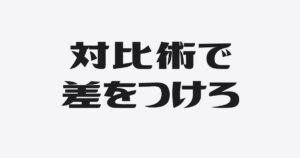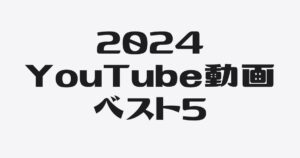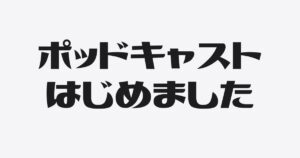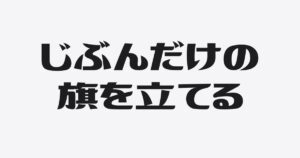誰もがSNSを使うのが、あたりまえの時代。はたしてSNSは発信と呼べるのか?約9年、各種メディアで発信を続けてきた僕が、考えていることをお伝えしてみます。
SNSは発信と呼べるのか?
「SNSで発信しています」
いまや、そんな自己紹介を耳にすることも、じぶんですることも、まったく珍しくなくなりました。X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、Threads、TikTok… 指先ひとつで、誰もが世界に向けて「何か」を伝えられる時代であり、本当にすごいことです。
でも、華やかなタイムラインを眺めたり、じぶんの投稿への反応を気にしたりするなかで、ふと胸によぎる小さな疑問はないでしょうか?
- 「これって、本当にじぶんが届けたかった発信なのか?」
- 「たくさんのいいねは嬉しいけど、じぶんの言葉はちゃんと伝わっているのだろうか?」
きょうは、そんなSNS時代のコミュニケーションについて、少し立ち止まって考えたい問いについて深掘りしてみたいと思います。テーマは「SNSは発信と呼べるのか?」です。約9年、各種メディアで発信を続けてきた僕が、考えていることをお伝えしてみます。
流れゆく言葉、積み重なる言葉
まず、インターネット上で行うコミュニケーションには、大きく分けて2つの性質があると言われています。「フロー型」と「ストック型」です。
フロー型とは、文字どおり「流れ」ていく情報であり、SNSのタイムラインがその代表例です。投稿した瞬間は注目を集め、たくさんの反応があるかもしれません。しかし、その熱狂は一過性のもので、数時間後、あるいは翌日には、もうほとんど誰の目にも触れなくなってしまいます。まるで川の流れのように、次から次へと新しい情報に押し流されていく…
いっぽうのストック型は、「蓄積」されていく情報です。たとえば僕がこうして書いているようなブログ記事、専門知識をまとめたウェブサイト、読者のために届け続けるメールマガジンなどがこれにあたります。
これらは、書かれてから時間が経っても検索されたり、誰かの悩みを解決したり、価値を提供し続けることができます。適切な手入れをすれば、時間が経つほどに深みを増し、まさにじぶんだけの「資産」となっていく可能性を秘めています。
この違いを意識したとき、僕たちは「発信とは何か?」という本質的な問いに立ち返らざるをえません。もし発信を、「届けたい誰かに、価値あるメッセージを、時間を超えて伝えていく行為」だと定義するならば、瞬間的に消費され、流れ去っていくSNSの投稿は、厳密にはこの定義から少しズレているのかもしれない、と感じるからですね。
もちろん、SNSのなかでもハッシュタグを工夫したり、まとめ機能を使ったりして、情報を「ストック」的に見せる工夫は可能です。しかし、その性質上、ブログやウェブサイトのように体系的に情報が積み重なり、いつでも容易に過去の情報にアクセスできる「蓄積性」とは、やはり大きな隔たりがあると言わざるをえないでしょう。
つい呟いてしまう手軽さのワナ
SNSの最大の魅力のひとつは、その「手軽さ」です。思い立った瞬間に、数タップでじぶんの考えや感情を世界に向けて放つことができます。このスピード感と気軽さは、僕たちの日常に彩りを与え、多くの人との繋がりを生み出してきました。
ですが、この手軽さゆえの落とし穴もあります。それは、深く考えるという過程を経ずに、「思いつき」や「瞬間的な感情」に突き動かされて投稿してしまいがちな点です。
- 「あ、これ面白い!シェアしちゃえ」
- 「きょうのランチ、美味しそうだからアップ」
- 「ちょっとムカついたから、グチっちゃおう」
- 「誰かに『すごいね』って言われたいから、がんばったアピール」
こうした衝動や感情に基づいた投稿が、タイムラインにはあふれています。もちろん、それ自体が悪いわけではありません。人間らしい感情のあらわれであり、共感を呼ぶことも多々あります。
ただ、こうした投稿ばかりが続けば、いつの間にか「じぶんは、誰に、何を伝えたいのか?」という発信の核となる部分が見えにくくなってしまう危険性があります。言葉が、誰かのための「発信」ではなく、じぶんの感情を処理するための「吐け口」になってしまうのです。
本来、「発信」とは、受け手を意識して届けたいメッセージを明確にし、言葉を選んで意図的に構成する、といった行為のはずです。そう考えたとき、僕たちが日々SNSで行っている1つ1つの投稿は、本当に「発信」と呼べるものになっているでしょうか?
いちど、じぶんの投稿履歴を冷静に振り返ってみる時間も、大切なのかもしれません。
「いいね」の呪縛と「他人軸」の世界
SNSには、独特の「空気」と「引力」があると感じています。
- あの人の投稿、すごくバズってるな…
- この投稿、やたら「いいね」が多いな…
- いま、この話題がトレンドなのか…
タイムラインを眺めていると、そうした情報が否応なく目に飛び込んできます。すると、無意識のうちに「こういう投稿が求められているんだ」「こういう言い方をすれば、もっと反応がもらえるんだ」と、他人の反応や世間の潮流にじぶんのアンテナが引っ張られていくのを感じたことはないでしょうか?
気づけば、「じぶんが本当に伝えたいこと」よりも、「多くの人にウケること」「好かれること」「炎上しないこと」を優先して言葉を選んでいる。これは、じぶんの発信の基準が「自分軸」ではなく「他人軸」、つまり他人の反応や評価にゆだねられてしまっている状態といえます。
もちろん、多くの人に受け入れられたい・共感されたい、という気持ちは自然なものです。しかし、それに過剰にとらわれてしまうと、じぶんの内側から湧き出るユニークな視点や、多少耳が痛くても伝えたい本質的なメッセージが、当たり障りのない、誰かの意見の焼き直しのようなものになってしまうおそれがあります。
SNSが「他人の反応」を可視化して、それを意識させるプラットフォームである以上、僕たちが意識的に「自分軸」を保とうとしない限り、その引力に流されてしまうのは、ある意味では必然なのかもしれません。
しかし、その状態でつくられた言葉は、果たして心からの「じぶんの発信」と呼べるのでしょうか?
「発信しなきゃ」が奪うもの
SNSの世界に身を置いていると、「常に何かを発信し続けなければいけない」という、見えないプレッシャーを感じることがあります。
タイムラインには、毎日、あるいは1日に何度も投稿している人たちがいます。楽しそうな日常、有益な情報、キラキラした成果…。それらを目にすると、「じぶんも何か価値ある情報を出さなきゃ」「存在感を示さないと忘れられてしまう」といった焦りが生まれることもあるでしょう。
でも、思い出してみてください。本当に心に響く言葉や、深い洞察に基づいた発信は、どこから生まれてくるのでしょうか?
それは、日常のなかにある些細な変化や違和感に気づく「観察力」と、それらをじっくりとじぶんの中で咀嚼して、意味を見出す「思考力」から生まれるのではないでしょうか?道端に咲く花の名前を調べてみる。カフェで聞こえてきた会話に耳を澄ませてみる。読んだ本の一節について、じぶんの経験と照らし合わせて考えてみる、とか。
こうした、インプットと内省のための静かな時間こそが、よい発信の土壌になるはずです。
ところが、SNSの「常にアウトプットし続けなければ」という空気は、この大切な「観察」と「思考」の時間を、僕たちから容赦なく奪っていきます。「発信のネタを探さなきゃ」という意識が先行し、腰を据えて何かをインプットしたり、じっくり考えたりする余裕がなくなってしまうのです。
結果として、インプットが枯渇し、表面的で中身の薄い投稿を繰り返してしまう…。これもまた、SNS時代の「発信」が抱える、見過ごせないワナの1つだと言えるでしょう。
「発信」しているのか「出演」しているのか?
もうひとつ、SNSにおけるコミュニケーションの本質的な問いがあります。それは、僕たちがSNSでおこなっていることは、「発信」ではなく、一種の「出演」になってはいないか? という視点です。
考えてみましょう。SNSは、フォロワーという名の「観客」が存在する「舞台」のようなものです。そして、僕たちはその舞台の上で、日々何らかの「役」を演じている側面はないでしょうか?
舞台に立つとなれば、当然、「観客からどう見えるか」「どう映るか」を意識するようになります。「いいね」や好意的なコメントという「拍手」を浴びたい。「炎上」という「非難」は避けたい。そう思うのは自然なことです。
しかし、その意識が強くなりすぎると、「ありのままのじぶん」や「飾らない本音」よりも、「見栄えのよさ」「ウケのよさ」「波風を立てない無難さ」などが優先されてしまう。すると言葉は、じぶんの内面から湧き出る「表現」ではなく、観客を意識した「演出」へと変わっていきます。
- 「本当はこう思うけど、反感を買いそうだからやめておこう」
- 「もっと、丁寧な暮らしをしているように見せたいな」
- 「このキャラでいけば、みんなに好かれるかな」
こうした考えが、投稿をつくるプロセスに介入してくると、それはもはや、じぶんの考えや感情を届ける「発信」というよりも、「理想のじぶん」や「求められているであろうキャラクター」を演じる「出演」に近いのかもしれません。
もちろん、TPOに合わせてじぶんを表現することは社会生活において必要なスキルです。しかし、SNSという舞台の上で「演じる」ことに慣れすぎてしまうと、いつしか「本当のじぶんの声」が何だったのか、分からなくなってしまう危険性も孕んでいます。
あなたはいま、SNSで心からの「発信」をしていますか? SNSという名の舞台に「出演」することに、少し疲れてはいませんか?
それでも、僕たちがSNSと付き合い続ける理由
ここまで、SNSが「本当の意味での発信とは言えないかもしれない」側面を、いろいろな角度から見てきました。フロー型であること、感情の吐け口になりやすいこと、他人軸に陥りやすいこと、観察力を奪うこと、そして「出演」になりがちであること。
「だったら、SNSなんてやめたほうがいいのか?」
そうおもわれるかもしれません。しかし、それでもなお、多くの人が(そしておそらく僕も)SNSを使い続けるのには、やはり理由があります。
それは、SNSには「まだ見ぬ誰か」と出会える、「きっかけづくり」の圧倒的な力があるからです。
ブログやメルマガといったストック型のメディアは、基本的に、すでに「じぶん」や「じぶんのテーマ」にあるていどの興味・関心を持ってくれた人が、検索などを通してたどり着く場所です。いわば、「待ち」のメディアともいえます。
いっぽうでSNSは、その拡散力とアルゴリズムによって、じぶんのことを全く知らない人、じぶんのテーマにこれまで関心のなかった人にまで、じぶんの存在や言葉を届けてくれる可能性を秘めています。言うなれば「攻め」のきっかけづくりができるのです。
SNSで何気なくシェアしたあなたの知識や経験、あるいは人柄がかいま見える投稿が、偶然誰かの目に留まる。そこから興味を持たれて、プロフィールに書かれたブログやウェブサイトへ訪問してくれる。さらに深くあなたの考えに触れ、メルマガに登録してくれたり、商品やサービスに繋がったり、あるいはリアルな場での交流へと発展したり。
SNSは、こうした「最初の接点」を生み出すための、非常に強力な道具となり得るのです。
だからこそ、大切なのはSNSを「発信のすべて」と捉えるのではなく、「発信の入口」「価値ある繋がりへのきっかけ作りの場所」として、戦略的に、そして割り切って活用する視点ではないでしょうか?
SNSの持つ「広がり」と「速さ」というメリットを理解して、それをじぶんの「本拠地」(ブログ、メルマガ、ウェブサイト、書籍、リアルな活動など、じぶんが本当に届けたい価値を蓄積する場所)へと繋げる導線として設計する。
この連携があってこそSNSは真の力を発揮し、じぶんの「発信」をより豊かにしてくれるはずだと、僕は考えています。
結論:SNSは「発信の一部」だからこそ「残る言葉」を育てる
SNSは、いまのコミュニケーションにおいて、間違いなくパワフルで魅力的な道具です。多くの出会いと可能性をもたらしてくれます。
ですが、その手軽さや即時性に慣れてしまうと、本来の意味での発信、つまり、「じぶんの軸を持ち、届けたい相手に、深く、長く価値を届け続ける言葉」を見失ってしまう危険性も、同時に存在します。
だからこそ、僕たちは意識する必要があります。SNSは「発信活動の一部」ではあっても、「発信活動のすべて」ではない、ということをです。
フロー情報があふれるSNSだけに、じぶんの言葉をゆだねるのではなく、時間をかけて思考し、推敲し、蓄積していく「ストック型の発信」の場を持つこと。 そして、SNSをその「入口」として賢く活用すること。
このバランス感覚が、情報過多の時代において、ますます重要になっていくようにおもいます。
流れゆく言葉の先で、じぶんの「残る言葉」を大切にしましょう。
タイムラインは、きょうもも絶え間なく流れ、更新されていきます。きのうのあなたの投稿は、もうほとんど見られることはないかもしれません。
だからこそ、流れ、消費されていく言葉とは別に、じぶんの内側から生まれ、誰かの心に深く届き、時間を超えて価値を持ち続ける「残る言葉」を意識的に紡ぎ、育てていかないとです。
- じぶんは、本当は何を伝えたいのだろう?
- この言葉は、誰の心に届けたいのだろう?
- なぜ、じぶんはこのメッセージを発するのだろう?
そんな問いを、常に自分自身に投げかけながら、SNSの喧騒に流されることなく、しかしそのチカラを賢く借りながら、1つ1つの言葉を大切に届けていく。
流れゆく言葉よりも、じぶんの心に、そして誰かの心に、深く「残る言葉」を。そんな意識を持つことが、これからの時代の「発信」において、僕たちひとりひとりに求められているのだと、考えているのですがいかがでしょうか?