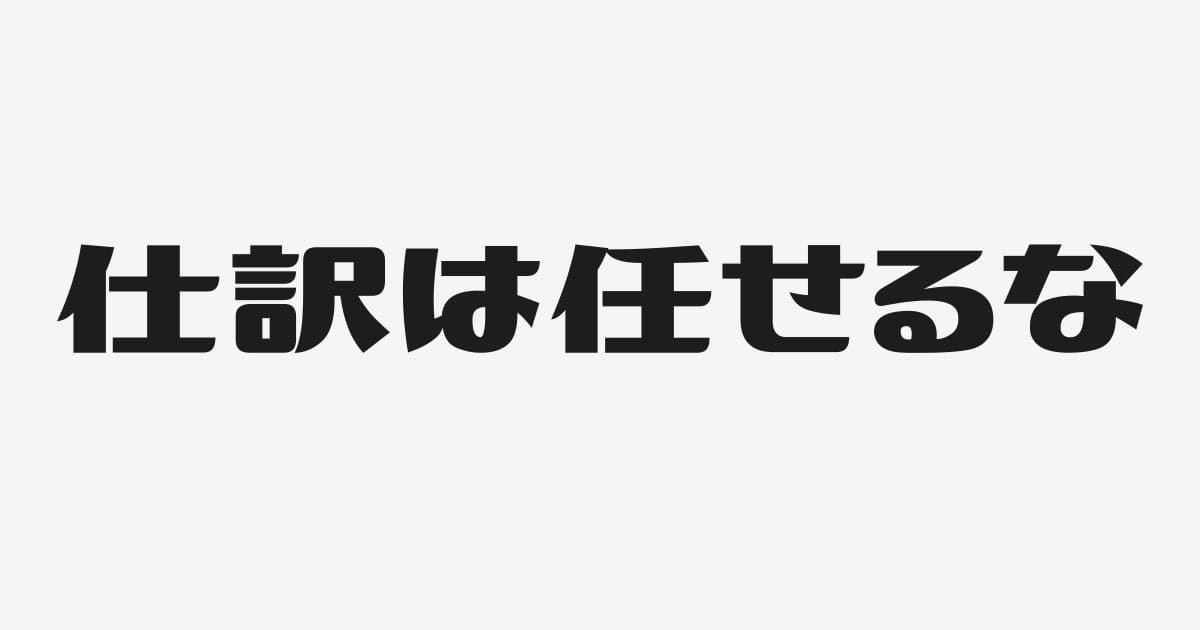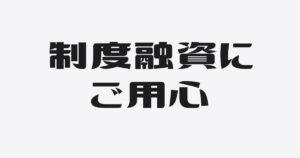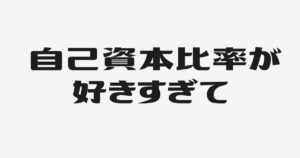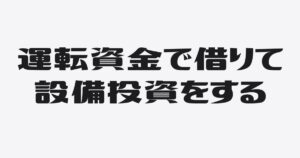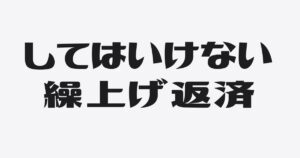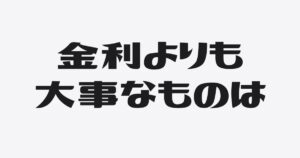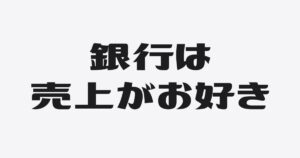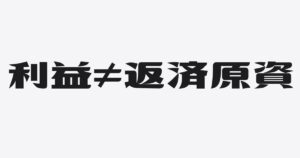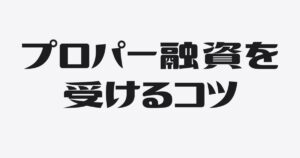仕訳を税理士やAIに任せきりにしている会社があります。結果として、社長が気づかないうちに融資を受けにくくしているケースはあるものです。この問題を深堀りしてみます。
仕訳を任せきりにしない
会社の銀行融資について、「仕訳を任せきりにしない」ことをおすすめしています。仕訳を任せきりにすることで、社長が気づかないうちに融資を受けにくくしているケースもあるからです。
なので、仕訳を任せきりにはしないようにしましょう。経理処理を税理士に丸ごとお願いしっぱなしにしているのは、仕訳を任せきりにしている典型例です。
また、最近ではクラウド会計の普及によって、自社で経理処理できるようになった会社が増えています。すると、「仕訳はAIが提案(処理)してくれるので大丈夫」とおもわれるかもしれません。ですが、やっぱりAIに任せきりというのはよくありません。
ではなぜ、仕訳を税理士やAIに任せきりにしてはいけないのか。なぜ任せきりにすると、融資を受けにくくしてしまうことがあるのか?このあと、次のように順を追ってお話ししていきます。
- 仕訳と融資の関係性とは
- 税理士でも知らない仕訳
- いまのAIには荷が重い
仕訳に対する自社の現状(考え方や取り組み方など)と照らし合わせながら、上記について確認をしていただければとおもいます。
仕訳と融資の関係性とは
銀行融資を受けにくくするから仕訳を任せきりにしない、というけれど。仕訳と融資にどのような関係があるのか?と、疑問におもわれたかもしれません。
その答えは、「決算書の元になるのが仕訳だから」です。社長であれば、融資を受けるにあたり決算書が重要であることはご存知でしょう。決算書の良し悪しが、融資審査に影響するということです。その決算書は、日々の仕訳からできあがっています。
したがって、決算書ができあがった段階で何か問題があっても「もう遅い」のです。仕訳の段階で問題を把握する必要があります。
なお、ここでいう問題とは、「仕訳が実態をあらわしていない」ということです。こうなると、銀行からは決算書を信用してもらえなくなります。なにより社長が経営判断を見誤りかねず、業績の悪化を招けばますます融資を受けにくくするでしょう。
では、仕訳が実態をあらわしていないとは、どのような状況であり、どのような仕訳をいうのか。具体例を挙げはじめるとキリがなく、とてもではありませんがこの記事にはおさまりません。それに、本記事でもっともお伝えしたいのは「仕訳を任せきりにしない」ことですから、具体例に寄り過ぎれば本筋から逸れてしまいます。
よって、ここでは「仕訳を任せきりにしていると、仕訳が実態をあらわしていないことがある。すると、融資を受けにくくすることもある」という点だけを押さえて、話を先に進めましょう。
ちなみに、仕訳が実態をあらわしていない具体例につきましては、書籍にまとめました。よろしければご参考にどうぞ。税理士必携となっていますが、社長であってもお読みいただきたい内容です。
『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』
(リンク先はAmazonの商品ページです)
税理士でも知らない仕訳
ここまで、仕訳と融資の関係性について、仕訳を任せきりにすると起きる問題についてお伝えしました。繰り返しになりますが、問題は「仕訳が実態をあらわしていない」ことです。
とはいえ、税理士は専門家なのだから、その問題を理解しているのではないかとおもわれるかもしれません。ところが、実際には理解していない税理士もいます。正直をいえば、昔のじぶんがまさにそうでした。
また、お客さまの銀行融資支援をするようになり、決算書を見せていただくと、税理士に任せきりの仕訳に問題があるというケースが、実際にも散見されます。誤解なきように申し添えると、すべての税理士が理解をしていないのではなく、理解していない税理士もなかにはいるということです。
この点、社長が税理士に任せきりにしていたのでは、問題に気づけません。ゆえに、社長もまた仕訳に関心を持ち、仕訳の理解をおすすめするところです。
しかし、仕訳が実態をあらわしていないのであれば、税金計算にも問題があるのではないか?と心配になるかもしれません。ですが、税金計算には問題が生じない(税務署からはおとがめなし)というケースがほとんどです。税理士が「税金」の専門家ゆえだといえます。
1つだけ具体例を挙げてみましょう。減価償却費を法定限度額まで計上していない場合、税金計算としては問題ありません(減価償却費の計上は任意のため)。いっぽうで、仕訳が実態をあらわしていない状態となり(実際には減価償却費は生じているため)、決算書は実態をあらわしません。
仕訳を税理士に任せきりにすることで、計上していない減価償却費がどれだけあるのかを把握していない社長もいます。すると、決算書を見て自社の業績を誤認するおそれがあり、ひいては経営判断を間違える原因にもなるわけです。
なお、減価償却費を法定限度額まで計上しない決算書を、銀行は「利益の水増し(粉飾決算)」とみなします。当然、融資の受けにくさにつながります。
このあたり、税理士が税務署の視点は理解していても、銀行の視点を理解していないことがあるため、やはり社長もまた仕訳の理解を深めておきたいところです。
いまのAIには荷が重い
仕訳を任せきりにするときに、AIに任せるという選択肢があることは前述しました。いまどきの会計ソフトは、AIが取引の内容から仕訳の提案(処理)をしてくれます。ただし、ここでもまた税理士に任せきりにするのと同じ問題が起きうるのです。
つまり、税金計算には問題が生じないとしても、銀行融資では問題が生じるかもしれないということです。
では、1つだけ具体例を挙げてみましょう。自社の在庫のなかに、正規の価格では売れないものがある。この場合、実態をあらわすためには、損失を計上する必要があります。もはや正規の価格では売れないのに、その価格のまま決算書に載せていているのでは資産の水増しです。
では、AIが「自社の在庫のなかに、正規の価格では売れないものがある」ことを把握できるのか?
いまのAIではできません。客観的データとしての取引が生じている場合(銀行口座に入金があった、クレカで決済したなど)は把握できても、在庫の価値減少のように客観的データがない状況では取引として認識できないからです。
また、客観的データがあってもなお、AIが実態をあらわす仕訳を提案できるとは限りません。同じ取引であっても、「より実態をあらわす仕訳」もあれば、「実態をあらわすには不十分な仕訳」もあるのです。この点、AIが前者を提案してくるケースはけして多くありません。
いずれの仕訳でも税金計算に問題はないものの、より実態をあらわす仕訳のほうが銀行融資にはよい影響があります。それでも、AIが実態をあらわすには不十分な仕訳を提案してくることがあるのは、いまのAIが税務署の視点はわかっていても、銀行の視点まではわかっていないということでしょう。
よって銀行融資のことまで考えると、仕訳を任せきるのは「いまのAI」には荷が重いのです。だから、社長もまた仕訳の理解を深めておきましょう、とおすすめをすることになります。
まとめ
会社の銀行融資について、「仕訳を任せきりにしない」ことをおすすめします。仕訳を任せきりにすることで、社長が気づかないうちに融資を受けにくくしているケースもあるからです。この点、本記事では、順を追って深堀りしました。
- 仕訳と融資の関係性とは
- 税理士でも知らない仕訳
- いまのAIには荷が重い
以上をふまえての結論は、「社長も仕訳に関心を持ち、仕訳の理解を深めましょう」ということです。それができれば、経営・財務の改善に役立つとともに、融資の受けやすさにもつながります。