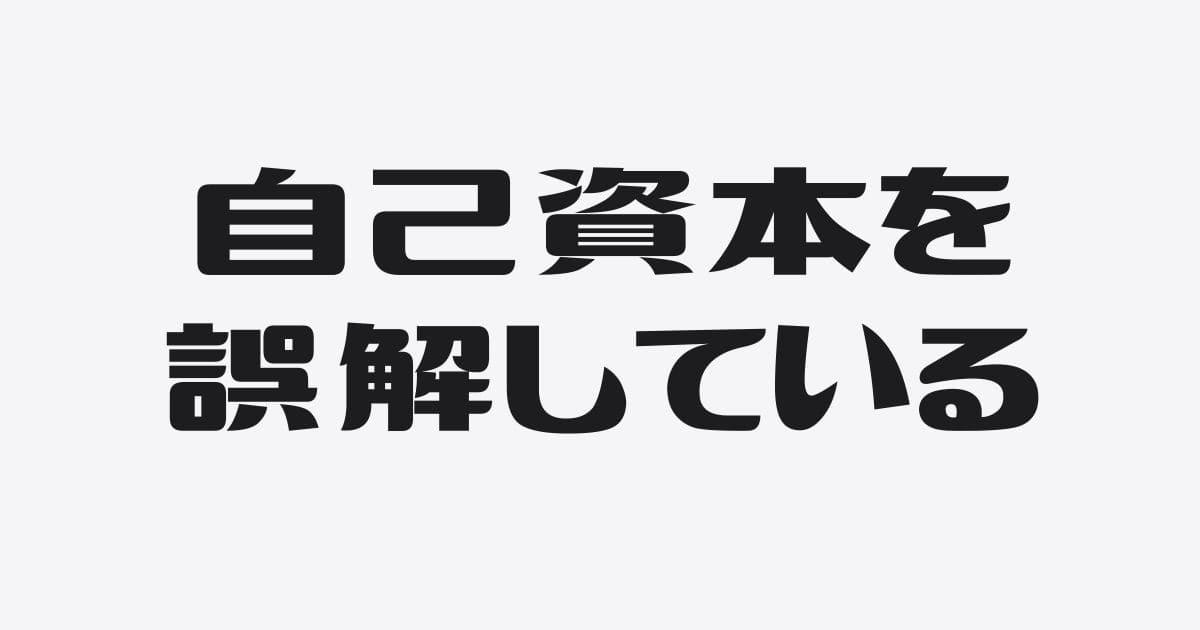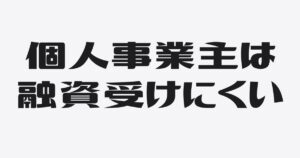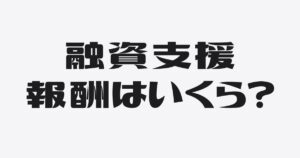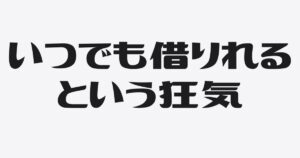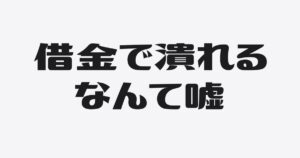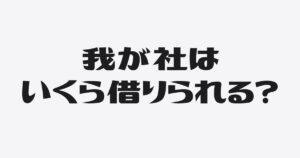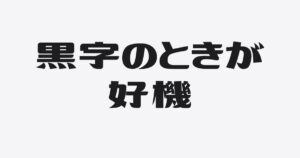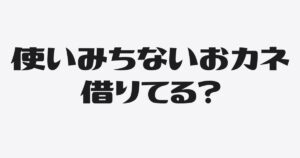自己資本(純資産)について、社長が陥りやすい3つの誤解があります。誤解にいたる理由と、正しい考え方を解説しました。決算書に対する見方を見直すきっかけにしてみましょう。
自己資本は融資でもチェックされる
「自己資本は厚いほうがいい」「自己資本比率を高めましょう」
というように、会社経営においては、自己資本(=貸借対照表の純資産)の重要性はよく語られます。たしかに、自己資本は会社の安全性や体力を示すバロメーターであり、銀行融資においても必ずチェックされる項目です。
しかし、その「自己資本」について、もしかしたら多くの社長が誤解をしているかもしれないと感じることがあります。良かれとおもって実行している自己資本を増やすための取り組みが、実はあまり効果がなかったり、場合によってはかえって会社の資金繰りを悪くしたり、銀行からの評価を落としてしまったり…といったケースも、残念ながら少なくありません。
そこで今回は、自己資本(純資産)について社長が陥りやすい「3つの誤解」を取り上げて、銀行融資の視点も交えながら、正しい見方を解説していきます。具体的には次のとおりです。
- 誤解1・借入を減らせばいい
- 誤解2・自己資本比率が大事
- 誤解3・率だけ見て額を見ず
これらを理解して、自社の決算書に対する見方を見直すきっかけにしてみましょう。
自己資本(純資産)のよくある誤解
具体的にどのような点で誤解が生じやすいのか。ここでは、多くの社長が勘違いしがちな自己資本(純資産)に関する3つのポイントを取り上げて、その理由と正しい考え方について、順番に解説していきます。
誤解1:借入を減らせばいい
まず、非常によく聞かれる誤解のひとつです。
社長が考えがちなこと:
「会社の借金(負債)を減らせば、計算上、自己資本(純資産=資産-負債)が増えるはずだ。手元のおカネに少し余裕があるし、繰り上げ返済して自己資本を増やそう!」
ややもすると、正しそうに聞こえます。負債が減れば、その分、純資産が増えそうな気がします。
なぜこれが誤解なのか:
ここで、貸借対照表の基本的な仕組みを思い出してみましょう。会社の資産は、どうやって調達したか(負債と純資産)を示しています。つまり、「資産の合計=負債の合計+純資産の合計」という関係が常に成り立っています。
この点、借入金(負債)を1,000万円繰り上げ返済するためには、会社の預金(資産)を1,000万円取り崩す必要があります。つまり、負債が1,000万円減ると同時に、資産も1,000万円減るわけです。
その結果、「純資産=資産-負債」の式に当てはめてみるとどうなるでしょう?資産も負債も同額減るのですから、その差額である純資産(自己資本)の額そのものは、繰り上げ返済をしても1円も増えません。
「でも、自己資本比率は上がるじゃないか?」と言われれば、たしかにそのとおりです。総資産が減ることで、自己資本比率(=純資産÷総資産)の分母が小さくなるため、比率自体はやや上昇します。
ですが、そのわずかな比率向上と引き換えに、会社の虎の子たる預金を大きく減らしてしまうリスクを、どう考えるべきでしょうか? 銀行は、自己資本比率ももちろん見ていますが、それ以上に会社がどれだけの手元資金(預金残高)を持っているかを重視します。
なぜなら、比率がいかに高くても、おカネがなければ支払いができず、会社はつぶれてしまうからです。繰り上げ返済によって肝心要の資金繰りが厳しくなってしまっては、本末転倒もはなはだしいと言わざるをえません。
結論:
借金を減らす行為そのものが、自己資本(純資産)の額を直接的に増やすわけではない、という事実をまずはっきりと理解しておきましょう。
誤解2:自己資本比率が大事
次は、自己資本比率に対する過度な期待や誤解です。
社長が考えがちなこと:
「銀行は自己資本比率を重視しているらしい。この比率をとにかく目標値(例えば20%とか30%とか)まで高めることが、財務改善の重要課題だ!」
自己資本比率が会社の安全性を示す重要な指標の1つであることは、間違いありません。比率が高いほど、外部からの借入への依存度が低く、財務的に安定していると一般的には評価されます。
なぜこれが誤解なのか:
しかし、「何よりも大事か?」と問われれば、答えは明らかにノーです。会社の存続にとって、自己資本比率以上に、もっと直接的で死活問題となるのは、繰り返しになりますが預金残高、つまり手元のおカネです。
極端な例で考えてみましょう。自己資本比率が100%、つまりまったく借金のない無借金経営の会社があったとします。しかし、もしその会社の手元におカネがまったく無ければ、仕入代金も払えず、社員の給料も払えず、会社は明日にも事業を停止せざるをえません。
いっぽうで、自己資本比率が低くても、しばらくは支払いに困らないだけの預金(たとえば、平均月商の3か月分など)があれば、会社は事業を継続して、立て直しのチャンスを待つことができます。
当然、銀行も預金の重要性を熟知しています。だからこそ、融資審査においては、自己資本比率という「中長期的な安全性」の指標と同時に、預金残高という「短期的な安全性(いわゆる手元流動性)」の指標を厳しくチェックしているのです。
とくに、預金残高が平均月商の1か月分を下回るような状態は、資金繰りが極めて不安定であると見なされて、銀行からの評価は著しく下がります。
結論:
自己資本比率の向上は目指すべき目標の1つではありますが、それが経営の目的になってはいけません。比率の改善だけを追い求めるあまり、会社の生命線である預金を犠牲にするような経営判断(行き過ぎた繰り上げ返済や、利益に繋がらない資産への投資など)は、絶対に避けるべきです。
誤解3:率だけ見て額を見ず
さいごに、自己資本を「率」だけで評価してしまうことの落とし穴です。
社長が考えがちなこと:
「同業他社のA社は自己資本比率が30%もあって、すごく健全そうだ。それに比べてウチの会社はまだ10%しかない…やっぱりまだまだ安全性が低いんだな…」
というように、自己資本を「比率」という一面だけで比較して、自社の評価としてしまう。
なぜこれが誤解なのか:
自己資本(純資産)は、「率(割合)」だけでなく、「額」で見ることも重要です。なぜなら、純資産の「額」は、その会社が創業してから現在に至るまで、どれだけの利益を内部に蓄積してきたか、その会社の「歴史」そのものであり、「体力」を示すものだからです。
具体例で比較してみましょう。
- A社:総資産 3,000万円、純資産 1,000万円 → 自己資本比率 30% (高い!)
- B社:総資産 10億円、純資産 1億円 → 自己資本比率 10% (低い?)
比率だけを見れば、A社のほうが財務内容が良いように見えます。しかし、会社の「体力」という観点で見たらどうでしょうか?
たとえば、何か予期せぬ大きなトラブルが発生し、両社ともに5,000万円の特別損失を計上しなければならなくなったとします。A社は純資産1,000万円しかないので、一瞬で4,000万円の債務超過です。
いっぽう、B社は純資産が1億円ありますから、5,000万円の損失が出てもまだ5,000万円の純資産が残ります。将来に向けて新たに投資を行う「余力」という点でも、B社のほうが大きいことがわかるでしょう。
銀行もまた、単に自己資本比率が高いだけでなく、純資産の「絶対額」が大きい会社を高く評価します。それは、いざというときのショックに対する耐久力があり、事業を持続・成長させていくだけの体力がある強い会社だと判断するからです。
結論:
自己資本比率という「率(割合)」だけに一喜一憂するのではなく、自社の純資産の「額」がいくらあるのか、それが自社の事業規模やリスクに対して十分な額なのか、という視点を持つことが大切です。
まとめ
自己資本(純資産)について、社長が陥りやすい3つの誤解を解説しました。
- 借金を返しても、純資産の「額」は直接増えない。預金も減るから
- 自己資本比率も大事だが、それ以上に預金も大事
- 自己資本は率だけでなく、額で見る視点も重要
では、どうすれば自己資本(純資産)を増やして、会社の財務基盤を強くすることができるのか? その答えは、とてもシンプルです。
それは「毎期、きちんと利益を出して、利益剰余金として着実に会社のなかに蓄積していくこと」です。
目先の税金を過度に恐れて利益を無理に圧縮したり、見かけの自己資本比率だけを上げようと繰り上げ返済したりするのではなく、本業でしっかりと利益を生み出し、納税後の利益として着実に蓄積していくことが大切になります。 それこそが、会社の体力をつけることにつながり、銀行からの揺るぎない信頼となり、経営環境の変化にも耐える強い会社をつくるための王道です。