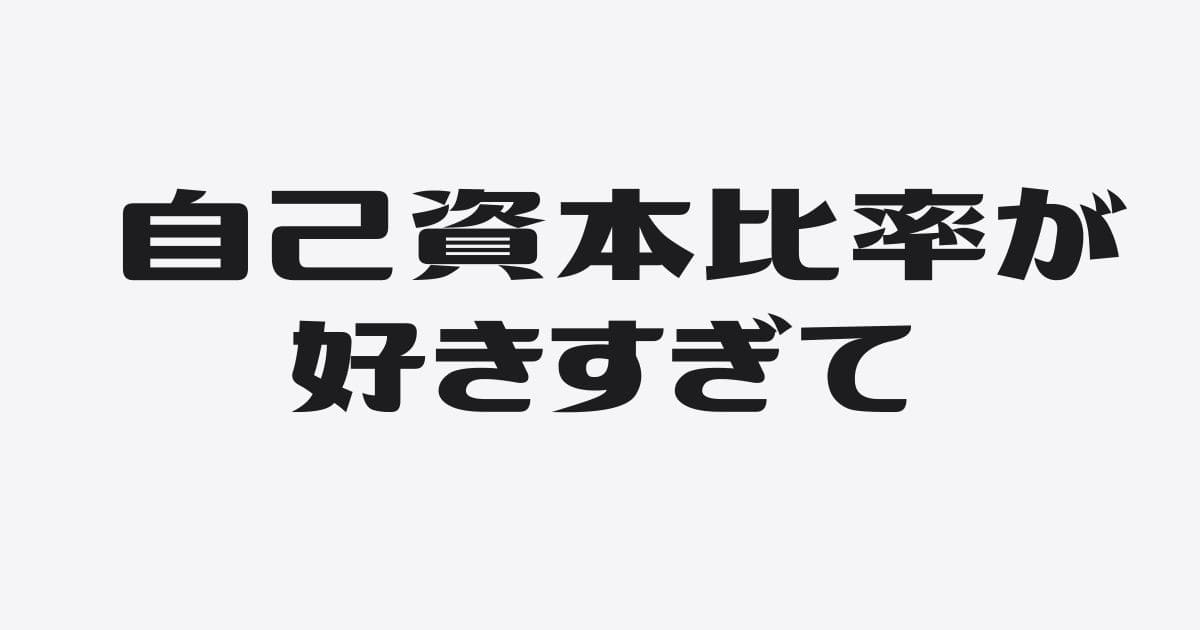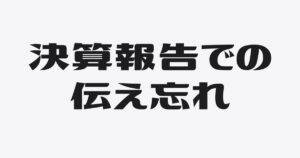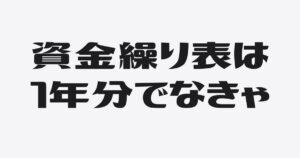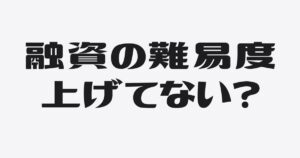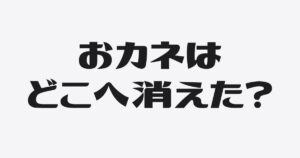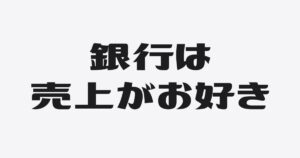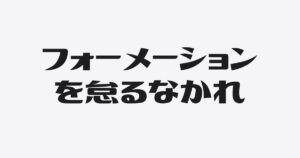自己資本比率は高いほどよい、と言われることがあります。ですが、必ずしもそうとは言えず、中小企業が資金繰りを考えるのであれば、自己資本比率よりも重視すべき指標もあるのです。
自己資本比率は高いほど
自己資本比率は高いほどよい、と言われることがあります。これに対して、今回のお話の結論は「必ずしもそうとはいえない」ということです。つまり、状況によっては自己資本比率は高いほうがよいとは言えません。
そもそも自己資本比率とは、いわゆる財務指標の1つであり、なかでも重要な指標として位置づけられています。しかし、中小企業が資金繰り(≒財務)を考えるのであれば、自己資本比率よりも重視すべき指標もあるのです。
このあたり順を追って、次のような内容でお伝えしていきます。
- 預金月商倍率を重視する
- 預金は事実、利益は不明
- 自己資本比率の改善は微
これを見ればおわかりのとおり、預金月商倍率という指標が重要です。ところが、自己資本比率の高さにこだわりすぎると、資金繰りに問題が生じる可能性が高まります。
と聞いても、「何を言っているのか、よくわからない」のであれば、このあとのお話を確認しておきましょう。放っておくと、ムダに資金繰りを悪くしてしまいかねません。
預金月商倍率を重視する
冒頭、「状況によっては自己資本比率は高いほうがよいとは言えない」と言いました。そして、「自己資本比率よりも重視すべき指標もある」と言いました。その指標が、預金月商倍率です。
預金月商倍率とは、算式であらわすと「預金÷(年間売上高÷12か月)」であり、預金が月商の何倍あるかをはかる指標です。算式を見ればわかるとおり、預金が多いほど預金月商倍率は大きくなり、預金が少ないほど預金月商倍率は小さくなります。
では、会社が自己資本比率を高くしようと、繰上返済をしたらどうなるか?
借入が減るので自己資本比率は高くなりますが、預金も減るので預金月商倍率は小さくなります。このとき、預金月商倍率が小さすぎるようだと問題です。言うまでもなく、資金繰りが悪くなるからです。そして、銀行からも危険だとみなされる可能性があります。
その目安は、預金月商倍率が1倍未満です。預金がかなり少ない状況であり、実際にちょっと何かが起きれば資金ショートすることはあるでしょう。ゆえに銀行は、「預金月商倍率は1倍以上が必須であり、できれば2倍以上」という見方をしているものです。
そのうえで、「預金月商倍率が大きいほど資金繰りが安定している」と見られるため、融資を受けやすくする効果があります。自己資本比率にこだわるあまり、預金月商倍率を小さくして、融資を受けにくくしないようにしましょう。
預金は事実、利益は不明
銀行が預金月商倍率に注目するのは、資金繰りの観点だけではありません。粉飾決算に対する備えでもあります。最近では、多額の粉飾決算をしている企業の倒産が増えていることから、銀行も粉飾決算への警戒を強めている点は覚えておいたほうがよいでしょう。
この点、「預金は事実」ですが、「利益は不明」だといえます。つまり、預金は「おカネ(預金残高)」という裏付けがあるためにウソはつけませんが、利益は経理処理しだいというところがあるためウソをつけてしまうということです。そのウソこそが、粉飾決算にあたります。
だとすれば、銀行が預金の多さを評価するのもわかるはずです。利益は多くても粉飾決算かもしれませんが、預金が多いのは事実であり信用できる。預金が多いほど、何かあってもしのげる可能性が高まりますから、預金が多い会社ほど銀行の評価は高くなるわけです。
そして、預金が多いかどうかをはかるための指標が、預金月商倍率です。
なお、利益と預金の動きは一致しません。たとえば、商品を納品して売上を計上すれば利益は増えますが、売上代金が入金されるまで預金は増えないのです。よって、利益は出ているけれど預金は少ないということはあります。
いっぽうで、粉飾決算により利益を増やすことはできるため、利益が多くても預金が少なければ、粉飾決算を疑われやすくもなるでしょう。すると融資も受けにくくなるため、預金が少ないことはやはり問題です。
自己資本比率の改善は微
とはいえ、繰り上げ返済をしたがる社長は少なくありません。金利も上昇傾向にありますから、無理もないでしょう。ですが、自己資本比率をよくすることが目的ならば、繰り上げ返済の判断は慎重にすべきです。具体的には、実際に自己資本比率を計算してみることをおすすめします。
たとえば、総資産1億円、純資産2,000万円の会社を例に考えてみましょう。自己資本比率は、20%です(2,000万円÷1億円)。ここで、1,000万円を繰り上げ返済するとどうなるか?
預金・借入ともに1,000万円減るので、総資産は9,000万円になります。すると、自己資本比率は22.2%になるので(2,000万円÷9,000万円)、繰り上げ返済前よりも2.2%ほど高くなりました。これをどう見るかです。
たしかに自己資本比率は高くなったものの、代わりに1,000万円の預金を減らしています。総資産1億円の会社にとって、1,000万円の預金はけして小さなものではないはずです。預金月商倍率も下がりますし、その分だけ資金繰りは悪くなり、銀行からの評価も下がります。
銀行は自己資本比率も見てはいますが、このケースでは2.2%の改善よりも、預金の減少のほうが気になるものでしょう。預金月商倍率が小さくなるほうが気になる、ということです。これは、「預金が尽きれば、会社はおしまい」という真理に起因しています。
極端をいえば、自己資本比率が多少低くても会社はつぶれませんが、いくら自己資本比率が高くとも、預金が尽きれば会社はおしまいなのです。1,000万円の預金に比べれば、自己資本比率2.2%の改善はわずかにすぎない。そういう見方もできるようにしましょう。
まとめ
自己資本比率は高いほどよい、と言われることがあります。ですが、必ずしもそうとは言えず、中小企業が資金繰り(≒財務)を考えるのであれば、自己資本比率よりも重視すべき指標もあります。それが預金月商倍率です。
銀行もまた、預金月商倍率に注目していることを理解して、自己資本比率の高さにこだわりすぎないように気をつけましょう。自己資本比率は高いに越したことはありませんが、引き換えに預金月商倍率が低すぎるようでは困ります。