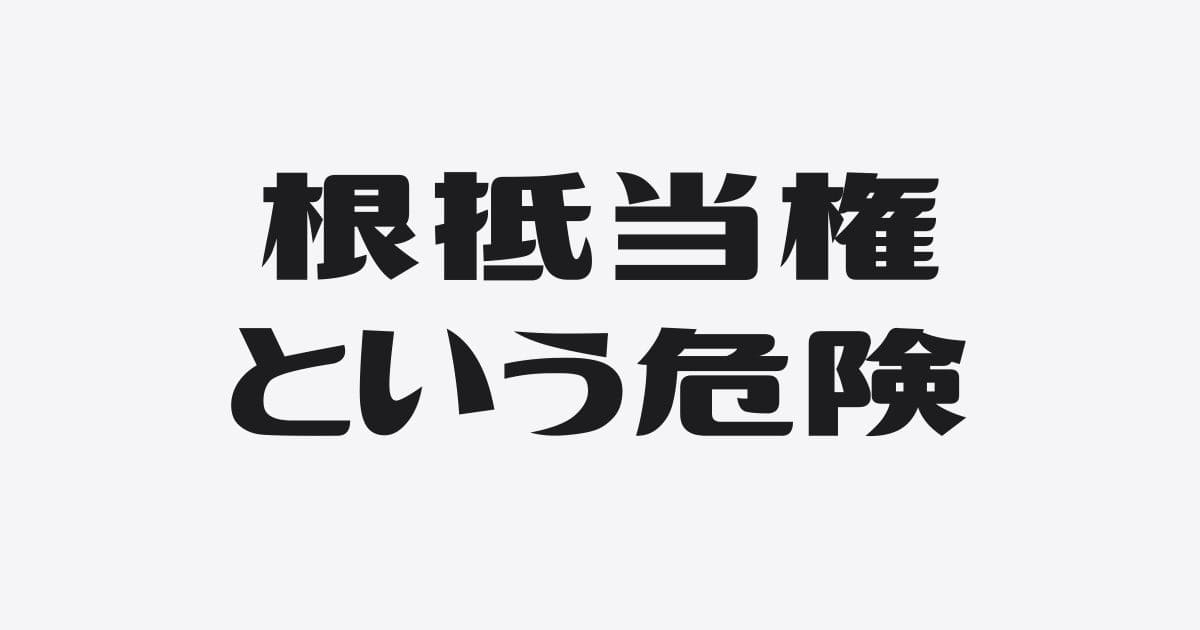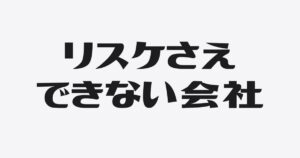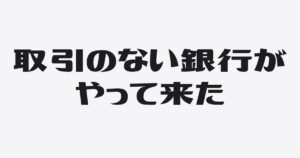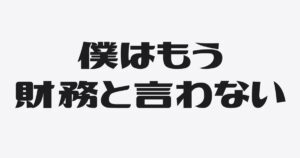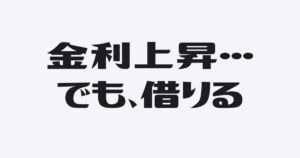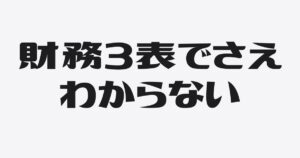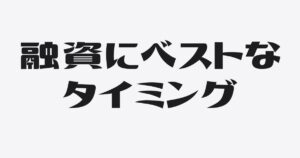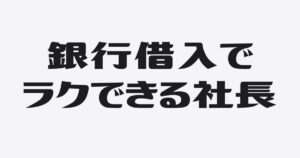不動産を担保に融資を受ける際、契約書にある「根抵当権」という言葉を見過ごしていませんか?銀行に有利なこの仕組みは、知らぬ間に会社の資金調達の自由を奪います。
担保契約の種類を理解していますか?
会社で融資を受ける際、会社の土地・建物や、社長個人の自宅などを担保に入れることはよくあります。そのとき、多くの社長は「いくら借りられるか」「金利は何パーセントか」に集中しがちです。
しかし、それと同じくらい重要なことに「担保設定の種類」があります。もう少し具体的に言うと、「根抵当権(ねていとうけん)」です。
「今後の取引にも便利ですから」といった銀行の説明を受けて、よく理解しないまま契約書に判を押してしまってはいないでしょうか。しかし、この根抵当権は、銀行にとっては非常に有利ないっぽうで、会社にとっては大きなデメリットやリスクをともないます。
いちど設定すると、会社の財務戦略を長期にわたって縛り付け、身動きが取れなくしてしまうことさえあるのです。
本記事では、この「根抵当権」について、その仕組みをはじめ、銀行が好む理由、社長にとってのデメリット、そして具体的な回避策までを解説していきます。
この記事のポイントは以下のとおりです。
- 「根抵当権」と「(普通)抵当権」の違い
- 銀行が「根抵当権」を使いたがる理由
- 社長が見過ごしがちな根抵当権のデメリット
- 根抵当権を回避・交渉するための具体策
「根抵当権」と「(普通)抵当権」の違い
根抵当権のリスクを理解するために、まずは、「(普通)抵当権」との違いをはっきりとさせておきましょう。この2つは、似ているようでまったくの別モノです。
(普通)抵当権:1つの借入と1対1で紐づく
一般には、単に「抵当権」と呼ばれますが、根抵当権との区別をわかりやすくするため、ここでは「普通抵当権」と呼ぶことにします。
「この設備投資のために3,000万円借りる。その借入に対して、この土地を担保に入れる」というように、特定の1つの借入と担保が1対1で紐づいているのが普通抵当権の特徴です。
重要なのは、その借入を完済すれば、この抵当権は解除(抹消)できることです。関係がシンプルで、社長にとっても分かりやすいのが普通抵当権だと言えます。
根抵当権:「担保の枠」で将来の借入までカバーする
いっぽう、根抵当権は、特定の借入に紐づくものではありません。「この不動産を担保に、極度額(きょくどがく)5,000万円までの借入を保証します」といったように、担保の「枠」を設定するイメージです。
この枠の範囲内であれば、今回の融資だけでなく、将来発生する不特定の借入も含めすべてカバーします。したがって、当初の借入を完済しても、その銀行からの他の借入が1円でも残っていれば、根抵当権は解除できません。借金がゼロにならない限り、不動産に設定されたまま残り続けるということです。
銀行は「根抵当権」を使いたがる理由
ではなぜ、銀行は社長にとって不利になる可能性のある根抵当権を好んで使うのでしょうか。それは、銀行にとって「ラク」であり、「有利」な仕組みだからです。
理由1:手間とコストを省ける
根抵当権の枠さえ設定しておけば、将来、その枠内で追加融資をする際に、あらためて担保設定の手続きをする手間が省けます。
登記にかかる登録免許税や司法書士費用、社長の印鑑証明取得といった手続きやコストが不要になるため、それらをメリットとして銀行は根抵当権を勧めるのがセオリーです。
理由2:担保を維持し続けられる
これが銀行にとって最大のメリットです。融資先の業績が向上して、本来なら無担保でも借りられるような状態になったとします。しかし、根抵当権が設定されていれば、銀行は「まだ他の借入が残っていますから」という理由で、担保を解除せずに維持し続けることができます。
いちど捕まえた優良な担保を、みすみす手放す必要がありません。
社長が見過ごしがちな根抵当権のデメリット
銀行にとってメリットが大きいということは、裏を返せば、社長にとってはデメリットが大きいということです。具体的なデメリットを見ていきましょう。
4つのデメリット
- 将来の自由度が低下する
前述のとおり、会社の信用力が上がっても担保が外れないため、いつまでも有担保での借入を続けざるを得なくなる可能性があります。 - 不動産の有効活用が阻害される
ある銀行に根抵当権を設定されると、その不動産を他の銀行への担保として提供することが極めて難しくなります。結果として、担保価値を十分に活かせず、受けられるはずの融資が受けられなくなったり、融資条件をムダに悪くすることになりかねません。 - 銀行評価の変化に気づけない
通常であれば、「これまで無担保だったのに、銀行が担保を要求してきた」という事実は、自社の銀行評価が低下している危険なサインです。しかし、根抵当権が設定済みだと、銀行はいつでもその枠内で融資ができるため、社長が自社の評価低下に気づくきっかけが失われてしまいます。 - 保証付き融資まで有担保化される
本来、信用保証協会の保証が付いていれば不動産担保まで必要ないはずの融資でも、「すでに根抵当権が設定されているから」という理由で、結果的に有担保での借入になってしまうケースがあります。
根抵当権を回避・交渉するための具体策
では、このやっかいな根抵当権に対して、社長はどう対策すればよいのでしょうか? 契約前と契約後、それぞれの場面で打てる手があります。
対策1(契約前):複数行に普通抵当権を交渉する
最善の策は、入口、つまり融資契約の時点で根抵当権を避けることです。不動産購入や大口の設備投資など、大きな融資を検討する際は、必ず複数の銀行に同時に相談しましょう。
そして、すべての銀行に対して「普通抵当権での設定でお願いします」と、はっきりと交渉します。1行でも普通抵当権に応じてくれる銀行があれば、それを交渉材料に、他の銀行とも有利に話を進めることができます。
対策2(契約後):極度額の引き下げを交渉する
すでに根抵当権が設定されてしまっている場合でも、諦める必要はありません。まずは、現在の借入残高に見合った金額まで、極度額を引き下げてもらうよう交渉しましょう。
例えば、極度額5,000万円で設定されているが、実際の借入残高は1,000万円しかない、という場合です。極度額を1,500万円などに引き下げられれば、その不動産の担保余力が生まれ、他の銀行と取引する際の選択肢が広がります。
対策3(契約後):他行借入で抹消を交渉する
これは少し難易度高めの戦略ですが、根抵当権を設定している銀行(A銀行)との取引を解消したい場合、他の銀行(B銀行)から融資を受けて預金残高を厚くするという方法があります。
そして、その潤沢な預金を背景に、A銀行に対して「御行からの借入は、この預金でいつでも全額返済できます。つきましては、根抵当権を解除してください」と、強い姿勢で交渉するのです。この「全額返済できる」という交渉カードを持つことで、銀行も解除に応じざるを得なくなる場合があります(全額返済されるのは困るので)。
まとめ
銀行が好む「根抵当権」は、銀行にとっては手間やコストを省け、取引先を囲い込める有利な仕組みですが、社長にとっては資金調達の自由度を奪われやすい、リスクのある契約です。
不動産購入や大口の融資を受ける際には、安易に1行とだけ話を進めず、必ず複数行に相談して、「普通抵当権での設定」を第一候補として交渉しましょう。
すでに根抵当権が設定されている場合でも、極度額の引き下げ交渉や、預金を厚くして解除を迫るなど、交渉の余地は残されています。
銀行の言うがままに契約するのではなく、自社の未来の選択肢を守るために、担保契約の内容を正しく理解して、交渉する。その意識を持つことが、社長には求められています。