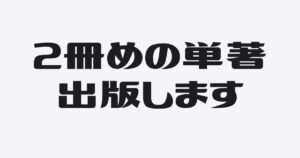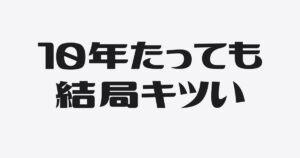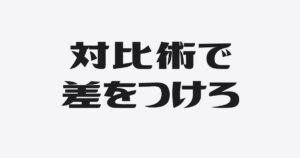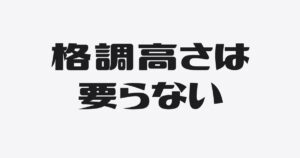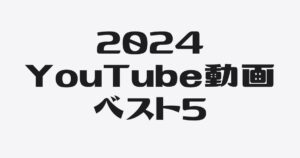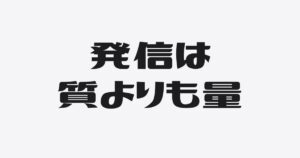4冊めのKindle本を出版しました。これに関連して、僕がその本に込めた3つのこだわりについてお話をしてみます。
4冊めのKindle本を出版しました
このたび、僕にとって4冊めとなる新しい本をKindle出版にて出しました。タイトルは『銀行に好かれる社長の習慣 ~定性評価で差がつく35の行動原則』です。
税理士として銀行融資の支援をするなかで、日々感じていること、社長にお伝えしたいことを、今回も心を込めて書き上げました。
そして、今回もまた、企画から構成、執筆、デザイン、Kindleのフォーマット調整、そして告知などのプロモーションまで、基本的な部分は「ぜんぶじぶんでやる」というスタイルを貫きました。
Kindle出版であっても、編集や表紙デザインなどを外注して、プロの手を借りるという選択肢はもちろんあります。それでも僕が、あえて時間も手間もかかる「じぶんでやる」ことにこだわるのには、それなりの理由があるのです。
なぜ、そこまでしてじぶんでやるのか?なぜ、日々のブログ発信だけでなく、あらためて「本」という形で伝えたいのか?そして、なぜ今回の4冊めでは「社長(個人)の習慣」という、一見すると「会社の銀行融資」とは離れたテーマを選んだのか?
この記事では、そんな僕の、新しい本に込めた「3つのこだわり」について、その背景にある想いとともにお話しさせていただければとおもいます。具体的には次のとおりです。
- ぜんぶじぶんでやる
- 5万字の長文に挑む
- 類書にはない視点で
僕が4冊めの本に込めた3つのこだわり
それでは、僕が今回の4冊めの本作りにおいて、とくに大切にした「3つのこだわり」について、順番にお話ししていきます。1つめは、本の内容に入る前の、そもそもの「つくりかた」に関するこだわりからです。
【こだわり1】ぜんぶじぶんでやる
Kindle出版では執筆以外の工程、たとえば編集や校正、表紙デザイン、販売ページの作成、Kindle用のデータフォーマット調整などを、外注して専門家に任せるという選択肢もあります。 そのほうがクオリティが高くなる部分もあるでしょうし、僕自身の負担も軽くなります。
しかし、僕は今回も「ぜんぶじぶんでやる」ことを選びました。その理由は、大きく2つあります。
理由①: 時間とおカネ
まず、現実的な問題として、外注に出すとコミュニケーションにどうしても時間がかかってしまう、という側面があります。 外注すれば、たしかにその作業自体の手間は省けるかもしれません。でもその代わりに、こちらの意図を正確に伝えたり、できあがってきたものを確認したり、修正をお願いしたり…というやり取りが発生します。
「ああでもない、こうでもない」と何度もやり取りを繰り返しているうちに、結局、じぶんでやったほうが早かった、なんてことも起こりえます。僕にとっては、思い立ったことをスピーディーに形にする、というスピード感はとても重要です。鉄は熱いうちに打て。
もちろん、外注には相応のコストもかかります。そのコストを抑えて、少しでも多くの読者の方に手に取りやすい価格で提供したい、という想いもあります。じぶんでやれば、かかるのは僕の時間だけですから(それが一番貴重ではあるわけですが…)。
理由② :じぶんでできる重要性
もうひとつの、そして僕にとってはより本質的な理由は、「そもそも、まずはじぶんで一通りやってみないと、外注するにしても勝手がわからない」ということです。
編集やデザイン、電子書籍のフォーマット調整など、それぞれの工程にどんな作業があって、どれくらいの手間がかかるのか。どこをどうすれば読者にとって読みやすくなるのか、品質の良し悪しを分けるポイントはどこなのか。
それらをまずはじぶん自身で経験して、理解していなければ、いざ外注しようとおもっても、的確な依頼先を選んだり、適切な指示を出したり、納品されたものの良し悪しを判断したりすることができません。
将来的に、本のクオリティをさらに上げるために、いちぶの工程をプロに外注する可能性はゼロではありません。ですが、その場合でも、まずはじぶんでやってみて、その作業の本質や勘所を理解しておくことが、結果的に良いものを生み出すために不可欠だと考えています。
今回の「じぶんでやってみた」具体例
とはいえ、すべてをゼロから独力で、というのは非効率ですし、限界もあります。そこで、今回もいろいろと工夫してみました。
たとえば、表紙デザイン。僕はデザインの専門家ではありません。そこで今回は、僕自身が「良いな」と感じたいくつかの既存の書籍(Amazonで見つけました)のデザインを参考にしています。その構成や色使い、フォントの選び方などを分析して、それを真似て、アプリはKeynoteを使って、じぶんでつくってみました。
世の中には優れたデザインの「お手本」がたくさんありますから、それを参考にさせてもらう。まずは自分で手を動かしてみる、というスタンスです(もちろん、著作権などには配慮が必要です)。
また、商業出版と違って、マンツーマンで伴走してくれる編集者さんはいません。そこで、編集・校正作業では、生成AIをだいぶ活用しました。書き上げた原稿を入力して、「わかりづらい表現はないか?」「誤字脱字や、文章中の言葉遣いの揺れ(表記ゆれ)がないかチェックして」といった具合にお願いすると、驚くほどの精度で指摘や修正案を提示してくれます。
もちろん、さいごは必ず僕自身の目で読み返し、最終的な判断をしますが、AIが編集者や校正者の役割のいちぶをじゅうぶんに代替してくれる時代になったことを、今回の執筆で改めて実感しました。便利な世の中になったものです。
【こだわり2】5万字の長文に挑む
僕は、このブログでも毎日、発信をし続けています(10年めになりました)。「それだけ発信しているなら、わざわざ本にしなくてもいいのでは?」とおもわれるかもしれません。
それでも僕が、あらためて「本」という形で、しかも今回は「約5万字」という、けして短くはないボリュームで伝えようとしたのには、明確な理由があります。
それは、ブログのような短い文章では、どうしても情報が断片的になりがちで、伝えられることに限界がある、と感じているからです。銀行融資や資金繰りといったテーマは、本来、とても奥が深く、いろいろな要素が絡み合っています。
それらについて、個別のテクニックや知識を知ることも大切ですが、それだけでは根本的な解決にはいたらないことが多いのです。背景にある考えかたや、物事のつながり、全体像を理解してこそ、本当の意味で会社は変わり、強くなれるのだと僕は考えています。
この点、5万字という文字数は、その体系的な理解のために、僕が必要だと考えた最低限のボリュームです。単に情報を羅列するのではなく、1つのテーマを多角的に掘り下げて、読者に深い納得感と実践へのヒントを提供したい。読み応えがあり、読んだあとで「たしかに、これだけの時間をかけて読む価値があった」と感じていただけるような本を目指しました。
それは同時に、僕自身がこのテーマに対して、中途半端なものは世に出さない、という「覚悟」を持って臨んだ証でもあります。
日々のブログ更新が、どちらかというと瞬発力や鮮度が求められる発信だとすれば、書籍の執筆は、じっくりと腰を据えて取り組む持久力が試される発信です。情報を集めて、整理して、論理を組み立て、そして、読者に誤解なく伝わるように一文一文、言葉を選び、推敲を重ねる。
ブログとはまた違った大変さがありますが、そのぶん、内容の密度と深さ、そして体系性は、ブログ記事とは比較にならないレベルになっているはずです。
ぜひ、まとまった時間を取っていただき、じっくりと読み込んでいただきたい。そして、読み終わったあと、何か1つでも読者の会社経営や銀行との付き合いかたに役立つ気づきがあれば、著者としてこれほどうれしいことはない。そんな想いで、この5万字を書き上げました。
【こだわり3】類書にはない視点で
僕が本を出すうえで、大切にしていることがあります。それは、「他にはない、独自の価値を読者に届けたい」ということです。世の中にはたくさんのビジネス書や実務書があります。そのなかで、わざわざ僕の本を手に取って、貴重な時間とおカネを使って読んでいただくのですから、どこかで聞いたような話の焼き直しや、ありきたりの一般論では意味がない、と考えています。
これまで商業出版で出させていただいた本も、常にその点を意識してきました。
1冊めの『税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック』では、それまで断片的に語られることが多かった銀行融資支援のノウハウや考え方を、「ゼロから学べる全部入り」として、網羅的かつ体系的にまとめることにこだわりました。
2冊めの『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』では、「銀行融資」と「日々の仕訳(経理処理)」という、これまでほとんど結びつけて語られてこなかった、極めてニッチな組み合わせに焦点を当てました。
そして、今回のKindle出版『銀行に好かれる社長の習慣 ~定性評価で差がつく35の行動原則』でも、同様に「他にはない切り口」を検討しました。
その結果たどり着いたのが、「社長の習慣」と「銀行融資(とくに、数字だけでは測れない定性評価)」をかけ合わせる、という視点です。
なぜこのテーマを選んだのか?
それは、僕が日々の税理士業務を通じて、多くの社長や銀行員の方々と接する中で、ある事実に気づいたからです。それは、銀行から継続的に信頼され、良好な関係を築き、結果として資金繰りが安定している社長には、単に業績が良いというだけでなく、共通した「思考や行動の習慣」がある、ということです。
もちろん、決算書の数字(定量評価)が良いことは大前提として重要です。しかし、銀行はそれだけでなく、社長の人柄、経営に対する姿勢、社員や取引先との向き合い方、情報開示のあり方といった、「数字には表れない部分(定性評価)」も、実はかなり注意深く見ています。
そして、金融庁の方針もあり、これからの銀行融資においては、ますますその「定性評価」の重要性が増していく、と僕は考えています。
決算書を良くするための努力は不可欠ですが、それだけでは十分ではない時代が来ています。むしろ、社長自身の日々の「習慣」こそが、銀行からの信頼を勝ち取り、会社の持続的な成長を支える、より本質的で、再現性の高い要素になるのではないか。その強い確信から、今回は一見異色ともおもえるテーマを選びました。
本書で紹介する35の行動原則は、けして特別なことではありません。しかし、これらを意識して、実践することで、銀行の見方は確実に変わってくるはずです。類書にはない、具体的で実践的なヒントが詰まっていると自負しています。
まとめ
今回、Kindle出版としては4冊め『銀行に好かれる社長の習慣 ~定性評価で差がつく35の行動原則』には、僕なりの3つのこだわりを込めました。
- ぜんぶじぶんでやる
- 5万字の長文に挑む
- 類書にはない視点で
この本が、銀行融資や資金繰りに悩む社長、銀行ともっと良い関係を築きたいと考える社長、そして会社をさらに良くしていきたいと願うすべての社長にとって、日々の行動を見直し、会社経営をより良い方向へ導くための一助となることを、心から願っています。
ご興味を持っていただけましたら、ぜひいちど、手に取っていただけると嬉しいです。Kindle Unlimited会員の方は追加料金なしでお読みいただけます。