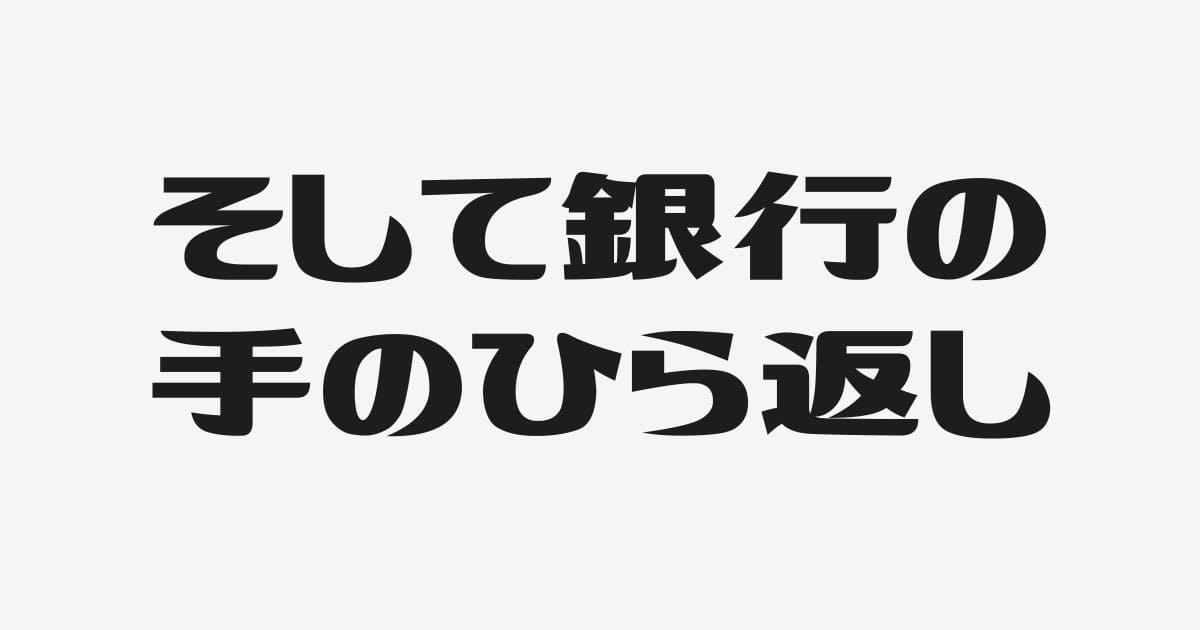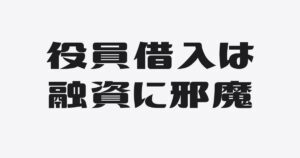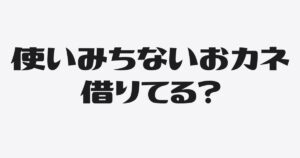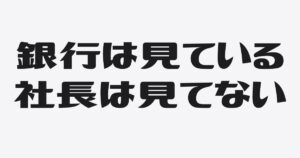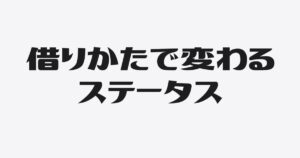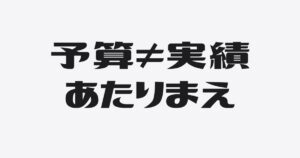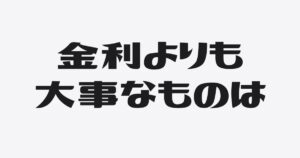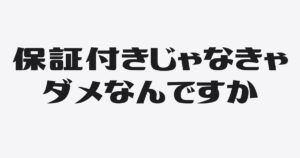会社の業績が良いときには何も言わなかった銀行が、赤字になった途端、決算書の細かい点を指摘し始める…。そんな経験はありませんか?この記事では、業績悪化時に銀行の見る目が厳しくなる3つのポイントを解説します。
銀行はなぜ手のひら返しをするのか?
会社の業績が赤字や債務超過に陥ってしまった…。社長にとっては、ただでさえ苦しい状況です。そんなとき、支援を求めて銀行に相談に行くと、追い打ちをかけるような事態が起こることがあります。
- 「社長、この貸付金ですけど、回収の見込みはあるんですか?」
- 「この在庫、ずっと動いていないようですが…」
これまで、会社の業績が良かったときには何も指摘してこなかったような決算書の中身について、銀行の担当者が急に厳しく問い詰めてくるのです。社長にしてみれば、「なぜ、いまさらそんなことを言うんだ…」と、不満や戸惑いを感じるかもしれません。
しかし、これは銀行員が意地悪をしているわけではありません。会社の業績が良いときと悪いときとでは、銀行の「リスク許容度」がまったく異なるため、同じ決算書を見ていても、チェックの厳しさが変わるのは当然なのです。
本記事では、業績が良いときには見過ごされがちでも、業績が悪化した途端に銀行から厳しく見られることになる3つのポイントについて解説します。平時からこれらの点を意識しておくことが、いざという時の助けになるはずです。
具体的には、以下3つが厳しく見られるポイントになります。
- 雑勘定(仮払金、貸付金など)
- 不良資産(不良債権、不良在庫など)
- 利益計画(業績改善の見込み)
業績悪化時ほど銀行が厳しく見るポイント
それでは、具体的な3つのポイントについて見ていきましょう。これらは、黒字のときには利益でカバーできていた「会社の弱点」とも言えます。赤字になると、その弱点が銀行の目にはっきりと映し出されるのです。
雑勘定(仮払金、貸付金など)
黒字のときの銀行の見方
決算書に仮払金や社長への貸付金といった「雑勘定」が残っていても、会社が十分に利益を出していれば、銀行はそれほど問題視しないことがあります。「まあ、そのうちに精算されるだろう」「何かあっても、利益で十分に吸収できるだろう」と、ある意味で大目に見てくれている状態です。
業績悪化時の銀行の見方
ところが、ひとたび会社が赤字に陥った途端、銀行の視線は一変します。これらの雑勘定は、会社の「管理体制の甘さ」や「隠れた損失」の象徴として、厳しく追及されることになります。
- 「この仮払金は、本当は経費として計上すべきものではないのか?(=赤字の額がさらに膨らむのでは?)」
- 「社長への貸付金は、本当に会社に返済されるのか?(=実質的な損失ではないのか?)」
このように、雑勘定は「回収不能な資産」と見なされ、銀行は決算書の純資産からその分を差し引いて、会社の本当の体力を評価します(実質債務超過の判定)。平時には問題視されなかったものが、有事には会社の命取りになりかねないのです。
不良資産(不良債権、不良在庫など)
黒字のときの銀行の見方
長期間回収できていない売掛金(不良債権)や、ずっと売れ残っている在庫(不良在庫)があっても、会社全体の業績が良ければ、銀行も強くは指摘しないかもしれません。「経営が順調だから、多少の不良資産は許容範囲だろう」と判断しているのです。
業績悪化時の銀行の見方
業績が悪化すると、これらの不良資産は、会社の「実態を偽る粉飾」であり、「経営判断の甘さ」の証拠として、厳しく見られます。
銀行は、「価値のない資産が、あたかも価値があるかのように決算書に計上されている。この決算書は信用できない」と判断します。
さらに、収益を生まない不動産や、社長の趣味のような高級車などについても、「なぜこれを売却して、おカネに換えないのか?」と、経営者の資産効率に対する意識の低さを問題視します。
赤字の会社に対しては、「まずは、こうした不良資産を処分して、自助努力で資金を捻出するのが先でしょう」というのが、銀行の基本的なスタンスです。
利益計画(業績改善の見込み)
黒字のときの銀行の見方
会社が黒字で、業績が順調なときには、来期の利益計画が多少甘くても、銀行は「この調子でがんばってください」と言うていどでしょう。実績が出ているので、計画の細部までを厳しく問う必要がないからです。
業績悪化時の銀行の見方
会社が赤字になり、融資やリスケジュールをお願いする立場になると、利益計画(業績改善計画)は、融資判断における最も重要な書類に変わります。銀行は、その計画の「確度」を徹底的に吟味もします。
- 「この売上目標は、希望的観測ではなく、具体的な行動計画に裏付けられているか?」
- 「経費削減は、精神論ではなく、実現可能なレベルで織り込まれているか?」
- 「そもそも、この計画を社長が本気で実行する覚悟はあるのか?」
このように、計画の実現可能性と具体性、そして社長の実行力が厳しく問われます。ここで根拠の薄い、甘い計画を提出してしまえば、「この社長には会社を立て直す能力も覚悟もない」と判断され、支援を打ち切られてしまうことにもなりかねません。
まとめ
黒字のときには見過ごされていたかもしれない、以下の3つのポイントが、赤字になった途端に厳しく追及されることになります。
- 雑勘定: 管理体制の甘さ、隠れ損失として指摘される
- 不良資産: 実質的な粉飾、経営判断の甘さとして指摘される
- 利益計画: 実現可能性と具体性が、徹底的に吟味される
重要なのは、会社の業績が良い平時から、これらの弱点をなくしておくことです。日ごろから貸借対照表をスマートにし、実現可能性の高い経営計画を立て、実行していく。そうした当たり前の経営努力が、いざという時に会社を守るための、最強の「備え」となるのです。