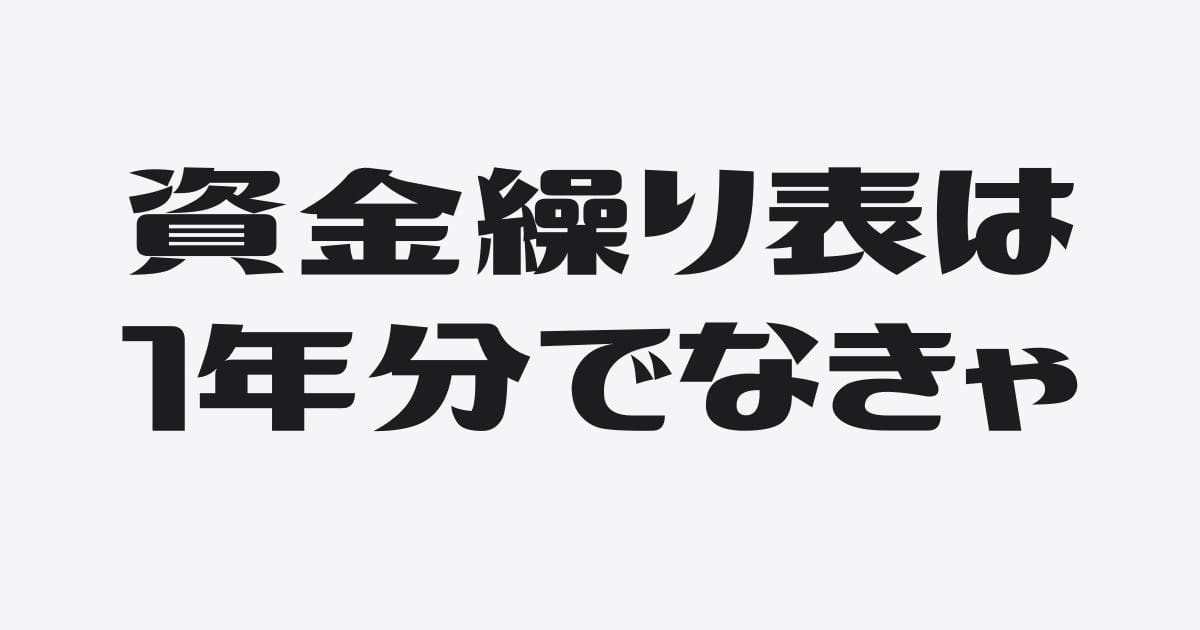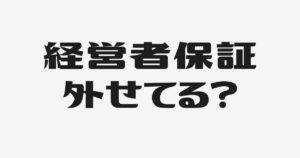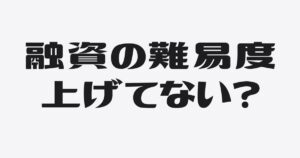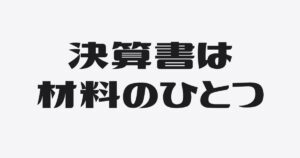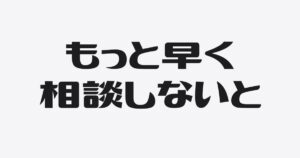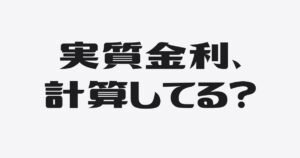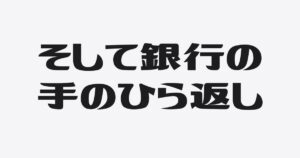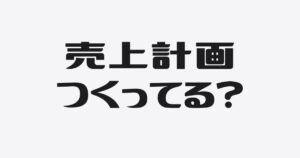会社の財務を考えるのであれば、必要不可欠なのが「資金繰り表」です。その資金繰り表は、1年先までつくってこそであり、その理由についてお伝えします。
6か月分くらいの資金繰り表が多い
会社の財務を考えるのであれば、必要不可欠なのが「資金繰り表」です。その資金繰り表について、「1年先までつくってこそ」というのが今回の結論になります。
いまが3月末だとしたら、4月から翌年の3月までの12か月分の資金繰り表をつくりましょう、ということです。実務的には、6か月分くらいの資金繰り表をつくっているケースが少なくないものと想像します。そのあたりもふまえて、1年先までの資金繰り表をおすすめするところです。
ではなぜ、資金繰り表は1年先までつくってこそなのか?その理由は3つ、次のとおりです。
- 年間の返済額を知るため
- 納税額を見逃さないため
- 季節変動を排除するため
いずれも、会社の資金繰りを考えるうえでは見逃せません。見逃していると、自社の資金繰りの良し悪しを「誤認」することにもなりかねず、社長は十分に注意したいところです。
そこでこのあと、上記3つの理由を詳しく解説していきます。資金繰り表に求められる役割でもありますから、しっかりと確認しておきましょう。
資金繰り表を1年先までつくる理由
会社の財務を考えるのであれば、必要不可欠なのが「資金繰り表」だと前述しました。あえて厳しいことを言うと、資金繰り表のない経営は「論外」です。銀行融資を受けるにあたっても、資金繰り表があるのとないのとでは難易度がだいぶ変わります(資金繰り表があるほうが難易度は下がる)。
とはいえ、そもそも資金繰り表の様式やつくり方がわからない…ということであれば、僕が執筆した書籍に詳しく掲載しています。よろしければご参考にどうぞ。書籍タイトルは「税理士必携」となっていますが、税理士でなくともお役立ていただける内容です。
税理士必携 顧問先の銀行融資支援スキル 実装ハンドブック
(リンク先はAmazonの商品ページです)
年間の返済額を知るため
資金繰り表を1年先までつくる理由、1つめは「年間の返済額を知るため」です。
社長が資金繰りを考えるうえで、必ず確認すべきものとして「年間の返済額」が挙げられます。銀行融資を受けている場合に、いまから1年でどれだけの返済をするのかです。
そのうえで、「年間の返済額(元金分)<税引後利益+減価償却費」の状態が、あるべき姿だといえます。これが成り立たないと預金を取り崩していくことになるため、そうならないように、社長は絶えず年間の返済額を把握しつつ、返済額と利益との対比が重要です。
この点、1年先までの資金繰り表であれば、すぐに「年間の返済額」を把握できます(資金繰り表の右端に年間合計欄をつくっておけば)。いっぽうで、6か月分の資金繰り表だと「年間の返済額」は把握できません(単純に2倍すれば「年間の返済額」になるとも限らず…)。不便です。
また、決算後には「年間の返済額」分の金額が、ひとまずの借入目標になります。それだけの額を借りることができれば、利益ゼロでも資金繰りは回るからです。したがって、借入目標としての「年間の返済額」を把握できる点でも、資金繰り表を1年先までつくることが役立ちます。
利益は借入返済の財源であり、「利益が出ていれば資金繰りは回る」との勘違いがないよう気をつけましょう。資金繰り表には、その勘違いを正す役割もあります。
納税額を見逃さないため
資金繰り表を1年先までつくる理由、2つめは「納税額を見逃さないため」です。
法人税であれば、予定申告による納税と確定申告による納税で、年2回の納税があります。消費税は、確定申告による納税額に応じて、予定申告による納税回数は変わります。いずれにせよ、会社は年に数回の納税があるということです。
では、たとえば6か月分の資金繰り表をつくっているとしたらどうでしょう?当然、年間の納税額を把握することはできません。すると、その6か月で見れば資金繰りは回るとしても、その先の納税のタイミングでは資金不足が生じることもありえます。
会社の決算も税金の申告も1年に1回であり、1年が1単位です。よって、資金繰り表を1年先までつくることで、1単位分すべての納税額を織り込めるようになります。そのうえで、資金繰りが回るのであれば、「納税が理由でおカネに困ることはない」との確認ができるわけです。
なお、納税額については顧問税理士に確認をしておくのがよいでしょう。社長が概算で考えていた金額と、実際の金額とだいぶ違っていた…ということもありえます。また、そもそも納税があること自体を見逃しているケースもあるので、納税時期・納税額は税理士に確認するのが無難です。
季節変動を排除するため
資金繰り表を1年先までつくる理由、3つめは「季節変動を排除するため」です。
季節変動による資金繰りへの影響は、多かれ少なかれあるものです。つまり、1年を通じて見れば、資金繰りがよくなる時期もあれば悪くなる時期もあることを意味します。
自社で扱う商品やサービスの特性として夏によく売れるとか、逆に冬によく売れるということもあるでしょう。結果として、よく売れる時期には資金繰りはよくなるが、あまり売れない時期には資金繰りが悪くなるわけです。
では、たとえば6か月分の資金繰り表をつくっているとしたらどうでしょう?言うまでもなく、季節変動の影響を受けることになります。よく売れる時期の6か月であれば資金繰りはよくなるし、あまり売れない時期の6か月であれば資金繰りは悪くなります。
よって、季節変動が「1年で1サイクル」だとすると、資金繰りは1年で見るのが妥当だとわかるでしょう。つまり、資金繰り表を1年先までつくることで、季節変動を排除した資金繰りが見えてくるわけです。
1年先の預金残高がいまの預金残高よりも増えていれば、「季節変動はあっても、長い目で見ればおカネは増えていく」といえます。ですが、6か月先の預金残高がいまの預金残高よりも増えているからといって、長い目で見てもおカネが増えていくとはいえません。季節変動の影響を排除できていないからです(次の6か月では大きくおカネが減るかもしれない)。
季節変動が大きな商売である会社ほど、1年先までの資金繰り表つくりましょう。
まとめ
会社の財務を考えるのであれば、必要不可欠なのが「資金繰り表」です。その資金繰り表についは、1年先までつくってこそであり、その理由についてお伝えしました。
- 年間の返済額を知るため
- 納税額を見逃さないため
- 季節変動を排除するため
いずれも、会社の資金繰りを考えるうえでは見逃せません。見逃していると、自社の資金繰りの良し悪しを「誤認」することにもなりかねず、社長は十分に注意したいところです。