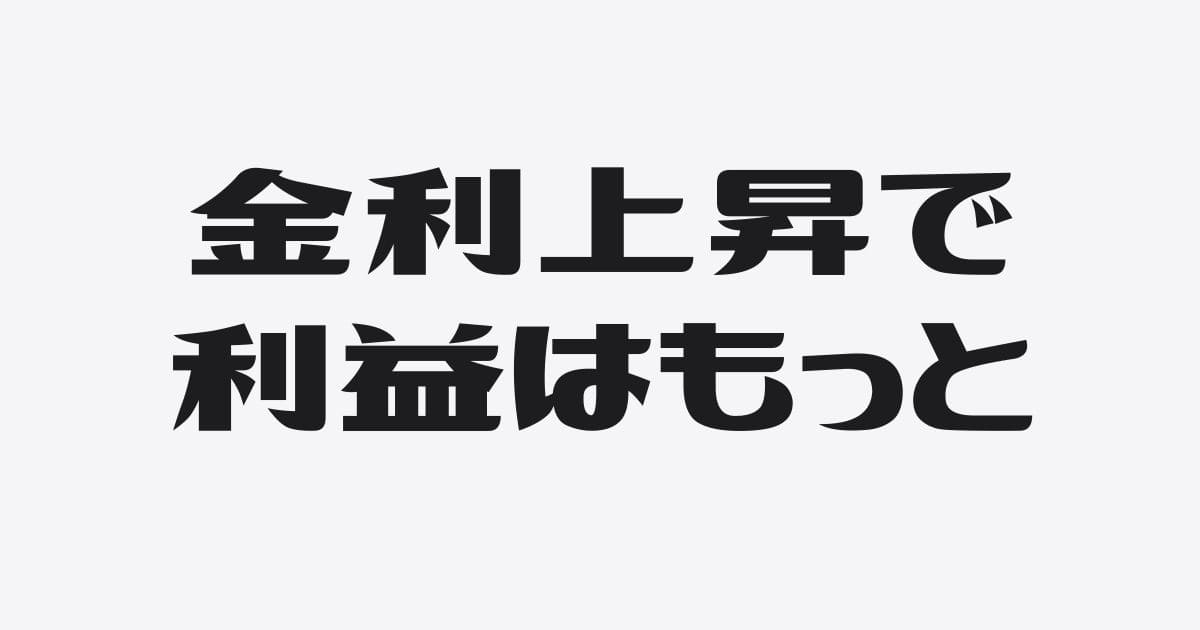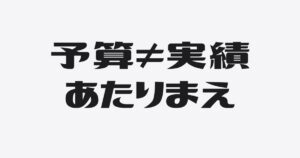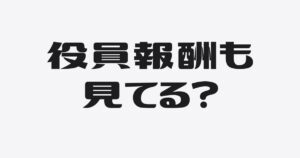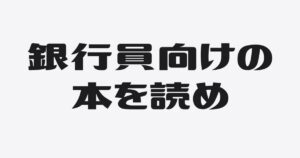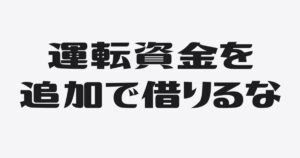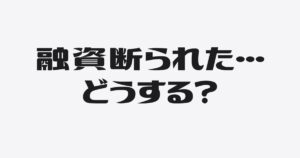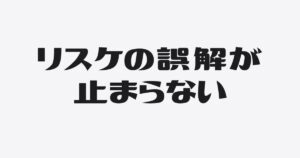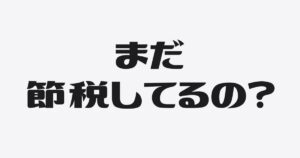金利が上がると、利益がもっと大事になります。納税が増えるのを嫌って利益を抑えようとしている社長や、値上げを躊躇している社長などはとくに、ご確認をいただきたい内容です。
これまでと同じ感覚でいると融資はどうなる
世の中の金利が上がると、利益がもっと大事になる。これは、中小企業における銀行融資の話です。実際にいまは日銀の利上げが進み、融資金利も上昇しています。これから先はさらなる金利上昇も予想されるところであり、すると利益がもっと大事になります。
ここでいう利益とは、いうまでもなく、融資を受けようとする会社の利益です。融資を受けるにあたって利益が大事だなどというのは、これまでもそうでした。ですが、金利が上がればもっと大事になることを忘れてはいけません。
社長が自社の利益について、これまでと同じ感覚でいると、融資が受けにくくなるおそれがあります。そこで、利益がもっと大事になることを理解するために、そして利益をもっと大事にするきっかけとして、「なぜ、金利が上がると利益がもっと大事になるのか?」という理由を押さえておきましょう。その理由は3つ、次のとおりです。
- 融資金利が上がる
- 金利負担が増える
- 返済の原資は利益
これら3つの理由について、このあと順番に解説していきます。納税が増えるのを嫌って利益を抑えようとしている社長や、値上げを躊躇している社長などはとくに、ご確認をいただきたい内容です。繰り返しになりますが、これまでと同じ感覚でいると、融資が受けにくくなるおそれがあります。
金利が上がると利益がもっと大事になる理由
納税が増えるのを嫌っている社長は、利益を出し惜しみします。客離れを恐れて値上げを躊躇している社長の会社は、利益がジリ貧になりがちです。結果として、融資が受けにくくなります。それでも、これまではなんとかなっていたかもしれませんが、金利が上がるとそうはいきません。
これまでよりも利益がもっと大事になる理由を確認していきましょう。
融資金利が上がる
冒頭でもふれたとおり、日銀の利上げによって、融資金利も上昇しています。世の中の金利が上がれば、融資金利も上がるのです。まずは、この流れを理解しておく必要があります。
世の中の金利が上がるということは、銀行が貸出原資を用意するにもコストが高くなるということです。銀行が会社に融資をするには、そのためのおカネ(貸出原資)を集めなければならず、そのおカネをどこからか借りて調達するのだとすれば、銀行の資金調達コストが上がります。
上がった分のコストを、融資金利の引き上げとして「価格転嫁」するのは当然の流れです。だとすれば、会社は「融資金利の引き上げを容認する」のも当然だとわかります。逆に、融資金利の引き上げをかたくなに拒むようだと、銀行からは「ならば貸せない」と言われてしまうでしょう。
もちろん、必要以上の引き上げにまで応じる必要はありませんが、妥当な引き上げであれば、会社は応じるべきです。それができなければ、融資自体が受けられなくなってしまいます。では、妥当な引き上げとはどのように考えればよいのか?
短期プライムレートやTIBORといった、融資金利に影響する指標の上昇幅と、自社が提示されている融資金利の上昇幅を比較する。あるいは、日本銀行が公表している貸出約定平均金利と、自社が提示されている融資金利とを比較してみるのもよいでしょう。
そのうえで、自社に求められている融資金利の引き上げが、各種指標の上昇幅の範囲内であったり、貸出約定平均金利の動きと同程度であれば、引き上げを容認することになります。なお、容認しがたいほどの引き上げを求められるのであれば、銀行にとって自社への融資はリスクが高いということです。
金利負担が増える
いましがた、「容認しがたいほどの引き上げを求められるのであれば、銀行にとって自社への融資はリスクが高いということ」だと言いました。リスクが高いとは端的にいえば、自社には金利負担に耐えるだけのチカラが不足していることをあらわします。
融資金利が上がれば、それだけ会社が銀行に支払う利息は増えるわけで、それでも資金繰りを維持するためには、金利負担に見合うだけの利益が必要です。したがって、融資金利が上がれば金利負担が増えるのであり、会社は金利負担が増えた分の利益を増やさなければいけません。
にもかかわらず、これまでと利益が変わらなかったり、ましてや赤字であったりしたらどうでしょうか?
会社は返済できなくなる可能性が高まりますから、銀行にとってはリスクです。すると、銀行が融資をするとしてもリスクを軽減するために、融資金利は上げざるをえなくなります。こうして、世の中の金利上昇以上に、融資金利の引き上げを求められる会社もあるのです。
しかし、もともと金利負担に見合うだけの利益が不足しているのに、さらなる融資金利の引き上げでは会社がもちません。遅かれ早かれ資金繰りで苦しむ未来が見えています。
これから先も日銀の利上げは予想されるところであり、融資金利のさらなる上昇が見込まれるのだとすれば、社長は「自社の利益を増やすことを考えなければいけない」とわかるでしょう。
返済の原資は利益
融資金利が上がれば金利負担が増えるのであり、会社は金利負担が増えた分の利益を増やさなければいけない、と前述しました。会社が銀行に利息を支払うには、利益が必要だということです。
また、「返済の原資は利益」というのが銀行の見方でもあります。つまり、利息の支払いにも元金の返済にも利益が必要なのです。
この点、利息に見合った利益の指標として「インタレスト・カバレッジ・レシオ」があります。金利上昇にともない、この指標の注目度が上がるものとして覚えておきましょう。算式であらわすと、「(営業利益+受取利息)÷(支払利息)」です。
受取利息は微々たるものでありゼロだとすれば、営業利益が支払利息の何倍あるかであり、インタレスト・カバレッジ・レシオが大きいほど利息の支払いに余裕があることになります。目安として、最低でも2倍以上と考えておきましょう。
いっぽうで、元金の返済に見合った利益の指標として「債務償還年数」があります。算式であらわすと「(借入金−預金)÷(税引後利益+減価償却費)」です。「税引後利益+減価償却費」を返済原資とした場合に、いまある借入金を何年で完済できそうかを意味しています。
借入金から預金をマイナスしているのは、預金があればその分の借入金は無いのといっしょだからです(いつでも返済できる)。そのうえで、債務償還年数の目安は「10年以内」です。
社長は上記2つの指標も参考に、自社の利益が十分であるかの確認をしましょう。不十分となれば、金利上昇にともない融資は受けにくくなってしまいます。
まとめ
世の中の金利が上がると、利益がもっと大事になります。これを理解するために、そして利益をもっと大事にするきっかけとして、「なぜ、金利が上がると利益がもっと大事になるのか?」という理由を押さえておきましょう。その理由を3つ、お伝えしました。
- 融資金利が上がる
- 金利負担が増える
- 返済の原資は利益
納税が増えるのを嫌って利益を抑えようとしている社長や、値上げを躊躇している社長などはとくに、ご確認をいただきたい内容です。これまでと同じ感覚でいると、融資が受けにくくなるおそれがあります。