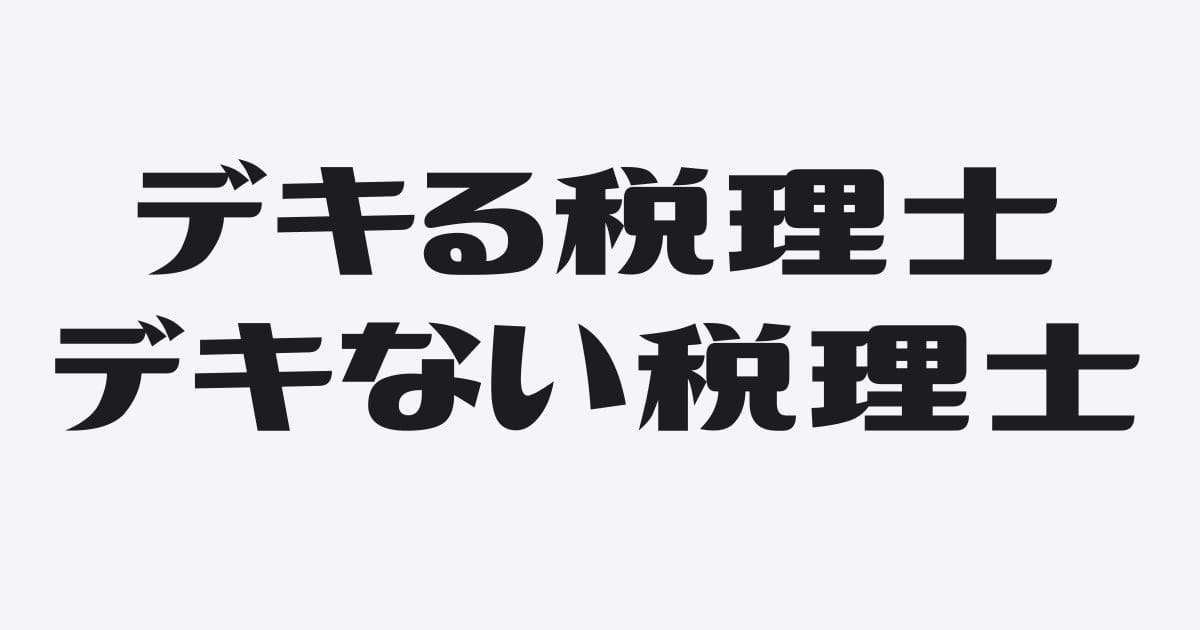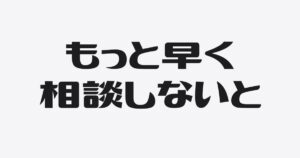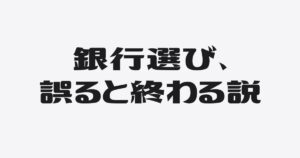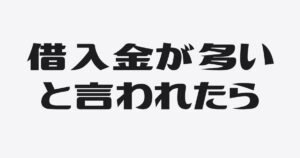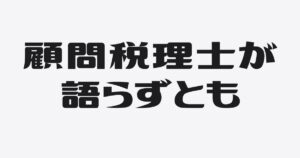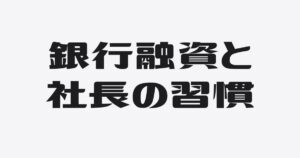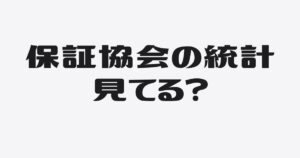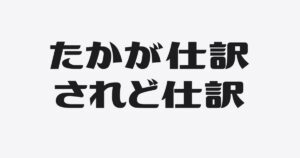銀行融資について、「相談できる税理士」と「相談できない税理士」がいます。税理士が何でも知っているわけではありません。そこで、銀行融資を相談できない税理士の特徴を挙げてみました。
税理士たるもの銀行融資のことくらい
会社の銀行融資について、「相談できる税理士」と「相談できない税理士」がいる。というのが、僕の考えです。つまり、銀行融資のことが「わかっている税理士」と「わかっていない税理士」がいるので、社長が相談するのであれば気をつけましょう、ということになります。
などと言えば、「税理士の格を落とすんじゃない」と叱られもするでしょう。「税理士たるもの、銀行融資のことくらいわかっている!」みたいな。でも、そんなことはないと感じています。だって、僕自身がさっぱりわかっていなかった時期もありましたし、周囲を見渡しても似たりよったりでした。
また、いまでは銀行融資の相談をお受けしているなかで、「顧問税理士には融資の相談ができない(相談しても答えを得られない)」という社長の声をお聞きしてもいます。だとすれば、多いか少ないかはさておき、銀行融資を相談できない税理士もいるということです。
この点、相談をしたときに「わかりません」と言ってくれるのであればまだよいものの、本当はわかっていないのに、いうなればテキトーな返しをしてしまう税理士もいるでしょう。恥を忍んで告白しますが、かつての僕がそうでした。聞かれたら何かしら答えなければ…と。いまにしておもえば、たいへんな不誠実です。
そのような反省の意も込めて、銀行融資を相談できない税理士の特徴を挙げてみます。いろいろあるのですが、ここでは以下の3つに絞ってみました。
- 借入を減らせとばかり言う
- 科目変更をかたくなに拒む
- タイミングを助言できない
上記の言葉尻だけでわかったことにはせず、その理屈まで理解できるよう、このあとの解説も確認していただければとおもいます。社長が理屈まで理解できれば、税理士に相談せずとも自身で判断できるようになるというものです。
銀行融資を相談できない税理士の特徴
銀行融資を相談できない税理士には、共通する特徴があります。銀行融資のことがわかっていないからこそあらわれる言動があるのです。これをサインとして、社長は見逃さないように観察しておくとよいでしょう。ここでは、おもに3つの特徴を取り上げます。
借入を減らせとばかり言う
銀行融資を相談できない税理士の特徴、1つめは「借入を減らせとばかり言う」です。
まず、端的に結論を述べるなら、借入を減らすことには危険があります。借入を減らしてもよいのは、借入をする必要もないくらい資金が潤沢な会社に限られるからです。ところが、資金が潤沢な中小企業は、割合でいえば少数派だといえるでしょう。
資金が潤沢の目安は「最低」でも、平均月商の3か月分以上です(できれば6か月分以上)。それくらいの預金がない場合、不測の事態に耐えられなかったり、成長のチャンス(投資のタイミング)を逃すことが多くなります。
この点、利益を増やして預金を増やすのが本筋ですが、利益だけでそれだけの預金を増やすのも容易ではありません。そこで、銀行融資を受けて預金を増やすのが財務のセオリーです。そのセオリーがわからずに、「借入=悪」という認識の税理士もいます。
誤解なきように申し添えますが、借入はしなくてよいならしないに越したことはありません。ですが、必要な借入まで拒むのはいけません。資金が不足すればどうなるかは、前述したとおりです。だからまずは、借入してでも預金を増やすこと。預金を最大化することをおすすめします。
ちょっと預金が増えると、繰上返済を勧める税理士もいるようです。しかし、いずれまた融資を受けるかもしれないのであれば得策ではありません。繰上返済は、銀行との関係性を悪くするものだからです。だとすれば、もう二度と融資は必要ないと言えるまで、繰上返済はしないことです。
自己資本比率の悪化を理由に、借入を減らせというハナシにも気をつけましょう。自己資本比率がいくら高くても、おカネがなくなれば会社はつぶれます。自己資本比率よりもまず、おカネ(預金)であり、その見方は銀行も同じです。
銀行対応を考えるうえで、自己資本比率が一桁はよくありませんが二桁あればよしであり、20%を超えていれば十分だと考えます。自己資本比率もいいですが、預金にも目を向けましょう。
科目変更をかたくなに拒む
銀行融資を相談できない税理士の特徴、2つめは「科目変更をかたくなに拒む」です。
銀行融資をスムーズに受けるにあたっては、いわゆる「勘定科目」も重要だと考えています。たとえば、「短期借入金」よりも「役員借入金」のほうがよいとか。また、似たところでは「区分」もあります。同じ支出であっても、販売管理費に区分するのか特別損失に区分するのかなど。
そのあたりの解説は割愛しますが、銀行融資の相談をしているなかで決算書を拝見していると、「勘定科目や区分を変えたほうがいいな」と感じるケースは少なくありません。ところが、勘定科目や区分の変更をかたくなに拒む、嫌がる税理士もいると聞いています。
理由はいろいろあるものと推測しますが、いずれにせよ、お客さまの「不利益(融資が受けにくくなる)」がわかっていないということでしょう。
ちなみに、勘定科目や区分の変更は「銀行融資のためだけ」におこなうものではありません。むしろ、会社のため・社長のためにおこなうものです。つまるところ、変更の目的は「より実態を正しくあらわす」ことにあります。結果として、銀行も融資判断がしやすくなるのです。
したがって、銀行融資をスムーズに受けるために勘定科目や区分を変更することは、そもそも社長が会社の状況をより正しく把握するのに有効であり、経営判断により役立つことを覚えておきましょう。だとすれば、勘定科目や区分の変更を、税理士が拒んだり嫌がる道理はありません。
なお、「より実態を正しくあらわす」ための勘定科目や区分について、具体的に知りたいということであれば、以下の書籍で詳しく書きました。よろしければご参考にどうぞ。
税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90
(リンク先はAmazonの商品ページです)
タイミングを助言できない
銀行融資を相談できない税理士の特徴、3つめは「タイミングを助言できない」です。
同じ額の融資を受けるでも、タイミングによって難易度が変わります。わかりやすいところでいえば、赤字のときに融資を受けるよりも、黒字のときに融資を受けるほうが難易度は低いものです。
よって、赤字になってから「融資を受けたほうがいい」とアドバイスする税理士は、銀行融資のことがわかっていないといってよいでしょう。決算書や試算表が黒字のときに、いまが融資を受けるのによいタイミングであることをアドバイスしない税理士も同様です。
また、銀行から融資提案を受けた際、社長が税理士に「提案を受けたほうがよいか(借りたほうがよいか)」と相談するのはよくあることでしょう。このとき、「いまはおカネがあるのだから、借りる必要はない」とアドバイスする税理士のハナシもよく聞きます。
ですが、僕は「原則、借りる」ようにアドバイスしています。なぜなら、融資提案を受けている状況は、会社のほうから融資相談をするよりも借りやすい状況だからです。銀行が「貸したい」から融資提案をしているのだと想像すれば、借りやすいことはわかるでしょう。
借りやすいということは、融資条件の交渉もしやすいということです。したがって、融資条件をよくするために「あえて借りておく」のも1つの選択肢になります。いずれ借りるかもしれないのであれば、条件がよい今のうちに借りておくほうが賢明というものです。
別のケースとして、売上増加時に融資を受けるようアドバイスできる税理士か。売上増加時には、いわゆる経常運転資金も増加するため、資金繰りが厳しくなります。よって、お客さまの売上増加に気を配り(社長から売上予測をヒアリングするなど)、いち早く経常運転資金増加分の融資をアドバイスできる税理士は、銀行融資がわかっているといえます。
というように、融資を受けるべきタイミングを、ふだんから助言してくれる税理士かどうかは確認してみるとよいでしょう。タイミングによって融資の難易度は変わるし、タイミングが遅れると資金繰りが厳しくなり、融資が受けにくくもなってしまいます。
まとめ
銀行融資について、「相談できる税理士」と「相談できない税理士」がいます。税理士が何でも知っているわけではありません。そこで、銀行融資を相談できない税理士の特徴を挙げてみました。
- 借入を減らせとばかり言う
- 科目変更をかたくなに拒む
- タイミングを助言できない
上記の言葉尻だけでわかったことにはせず、その理屈まで理解しましょう。すると、税理士に相談せずとも社長自身で、銀行融資に関する判断ができるようになるはずです。
【補足(という名の言い訳)】
本文中ではエラそうに、「銀行融資のことがわからない税理士」などと書きましたが、前述したとおり、以前は僕自身もわかっていませんでした。いまだって銀行融資のことはわかるようになっても、ほかにはわからないことだってあります。
なので、「銀行融資のことがわかる税理士がエラい」などとはまったく考えていませんし、本記事にそのような意図はありません。税理士によって得意不得意もいろいろなので、社長が相談をするなら気をつけましょう、という注意喚起を狙いとしています。