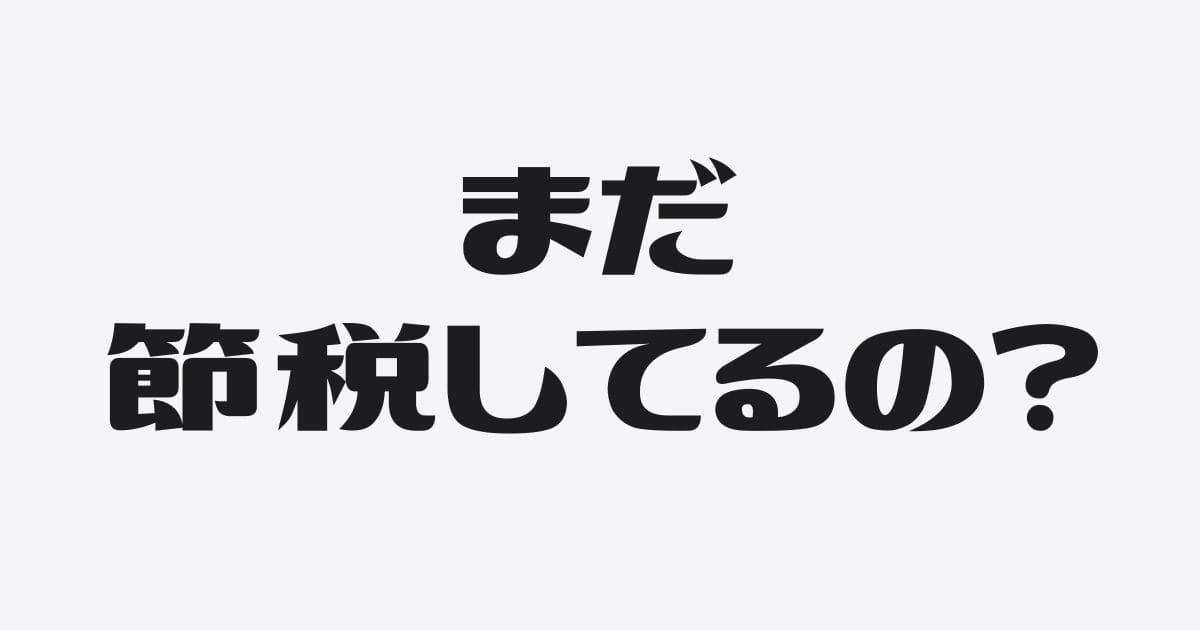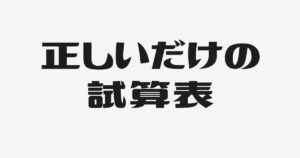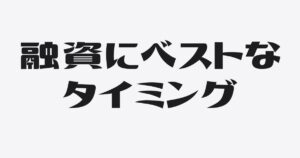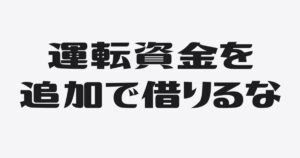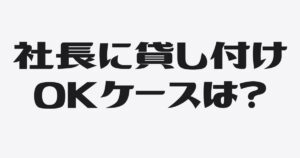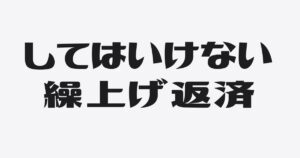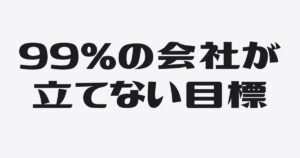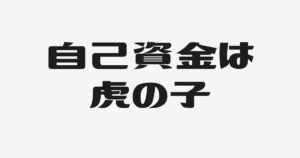「こんなに税金払うくらいなら、決算前に経費を使って利益を減らしてやる!」という社長がいます。ところが、節税で得したつもりが融資で大損しているかもしれません。
経費を使って利益を減らしてやる
「今期はだいぶ利益が出そうだな。でも、税金もだいぶ多そうだ…」
決算が近づくと、そのように頭を抱える社長もいるでしょう。僕も社長から相談を受けますが、利益が出ているのに、なぜか浮かない顔をしている。その理由が、税金だったりもするのです。
「こんなに税金払うくらいなら、決算前に経費を使って利益を減らしてやる!」
そんな気持ち、社長ならわかるかもしれません。でも、ちょっと待った。その節税、本当に会社のタメになっているのでしょうか?
実は、目先の税金を惜しむあまり、将来の銀行融資の可能性を大きく狭めてしまい、結果的に会社を苦しめる… そんな笑えない事態に陥っている会社もあるのです。
そこで今回は、社長が見落としがちな「利益」と「税金」、そして「銀行融資」の三角関係についてお話しします。これを知らないと、節税で得したつもりが融資で大損しているかもしれません。
【大前提】銀行の見方は「利益=返済力」
まず、大前提として絶対に忘れてはいけないこと。それは、銀行は会社の「利益」を「返済力」として見ているということです。
そもそも、なぜ銀行が利益を気にするのか?シンプルです。銀行は、貸したおカネをきちんと返してもらって、はじめて商売が成り立ちます。その返済の原資となるのが、会社が生み出す利益だからです。
利益が出ていない会社は、銀行から見れば「返済能力がない会社」となります。そんな会社におカネを貸すのは、銀行にとってリスクでしかありません。だから、銀行から融資を受けたければ、利益を出すことが絶対条件なのです。
ここを理解せずに、「税金を払いたくないから利益を減らす」というのは、銀行に対して「うちは返済するチカラがありません(あるいは、返済する気がありません)」と宣言しているようなものです。銀行に嫌われるだけで、よいことはひとつもありません。
「いやいや、ウチは本当はもっと利益を出せるんだ。たまたま今期は節税しただけで…」などという言い訳も、銀行には通用しません。銀行にしてみれば、本当にそうなのかわかりませんし、そもそも利益を積極的に減らそうとする考え方自体、歓迎できるものではないのです。
銀行融資を考えるなら、まず利益。話はそれからです。
【核心】節税で「借入余力」を捨てている
「利益が大事なのはわかった。でも、やっぱり税金は安くしたい…」
そう考える社長のために、核心としての事実をお伝えします。その節税、将来銀行から借りられるはずだった「借入余力」をドブに捨てる行為かもしれません。少し刺激的な表現をしましたが事実です。
銀行が「この会社に、あとどれくらい融資できるか(借入余力)」を判断するとき、重要な指標のひとつに「債務償還年数」があります。算式でいうと「借入金残高÷(税引後利益+減価償却費)」であり、「いまの利益水準なら、借金を何年で返せるか?」を示すものです。
銀行はおおむね、「債務償還年数は10年以内」を目安にしています。10年を超えると「貸しすぎ(返済力が足りない)」と判断するわけです。
この考え方を逆算すると、会社が借りられる金額の目安が見えてきます。それが次の算式です
借入余力 = ( 税引後利益 + 減価償却費 ) × 10年 - 現在の借入金残高
注目したいのは、「税引後利益」の部分です。利益が大きいほど、借入余力も大きくなる、という関係にあることがわかります。では、具体例で見てみましょう。
決算前に、今期の予測利益が500万円の会社があったとします。
- パターンA(節税しない)
- 税引前利益:500万円
- 減価償却費ゼロ、既存借入ゼロ
- 法人税等(税率25%):125万円
- 税引後利益:375万円
- 借入余力の目安:375万円 × 10年 = 3,750万円
- パターンB(400万円の経費を増やして節税)
- 税引前利益:500万円 – 400万円 = 100万円
- 法人税等(税率25%):25万円
- 税引後利益:75万円
- 借入余力の目安:75万円 × 10年 = 750万円
これを見てどうでしょうか?
パターンBはパターンAに比べて、税金は100万円安くなりました。ところが、その代償として、銀行から借りられるはずだったおカネ(借入余力)が、なんと3,000万円も減ってしまったのです(3,750万円 – 750万円)。
あえてこう言いますが「たった100万円」の税金を惜しんだばかりに、将来、会社の成長や、いざというときに必要になるかもしれない3,000万円の融資の道をみずから閉ざしてしまった。これが、節税が招く恐ろしい事実です。
「それでもあなたは、節税を選びますか?」と、僕は社長に問います。
【追い打ち】失ったのは融資だけではない
話はこれでおわりません。
「経費を増やして節税」の恐ろしさは、借入余力を減らすだけでなく、会社の「手元のおカネ」そのものを、節税額以上に減らしてしまうことです。
さきほどの例をもういちど見てみましょう。
- パターンA(節税しない)の税引後利益(≒手元に残るおカネ)は375万円。
- パターンB(節税する)の税引後利益(≒手元に残るおカネ)は75万円。
その差は300万円です。
税金は100万円安くなったかもしれませんが、会社からは節税のために400万円の現金が出て行きます。差し引きすると、300万円も会社のおカネが減ってしまったのです。
借入余力が減るわ、手元のお金は減るわで、資金繰りが苦しくなるのは目に見えています。いざおカネが必要になって銀行に駆け込んでも、「借入余力がない・おカネもない」で断られてしまう。まさに八方ふさがりです。
もちろん、経費を増やす節税がすべて悪だと言っているのではありません。将来の売上や利益につながる「投資」としての支出や、もともと予定していた支出の時期を前倒しする、といった前向きなものであれば問題ありません。
問題なのは、「税金を払いたくない」という一心だけで、場当たり的に経費を使ったり、社長個人の浪費に近いような支出をしてしまうことです。それでは会社におカネは残りません。
まとめ
「納税は損だ」「税金を払うくらいなら経費を増やす」
そのような考えは、会社の未来を危うくします。目先の税金を惜しむ「過度な節税」は、
- 銀行からの「借入余力」を大幅に減らし、
- 会社の「手元のお金」を節税額以上に減らす
という、二重のダメージを会社に与えるのです。
本当に会社の成長と安定を願うなら、目先の税金にとらわれず、中長期的な視点を持つべきです。
出せる利益はきちんと出し、必要な納税をする。そうやって会社の体力をつけて、財務内容を良くしていくことこそが、結果的に銀行からの信用を高め、いざというときの資金調達力(=借入余力)を高め、会社の選択肢を広げることにつながります。