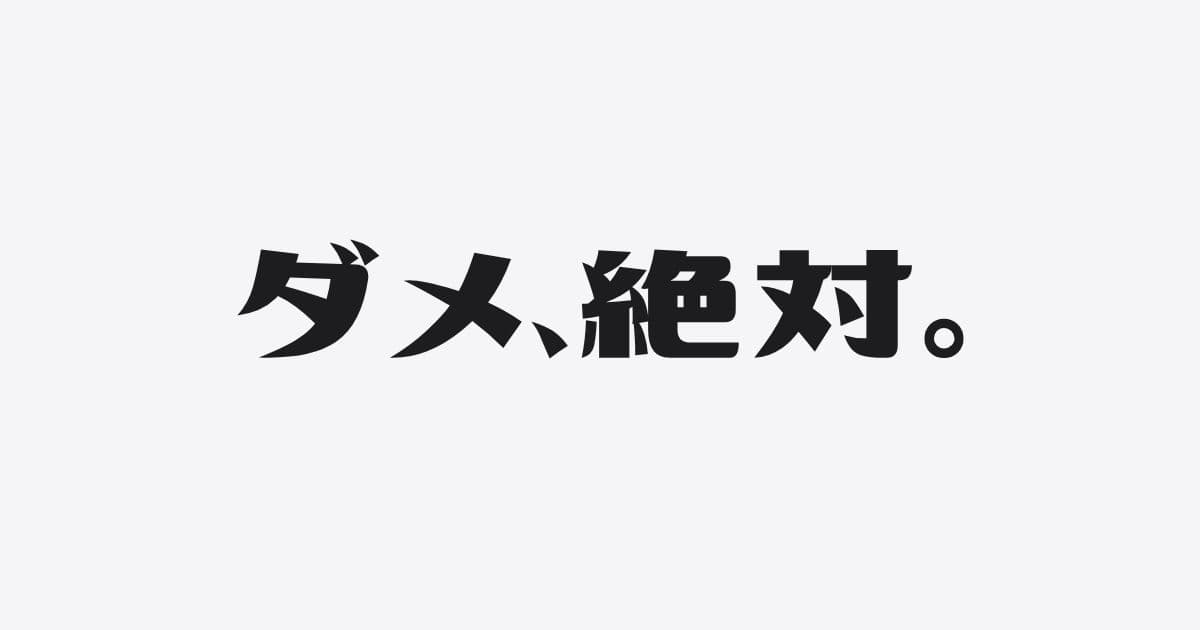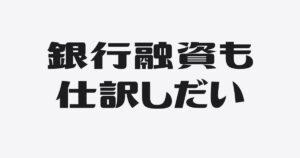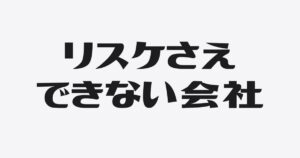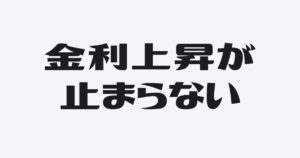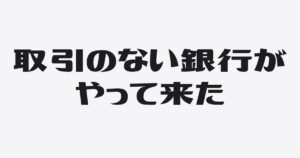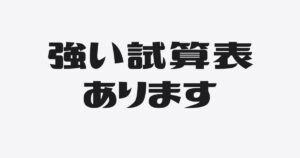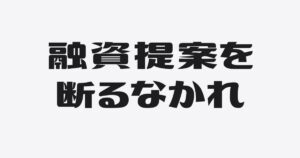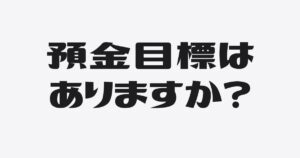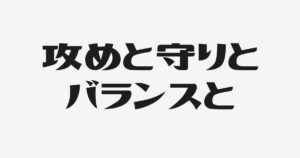銀行との信頼関係は、長年かけて築くもの。ですが、たったいちどの誤った対応で、その信用は一瞬にして崩れ去ることがあります。そんな、社長が絶対にやってはいけない銀行対応とは…?
その銀行対応が命取りになる
日ごろから銀行と良好な関係を築こうと、多くの社長が努力をされていることでしょう。定期的に業況を報告したり、担当者とコミュニケーションを取ろうとしたり。そうした地道な積み重ねが、いざというときの融資につながります。
しかし、ときに資金繰りのプレッシャーや焦りから、社長が「致命的」とも言える誤った対応をしてしまうことはあるものです。良かれと思って、あるいは「これくらいなら大丈夫だろう」と安易に考えて取った行動が、銀行との信頼関係を根底から破壊すれば、会社の未来を閉ざしてしまうことになりかねません。
今回は、僕が銀行融資の支援をするなかで実際に見てきた、「これだけは絶対にやってはいけない」と断言できる銀行対応を3つに絞って解説します。知らずにやってしまって、取り返しのつかない事態になる前に、ぜひ確認しておきましょう。具体的には、以下の3つです。
- 資金使途を偽る
- ノンバンク借入
- ウソの売上見込
絶対やってはいけない銀行対応3選
それでは、具体的な3つのNG対応について見ていきましょう。これらは、厳しい状況にあるときほどやってしまいがちな行動かもしれませんが、その代償はあまりにも大きいことを理解してください。
対応1:資金使途を偽る
やってはいけないこと
たとえば、「あたらしい機械を買うための設備資金」として銀行に融資を申し込み、実際には機械を買わずに、借りたおカネを赤字の補てんなどに充てるといった行為はいけません。
銀行に伝えたおカネの使いみち(資金使途)と、実際の使いみちとが異なる。これは「資金使途違反」と呼ばれ、銀行が忌み嫌う行為のひとつです。
なぜ致命的なのか?
銀行は、社長が示した「資金使途」の妥当性や計画性を審査したうえで、「その使いみちであれば、会社の成長につながり、返済も見込めるだろう」と判断しておカネを貸しています。それを破ることは、銀行に対する明確な「契約違反」であり、極端に言えば「詐欺」と見なされても仕方がない行為です。
銀行との取引関係は「信頼」がすべてです。「この社長は、大切な約束を守らない人だ」「平気でウソをつく人だ」と、いちどでも思われてしまえば、その信頼関係を回復するのはほぼ不可能だと言えます。
その後の末路は?
資金使途違反は、いずれ必ず銀行に発覚します(決算書の内容や、預金通帳のおカネの動きなどから)。それが発覚した場合、今後の追加融資は絶望的になると考えるべきです。
そればかりか、契約違反を理由に、最悪の場合、既存の融資についても一括での返済を求められる(これを「期限の利益の喪失」と言います)可能性があります。そうなれば、会社の存続そのものが危うく、資金使途違反は極めてリスクの高い行為となります。
対応2:ノンバンク借入
やってはいけないこと
銀行からの融資を待てずに、あるいは銀行に相談もせず、カードローンや消費者金融といったノンバンクから安易におカネを借りてしまうのはいけません。似たところでは、最近よく見かける「ファクタリング(売掛債権の買取)」も、銀行からは同類と見なされることがあるので注意が必要です。
なぜ致命的なのか?
銀行は、決算書や信用情報をとおして、ノンバンクからの借入を把握しようとしています。そして、ノンバンクからの借入がある会社に対しては、強い警戒感を抱くものです。なぜなら…
- 高コスト体質を嫌うから
ノンバンクの金利やファクタリングの手数料は、銀行融資に比べてとても高コストです。そんな高コストなおカネに手を出していること自体が、「会社の収益性や資金繰りをさらに悪化させる要因だ」と銀行は判断します。
- 経営管理能力を疑うから
「なぜ、まずメインバンクであるウチに相談しなかったのか?」「計画的な資金繰りができていないから、安易で高コストな方法に手を出したのではないか?」など、社長の経営管理能力そのものに大きな疑問符がつきます。
その後の末路は?
ノンバンクからの借入が発覚すると、銀行はその会社に対する警戒レベルを一気に引き上げます。「この会社は、我々が知らないところでもっと大きな問題を抱えているのではないか」と疑心暗鬼になり、プロパー融資はもちろん、保証付き融資ですら審査が厳しくなるでしょう。
ゆえに、安易なノンバンク借入は、自ら銀行融資への道を狭めてしまう行為です。
対応3:ウソの売上見込
やってはいけないこと
融資審査を通りやすくするために、根拠のない、実態よりも過大な売上見込や利益計画を銀行に提出する社長がいます。「これくらいの威勢の良い計画にしておけば、銀行も納得してくれるだろう」といった安易な考えで、希望的観測を盛り込んだ事業計画を作ってしまう行為です。
なぜ致命的なのか?
ここで社長が絶対に知っておくべきなのは、「銀行は、社長が伝えたことをすべて記録している」という事実です。融資申込時に提出した事業計画書はもちろん、担当者との面談での発言なども、稟議書や面談記録として、銀行の内部に残り続けます。
その場しのぎでウソの計画を伝えても、時間が経てば、実際の業績(月々の試算表や、翌年の決算書)との大きな乖離は必ず明らかになります。
その後の末路は?
実績が、提出した計画と大きくかけ離れていた場合、銀行は社長に対してどう思うでしょうか?「この社長は、自社の事業をきちんと見通せないのか(=経営能力がない)」、あるいは「この社長は、融資を受けるために平気でウソをつく人なのか(=信頼できない)」のどちらかです。
どちらにせよ、社長と、その社長が作る事業計画に対する信頼性はゼロになります。いちど失った信頼を取り戻すのは極めて困難であり、今後の融資申し込みにおいて、社長が語る未来の言葉は、もう信じてもらえなくなるのです。
まとめ
銀行との信頼関係を破壊し、会社の未来を閉ざしかねない「絶対にやってはいけない銀行対応」を3つ、解説してきました。
- 資金使途を偽る(=契約違反・詐欺)
- ノンバンク借入(=高コスト体質・管理能力欠如の証明)
- ウソの売上見込(=信頼性の喪失)
これらに共通するのは、その場しのぎの安易な考えが、取り返しのつかない深刻な事態を招くという点です。
資金繰りが厳しいときほど、こうした過ちを犯してしまいがちだったりします。しかし、本当に社長がやるべきことは、ウソやごまかし、安易な近道ではないはずです。
厳しい状況であるならば、その状況を正直に伝え、できるだけ早い段階で銀行に相談すること。そして、ともに解決策を探っていくこと。遠回りに見えても、その誠実な姿勢こそが、銀行との信頼関係を守り、会社の未来を切り開く道となります。