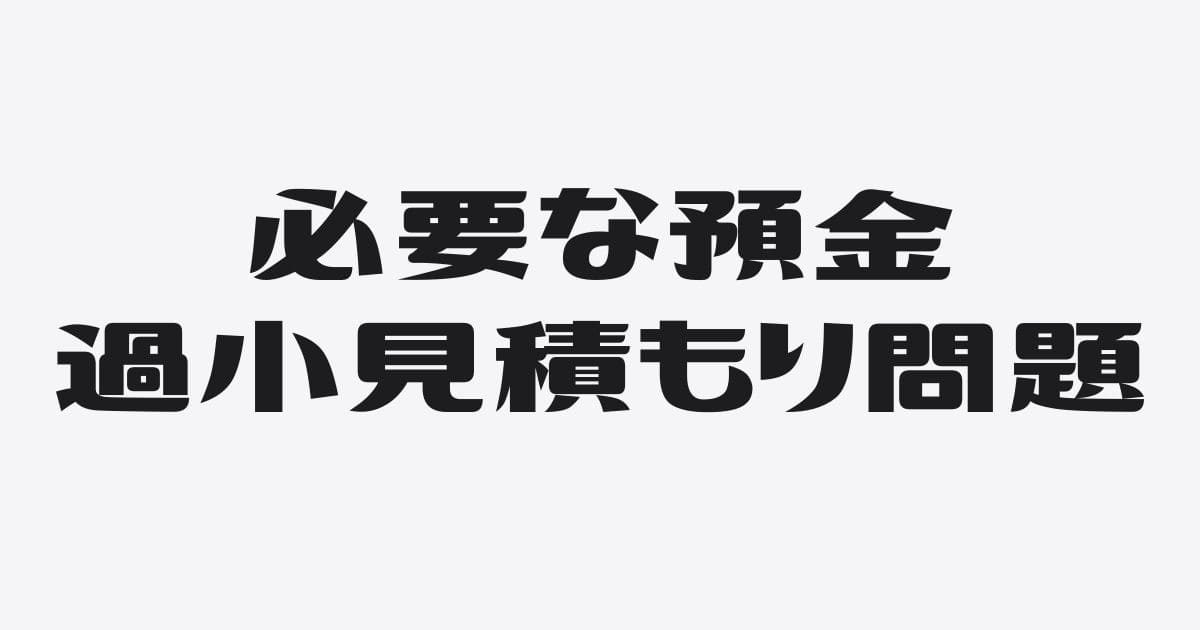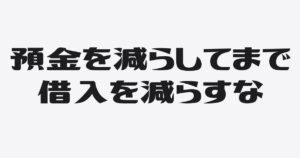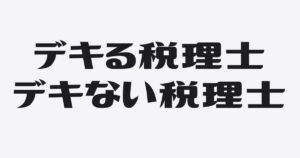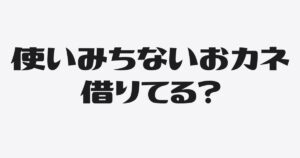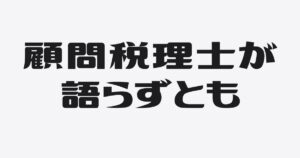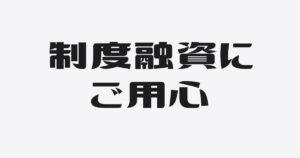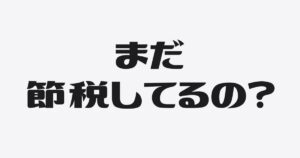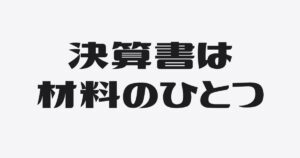会社が事業に必要な預金の目安は「平均月商×6か月分」です。これを過大とする見方もありますが、過小に見積もらないよう気をつけなければいけません。
必要な預金を過小に見積もっている
会社が事業を続けるにあたり、どれだけの預金が必要か?
意見はいろいろでしょうが、僕は「平均月商(年間売上高÷12か月)の6か月分を目指す」との考えです。半年のあいだ売上がゼロでも耐え忍ぶことができるから、という理由によっています。
しかし、「そこまで多くの預金は必要ないだろう」とおもわれるかもしれません。つまり、「平均月商×6ヶ月分」の預金は過大だとおもわれるかもしれません。
ですが、僕からすれば「むしろ逆」です。そこまで多くの預金は必要ないというのであれば、事業に必要な預金を過小に見積もっているのでは?というのが僕の考えです。
そこで、事業に必要な預金の目安が「平均月商×6か月分」である理由を深堀りします。具体的には、以下の3点です。
- 原価率が高くても固定費ならば
- 改善・投資にはおカネがかかる
- 預金があるほど銀行に好かれる
これらを見落としていると、会社は必要な預金を過小に見積もることになり、ひいては資金繰りを厳しくしてしまいます。
月商×6か月分の預金が必要な理由
冒頭、事業に必要な預金の目安が「平均月商×6か月分」である理由として、「半年のあいだ売上がゼロでも耐えしのぐことができるから」を挙げました。
この理由を、以下の3点で深堀りします。
原価率が高くても固定費ならば
「平均月商×6か月分」の預金は過大だとする見方があります。売上がゼロなら原価(仕入)もゼロなのだから、「販売管理費×〇か月分」で充分だとする考えです。
だとすれば、原価率が高い会社ほど販売管理費は少ないので、必要な預金はだいぶ少なくなります。もっともらしいハナシですが、本当にそれでよいのでしょうか?
この見方には「原価=変動費(売上の増減にあわせて増減する費用)」との前提があります。典型例が仕入です。だから、「売上がゼロなら仕入もゼロ」という考えになります。
ところが、原価のすべてが変動費ではありません。会社によっては・事業によっては、原価のなかに固定費(売上がゼロでも発生する費用)も含まれるのです。たとえば、オリエンタルランド(ディズニーリゾート)の原価には、ショーやパレードの人件費が含まれています。人件費というと販売管理費かつ固定費をイメージするかもしれませんが、そうではないケースもあるわけです。
また、仕入にも固定費的な要素はありえます。売上がゼロのあいだであっても、仕入ルートを確保するために一定量の発注を続けなければならないケースもあるのです。したがって、必ずしも「原価=変動費」ではありません。
以上をふまえて、必要な預金は「販売管理費×〇か月分」とする考え方には気をつけましょう。
ちなみに、売上ゼロでも耐え忍ぶには借入返済のおカネも必要です。であれば、「(販売管理費+月返済額)×〇か月分」という考え方もあるわけですが、「平均月商×6か月分」には月返済額も含まれています。
多くの会社では、「売上(平均月商)=原価+販売管理費+借入返済」がおおむね成り立つからです。
改善・投資にはおカネがかかる
新型コロナが猛威をふるった折、多くの会社が「転換」を余儀なくされました。あらたな生活様式となったことで、従来の商売が成り立たなくなったからです。イートインのみだった飲食店が、テイクアウトや配達、ネット通販をはじめたのは典型例だといえます。
このとき必要になるのがおカネです。あたらしいことをはじめるには、多かれ少なかれおカネがかかるものであり、おカネがあるほうが採れる選択肢も広がります。だとすれば、ふだんからおカネがある会社のほうが、コロナの折にも転換しやすい環境にあったといえるはずです。
これは、コロナのような特殊な状況に限りません。時代は変化していますから、旧態依然の商売ではいずれジリ貧…というのが常でしょう。よって、事業に改善や投資は必須です。既存製品をよりよい製品に改良したり、あたらしい商品・サービスを開発したり。そこには、やはりおカネが必要です。
おカネがなくてもアイデアで、などともいいますが。前述したとおおり、おカネがあるほうが採れる選択肢も広がることは間違いありません。社長にとって、おカネがあるのとないのとどちらがよいかはいうまでもないでしょう。
会社が苦境に立たされたとき耐え忍ぶだけなら、必要な預金は「販売管理費×〇か月分」との考えもありますが、転換をはかるための改善・投資まで考えるのであれば、その預金では足りません。ゆえに、「平均月商×6か月分」をおすすめするところです。
預金があるほど銀行に好かれる
中小企業の多くは、顕在的にも潜在的にも銀行借入を必要としています。つまり、いますでに銀行借入を利用している会社もあれば、いまは借入していなくても将来は借入するであろう会社が多いのです。
だとすれば、銀行から好かれる会社になることが重要になります。好かれる要素のひとつが預金です。端的にいえば、預金があるほど銀行に好かれます。銀行にとっては「預金=返済原資」であり、預金があるほど貸したおカネを回収しそびれる不安がやわらぎます。
したがって、預金があるほど銀行に好かれるし、借入がしやすくなるわけです。
この点、銀行には預金に対する目安があります。まずは、「平均月商の1か月分未満は危ない」という目安です。それしか預金がないと、なにかあれば資金ショートするおそれがあるので、銀行は「平均月商の2か月分くらいの預金があるといい」と考えています。
平均月商の3か月分くらいの預金になると、「だいぶ安全」との判断から、銀行は「もっと貸したい(貸しても大丈夫)」と考えるものです。こうなると、銀行のほうから融資提案も増えるでしょう。結果、銀行借入を増やしながら、「平均月商×6か月分」くらいまでの預金を目指すことが可能です。
借入が増えたら自己資本比率も下がるし、銀行から嫌われるのでは?と考えるのであれば違います。借りたおカネが使われずに預金としてあるかぎり、その借入は無いのと同じです。よって、「借入が多い=危険」とはなりません。
たとえ借入が多くても預金が多い会社のほうが、借入は少なくても預金が少ない会社よりは安全であり、銀行からも好かれることは理解しておきましょう。
まとめ
会社が事業に必要な預金の目安は「平均月商×6か月分」です。これを過大とする見方もありますが、過小に見積もらないよう気をつけなければいけません。
そこで、事業に必要な預金の目安が「平均月商×6か月分」である理由を、以下の3点から深堀りしました。
- 原価率が高くても固定費ならば
- 改善・投資にはおカネがかかる
- 預金があるほど銀行に好かれる
これらを見落としていると、会社は必要な預金を過小に見積もることになり、ひいては資金繰りを厳しくしてしまいます。見落としがないように、確認をしておきましょう。