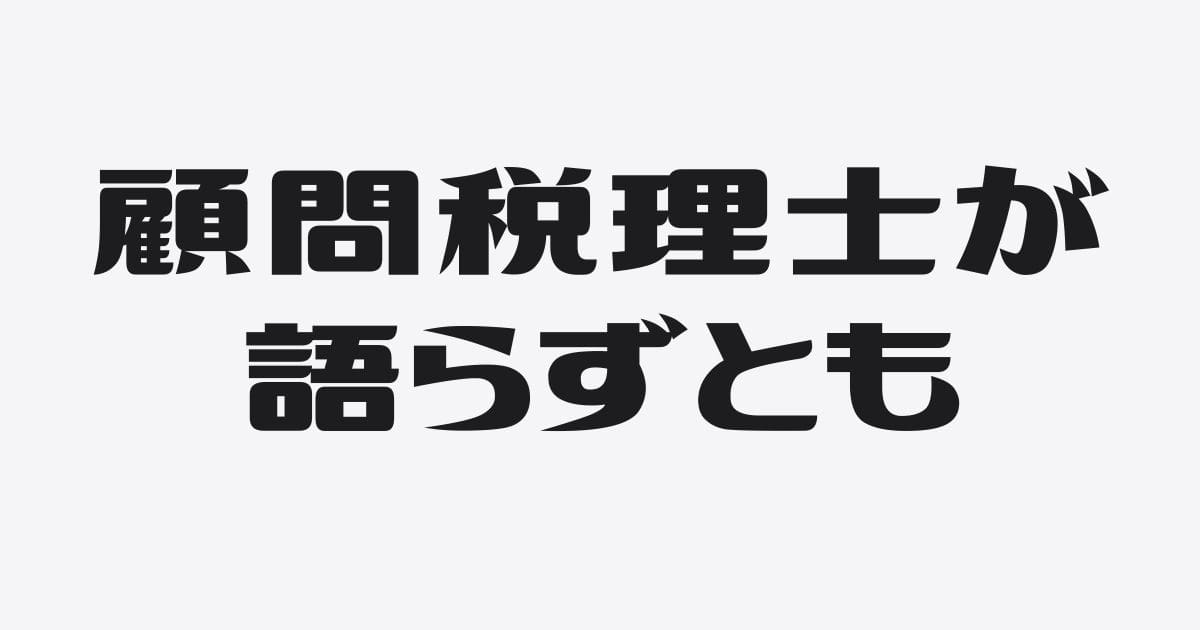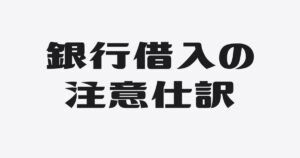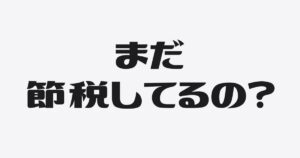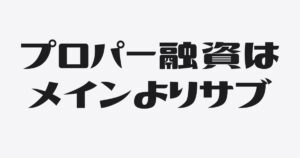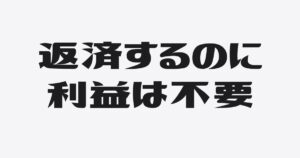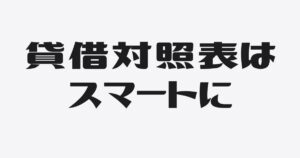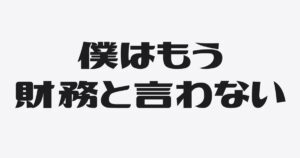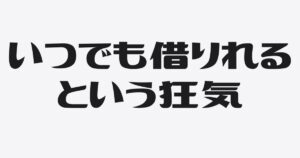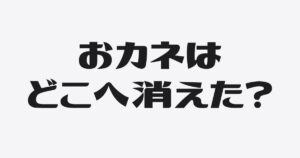税理士が専門分野である税務計算に重きを置くあまり、あえて詳しく説明しないけれど、実は会社にとっては重要なポイントがあります。社長自身で理解を深めることが欠かせません。
その決算説明で本当に十分か?
顧問税理士から受ける決算説明について。損益計算書を中心に、「今期の売上は〇〇万円で、利益は〇〇万円でした」といった報告を、毎年聞いている社長は多いでしょう。
ですが、その説明は本当に自社の「重要なポイント」を網羅しているのでしょうか? もしかしたら、税理士が専門分野である税務計算に重きを置くあまり、あるいは「社長には難しい話は不要だろう」と配慮(?)するあまり、あえて詳しく説明していない、あるいは説明自体が漏れてしまっている、でも、経営や銀行融資において重要なことがあるかもしれません。
けして、税理士を批判したいわけではありません。ただ、税理士の説明が必ずしも万能ではない、という現実を知っておくことは、社長にとって大切なことです。
今回は、税理士の説明では意外と触れられないけれど、会社の経営判断や、銀行からの融資評価に大きく関わってくる「3つの重要ポイント」について、銀行融資の支援にたずさわる僕の視点から解説していきます。具体的には次のとおりです。
- 貸借対照表
- 隠れ粉飾
- キャッシュフロー
ぜひ、ご自身の会社の状況と照らし合わせながら読んでみましょう。
税理士が説明しないけれど3つの重要ポイント
それでは、税理士の説明だけでは見落とされがちな、会社の経営や銀行融資における3つの重要ポイントについて、具体的に見ていきましょう。まずは、損益計算書に比べて、意外と説明が少ないかもしれない、あの書類のお話からです。
ポイント1:貸借対照表
決算説明というと、どうしても損益計算書、つまり「いくら儲かったか、損したか」の話が中心になりがちです。これは社長にとっても一番わかりやすく、関心が高い部分でしょう。
その一方で、貸借対照表、つまり「決算日時点で会社にどれだけの資産と負債があるか」についてはどうでしょうか。「資産の合計がこれで、負債の合計がこれです」ていどの簡単な説明でおわってしまったり、場合によっては説明自体がほとんど省略されてしまったり、というケースも少なくないように感じます。
社長自身も、貸借対照表の数字は損益計算書に比べて馴染みが薄く、とっつきにくいと感じているかもしれません。
しかし、貸借対照表には会社の「財政状態」、つまり会社の「安全性」や「体力」を示す、とても重要な情報が詰まっています。損益計算書が短期的な「成績」だとすれば、貸借対照表は長期的な「健康診断の結果」のようなものです。
銀行が貸借対照表を見るうえで、とくに厳しくチェックしているのが「純資産の部」です。なかでも「利益剰余金」(これまでの税引後利益の蓄積)の状態は、会社の命運を左右すると言っても過言ではありません。
なぜなら、この利益剰余金がマイナスになり、結果として純資産全体もマイナスになっている状態が「債務超過」だからです。債務超過とは、会社のすべての資産を売り払っても、借金などの負債を返しきれない状態を意味します。銀行から見れば、これは極めて危険な状態であり、原則としてあらたな融資は受けられません。
たとえ債務超過でなくても、純資産の額が小さい(=利益剰余金の蓄積が少ない)ということは、会社の体力が弱いことを示しています。そうなると、少し業績が悪化して赤字が出ただけで、あっという間に債務超過に転落してしまうリスクを抱えていることになります。
税理士の決算説明で、この貸借対照表、とくに純資産の部の重要性や、債務超過のリスクについて十分な説明がされていないとしたら…社長は、自社が抱える財務上のリスクに気づかないまま経営を続けることになりかねません。損益計算書の利益だけを見て安心していてはいけないのです。
ポイント2:隠れ粉飾
「ウチは粉飾決算なんて絶対にしない!」
ほとんどの社長は、そう考えているはずです。意図的に売上を水増ししたり、架空の経費を計上したりといった悪質な粉飾は、もちろん論外です。
しかし問題なのは、社長にも税理士にも悪気がないにもかかわらず、結果的に銀行からは「粉飾」と見られてしまう、いわば「隠れ粉飾(≒不適切な会計処理)」が決算書に潜んでいるケースが、実は少なくないということです。
具体的には、次のような処理が「隠れ粉飾」と見なされる可能性があります。
- 回収の見込みがほとんどない売掛金があるのに、「貸倒損失」や「貸倒引当金」として処理せず、資産として計上したままになっている
- 長期間売れずにホコリをかぶっている在庫(不良在庫)や、破損・劣化して価値が著しく下がった在庫を、いつまでも取得時の価格のまま資産計上している
- 決算の利益を少しでも良く見せるために、本来計上すべき「減価償却費」を意図的に少なく計上している(あるいは、まったく計上していない)
- 決算日時点で支払義務が確定している費用(たとえば、未払いの社会保険料や家賃、水道光熱費など)を、「未払金」や「未払費用」として計上していない
なぜ、このような「隠れ粉飾」が起こってしまうのでしょうか?
ひとつの理由として、「税務上は問題ない(あるいは許容範囲内だ)」という認識があります。税金計算のルールと、会社の財政状態を正確に表すための会計ルールは、必ずしも一致しません。税務上のルールを優先するあまり、会計上の実態から乖離してしまうことがあるのです。
また、「決算の数字を少しでも良く見せたい」という社長の心理が働く場合や、「赤字だからこれ以上費用を計上したくない」といった状況もあるでしょう。あるいは、税理士自身が銀行融資の視点を持っておらず、これらの処理が銀行評価に与える影響を認識していないケースも考えられます。
しかし、理由はどうあれ、これらの処理は銀行から見れば「実態よりも利益を多く見せている(利益の水増し)」、あるいは「本来あるべき負債が計上されていない(簿外債務)」と判断され、結果的に粉飾決算と同じように見なされてしまう可能性があります。
いったん銀行に「この会社の決算書は信用できない」と思われてしまうと、決算書全体の信頼性が失われ、銀行からの評価は下がります。当然、融資は受けにくくなります。
税理士から「税務上は大丈夫ですよ」と言われている処理であっても、銀行の視点では問題になることがある、ということを社長自身も知っておく必要があります。とくに赤字決算のときなどは、利益を少しでも良く見せようとする心理が働きやすいので、注意が必要です。
ポイント3:キャッシュフロー
税理士からの決算説明では、「利益」がいくら増えたか、あるいは減ったか、という話はあるでしょう。いっぽうで、「会社のおカネ(キャッシュ)が、その結果としていくら増えたのか、あるいは減ったのか(キャッシュフロー)」について、詳しく説明を受ける機会は、意外と少ないのではないでしょうか。
なぜ、キャッシュフローの説明が不足しがちなのでしょうか?
ひとつには、多くの中小企業で、おカネの増減とその原因を示す「キャッシュフロー計算書」や、精度の高い「資金繰り表」が日常的に作成・活用されていないので、税理士としても説明するための材料が手元にない、という現実があります。
また、税理士のおもな業務はやはり税金の計算であり、その基礎になるのは「利益(≒課税所得)」です。ゆえに、税理士によっては、「おカネ」の流れそのものについては、直接的な専門領域ではない、と捉えている場合もあるかもしれません。
しかし、社長にとって、そして会社の存続にとって、利益以上にシビアな確認を要するのが「おカネ」の流れ、つまりキャッシュフローです。よく言われることですが、会社が最終的に立ち行かなくなるのは、赤字が続いたからではなく、「おカネが尽きたから」です。
たとえ損益計算書上は黒字であっても、手元のおカネが足りなくなれば、支払いができなくなり、会社はつぶれてしまいます(いわゆる黒字倒産)。
では、なぜ利益が出ているのにおカネが減ることがあるのか?おもな要因としては、売掛金や在庫が増加している(売上は立ったがおカネはまだ入ってきていない、仕入はしたがまだ売れていない)、借入金の返済額が大きい、多額の設備投資を行った、などが挙げられます。
これらの「利益とおカネのズレ」を把握せずに、損益計算書の利益だけを見て経営判断をしていると、気づいたときには手遅れ、という事態になりかねません。
当然ながら、銀行も損益計算書の利益だけでなく、キャッシュフローの状況を厳しくチェックしています。とくに「簡易キャッシュフロー(税引後利益+減価償却費)」が、年間の借入金返済額を上回っているかどうかは、会社の返済能力を測るうえで非常に重要なポイントと見なされています。
税理士からキャッシュフローについて十分な説明がない場合でも、社長自身が、最低でも資金繰り表を作成・活用するなどして、「おカネ」の流れをしっかりと把握し、管理していくことが不可欠です。利益の裏側にある、おカネの動きにこそ、経営の巧拙が隠れています。
まとめ
顧問税理士は、会社の経営にとって頼りになるパートナーです。しかし、税理士からの説明が、必ずしも会社の全体像や、銀行評価に関わる全ての重要ポイントをカバーしているとは限りません。社長自身が「会社の状態を正しく知るために、何を確認すべきか」を理解しておくことが、重要です。
今回お話しした3つのポイント、
- 貸借対照表(とくに純資産・利益剰余金の状況)
- 隠れ粉飾(悪意なき不適切会計処理のリスク)
- キャッシュフロー(おカネの流れの実態)
これらは、税理士の説明ではときに触れられにくい部分かもしれませんが、会社の財務的な健全性や、銀行からの評価、ひいては会社の存続そのものに直結する、とても重要な項目です。
ぜひ、今後の顧問税理士とのコミュニケーションにおいては、これらの点についても意識的に質問をしたり、より詳しい説明を求めたりしてみましょう。必要であれば、キャッシュフロー計算書や精度の高い資金繰り表の作成・説明を依頼することも有効でしょう。
「税理士任せ」にすることなく、社長自身が自社の数字と向き合い、理解を深めること。それが、変化の激しい時代において自社の未来を守り、持続的な成長を実現するための、たしかな一歩になるはずです。