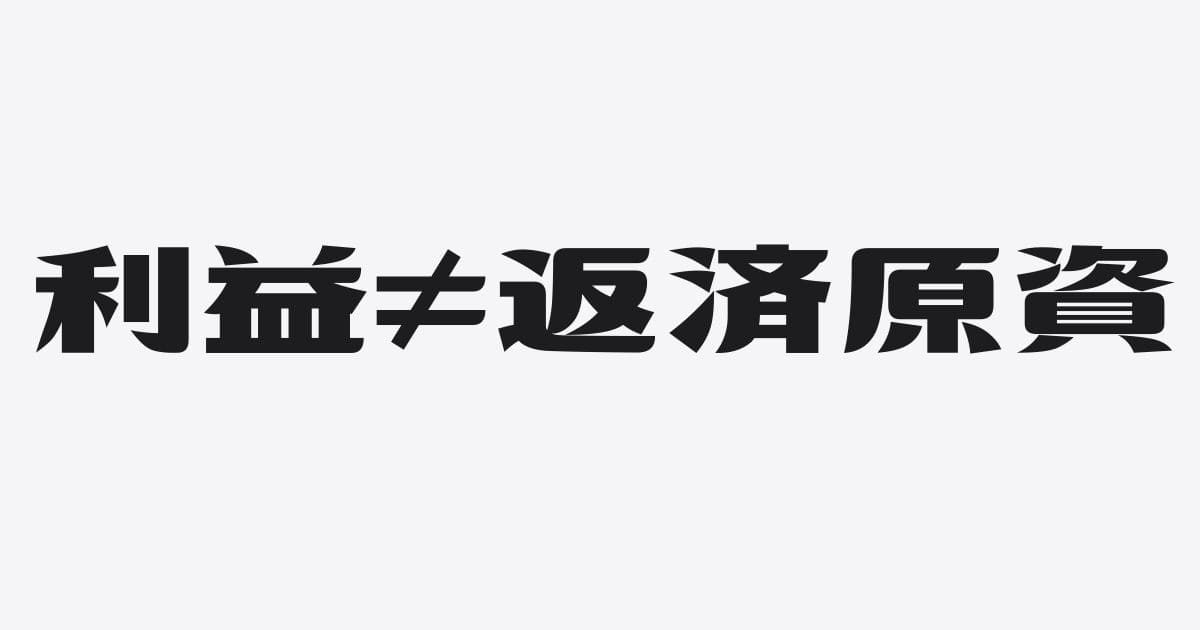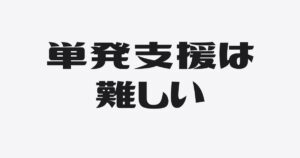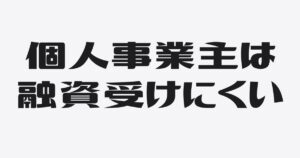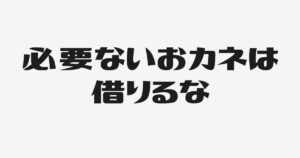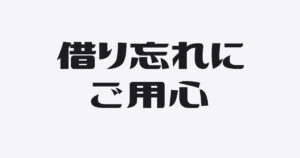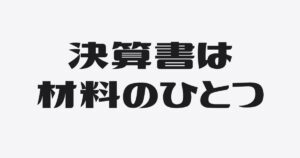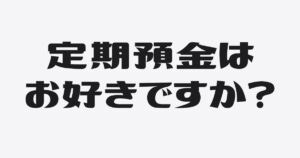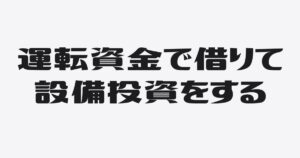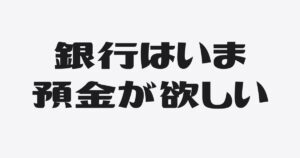「返済には利益が必要だ」というのはよく見聞きするハナシです。が、本質的にはちょっと違います。では、返済に必要なものは何なのか?資金繰りの良し悪しに関わる大事なお話をします。
返済の本質は、おカネにある
会社の銀行借入について、「返済には利益が必要だ」というのはよく見聞きするハナシです。間違いではないものの、本質的にはちょっと違うことはご存知でしょうか?
端的に言えば、返済に必要なものは利益ではない。返済に必要なものは別にあるということです。先に結論を言ってしまいます。利益ではなく、「おカネ」です。
「利益が出てないから借入するには早い」とか、「利益が少ないのに返済なんてムリ」といった考えを持っている社長は気をつけなければいけません。この点、次の流れで解説をしていきます。
- 返済は利益で払うのではない
- 利益がいらないケースがある
- 利益が出てからでは遅すぎる
返済の本質は、おカネにあります。これが理解できていると、資金繰りはよりよくなります。逆に、「返済には利益が必要だ」という考えにしばられると、資金繰りは悪くなるものです。このあとのお話で、あらためて考えを見直していきましょう。
返済は利益で払うのではない
いきなりではありますが、そもそも「返済」とは何なのか?返済という行為をイメージすればわかります。それは、「借りたおカネを返すこと」です。
ここで気がつきたいのは、「返すのは利益ではなくておカネだ」というところ。いくら利益が出ていても、おカネがなければ返済ができないことはわかるでしょう。これが、返済の本質です。
逆に、利益が出ていなくても、おカネがあれば返済はできてしまいます。だとすれば、返済に必要なものはおカネです。
実際、会計(仕訳)でも「元金の返済」は経費として扱われません(利息は経費)。ですから、元金の返済が多いことが原因で赤字になった…なんてことはないわけです。
いっぽうで、「税引後利益が返済原資」という考えが浸透していますが、これは「利益=おカネ」を前提にしています。その証拠に、厳密には「税引後利益+減価償却費が返済原資」です。これはちょっと専門性の高いハナシなのでさておくとして。
大事なのは、利益とおカネは必ずしもイコールではないということです。たとえば、商品を販売して引き渡せば売上が計上されて利益は増えますが、その後、代金を回収するまでおカネは増えません。よって、売り上げてから代金回収までのあいだは、利益とおカネはイコールではないのです。
とにもかくにも、ここで押さえておきたいのは次の1点になります。それが、「おカネがありさえすれば返済は可能だ」ということです。返済は利益で払うのではありません。
利益がいらないケースがある
続いて、利益がなくても返済できるケースを2つ紹介します。言い換えると、利益がなくてもおカネがあるから返済できるケースです。
1つめは、余裕資金を借入するケース。たとえば、銀行から1,000万円の借入をしたあと、そのまま預金にしておくような場合がそれにあたります。もはや言うまでもありませんが、この1,000万円のおカネを使わずにいれば、返済にそのまま使えるわけです。
つまり、借入した瞬間から返済原資を持っているのであり、返済するのに利益は必要ありません。
2つめは、経常運転資金を借入するケース。経常運転資金とは、算式であらわすと「売掛金+棚卸資産−買掛金」となります。この分の借入をするのは財務のセオリーですが、やはり返済に利益は必要ありません。
なぜなら、売掛金や棚卸資産がやがて現金化されることで「おカネ」となり、そのおカネで返済できるからです。よって、経常運転資金分のおカネを借入する限りは、利益を気にする必要はないといえます。
というように、実際にも、利益がなくても返済できるケースがあることを覚えておきましょう。にもかかわらず、その借入をしなければ、借入をしない分だけ(つまり借入によりおカネが増えない分だけ)資金繰りは悪くなります。
利益が出てからでは遅すぎる
それでもなお、「利益が出てから借りる」と考える社長がいます。利益を待っていたら、先に資金繰りが厳しくなってしまうかもしれないのにもかかわらずです。
ここで大事なのは、利益ではありません。「いま返済できるおカネがあるかどうか」です。もしくは、近い将来におカネが入ってくる確実性があるかどうかです(前述の売掛金や棚卸資産のように)。
これが、「借入するかどうか」の本当の判断基準になります。ところが、「返済には利益が必要」という考えにとらわれすぎると、必要な借入まで躊躇してしまい、かえって資金繰りを悪化させかねません。
たとえば、返済期間5年で1,000万円の借入をすれば、年間の返済額は200万円です。よって、返済をするためには200万円の税引後利益が必要だと考えるのであれば、利益にとらわれすぎだといえます。
繰り返しになりますが、利益がなくても返済できるケースはあるからです。だからこそ、返済原資は利益ではなく「おカネ」だとの理解が大切になります。
利益が返済原資だといわれるのは、「利益=おカネ」を前提とするからです。いっぽうで、利益がなくとも増やせるおカネがあることを覚えておきましょう。2つのケースを挙げたとおりです。
利益が多くはなくても、利益を必要としないのであれば借りる。借りたおカネで資金繰りをよりよくできれば、社長は経営に集中できます。すると、利益も増えるので好循環です。
まとめ
「返済には利益が必要だ」というのはよく見聞きするハナシです。が、本質的にはちょっと違います。では、返済に必要なものは何なのか?資金繰りの良し悪しに関わる大事なお話をしました。
- 返済は利益で払うのではない
- 利益がいらないケースがある
- 利益が出てからでは遅すぎる
返済の本質は、おカネにあります。これが理解できていると、資金繰りはよりよくなります。「利益が出てないから借入するには早い」とか、「利益が少ないのに返済なんてムリ」といった考えを持っている社長は、その考えをあらためていきましょう。