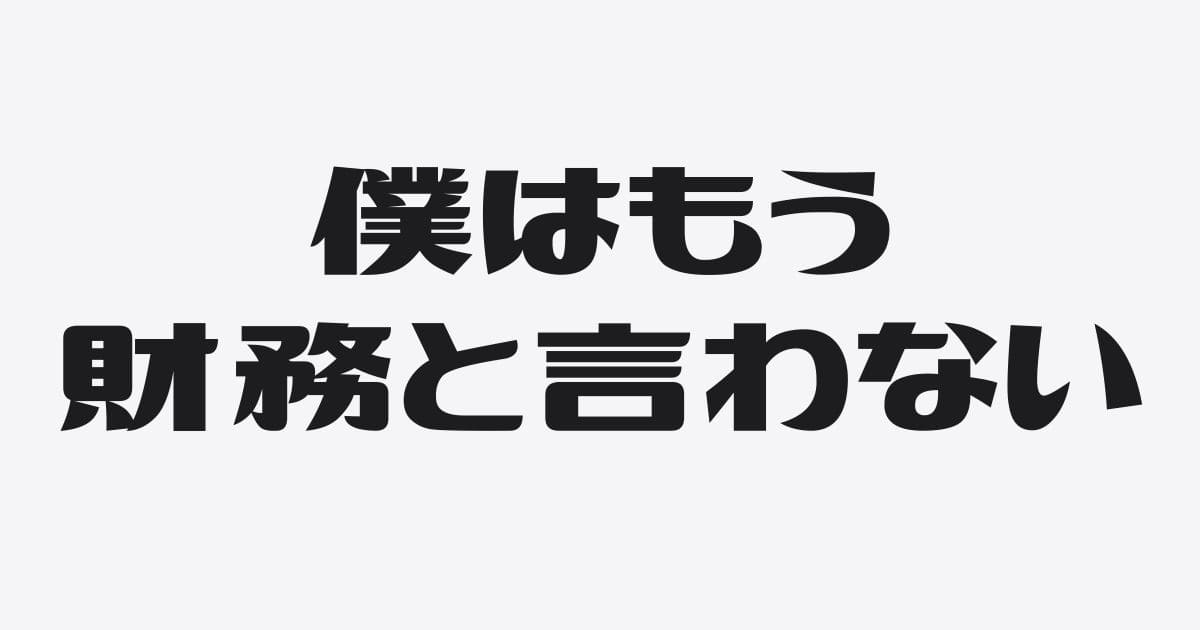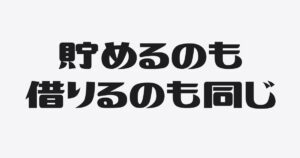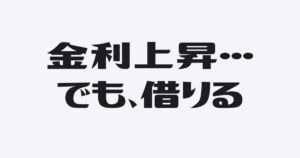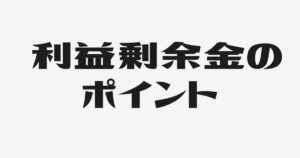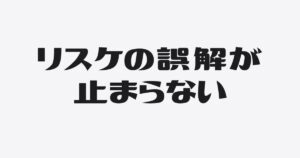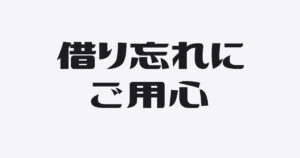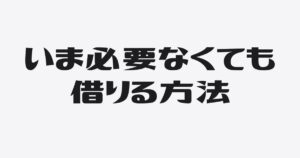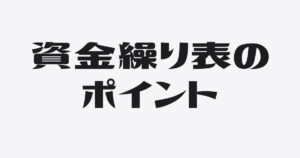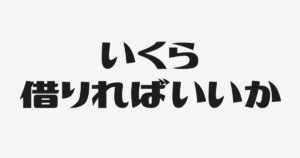僕が銀行融資の話をするときに、あえて使わない言葉があります。それは、「財務・資金・金融機関」の3つです。代わりに置き換える言葉と、その理由についてお話をします。
より伝わるように、言葉を選ぶ大切さ
僕が、銀行融資や会社のおカネの話をするときに、どんな言葉を使っているか? 実は、言葉の選びかたひとつで、相手への伝わりかたが大きく変わることがあります。専門家が当たり前に使う言葉でも、社長にとってはピンとこなかったり、どこか他人事のように聞こえてしまったり…
僕自身、税理士として多くの社長とお話しするなかで、また、このブログで情報をお伝えするときなどには、「あえて使わないようにしている言葉」がいくつかあります。けして専門用語が間違っているとか、それを軽んじているわけではありません。
ただ、社長に「より伝わる」こと、社長の「実感」により近い言葉を選ぶことを大切にしたい、と考えているからです。
今回は、僕が銀行融資について話すときに、あえて使わない3つの言葉と、その理由についてお話しします。具体的には、次の3つです。
- 財務
- 資金
- 金融機関
これらの言葉をなるべく使わないようにしていますし、代わりに別の言葉に置き換えています。というように、言葉選びの背景にある僕なりの意図を知っていただくことで、銀行と話しをするときや、周囲とコミュニケーションをとるときのヒントが見つかるかもしれません。
あえて使わない3つの言葉とその理由
それでは、僕が銀行融資の話をするときに、とくに意識して使わないようにしている代表的な3つの言葉、「財務・資金・金融機関」について、なぜそうしているのか、その理由を具体的にお話ししていきましょう。言葉の裏にある意図を知ることで、見えてくるものがあるはずです。
財務ではなく、融資
まず1つめは「財務」という言葉です。
銀行融資を受けることや、その結果として目指すべきは、突き詰めれば会社の「財務体質を改善・強化する」ことです。ですから、専門家としては「財務戦略を考えましょう」「財務改善が必要です」といった言葉を使うのが、本質的で正しいのかもしれません。
でも、僕が社長と話すときや、ブログを書くときには、できるだけ「財務」ではなく「融資」という言葉を使うようにしています。なぜか?
それは、多くの社長にとって、まず一番の関心事であり、話の入口となるのが「融資を受けられるかどうか」だからです。「財務」という言葉は範囲が広く、抽象的に聞こえがちです。「ウチみたいな小さな会社にはまだ関係ない」「なんだか難しそうだ」と、社長によっては少し壁を感じさせてしまうこともあるでしょう。
それよりも、「融資」というより具体的で、社長が日々直面している可能性のあるキーワードから話を始める。そうすることで、社長に「これはじぶんの(会社の)話だ」と、より「じぶんごと」として捉えてもらいやすくなると考えています。
もちろん、融資の話をきっかけにして、その先にある財務体質の改善や、資金繰りの安定化といった、より本質的な話につなげていくことはとても重要です。しかし、最初の入口で社長の関心を引きつけ、話を聞いてもらうためには、「融資」という言葉のほうが有効だと僕は考えています。
最終的な目的(財務改善)は大切ですが、社長にとっての身近な入口(融資)から取り組んでもらうことを優先しているのです。取り組みをはじめなければ、目的にもたどり着けません。
資金ではなく、おカネ
2つめは「資金」という言葉です。
これもまた、会社の現預金や借入金などを指す言葉として、とてもよく使われています。「資金繰り」「運転資金」「設備資金」「資金ショート」など、僕もまったく使わないわけではありません。
ただ、社長と直接話すときや、ブログで語りかけるときには、できるだけ「資金」ではなく「おカネ」という言葉を選ぶようにしています。
なぜなら、「資金」という言葉には、どこか客観的で、少し無機質な響きがあるように感じるからです。決算書や財務分析など、客観的なデータを示す場面では適切な言葉ですが、社長が日々、現場で感じている切実さとは、少し距離があるようにおもうのです。
社長が本当に困っているとき、眠れない夜に頭の中でグルグルと考えてしまうのは、「資金が不足している」という分析的な言葉でしょうか? おそらく違います。もっと直接的に、「おカネがない」「おカネが足りない」といった、切実で生々しい感覚ではないでしょうか。
だから僕は、できるだけ「おカネ」という言葉を使うようにしています。その方が、社長が抱えている問題の深刻さや、その解決の重要性を、よりリアルな温度感で共有できる気がするからです。数字や理屈だけではない、社長の「実感」に寄り添うための言葉として、「おカネ」を選んでいます。
なお、「お金」ではなく「おカネ」としているのは、そのほうがより生々しさを感じるからです。
金融機関ではなく、銀行
3めは「金融機関」という言葉です。
おカネを貸してくれるところには、銀行(都市銀行、地方銀行)だけでなく、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫、商工中金など、さまざまあります。それらをすべて含めて正確に表現するなら、「金融機関」という言葉を使うのが正しいでしょう。
でも、僕はこれも、多くの場合「銀行」という言葉で話すようにしています。
なぜか? もちろん、「金融機関」という言葉が間違いだからではありません。ただ、日常会話や、特に社長と1対1で話すような場面で「金融機関がですね…」と言うと、少し堅苦しく、よそよそしい響きになってしまう可能性があると感じるからです。社長とのあいだに、見えない壁を作ってしまうような気がするのです。
多くの中小企業にとって、日ごろから付き合いがあり、融資の相談をする相手の中心は、やはり「銀行」であったり、「信用金庫・信用組合(これも社長の感覚としては「銀行」に近いことが多い)」ではないでしょうか。社長にとっても、「銀行」という言葉のほうが、圧倒的に馴染みが深くて、わかりやすいはずです。
もちろん、制度の説明などで正確性が求められる場合や、日本政策金融公庫などを特定して話す必要がある場合には、「金融機関」や具体的な名称を使います。しかし、一般的な話として、あるいは社長との会話においては、厳密な正しさよりも、コミュニケーションの円滑さ、話のわかりやすさ、そして親近感や共感を優先したい。
そのために、多くの場合「銀行」という言葉を選んでいるのです。
まとめ
言葉は、僕たちが考えや情報を伝え、相手と心を通わせるための大切な道具です。そして、その道具は、相手に「伝わって」はじめて、その役割を果たします。
専門家として、正確な用語を使うことはもちろん大切です。しかし、それにこだわりすぎるあまり、相手(社長)が話についてこられなくなったり、伝えたい本質がぼやけてしまっては、元も子もありません。
僕は、銀行融資の話をするにあたって、常に「社長の目線」を忘れたくないと考えています。社長がふだん使っている言葉、社長の心に響くであろう言葉、社長が実感として理解できる言葉を選ぶように心がけています。
それは、言葉ひとつで、社長の理解度や共感の度合いが変わり、その先で、融資や財務改善に向けた前向きな「行動」が生まれると信じているからです。
というわけで、誰かと話をするときには、その相手に応じて、少しだけ「伝わる言葉」を意識してみるのはいかがでしょうか。きっと、コミュニケーションがよりスムーズになるはずです。