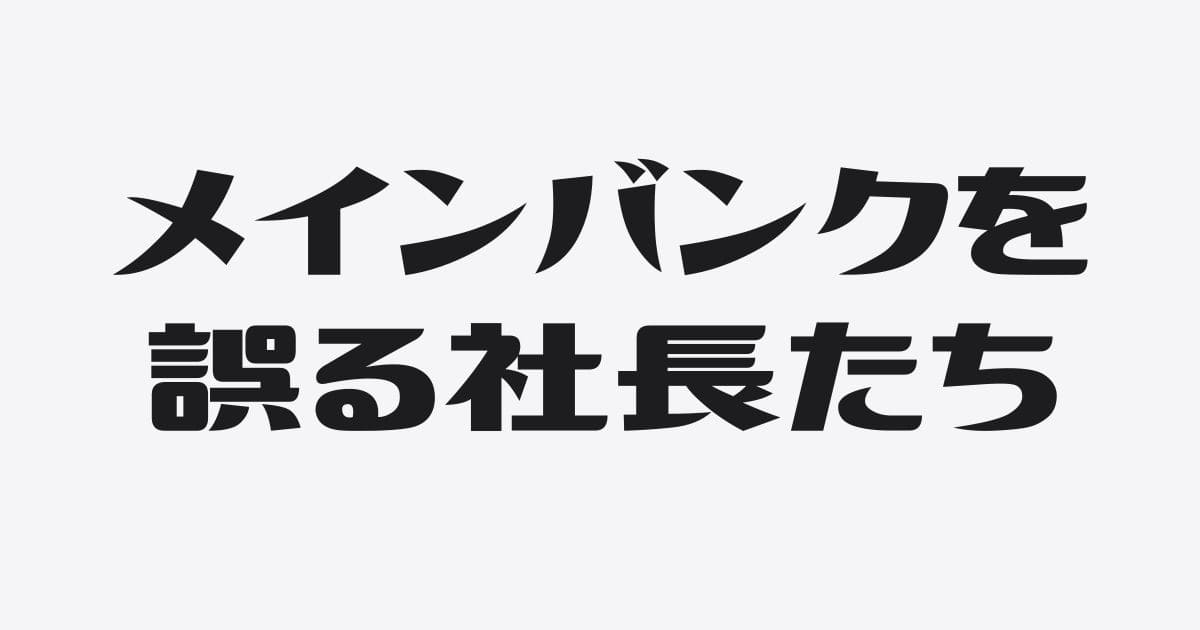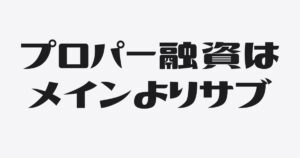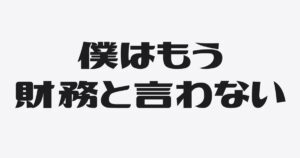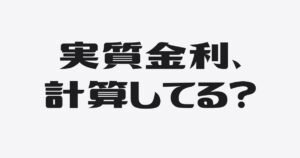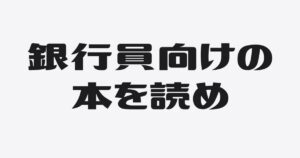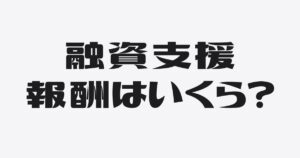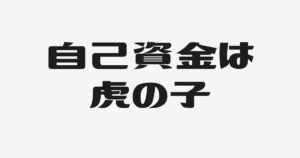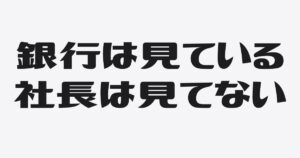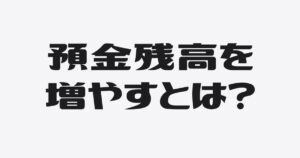あなたの会社のメインバンク、その認識は本当に正しいですか?社長が陥りがちなメインバンクを勘違いする理由と、銀行との賢い付き合い方をわかりやすく解説します。
そのメインバンクは、勘違いかも?
「あなたの会社のメインバンクは、どこですか?」
こう聞かれて、多くの社長は「もちろん、〇〇銀行だよ」と即答できるかもしれません。しかし、その認識は本当に正しいのでしょうか?実は、社長が「メインバンク」を勘違いしている、あるいは認識が曖昧なままになっているケースは、意外と少なくありません。
「ウチはまだ小さい会社だから、メインバンクなんてとくに意識していない」「複数の銀行と、平等に付き合っているから大丈夫」…そう考えている社長もいるでしょう。ですが、僕はそうはおもいません。
むしろ、会社の規模が小さいうちからこそ、特定の銀行と意識的にコミュニケーションを増やし、会社と銀行双方が「この会社(銀行)がメインだ」という認識を共有して、関係を深めることが重要だと考えています。
なぜなら、信頼できるメインバンクを持つことは、いざというときの借入をスムーズにするだけでなく、日々の経営に関する有益な情報提供や支援を受けやすくなるなど、会社の持続・成長にとって多くのメリットをもたらすからです。
そのうえで今回は、社長がなぜメインバンクについて勘違いをしてしまうのか?その代表的な理由を取り上げて、正しいメインバンクとの付き合い方を解説していきます。具体的には理由は3つ、次のとおりです。
- 見栄やネームバリューへの関心
- 「どこで借りても同じ」の考え
- 「銀行も同じ」という思い込み
社長がメインバンクを勘違いする理由
なぜ社長は、自社のメインバンクについて勘違いをしてしまうのでしょうか?僕がこれまで多くの中小企業の社長や銀行員と接してきたなかで、とくに多いと感じる3つの理由について、具体的に見ていきましょう。
見栄やネームバリューへの関心
社長の勘違い
「やっぱりメインバンクは、名の知れたメガバンクじゃないと格好がつかない」「大手銀行のほうがなんとなく安心感があるし、周りからの見栄えも良い」といった、見栄やネームバリューで、自社のメインバンクを「決めたつもり」になってしまっているケースです。
なぜこれが勘違いか?
メガバンク(≒都市銀行)は大きな組織で、ブランド力や安心感があるかもしれません。しかし、中小企業、とくに事業規模がまだ小さい会社に対しては、必ずしもきめ細かい、親身な対応をしてくれるとは限りません。
多くの取引先を抱えるなかで、取引規模が小さい会社はどうしても優先順位が下がりがちになり、担当者が頻繁に変わったり、相談に対するレスポンスが遅かったりすることも少なくありません。
本当のメインバンクとは、会社の規模の大小に関わらず、社長や会社のことを深く理解しようと努め、親身になって相談に乗ってくれる、ときには厳しいことも含めて的確なアドバイスをくれる銀行です。
「かっこいいから」「有名だから」という理由だけで選んだ銀行が、いざというときに本当に自社を支えてくれるメインバンクとして機能しているとは限りません。肩書や看板ではなく、実質的な関係性に目を向けましょう。
「どこで借りても同じ」の考え
社長の勘違い
「どうせ信用保証協会の保証付き融資なら、メガバンクで借りても信用金庫で借りても、金利や条件はほとんど同じだろう」「プロパー融資は難しいから、保証付きで借りられるなら、どこの銀行でもかまわない」というように、融資の中身や銀行の特性をあまり考慮せず、「借りられればどこでも同じ」と考えてしまうケースです。
なぜこれが勘違いか?
たしかに、保証協会の保証付き融資の金利や保証料率といった条件面では、銀行による大きな差は出にくいかもしれません。ですが、銀行によって審査のスピード感、融資実行までの柔軟性、そして何よりも「融資後のフォロー体制」や「会社への関与度合い」は大きく異なります。
さらに重要な違いとして、将来的なプロパー融資への期待度が挙げられます。たとえば、地元の地方銀行や信用金庫・信用組合であれば、最初は保証付き融資からのスタートだとしても、取引実績を重ねて、会社の成長性や社長の経営手腕を理解してもらうことで、将来的にプロパー融資に切り替えてもらえたり、追加でプロパー融資を受けられたりする可能性は十分にあります。
地方銀行や信用金庫・信用組合は、地域の中小企業を育て、支えるという役割を強く意識しているからです。
しかし、おもに大企業との取引が中心である都市銀行の場合、中小企業(とくに小規模企業)に対して、保証付き融資からプロパー融資へと積極的にステップアップさせてくれるケースは、残念ながら期待しにくいのが現実です。
銀行の規模やビジネスモデル、そして審査の基準によって、中小企業に対する姿勢には明確な違いがあるのです。けして「銀行はどこでも同じ」ではありません。
また、将来的に会社の信用力が高まり、銀行が直接リスクを負うプロパー融資を目指していくのであれば、ふだんから会社の事業内容や成長性をしっかりと評価して、リスクを取ってくれる可能性のある銀行との関係を地道に深めておくことが大切です。
保証付き融資ばかりに頼っていると、銀行が自社に対してどれくらいのリスクを取ってくれるのか、その「本当の評価」が見えにくくなってしまいます。
真のメインバンクであれば、保証付き融資を検討する際にも、より積極的に、かつ迅速に対応してくれる可能性が高く、会社の状況にあわせて多様な融資制度(たとえば、短期運転資金のための当座貸越や、成長のための設備資金など)を提案してくれることも期待できます。
「銀行も同じ」という思い込み
社長の勘違い
これが、もっとも厄介で、かつ気づきにくい勘違いかもしれません。社長自身は「A銀行がウチのメインバンクだ。長年取引しているし、融資残高も一番多いから間違いない」と固く信じている。でも、A銀行側はそう認識していなかったり、あるいは社長が思っているほど自社を重要視していなかったりするケースです。
なぜこれが勘違いか?
メインバンクとしての関係性は、「社長と銀行の双方が、互いにそう認識している」という共通認識があってはじめて成立します。社長の一方的な思い込みだけでは、残念ながらメインバンクとしての手厚いサポートや、いざというときの迅速な対応は期待できません。
銀行があなたの会社を「重要な取引先(メインバンク先)」として認識しているかどうかは、単に融資残高の大きさだけでは決まりません。
むしろ、預金取引のシェア、日々の決済口座としての利用状況(給与振込口座や売上入金口座として利用しているかなど)、社長と銀行担当者との面談頻度や情報交換の密度、プロパー融資の実績の有無、銀行からの積極的な情報提供や経営支援の提案の有無など、さまざまな要素を総合的に見て判断します。
もし銀行が、自社を「数ある取引先の一つ」としか見ていないのであれば、いざというときに「まずはメインの銀行さんにご相談されてはいかがですか?」と、支援の優先順位を下げられたり、あるいは期待していたようなサポートが得られなかったりするリスクも十分に考えられます。
まとめ
社長がメインバンクについて勘違いしやすい3つの理由について解説してきました。
- 見栄やネームバリューへの関心
- 「どこで借りても同じ」の考え
- 「銀行も同じ」という思い込み
大切なのは、会社の規模の大小に関わらず(小規模企業であっても)、自社の事業内容や将来性を本当に理解して、親身になって相談に乗ってくれる、ときには厳しい助言も真剣にしてくれる銀行を「見極める」ことです。
そして、その銀行と「共にメインバンクとしての良い関係を意識的に育てていく」という、社長自身の積極的かつ能動的な姿勢です。
そのためには、日ごろから決算書だけではなく、自社の強みや抱えている課題、将来の事業計画などを積極的に銀行に開示して、密なコミュニケーションを取ることが欠かせません。良いときも悪いときも、正直に情報を共有することが信頼関係の基礎となります。
単なる「名ばかりのメインバンク」ではなく、いざというときに本当に頼りになる、会社の成長を融資面だけではなく多方面から支援してくれる「実質的なメインバンク」を持つこと。それが、会社の安定と成長、何よりも社長自身の安心につながる、財務戦略のひとつです。
あなたの会社のメインバンクは、本当に「メインバンク」として機能していますか? いちど、じっくりと考えてみましょう。