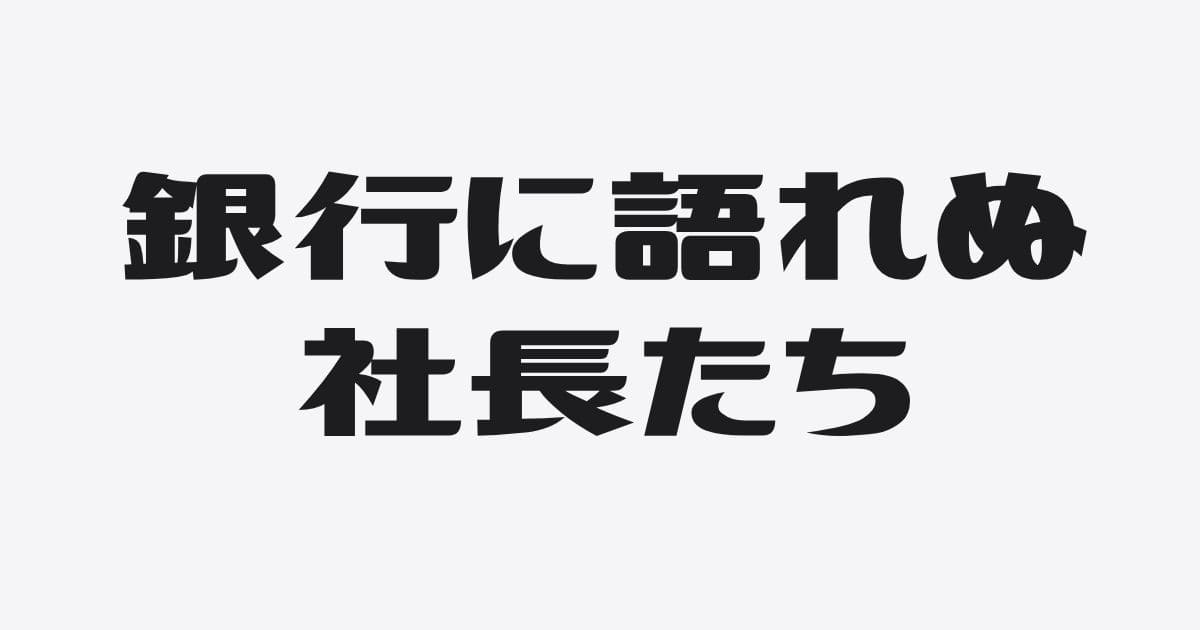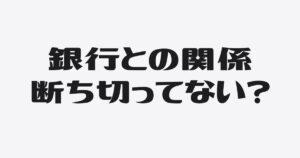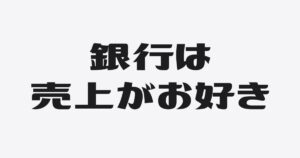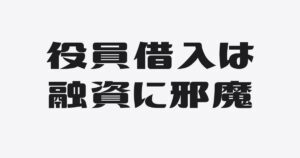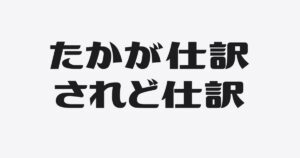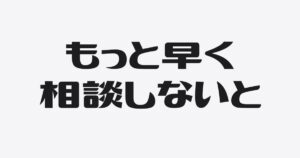銀行から「貸せない」と言われるのは、業績が悪いからとは限りません。社長が、銀行が安心して貸すために必要な「3つのこと」を語れていないだけ、というケースはあるものです。
銀行が融資したくてもできないワケ
- 「銀行はなかなかおカネを貸してくれない…」
- 「うちの会社の状況を、銀行はきちんと理解してくれない…」
多くの社長が、銀行融資に対してそんな不満や悩みを抱えているかもしれません。たしかに、銀行の審査が厳しい、という側面はあります。しかし、銀行融資の支援という仕事を通じて現場を見ている僕の目からは、少し違う景色が見えることがあります。
それは、「銀行は貸したいと思っているのに、社長が“ある重要なこと”を語ってくれないから、貸すに貸せない」というケースが、実は少なくないということです。
誤解を恐れずに言えば、銀行も商売です。融資をして利息を得ることで成り立っていますから、健全な会社にはどんどんおカネを貸したい、というのが本音です。ところが、銀行には「きちんと返してもらえる見込みのある先にしか貸せない」という、絶対に変えられないルールがあります。
その「返済の見込み」を判断するために、銀行は知りたいことがあるのです。でも、多くの社長が的確に、あるいは具体的にそれを語ることができません。結果として、銀行は「この会社の実態がよくわからない」「将来性が判断できない」と感じるため、融資をあきらめざるをなくなります。
そこで本記事では、社長が銀行に融資を申し込む際に、「本当は社長が語るべきなのに、語れずにいる3つのこと」について、その重要性と、どう語るべきかのポイントを解説していきます。この記事のポイントは以下のとおりです。
- おカネが必要な理由は?(資金使途)
- 会社をどうしたいのか?(数値目標)
- 借りるとどうなるのか?(借入効果)
社長が銀行に語れない、融資を引き出す3つの重要ポイント
銀行が「この会社になら安心して貸せる」と判断するために、社長から聞きたいと思っていることは、実はそう多くありません。しかし、その核心となる部分が語られないために、多くの融資機会が失われています。具体的に見ていきましょう。
ポイント1:おカネが必要な理由は?(資金使途)
社長が言いがちなNGワード
- 「いくらなら貸してもらえますか?」
- 「借りられるだけ多く借りたいんです」
- 「手元のおカネが足りないので…」
なぜ語れないのか?
おそらく、社長の頭のなかには「運転資金として必要だ」という考えはあるのでしょう。しかし、それを具体的な内訳まで落とし込んで考えていないケースは多いものです。
「運転資金」という便利な言葉で、すべてをまとめてしまっている。あるいは、銀行に使い道を細かく話してしまうと、自由におカネが使えなくなるのではないか、といった漠然とした懸念があるとの声も耳にします。
銀行が本当に聞きたいこと & どう語るべきか?
銀行は、「おカネを借りたい」と言われたら、まず「何に、いくら、いつまでに必要なのか」を具体的に知りたいと考えます。それによって、融資の必要性や妥当性、適切な融資額、必要な期間などを判断するからです。
いっぽうで。資金使途が曖昧な相手に、大きなおカネを貸すことはできません。ですから、社長が語るべきことは明確です。つまり…
「今後、売上が増加する見込みであり、それにともなう仕入資金として〇月に〇〇万円、増加する人件費として〇〇万円、外注費の支払いとして〇月に〇〇万円が必要です。合計で〇〇万円の運転資金をお願いします」
といったように、たとえ運転資金であっても、その内訳をできるだけ具体的に分解して説明することが重要です。また設備資金が必要なのであれば、その設備の見積書を提示して、なぜいま、その設備への投資が必要なのかを伝えます。
明確な資金使途を語ることは、社長が自社の経営状況を客観的に把握し、計画的に事業を進めていることの何よりの証明です。それが、銀行からの信頼を高める第一歩になると理解しましょう。
ポイント2:会社をどうしたいのか?(数値目標)
社長が言いがちなNGワード
- 「とにかくがんばります!」
- 「社員一丸となってなんとかします」
- 「これから景気もきっと良くなるので大丈夫です」
- 「(未来のことはわかりませんから)計画はありません」
なぜ語れないのか?
未来のことは誰にも分からない、という気持ちはよくわかります。「計画を立てても、そのとおりにいかないじゃないか」と考えて、計画自体を軽視している社長もいます。あるいは、シンプルに数字に苦手意識があり、具体的な計画に落とし込む作業そのものを避けているのかもしれません。
銀行が本当に聞きたいこと & どう語るべきか?
銀行は、融資したおカネが、将来どのようにして返済されるのかを知りたいのです。その返済の原資となるのが、会社の「利益」です。そして、その利益が将来にわたってどのように生み出されていくのか、その道筋を示すものが「数値目標(事業計画)」に他なりません。
したがって、社長が語るべきは、根性論や希望的観測ではなく、具体的な数字です。つまり…
「来期は、〇〇という新商品を投入することで、売上高を前期比〇%増の〇〇円、経常利益を〇〇円とすることを目指します。そのための行動計画は…」
といった、具体的な数値目標を語ることが不可欠です。もちろん、その目標の根拠(なぜその数字が達成できると考えるのか=行動計画)も、あわせて説明できれば説得力は格段に増します。
たとえ計画どおりにいかないことがあったとしても、それはそれです。重要なのは、目標を立て、それに向かって会社全体で努力し、ズレが生じたときにはその原因を分析して修正していく、という経営姿勢そのものです。その姿勢こそが、銀行からの評価につながります。
ポイント3:借りるとどうなるのか?(借入効果)
社長が言いがちなNGワード
- 「とにかくおカネがないんです…」
- 「このままでは資金繰りが苦しくてもちません」
- 「お願いだから助けてください!」
なぜ語れないのか?
資金繰りが厳しい状況では、どうしても目の前の「おカネがない」という事実ばかりに目がいってしまい、その先のこと、つまり「おカネを借りたあと、会社をどう良くしていくか」まで考えが及ばなくなってしまうことがあります。
これは、借りること自体が目的化してしまっている状態です。
銀行が本当に聞きたいこと & どう語るべきか?
銀行員が社長の話を聞くときの大きな関心ごとは、「この会社に融資をすることで、この会社は良くなるのだろうか?具体的には、売上や利益は増えるのだろうか?(=ひいては、さらに融資ができそうか)」という点です。
融資が会社の抱える課題を解決し、成長に貢献し、その結果として返済がより確実になる。銀行は、そんな前向きなストーリーを求めています。社長が語るべきは、苦しい現状の訴えではありません。つまり…
「今回〇〇万円の融資を受けることで、〇〇への投資が可能になり、生産性がさらに向上します。その結果、売上が年間で〇〇円増加し、利益が〇〇円改善する見込みです。それによって、返済も問題なく行えます」
といった、融資がもたらす具体的なプラスの効果(借入効果)を語ることが、何よりも重要です。
単に「苦しい」「助けてほしい」と訴えるだけでは、銀行は「この会社におカネを貸しても、根本的な問題は解決せず、またすぐに行き詰まるのではないか?」と不安になってしまいます。融資を単なる延命措置ではなく、「未来への投資」として位置づける。そのリターン(借入効果)を具体的に示すことで、銀行は安心して前向きに融資を検討できるようになるのです。
まとめ
銀行が融資をしたくてもできない。その背景には、社長が、
- なぜおカネが必要で(資金使途)
- それをどう使い、会社をどう成長させ(数値目標)
- 結果としてどのようなプラスの効果があるのか(借入効果)
という、融資における3つの核心部分を、具体的に、そして一貫したストーリーとして語れていないケースが少なくありません。
これら3つを語ることは、けして難しいことではありません。日ごろから自社の経営と真剣に向き合い、会社の未来について考えて計画を立てていれば、自然と語れるようになるはずです。
銀行との面談は、「おカネを貸して」とお願いをする場ではありません。自社の将来像と、その実現に向けた具体的な計画をプレゼンし、銀行に「パートナー」として協力してもらうための、対話の場だと心得ましょう。
社長は今日から、3つの視点で自社の状況を整理して、いつでも自分の言葉で語れる準備をしておくこと。それが、銀行融資への道を切り開き、会社の未来をより確かなものにするための、たしかな一歩になります。