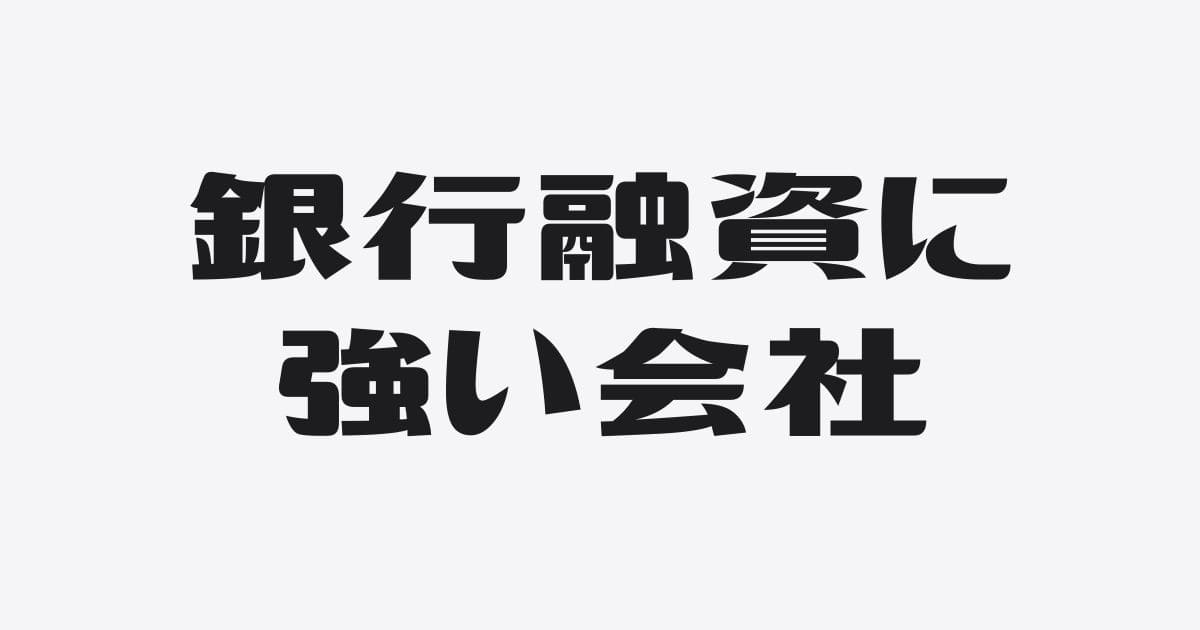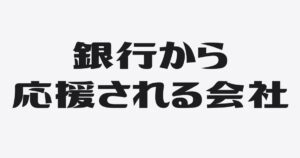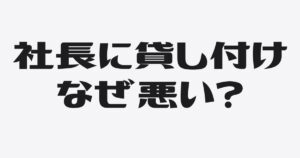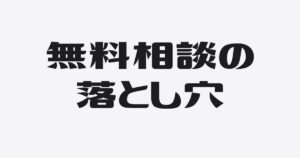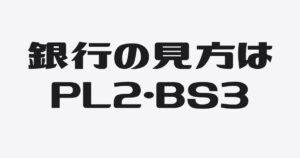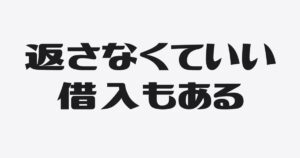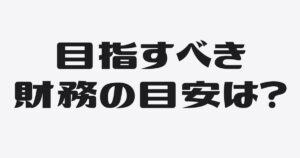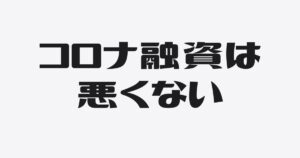「決算書は黒字なのに、なぜか銀行の反応が悪い…」その原因は、社長も税理士も見落としている「日々の仕訳」にあるかもしれません。銀行は、税務署とはまったく違う視点であなたの会社の経理を見ています。
なぜ「たかが仕訳」で銀行評価が変わるのか?
突然ではありますが。なぜ、日々の経理処理である「仕訳」が、銀行融資にまで影響を与えるのでしょうか。その理由は、大きく3つあります。
理由1:仕訳は決算書の「起点」だから
銀行が融資審査で最も重視するのは決算書です。そして、その決算書は、日々の膨大な仕訳の積み重ねによって作られます。つまり、
仕訳はいわば決算書の起点であり、銀行評価のすべての始まりなのです。
理由2:税務署の視点と銀行の視点は違うから
税理士は「税務会計(税金計算の正しさ)」の専門家です。いっぽうで銀行は、「企業会計(会社の実態の正しさ)」の視点で決算書を見ています。
この視点の違いが重要です。税金計算においては問題のない仕訳であっても、銀行融資においては問題のある仕訳があるのです。銀行から見れば「利益の水増し」や「隠れた負債(簿外債務)」を疑われる「銀行にとって心証のよくない仕訳」が存在します。
税理士の視点が税金計算に寄りすぎるあまり、顧問先の仕訳がおざなりになることもありえます(実際に目にしています)。
理由3:仕訳から「社長と税理士の姿勢」が見えるから
雑な仕訳や不透明な勘定科目が並ぶ決算書は、銀行に「この会社の経理は杜撰だ」「社長は数字に関心がないのでは?」という印象を与えます。
それは同時に、「この会社の顧問税理士は、誠実さが足りない」という評価にもつながりかねません。仕訳の丁寧さが、会社の管理体制や社長、ひいては顧問税理士の姿勢を示すものとして、銀行に見られているのです。
銀行に嫌われる「もったいない仕訳」3選
では具体的に、どのような仕訳が問題になるのでしょうか。税理士さえ見落としがちな、銀行に嫌われる「もったいない仕訳」の代表例を3つご紹介します。
事例1:安易な「雑勘定(仮払金・貸付金など)」で信頼を失う
貸借対照表に「仮払金」や「社長への貸付金」といった勘定科目が残っていませんか?
これらの「雑勘定」は、銀行から「使途不明金」「公私混同」「粉飾」を疑われる典型例です。決算書に「仮(仮払金)」が残っていること自体が、経理の機能不全をイメージさせ、銀行の心証を著しく損ないます。
顧問税理士も、税務上の問題がないと判断すれば、そのままにしてしまうことがあるかもしれません。しかし、銀行融資の視点では大きなマイナスです。
事例2:「本業の利益(営業利益)」をわざわざ減らしてしまう
銀行が本業の収益力として最も重視するのは「営業利益」です。しかし、仕訳の仕方ひとつで、この営業利益を不必要に低く見せてしまっているケースがあります。
たとえば、数年にいちどしか発生しないような大規模な修繕費や、臨時の退職金など。これらは「特別損失」として計上すれば、営業利益に影響はありません。しかし、税理士が手間を惜しんで「販売費及び一般管理費」で処理してしまうと、その分だけ営業利益が減り、銀行からの評価を不当に下げてしまうのです。
在庫の評価損なども同様で、「どうせ税務上は損金にならないし、別表で加算するのも面倒だから」と、会計上必要な損失計上をしない税理士もいますが、これも銀行評価を下げる要因となります。
事例3:月次決算で「利益をならす」意識がない
賞与の支払いや年払いの保険料など、特定の月にだけ大きな費用が発生していませんか?これをそのまま費用計上すると、その月だけ赤字になってしまうことがあります。
銀行は、決算書はもちろん、毎月の試算表も見ています。そして、赤字の月が混在している試算表より、1年を通じて毎月黒字の試算表を好みます。
そこで重要になるのが「利益をならす」という考え方です。賞与であれば「賞与引当金」を毎月計上する、年払いの保険料であれば「前払費用」として資産計上し、毎月費用に振り替えるといった処理で、月々の利益のブレをなくすことができます。
この「ならす」ひと手間を、税理士が面倒くさがって怠ると、本来は黒字基調の会社でも、月によっては赤字の試算表が出来上がり、銀行の心証を悪くしてしまうのです。
ここでちょっと、宣伝です
今回取り上げた3つの事例は、銀行が見ている仕訳のポイントのほんの一部に過ぎません。「もっと具体的に、どんな仕訳に気をつければいいのか?」そう思われた方もいらっしゃるでしょう。
僕が執筆をした『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』では、まさにこの「銀行融資と仕訳」という、これまでほとんど語られてこなかったテーマに真正面から切り込みました。
本書では、銀行から評価される「イチ推し仕訳」と、評価を下げてしまう「要注意仕訳」を、貸借対照表・損益計算書の項目に沿って具体的に90個、徹底的に解説しています。
税理士向けと銘打ってはいますが、社長や経理担当者の方にも「銀行はこういう視点で数字を見ているのか」という気づきを得ていただける内容です。日々の経理処理を見直すきっかけとして、ぜひご活用ください。
社長の「当事者意識」が銀行を動かす
では、社長はどうすればよいのでしょうか。大切なのは、仕訳を「他人事」と考えず、社長自身が「当事者意識」を持つことです。
決算説明などの場で、ただ税理士からの報告を受けるだけでなく、「この仕訳について、銀行はどのように評価しますか?」「もっと銀行評価を高める仕訳はありますか?」と、主体的に質問を投げかけてみましょう。
その社長からの問いかけが、税理士にとっても銀行融資をより意識するきっかけとなり、会社全体の財務力を高めるための「協働作業」へと繋がっていきます。
まとめ
仕訳は、単なる過去の記録作業ではありません。銀行との信頼関係を築き、社長自身が会社の正しい姿を把握するための、未来に向けた重要な経営判断です。
AIによる自動仕訳が普及するいまだからこそ、銀行融資という戦略的な視点を持って仕訳を見直すことは、他社との大きな差別化につながります。
本文中でも触れましたが、より詳しい仕訳のポイントについては、僕の著書『税理士必携 銀行融資を引き出す仕訳90』で網羅的に解説しています。日々の経理処理を見直す具体的なヒントとして、ぜひこちらもご活用いただければ幸いです。